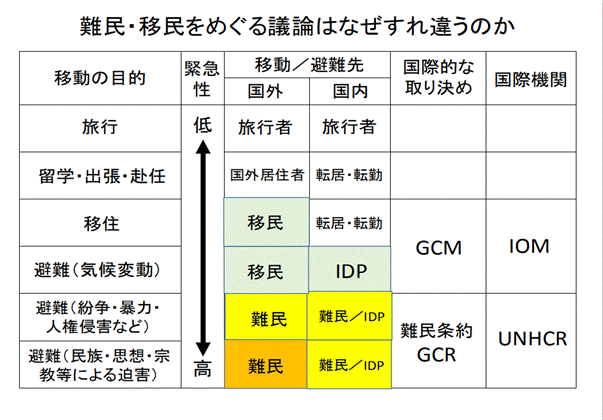「世界の難民・日本の難民」講演会レポート
2025年1月25日に開催しました認定NPO法人AARJapanの講演会のレポートを掲載します。
是非、ご一読下さい。
AAR Japan講演会「世界の難民 日本の難民」
講師 穂積武寛さん(AAR プログラムマネジャー)
[AAR Japanについて]
「難民を助ける会」が正式名称だが、海外で活動するのにAAR Japanと名称しています。現在85人くらいが所属していて、50人くらいが国内、30人くらいが海外事務所に駐在しています。
AARができたのは1979年。作ったのは相馬由紀さんというおばあちゃん。作った時すでに60代後半でした。当時、アジア一帯で難民がボートピープルといわれ社会問題になっていましたが、当時は日本はまだ難民受け入れ制度がなく、外務省はどうしようかと言っていました。それに対し、相馬さんが一念発起し、仲間などに声をかけ、小さく始めたのがAAR。最初は任意団体、最初の十年間はお給料をもらっている人は誰一人いなくて全員ボランティアでした。最初の有給職員第一号が今の会長である長 有紀枝(おさゆきえ)。現在、長はメインの仕事は立教大学の先生だが、引き続きAAR会長をやっています。日本を含めて17か国くらいで事業をやっています。海外がメインですが、日本でも大きな自然災害が起きたときに緊急支援をしています。能登の地震、東日本大震災、九州の地震など。
[活動する分野]
人道的危機にさらされた人々への緊急支援を未来を切り開くための長期的な支援と6つの分野に注力して行っています。
- 難民支援
- 地雷・不発弾対策
- 障がい者支援
- 災害支援
- 感染症対策/水・衛星
- 提言/国際理解教育
難民を助けようとできたAARですが、難民支援にもいろいろあります。難民は自分の国にいられなくて国外で避難生活をしている人のことなので、ありとあらゆることに困っています。それを全部引き受けられたら良いのですが、現実にはお金も人も限られています。限られたお金をどこに費やしたらいいんだと考えることを繰り返す中で、AARの得意分野、重視していく分野が出来てくるようになりました。
ひとつは緊急支援。大きな自然災害が起きた時や戦争が起きて大量の難民が短期間に発生した時は、現場に行ってニーズに答える、物資配布をすることが多いです。その中で、地雷の問題が出てきて、地雷対策もやるようになりました。地雷で被害を受けて生き残った人が障がい者になるのでその人たちの支援も一生懸命やったり。事業の中身はいろいろな分野に渡っています。
[「難民(refugee)」とは]
国際的な合意があります。国家間で合意したことは条約・協定と呼び、難民に関してもそういう取り決めがいくつかあるのでそれをまとめて難民条約と通称されています。
難民条約(1951,1967)
「人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護をうけることができない者またはそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができない者またはそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まない者。」
誤解を避けるためにとてもまどろっこしい書き方をされています。平たく言うと
①人種、宗教の違い、もしくは特定の集団のメンバーであること、政治的意見の違いなどの理由から
②迫害される恐れがあり、
③自分の国の政府の保護を受けられない、または受けることを望まないために、
(本来なら国や警察が保護してくれるはずだが、最悪の場合、国や警察が率先して捕まえに来るかもしれない、そのため怖くてその国にいられない)
④国籍のある国(国籍国)を離れている人々
そういう人たちが来たら言われた国の政府は、その人たちを受け入れて保護しなくてはならないということです。
ただ、これは一番狭い難民の定義。これには当てはまらないが、やはり自分の国には帰れない人たちがいるという声が上がるようになってきました。
[「難民」の定義の拡充]
アフリカ連合(OAU)難民条約(1969)
「外部からの侵略、占領、外国の支配、出身ないしは国籍国の一部ないしは全体において、公的秩序を大きく乱す出来事のために出身ないしは国籍国の外に避難所を求めるために常居所地をさることを余儀なくされた者」
カルタヘナ宣言(1984)
「一般化した暴力、外国からの攻撃、国内紛争、大規模な人権侵害、または公の秩序を著しく乱したその他の状況によって、生命、安全、または自由が脅かされているために国を逃れた人たち」
アフリカの人たちが声を上げました。アフリカは国内での紛争が多い、そうすると自分の国の外に非難をせざるを得ない人が多いんじゃないか、そういう人も難民として考えるべきではないか。同じようなことを中南米の人たちも言いました。中南米もおなじように治安が悪くて、うっかり住んでいられない国の人が国外へ出ることが起きていて、そういう人たちも難民に含めるべきではないかと。
[「難民」かどうかは誰が決める?]
国連には難民を専門にする機関があります。UNHCR/国連難民弁務官事務所。少し前に、日本人の緒方貞子さんがトップだったので、日本では知られています。UNHCRが今誰を支援の対象にしているかというと、狭い定義の難民条約ではなく、その後広がった、いろいろな理由で自分の国にいられない人たちも支援する立場でやっています。ただ、難民かどうかは誰が決めるの?見ただけではわかりません。難民条約には書いていません。それは基本的には各国で決めてくださいということになっています。判断基準がなく、国ごとにばらばらです。割と緩い国もあれば、日本はどちらかというともとから厳しい方。厳しいというか厳密というべきでしょうか。ヨーロッパは比較的緩かったのですが、最近難民の流入が増えてきているのでどの国も判断基準を厳しくする傾向にあります。
アメリカは、急に受け入れませんという大統領になり困っているが、世界的に厳しくなっている印象があります。ただ、政治的配慮もあって、ウクライナの人たちの扱いは極めて寛大でした。ほとんど審査もなしで、どんどん来てくださいみたいな。状況が明らかだったというのもあります。でも、難民かどうかは、政治的状況で判断されがち。
・その人が国際上の「難民」に当たるかどうか(難民性)の判断は、各国政府に任されている。
・国毎に判断基準が異なるが、近年の難民増加に伴い全般的に厳しくなる傾向
・状況によっては寛大な措置が取られる場合(ウクライナ難民など)もあり、政治的判断に左右されがち
[「移民(migrant)」とは?]
最近のニュースで、「移民に対する反発が強まっている」というようなニュースを聞くようになりました。
移民と難民はよく似ている言葉。移民と難民は何が違うのかを考えてみたい。難民には定義があるが、移民にはそれにあたるものがありません。
●「移民」について国際的に合意された定義はない
・「通常の居住地以外の国に移動し、少なくとも12か月間当該国に居住する人(国連)
・「EU加盟国以外の国の国籍を持ち、EU諸国内に3か月以上滞在する外国人」(EU)
・入国管理法の「中長期在留者」と「特別永住者」(日本)
●世界に少なくとも2億人以上
いろいろな定義があり、国連では「自分の国の外にいて1年以上他の国にいたら移民と考えよう」EUは「EUの中に3か月いたら、短期滞在者。旅行者ではなく移民とみなす」日本は政府の定義はありません。学者さんたちが話をするときは、日本の在留資格で入国管理法の中長期在留者と特別永住者の資格を持っている人を移民とみなすのが妥当であろうということになっています。あやふやではっきりとした統計もないが、少なくとも世界に2億人以上はいるだろうと言われています。
ちなみに難民がどのくらいいるかというとこれはUNHCRが毎年数字を出していて、今は1億2千万人と言っています。1億2千万人が全員難民の定義の人かというとそうではなく、自分の国の中で避難生活をしている人もいます。そういう人は「国内避難民」と言って「難民」とは別扱いではありますが、いる場所の違いだけで抱えている問題は同じなので、UNHCRは支援の対象にしています。この数字は日本の国民と同じです。
世界の人口が80億人と仮定すると80人に1人が難民。
自分の住んでいた国におちおち住んでいられないというのが今の世界です。
グローバル・コンパクト
●法的な拘束力のある「条約(convention)」ではなく、「合意(compact)」
●意義:「難民・移民」を世界が協力して対応すべきグローバルな課題として提示したこと
●移民に関するグローバル・コンパクト(GCM)と難民に関するグローバル・コンパクト(GCR)がある
●GCRについては、各国の状況を報告する会議(グローバル難民フォーラム、GCF)が4年に一度開かれている
[グローバル・コンパクト]
概念的なものでグローバル・コンパクトというものがあります。国の間で取り決めたものを条約と呼び、条約は国際法という法律。本当に守らないといけないし、守らないとペナルティがあります。すごく議論のある問題について国際条約を作るのはなかなか大変。みんな縛られたくないから。移民問題もそういう条約があったらいいのではという話はありましたが、国によって立場があまりにもちがうので統一のルール、条約は作れないのでは、でもこのままほっとくわけにも行かない。じゃあ、拘束力ないけどゆるっと合意しましょうとなりました。合意のことをコンパクトと言い、agreementくらいの意味。
移民問題、難民問題に関して合意しましょう、と会議を何回も開いて一応合意しました。拘束力がないガイドラインみたいなものを作って意味があるのかということですが、難民・移民の問題は世界が協力して対応しないと大変なことになるぞっていう姿勢を世界に示したという意義はあるかと思います。移民に対するグローバル・コンパクト。頭文字を取ってGCM、難民に関するグローバル・コンパクトGCRというふたつのコンパクトがあります。難民に関するグローバル・コンパクトについては定期的に集まって、どんな取り組みをしているか、どんなことが問題なっているかという会議が4年に1回開催されています。
[難民移民の位置づけ]
難民・移民に対する各国の態度は振れ幅が大きい。片方には「いやいやもうそんな人うちの国に来てくれたら困る。もう、うちには入れません」という国があるかと思えば、もう片方には「いやいやそういう人は支援を必要としているのだから保護してあげなくてはいけないんじゃないか。人権的にも問題ではないか」という立場の国もあり話がなかなかかみ合わない。
移動という観点から、私なりに考えてみたのがこの図です。ある人がどこかからどこかへ動いているということにおいて、何か問題が発生しているということです。移動にもいろいろあります。
一番騒ぎ立てる必要がないものは「旅行」。旅券を持っていなくてはならないし、航空券を買ってビザが必要なところは取らなくてはならない。これは「旅行者」と呼ばれます。もう少しきちんとしなくてはならないのは「留学・出張・海外赴任」など。少し時間が伸び、準備も大変になり、「国外居住者、国内での移動は転居・転勤」。
さらに大きな移動になると移住。生活拠点をすべて移しますとなるとそこで「移民」という扱いとなります。国内であれば、転居・転勤、引っ越しの延長上で別に問題ではありません。ただアメリカに移住しますとなると手続きがいろいろ発生していきます。
ここから先はが話がややこしくなります。「避難」。つまり、本当は動きたくないけれどもう動かざるを得ないということ。非常に微妙なのが今まで戦争や政治とか思想の違いのような話をしていましたが、最近多いのが気候変動でもう自分たちの元居たところに住んでいられないと言って移動してくる人たちが非常に多いです。特にアフリカが多い。雨が一滴も降らない、作物が育たない、もう自分たちの元居た地域には住んでいられないと言って国境を越えていく人たちが多い。この人たちが難民なのかというのは非常に微妙な問題。一応、移民として扱われるが場合によっては、難民としてとらえられることもあります。国内でそういう人たちが出ると、単なる引っ越しではないのでIDP、国内避難民(internally displaced person)となります。
これから先が、「避難(紛争・暴力・人権侵害など)」難民条約に書かれたような拡張された定義にかかってくる人たち。こうなってくると難民扱いになります。それが国内であれば難民と呼ばれたり国内避難民と呼ばれたり。
一番シリアスなのが、難民条約で提示された「捕まる・不法に拘束される」という状態の人たち。そういう人たちは間違いなく難民。国内であれば国内避難民扱い。
そういう人たちのための国際的なルールは何があるかというと、移民に関してはGCMがあります。こういうところは大事ですよね、という取り決めの項目がいくつかあります。GCMはインターネットで全文が検索できるので関心のある方は、どんなことが大事だと言われているのか調べてみてください。
難民に関しては先ほどご紹介した「難民条約」とGCRがある。これらのことについて取り仕切っているのが、GCMに関してはIOM、難民に関してはUNHCR。
こう見ると、難民と移民の間にきっちりと線が引かれているとわかります。国際法的にも対応する組織・団体がきっちりと分けられています。しかし、その人が移民なのか難民なのかは見た目ではわからない。いろいろな人がひっくるめてやってきます。単にヨーロッパで仕事がしたいというような人も当然含まれています。そうなると、もうこれ以上来てくれるなという拒否反応のようなものも起きます。ただ、本来はやはりごっちゃにしてはいけない問題。保護されてしかるべき人たちというのは厳然としているのです。
問題になっているのは、不法に、合法的な手続きを経ないで無理やり国境を越えてきたよく使われる言葉で言えば「不法移民」とみなされる人たちの扱いをどうするかが一番問題になってきます。これに関しては国際ルールが何もありません。「難民」についてはやめてしまえ、のような声はありません。保護されるべき人は保護されるべきというところは変わらず、少なくとも政府レベルでそういう議論は全く起きていません。
いろいろなことをいう人がいるが、その人がどこに軸足を置いて話をしているのかを考えると話の整理がつきやすいと思います。
[AARの現在の活動]
シリア難民支援
私たちの活動では、難民なのかは関係ありません。その人がそこにいて困っている状況にあるのであればその人が国際法に照らして難民なのかIDPなのかそれとも移民なのかは問題ありません。物資配布をしますと言ったら平等に配布します。難民の問題は世界各地で現在進行形で発生中です。シリア難民支援は10年くらい前からやっています。
最近シリアは情勢が変わりました。シリアは10年くらい内戦をしていて、国の半分くらいの人が国の外に出て難民になりました。アサド大統領と反アサド派の戦い。アサド大統領の後ろにはロシア、反アサド派の後ろにはアメリカという構図でやっていましたが、ロシアはいろいろ忙しく、アサド大統領は急に弱腰になって大統領職をほっぽり出してロシアに逃げました。反アサド派が政権の座について、これから新しいシリアを作っていくというスタートラインに立ったところ。ただ、新しいシリアがどんな国になるかはわからず、独裁的なところになるかあるいは、アフガニスタンみたいなねじ曲がったイスラム教の教えを押し付けるようなことをしないか、国際社会は固唾をのんで見守っています。一応、今の暫定的なリーダーはそういうことはしませんと言っているので各国は話し合いの姿勢を見せています。
AARもシリアの隣のトルコで活動をしていました。トルコは一番多くのシリア難民を受け入れた国で300万人以上受け入れました。トルコ政府は難民キャンプを何か所も運営してましたが、今の方針はもう十年たっているので、トルコで生活しているシリアの人たちはトルコ社会でちゃんと順応してほしいというのが基本方針になっています。トルコの学校に行ってくださいということです。でも、シリアの子どもたちはアラビア語なので急には無理、なので学校にアラビア語の先生を配置したり、トルコ政府もそれなりにいろいろ努力をして難民の人たちがトルコ社会にうまく軟着陸できるような方法で支援を行っています。
AARはシリア国内で国内避難民になっている人たちへの支援もほそぼそ続けていました。日本人はシリアに入っちゃいけないと言われていたので、現地で支援をしていた別のNGOと協力をして物資配布を中心にやっていました。今後シリアがどうなるかを見極めながら、シリアに戻ろうとする人も増えてくると思うので、われわれもこういった国内避難民への支援と合わせて戻ってくる人たちへのサポートも視野に入れて行きたいなと考えています。
ミャンマー避難民(ロヒンギャ)
アジアに目を向けると、ロヒンギャと呼ばれる人たちがいます。ミャンマーの西の方、西隣はバングラデシュですが、その国境付近に住んでいたベンガル系の少数民族の人たちが、自分たちを称してロヒンギャと呼んでいます。ミャンマーも多民族国家ですが、大半はビルマ系の人たち、いわゆる東南アジア系の顔だちをしていて、ミャンマー語、近縁の言葉。ところがロヒンギャと呼ばれる人たちは、顔がベンガル系、隣のバングラデシュの人たちにそっくり、どちらかというとインド的な顔立ちをしている。言葉もバングラデーション、バングラ語のなまったようなもので、宗教はイスラム教。ミャンマー国内でもずっと軋轢が絶えず、ひどい弾圧の歴史をもっている人たち。特に今、アウンサウン・スーチーさんが捕まって軍事政権になってからひどい弾圧があり、住んでいた村が一晩で焼き払われるというような無茶なことがありました。西隣のバングラデシュに大量のロヒンギャが流出して難民になっています。100万人くらい。ただ、バングラデシュにとっても、人種的には近いが、ウェルカムかというと全然そうではなく、バングラデシュ自体が大変貧しい国で、国としてもそういう人たちを受け入れる余力が非常に少ないということもあり、彼らはバングラデシュの中でも非常に制限された生活をしています。巨大難民キャンプのようなものがあり、基本的には、そこから一歩も出るなと言われています。我々もいろいろ支援をしたいのです、ロヒンギャの人たちを支援することについてはバングラデシュが非常に神経をとがらせています。つまり、バングラデシュ政府の立場は、はやくミャンマーに帰ってほしい。バングラデシュとミャンマーの政府間では帰還させるという合意だけは成立しています。ただ、ロヒンギャの人たちは全く戻る気はありません。ミャンマー政府の立場が全く変わっていないから。戻っても何もいいことはないと思っています。非常に窮屈な暮らしをしていますが、バングラデシュ側で生活しています。バングラデシュ政府から活動許可を得るのが非常に難しく、今は、現地団体でロヒンギャ支援をしているNGOを通じてほそぼそと女性と子どもにターゲットを絞った支援をつづけています。手に職をつけるようなことや女性と子どもが安心して時間を過ごせるような場所を運営したりしている。
アフリカ カクマ難民キャンプ支援
アフリカでも難民は絶えません。どうしてなんだろうというくらい絶えません。ケニアにあるカクマという町の近郊にある強大な難民キャンプ。UNHCRが運営しています。本当に巨大。人口の出入りは激しいですが、私が一度聞いた数字では17万人。17万人だとキャンプというイメージではありません。カクマ難民キャンプは歴史も古く、何十年もたっていてどんどん街化していっています。実際のカクマ難民キャンプの中にはショッピングストリート=商店街があります。学校、教会、モスクがあります。この中で経済が回っています。ここで生まれて育った人も多いです。ケニア政府は、去年?おととし?カクマ難民キャンプを閉鎖するとと言いましたが、閉鎖するって17万人どこに行くの?とみんな思ったのですが、ケニア政府も具体的に方針があったわけではなく、一応言ってみましたが、閉鎖するわけにもいかずいまだに存在しています。
AARはカクマ難民キャンプで助成金を獲得して中学校を建てました。「小学校じゃなくて中学校なんだ」と思うかもしれません。我々も最初は小学校をやりたかったので、UNHCRの人と会って「小学校を建てたい」と言ったら「小学校を建てたい団体は多くて間に合っている。中学校はいかがですか。」と言われました。
「小学校をやる団体は星の数ほどいるが、そのあとがいない。「中学校をやります」と言ってくれる団体が非常に少ない。中学校がないとどうなるか。小学校を出たあと、行くところがない。社会のなかでステップアップしていく道筋がこの難民キャンプにいる子どもたちは描けない。そこを何とかしてあげたい。AARさんには中学校をやってもらいたい」「そうですか、じゃあ頑張りましょう」と。助成金の審査でも「中等教育?初等教育じゃないのですか?」と聞かれ、先ほどの説明を何回もして助成金を取れて、現在は稼働しています。2000人くらいが在籍していて、ちゃんと給食も出しています。
現地から授業を受けている写真が送られてきて、どうみても中学生じゃないような子がいます。担当者に聞いたら、「いままで中学校がなかった。やっと通える学校ができたのですよ、彼らは必死なんです。ここを出れば、高校、次はその先の大学に行けるかもしれないし、それは無理でも少しでも教育を受けたということになれば、いい仕事、よりいい収入に繋がるかもしれないという思いがあるので。背水の陣、必死なんです」それを聞いて我々もそうかと思いました。
我々はカクマ難民キャンプの中でサッカー大会をやりました。「サッカー大会?何をお気楽な」と思いますよね。難民キャンプにはいろいろな国からいろいろな民族、いろいろな言語の子どもたちが集まってきます。アフリカは民族同士の対立が激しい場合も多いから大人同士は銃を向けあって脅しあっているような人たちもいます。我々はそういうところをちょっとでも変えたい。変えるためには、「平和は大事」というのも大事だが、実体験として一緒に何かする経験をそういう機会を持たせてあげたい。それにいいのはスポーツではないのか?サッカーだったらボール一個あればできるし、たいしてお金かからないし、ルールはみんな知っている。サッカー大会で一つのチームになって少なくとも大会の間は勝利を目指してみんなで頑張ろうというそういう経験を共有しているかしていないかこの差は大きいのではないかという説明をして、助成金を使いました。いろいろな民族の子どもたちをわざと混ぜてチームにしました。中には言葉が通じない子どもたちもいます。でもその子どもたちがサッカーという共通のスポーツを通じて何か問題が起きたときに銃を向けあうばかりが解決方法ではないよね、一緒に何かやれるよねということを身をもって体験する。という機会にしてほしいという願いを込めてサッカー大会を実施しました。スポーツは国際協力の手段として大きな意味を持っていると思います。
ウクライナ難民支援
ウクライナの主に東の方で戦争をやっているので、西の方に避難している人がたくさんいます。市民の方々、教会の方々、団体の方々が沢山を支援をしています。そういう人たちと連携してウクライナ国内での支援活動をやっています。防寒着などの支援物資を送ったりということを続けています。
余談ですが、最初のうちに縁があって連携したところが修道院でした。その修道院が避難民を受け入れて、食事と寝起きする場所を提供していたので、そこに必要な物資を届けていました。我々は特定非営利活動法人なので東京都庁に活動報告をしなくてはならないのですが、東京都の担当者が「修道院に?AARは宗教活動に支援したのですか?」みたいなことを言われました。修道院からは寄付したお金を何に使ったか綿密に帳簿をつけていたので、それを見せて納得してもらいました。
ウクライナはたくさんの人々がヨーロッパ側に避難して難民になっています。我々が支援しているのは西隣のモルドバという小さい国。人口が400万人くらいしかいない小さい国。でもいまだに10万人くらいのウクライナの人々が生活しています。ウクライナの難民の大きな特徴は、家族が離れ離れになっていることが多いことです。ウクライナの青年男性、18歳から60歳未満の青年男性は原則として国外に出てはいけないということになっています。国を守れということになっています。なので、難民で出てくるのが圧倒的にお母さんと子どもたちとおじいちゃん、おばあちゃんという組み合わせが多い。話を聞くと、お父さんとお兄ちゃんは国に残っている。なので、心配で心配で、中には精神的バランスを崩す方も多いです。モルドバは言葉が違います。ウクライナ語はロシア語に非常に近いが、モルドバで話されているのはルーマニア語。ルーマニア語はラテン系の言葉で、イタリア語スペイン語と近く、なので言葉もわかりません。非常に心細いので、我々はそういったお母さんたちが集える場所を作ろう、保育園プラスアルファみたいな感じです。子どもたちは遊び、お母さんたちは自国のお仲間たちとウクライナ語でいろいろ情報交換をしたり、励ましあったりできる。その中でカウンセリングを受けたほうがいいのではないかという人には協力関係を結んだモルドバのカウンセラーにカウンセリングを受けていただく。このような事業を続けています。
地雷・不発弾への対応
・地雷除去(専門団体と連携して実施)
・地雷の被害にあわないようにする教育
地雷に対する活動は主にアフガニスタンなどでやっていましたが、そこで関係のできた団体もあり、今後ウクライナで戦争が終わって、東へ戻っていく際には、当然地雷源がたくさん残っているはずなので、うっかり巻き込まれて死んだり、障害者になったりしないように教育する必要があります。埋まっている地雷を除去することと、地雷に気をつけることを伝えることはおいおいやっていく必要があるだろうと思っています。アフガニスタンで長年一緒にやっているイギリスの地雷除去専門のNGOとすでに話をしていて、ウクライナでも一緒にやりましょうと言っています。除去は非常に危険でトレーニングや機材が必要なので我々が直接タッチするのではなくイギリスの団体にその資金を提供しています。
日本の難民
日本に難民はいるのか?
AARは国内での難民支援活動はそんなに大規模にやっていないのであんまりかっこいいことは言えないのですが。
日本は1978年から2021年までの40年間で16,000人以上の「自分の国へ帰れない人たち」を受け入れてきました。日本はボートピープルの時代から、特にボートピープルと呼ばれる人たちに関しては特別枠を設けて、審査も軽めで受け入れてきました。今は、特別枠はなくなっています。ミャンマーやラオスやカンボジアの人たちも他の国の人たちと同じように審査を受けなくてはならないということになっています。40年で16,000人、多いといえば多いですが、ヨーロッパやアメリカは厳しくなっているとは言いつつも一年間で〇〇万人〇十万人という単位なのでやっていないわけではないが、胸張って言えるかな?という数字。ここはよくつっこまれるところです。難民申請した人が今年何人でした?うち認められた人が両手で数えられるくらいでした。日本政府は実に厳しいけしからんみたいな論調が非常に多い。厳しいというのは確かにその通り。ただ、本当に単に意地悪しているかっていうと、ばか正直に難民条約もしくはその拡張された定義に該当するのかというのを必死に裏を取ろうとしているということ。そこはとても律儀。もともと日本に行きたいという人がそんなにいないのも事実。日本がどんな国かは大体知っていて、全然違う言葉をしゃべって生活習慣もだいぶ違うみたい。かつ遠いというのもわかっているので、日本を希望しますという人は、何らかの日本との縁がある人が多い。日本に行ったことがあるとか。友達が日本に住んでいるとか、家族とか知人が日本に留学したことがある、仕事をしているとか、親しい日本人がいて日本に来たら面倒見てあげるよと言ってもらっているとか。
ウクライナやアフガニスタンから2000人以上は避難してきていまる。
その他にも外国から来た人が300万人以上暮らしていて、その大半は普通に仕事をしていて、ちゃんと税金も払っていて、我々の普段の暮らしはそういう人なしでは立ち行かない部分があります。コンビニで買うおにぎりを作ったりお弁当を詰めているのは外国籍の人。
日本にいるにせよ、アメリカやヨーロッパにいるにせよ、難民・避難民に関しては共通の問題を抱えています。一つは言葉。それから仕事。教育。これが三大問題。日本は言葉のハードルが高いです。ぱっと見では読めませんし、日本語が普通に読めるようになるのはすごく大変。ひらがな・カタカナだけならまだしも漢字の壁はものすごく高い。世界の言語で日本語だけ3種類も文字を使っているのは。言葉ができないとおのずとできる仕事は限られますし、子どもたちも学校に行ってもちんぷんかんぷん。
それ以上に、私が問題だとおもっているのは、地域社会との関係。地域社会との関係が非常に薄い人たちが多いんです。これも難民であるかどうかには関わらないです。留学で来て、そのまま日本で仕事をしていますという人でも、もう日本に十年以上暮らしていますみたいな人でも日本人でいろいろなことを相談できるお友達は1人もいません、みたいなことをよく話に聞きます。我々は「日本人じゃないよね。何語だろう?」みたいな感じで向こうは「日本語難しい」みたいな感じで遠慮しあってお互いにお見合い状態。そこに誤解が生じるわけです。
政府がんばれというのもそうだけど、政府がずっと面倒を見るわけにもいかない。難民を保護する義務は政府にあるが、在留資格を与えて、最後にはその人は地域社会に出てきて、皆さんのお隣に来るかもしれない。その人たちが言葉で困っている、仕事で困っている、教育で困っているという場合に、どれだけその人に支援の手を差し伸べられる仕組みがあるのかということが問題となってきます。我々に指が向けられているような気がする。NGOもっと頑張れ、もっとできることあるだろうと言われている気がします。国内の難民はAARの発端でした。日本に来た難民を支援するというところから始まりました。そこが分かれて、サポート21という小さな団体が同じビルの中にあって、そこが国内の難民として認められて日本で定住している人たちの支援をやっています。
でもAARもやらなくてだめだと、初期のころはウクライナから来た人たちに一時金を渡すことをやっていたが、これがなかなか続かない。最近は、アーシアンさんのようなところといろいろ話をして、その地域とのつながりを作る機会をどんどん作っていこうということになりました。刺繍教室、アフガニスタンの刺繍を教えますよと地域の方に声をかけやっています。アーシアンさんとやっているのは料理。食べるものはみな興味があるだろうということで。
実際に来た方の中で「初めてお母さんの顔を見ました。」という声がありました。今までその家を訪れても出てくるのはいつもお父さん、女性を外に出さない。これは問題だと考えられていますが、「お母さんがいるのはわかってたが、会ったこともなく、話したこともなかった。今回初めてお会いして、顔も分かって名前も分かって、どんな思いでるのかという話も聞けた。これからはお話しできますね。」という感想を聞いて、ああこれだ、これをやっていかないといけないんだと思いました。この輪をもっともっと広げていかないといけない。そうすれば、「あの人は得体のしれないどこか変な国から来たよくわからない人たち」ではなく、「料理教室で料理を一緒に作ったなんとかさん、なんとかちゃんのお母さん」というふうになると、全然見方が変わります。そういうことをアーシアンさんみたいなところと一緒に。なかなか助成金をとるのも難しいのですが、頑張って続けて行きたいと思っています。
質問
アフリカのカクマ難民キャンプは何か国くらいの人が、集まってきたのか、あるいは追い出されてくるのでしょうか。
答え
カクマ難民キャンプは世界最大と言われています。ウクライナ、シリアの難民とアフリカの難民を比べると大きな違いがあります。ウクライナ難民キャンプというのは聞いたことがありません。実際ウクライナ難民がギューッと大量に住んでいるところはありません。ヨーロッパ側、特にポーランド側に入るとそこはEUだから、自由に好きなところにどうぞで、各国は支援に前向きなのでいろいろなサポートもうけられるということで、みんなちりぢりばらばらにいろいろなところに行きます。シリアの人たちもそう。トルコ政府は最初難民キャンプを作っていたが、とてもじゃないけどみんなそこには入れない。だからみんなトルコの中でばらばらに暮らしている。支援する側からみるとどこにいるかわからない。
アフリカにはカクマ難民キャンプのようなキャンプがあり、みんなそこに集まってくる。逆に言うと地域社会に吸収する能力がほとんどない。そういうところに行かないとサポートしてもらえないのでみんなそこを目指すということが起きます。カクマ難民キャンプもスーダン、南スーダン、ウガンダ、コンゴ、ザイール、遠くはソマリアあたりから。遠路はるばる何百キロと歩いて。そして、同じ国、同じ言語の人たちとグループができる。情報交換もできるし、支援する側もやりやすい。そういった中でおのずとリーダー的な人ができてくる。支援する側もとりあえずリーダーの人にちゃんと話をしておけば話が伝わるということが期待できる。そういったことが難民キャンプで起きています。
質問
国際理解国際協力に興味がない人たちにどういうアプローチをしていくのがいいでしょう。
答え
いい質問ですね。私たちも常に悩んでいる所です。
ここに参加している方は、いわば意識高い系ですね。この人たちはお知らせをだせばそれなりに参加してくれるのでそれでいい。問題はその周辺の人たち。関心はあるんだけど周りからチラッチラッとこっちを見ているような人たち。あるいはその外側にいる全然関心のない人たちにどうやってこっちを向いてもらうか、あわよくばその人たちに支援の輪に入ってほしいと思っています。そういう人たちはこういう場には来ません。
一つはサッカー大会、お料理教室、刺繍教室です。「なんか変わった飯が食えるなら行こうかな」とか、ダンスショーでもいい。その中でもちろんお料理も楽しんでいただいた上で
「実はこのイベントの趣旨は・・・」と説明して、会場の片隅に写真をおいたり。「そんな問題もあるんだ」みたいに思ってもらえる。そこで「いろいろな参加の仕方がありますよ」と提案する。その中から「月千円のマンスリーサポーターやります」とか「一回だけボランティアやってみようかな」みたいに考える人も出てくる。そういうことを地道に続けていくことが大事だと考えています。こういった活動を報告していく場も必要ですが、周りの人たちを取り込むにはそういった工夫が必要かなと思っています。
最後にひとつだけお伝えしたいことがあります。
こういった日本語を母語としない人たちと一緒に何かやってくださいと言っても「えー、苦手なんです」という声非常に多いんです。でも全然気にすることはありません。日本語でオッケーです。気持ちは伝わります。「この人は自分に文句言おうとか咎めようとしているのではなく、自分のことを気にかけてくれてるんだ、なんか心配してくれてるんだ」というのは絶対伝わります。「それだけでも嬉しかった」という声は聞きますので日本語でオッケーですので話しかけてあげてください。