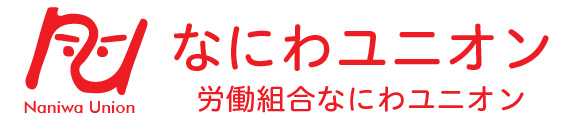ワオ・コーポレーション分会(能開センター・個別指導Axis)活動報告 ※2025.06.21組合定期大会:議案書より
 ワオ分会 “能開センター・個別指導Axis” 活動報告
ワオ分会 “能開センター・個別指導Axis” 活動報告
「労働組合なにわユニオン第30回定期大会」が大阪JAM西日本会館、大ホールで開催されました。当日は大阪府下のみならず、京都、滋賀からも支部・分会組合員、役員、特別執行委員、来賓の皆さんが参加され、第1号議案~第7号議案の発表と承認が行われました。第1号議案:活動経過報告では、各分会・支部より闘争状況が発表され、「ワオ・コーポレーション分会」も議案書を基に活動報告を行いました。
(2025.06.21組合定期大会:議案書より(一部改、追加)
①【最近の闘争報告】
1. 年俸更新に伴うベースアップ要求の団交実施
会社は要求書の本給6%以上引き上げ(全国の会社ベア基準)に対して、1号俸アップ、年額ベースで3万円アップを回答しましたが、査定での評価を持ち出したので、評価表の32項目について評価結果を組合へ提出する旨要求。2回目団交で、「C評価」項目の理由を説明させ、「上長がそう判断した」などと回答したので、具体的な理由説明を要求。評価項目には「自分がやるべきことを見極め、ものごとに進んで取り組み力」など、抽象的な内容が多くあり、これらに関して評価の判断理由を明確に説明させ、論理の整合性の破綻を指摘し、評価のテーブルでも6%以上アップを目指す。
2.育児休暇復帰後の勤務で育児・介護休業法に基づいた労働条件を勝ち取る!
当該組合員の2024.04.16から育児休業から職場復帰するに際して、育児・介護休業法23条による短時間勤務制度を要求。当該は育児など障壁があるのに、大阪へ来て対面参加を要求するなど、子育てという女性の大きな仕事を軽視しました。2024.04.11にZOOM形式で団交を行い、勤務時間は10:00~18:00(休憩1時間)で、希望通り深夜勤務を避けた時間帯で、子が3歳になってから、時短勤務する場合は、改めて申請する・・・など、会社は全面的に組合の要求をのみました。
3.65歳後の継続雇用拒否で会社を提訴(現在も裁判中)
分会長の65歳を過ぎて継続雇用の労働条件の確認のため、団交を行ったところ会社はこれを拒否したため、2023年9月6日に会社を提訴。提訴理由は「大阪本社では65歳を過ぎた者7人全員が継続雇用されたが、分会長だけがされなかった差別」で、内容は「期待権の侵害と不当労働行為」からなります。前者は、会議で「この部署は70歳まで雇用を考えている」という西澤代表発言が反故にされたこ。後者は、労働条件の変更は事前協議を行う協定を遵守しなかった「協定違反」、「継続雇用をしない明確な理由を説明しない、他」などです。
2025.05.23大阪高等裁判所での「一審判決を取り消す」「地裁へ差し戻す」の判決を受けて、2025年6月現在も係争中。裁判にあたり、35項目に及ぶ甲証(証拠)を提出しましたが、会社は3往復半に及ぶ答弁書、準備書面で全社員が共有しなければならない情報に関しても「不知」や「原告独自の見解」などを連発し、論理に基づいた反論をしません。差別は人権侵害であり、差別でなく区別であるなら、説明しなければなりませんが、会社は結論的に「差別とは無関係である」など主張するだけで、根拠理由を説明しません。レジティマシーと法の下の平等を信じます。
②【会社・労働問題に対する分会の姿勢】
ワオ分会は2004年に10%を超える減俸、ひいては退職強要という不当労働行為と闘うために立ち上げました。会社はコンプライアンス遵守など美辞麗句をクリシェ(常套句)として唱えていますが、白昼堂々と違法行為を行いました。これに対し、なにわユニオンの組織力で撤回させました。
この間、延べ8人の社員が分会員となり、団交では硬派のロジシャンとして「やられたら、やり返す」のスタンスをとってきました。その結果、「年休取得」「恣意的な人事考課」「パワハラ・セクハラ」「契約更新時の賃金引き下げ」などが全社的に是正されるようになってきました。このことは、労働組合が夜警警察として機能した大きな成果だと自負しています。
③【分会拡大に向けてSNSの活用と今後】
ここ数年、IT(Information Technology, IoT(Internet of Things) ,DX(Digital Transformation), SNS(Social Network Service)という言葉が氾濫してきました。これに対応し、組合ホームページにも分会の活動報告を6シリーズ掲載しました。「ワオ・コーポレーション + 組合」でググると、なにわユニオンホームページ、「ワオ分会」にヒットするようになりました。そして、これに呼応するようにワオ・コーポレーション分会への労働相談、職場の不満の声などがソーシャル・メディアを通じて、全国各地から連絡が来るようになりました。今後も、分会の活動報告を頻繁に発信し、全国47都道府県の社員・契約社員、教務スタッフ、講師にアピールしてゆき、安心して働ける職場つくりを行います。
以上