母なるナイル
まずは、地図を見ながら、ナイル河をさかのぼっていただきたい。
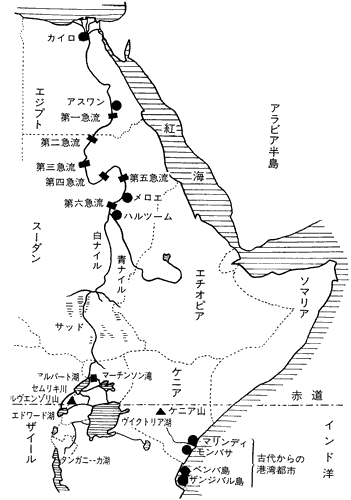
エジプト史学者のほとんどは、ナイル河中域、アスワンからハルツームまでの、6つの急流を、「瀑布」(カタラクト)として描きだした。そしてこの急流が、文化交流の非常なさまたげになったかのように、主張してきた。
しかし、大型で、吃水の深い遠洋航海船ならいざしらず、古代の葦舟をあやつる人びとにとって、岩場の急流は、何らの障害でもなかった。日光の鬼怒川下りの平底船の、軽快な航行に似たものであろう。難所では、岸に上がって、葦舟を肩にかつげばよい。
さらに、近代ヨーロッパの探検家たちは、冒険談の潤色によって、スーダン南部の湿原地帯を、ひとつの恐るべき魔境に仕立てあげた。これは日本の関東地方の総面積の二倍にも達する、広大な沼沢地だが、千葉県の水郷を、大きくしたようなものといえる。サッドという名でよばれているが、これもアラビア語で、単に浮草の意味でしかない。熱帯性の昆虫類や、ワニなどがいるのはたしかだが、土着のアフリカ人にとっては、決して、危険地帯ではなった。
実際にも、ヨーロッパの探検隊や侵入者が一番恐れたのは、「異教徒」の襲撃であった。そして、他ならぬ異教徒のアフリカ人は、この湿原に散在する島々を根拠地とし、牧畜・漁撈・農耕を営み、いくつかの王国を形成していた。浮草の間を自由自在に走りまわる葦舟は、古代の王国にとって、水の都ヴェネチアにおける、ゴンドラのごとき交通機関であったろう。
これらの王国の兵士たちが、近代の奴隷狩り商人や、デヴィッドソンの表現を借りれば、「すべて植民地侵略のつゆばらいであったヨーロッパ探検家」の侵入に対抗したのは、当然の行為であった。デヴィッドソンは、「1884年以前に東部および中部アフリカに入っていた約300名の宣教師のうち、アフリカ人に殺されたのがわかっているのは6名だけであり、この6名も勝手気ままに殺されたのではなかったようである。……生命への大きな危険のように見えたものは、ほとんどつねに途方もない誇張であった」、と書いている。そして、その当時のヨーロッパ諸国での旅行よりも、内陸アフリカでの旅の方が、はるかに安全だったとさえ断言している。
古代ローマの遠征軍が、このサッドにさえぎられて、引きかえしたことを、文化交流の障害の論拠とする学者もいる。しかし、古代ローマ軍得意のファランクス(重装密集歩兵槍隊)戦法や、ガリー船を漕ぎよせる海戦方式が、この地帯では全く通用しなくなることも、考えにいれなくてはなるまい。果てしなくひろがるサッドの存在は、遠征隊の指揮官にとって、都に引き返すための、絶好の口実になったであろう。彼らより5世紀も前の、ペルシャの遠征軍は、この手前の沙漠地帯で、糧食がつきて、撤退している。それよりは前進した、という理由で満足したのかもしれない。
さらに、サッドを越えて上流に向かうと、若干の急流はあるが、小舟艇の航行にはさしつかえない、アルバート湖から、本流のヴィクトリア・ナイルへ向えば、たしかに、マーチンソン滝がある。これがはじめての、本当の滝である。だが、ナイルのみなもとは、もうひとつある。アルバート湖から、ザイール(コンゴ)領内を通って、エドワード湖に通ずるセムリキ川の流れは、非常にゆるやかである。
セキリム川について、地理学者の小堀巌は、つぎのように描写している。
「この川は240キロメートルにわたってコンゴを通り、ゆるい水流となり、コンゴ、ウガンダの自然の国境となって東方向にすすみ、最期にはアルバート湖にはいる。水流は短いが、セキリム川の流域はたいへん色彩にとんでおり、アフリカにすんでいるすべての草原性の獣類――象、サイ、ライオン、カバ、カモシカなど――がすんでおり、また沼沢性の川岸にはほとんどすべての種類の水鳥がたわむれている。」(『ナイル河の文化』、P.36)
セキリム川の水源に当るエドワード湖は、魚類に富み、漁業はいまも、ウガンダ西部の重要産業にひとつである。湖のまわりには、間歇泉、火口湖群があり、観光・保養地ともなっている。
さて、セキリム川の東側には、月の山として古代から知られた、ルヴェンゾリ山がある。この山塊は、「地上で最も湿っぽい場所の一つで、年間360日は雨が降り、降雨量は5000ミリメートルに達する」(同前、P.32)。
ところが、今では頂上に雪をいただいた、この神秘な山塊が、かつては活火山で、紀元前6000年頃に、大爆発を起し、巨大なセキリム湖を埋めたてて、細い川にしてしまった、という意外な事実が明らかになった。しかも、その溶岩と火山灰の下には、何万年、何十万年となくつづいてきた、人類文化・文明の歴史が、ひっそりと埋れていた。
もちろん、イタリア半島のヴェスヴィウス火山の爆発によって埋められた、ポンペイー市のような状景が現われるはずはない。時代も違うし、とくに、風土が違う。アフリカでは、沙漠的気候(エジプトも含む)のところをのぞけば、土壁の木造の建物の方が、住む人の健康にも良い。つまり雨季には湿度があがる。この点は、梅雨季のある日本と同じだ。日本の建物が、しっくいぬりの壁、つまり土壁と、木や紙でつくられてきたのには、それなりの理由がある。
このへんの事情が、ヨーロッパ系の学者には、よく分らないらしく、アフリカで石造建築が発見されると大騒ぎするが、土造りの村落は軽視している。しかし、初期の人類文明は、うたがいもなく、最も気候のいい、アフリカ大陸の高原地帯に花咲いたのである。
では、ルヴェンゾリの火山灰の下からは、どんなものがでてきたのだろうか。それは、どういう歴史を物語っているのだろうか。