ミルラの秘蹟
フランス人のド・ボーが書いた『アフリカ探険五千年史』によると、紀元前2300年頃に死んだ古代エジプトの王女のミイラのそばから、アンチモンが発見された。この金属は鉄を触媒にして、輝安鉱という鉱石と一緒に熱すると、還元され、分離してくるものである。
アンチモンはすでに、紀元前4000年頃から、陶器の壷の装飾などに使われはじめていた。しかし、これもエジプトには鉱石がない。そこでド・ボーは、現在の分布からして、ローデシア産の可能性ありと指摘している。ローデシアは、すでに紹介したように、6万から7万にも達する鉱山遺跡があるところだ。
一方、同じローデシアから、古代エジプトの神、オシリスの小像が発見された。それには、紀元前15世紀のファラオ、トゥトモシス3世の碑銘がきざみこまれていた。また、ザイール(コンゴ)からも、紀元前7世紀と年代づけられる別のオシリス小像が発見された。ザイールのシャバ(カタンガ)州にも、やはり、数千ないし数万の鉱山遺跡がある。ここでは、現在でも、銅、ウラニウム鉱山などが開発されている。しかも、このシャバを中心にして、南はローデシアから、北はルワンダ [巨人の多いワッシ民族のいるところ] にかけては、つい最近まで、ルンダ帝国が勢威をほこっていた。このあたりに、中世の内陸貿易ルートが縦横につながっていた。
以上の事実、およびド・ボーの指摘から、どういう推測がなしうるだろうか。
中央アフリカの鍛冶師、または土師部の女たちは、早くから、鉄だけでなく、アンチモン、ベンガラその他の金属粉末をつくりだすことを、学んでいたのではないだろうか。そして、古代エジプト人は、そのような金属粉末または金属塊を、必要としたのではなかろうか。壁画の顔料や、陶器の模様として、いわば安全な場所にとじこめられたものは、現在につたわっている。しかし、もしかすると、軟鉄しかとれない鉄鉱石を利用し、中央アフリカから、ニッケル、コバルト、マンガンなどをとりよせて、特殊鋼をつくっていたのではないだろうか。壁画や壷の絵の彩色は、その余技として発達したものではないだろうか。
中央アフリカの土師部の女たちは、いろいろな場所の粘土から、さまざまな色彩の土器が出来あがることを知っていた。出来あがった鉄が固くなったり、軟かくなったり、時にはもろくなったりすることも知っていた。この条件の下でこそ、諸金属の分離、精錬がはじまったのではないだろうか。わたしは、この謎の鍵を、「ミルラ」に求める。ミルラは、一般に、神殿でつかう「没薬」として説明されているものである。
古代エジプトのファラオは、ミルラを求めて何度も南方に遠征隊を送っている。その記録は、第1王朝ないし第2王朝にはじまっている。第5王朝(前2563~2423)のサフラーは、南方の国プーントから、「8万枡のミルラ、6200斤のエレクトン(金と銀の合金)、2600斤の貴重木」(『アフリカ探検五千年史』、p.8)を持ち返ったことを、記録にとどめている。
このプーントが、どこにあった国かということは、ミルラとはなにか、ということともに、大変な謎である。従来のエジプト史・オリエント史学者は、このプーントの国を、現在のエチオピアの北、ソマリアの海岸地帯に求めつづけてきた。しかし、現在のソマリアやエチオピアからは、何らの考古学的証拠も発見されていない。一方、セネガル人のディオプは、例のロ-デシアで発見されたオシリス神像と、エジプトの壁画にのこるプーントの王族の姿 [次の写真。第六章の扉絵と同じもの] 、風俗を根拠に、プーントはローデシア近辺にちがいないと主張している。

エジプトの壁画にのこるプーントの王族の姿(『黒色人文化の先行性』より)
わたしはまず、ディオプの主張にほぼ賛成であるといっておこう。そして、ミルラをどう解釈するか、という問題を先に片づけておきたい。
ミルラは、神殿でつかわれたとされている。では、神殿ではだれが、何をしていたのだろうか。「8万析」ものミルラは、線香のように燃やされていたのであろうか。
ところが、あらゆる学者は、古代の金属精錬が神殿で、神官によって行なわれたと主張している。わたしはこれに、巫女の役割を加える。わたしの考えでは、巫女そのものも、中央アフリカの鉄鍛冶師の一族の出身であった。彼女たちは、金属精錬の秘法を守っていた。ミルラとして総称されているものの中には、何種類もの稀少金属、重金属が含まれていた。巫女たちは秘法を知り、奇蹟を行なうものとして、あがめられていた。
さて、英語で奇蹟のことをミラクルというが、これはラテン語のミラクルムに発する。わたしはこれを、かりに(正確にはたどりにくいので)、ミルラ・ケムと解釈する。ケムは化学、ケミストリーの語源である。つまり、ミルラをつかった冶金化学が、奇蹟または秘蹟と考えられたわけだ。ラテン語の動詞、ミロールは、それゆえ、「驚嘆する」、「崇拝する」、という意味を持っている。また、英語で金属の総称となっているメタルは、ギリシャ語に由来している。ギリシャ語でメターラは、金と銀の鉱山の意味であるが、この語根を持つ単語の中には、粗鉱という名詞であるとか、変えるという動詞であるとか、金属精錬を意味する単語が沢山ある。このメターラも、ミルラの変化にちがいない。
ギリシャ人やローマ人は、エジプトを征服する以前に、金属類の輸入者であった。彼らの金属や化学に関する単語は、ほとんど古代エジプト語に由来している。これだけでも、ミルラの正体については、充分な証明になるだろう。
しかし、さらに面白いことがある。ド・ボーの記述によると、ミルラは、オーともよばれていた。ギリシャ語では、鉄をオラオーといった。オーと、オラオーとは、つながりがある。そしてこの系列の単語は、英語でまた、オーとなり、鉱石、粗鉱の意となっている。わたしは、普通の鉄鉱石に、ミルラ、つまり、重金属類を加えて特殊鋼をつくっていたのだと考えるから、言葉としてのミルラとオーの歴史的なつながりにも、大いに惹かれる。
さて、プーントの位置の問題に戻ってみよう。今度は、他の要素も加味して考えたい。
紀元前2300年頃、古代エジプトの貴族ハルクーフが、ナイル河上流に、2回の旅をした。これは現代風にいえば、スパイとして調査活動を行なったのである。そして、4回の軍事的遠征を成功させた。旅については、最初は7ケ月で帰ってきたことを誇っており、2回目は8ケ月かかっている。相当に遠くまでいったことになる。
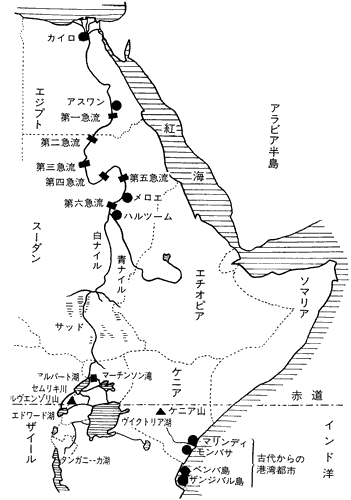
まずハルクーフは、「精霊の国」から小人をつれてかえった。そしてこの小人は、かつて「宝物係りのブールデッドがプーントから連れて帰った小人とおなじような踊る小人の神様」であった。つまり、ハルクーフより前に、「宝物係りのブールデッド 」が、「プーント」に行ったのであり、そこには、「小人」がいたのである。ハルクーフも、間違いなしに、プーントの近くにいっている。中央アフリカに住む現在のバトワ民族には、毎晩、焚き火を囲んで踊り、歌う習慣がある。非常に踊りが巧みであることについては、いろいろな証言もあり、どの学者も、この「小人の神様」を、バトワ民族と結びつけている。
ところが、現在のソマリア周辺には、バトワ民族に類する背の低い集団は、まったくいない。そこでプーントの国をソマリアに設定する歴史学者に呼応して、ヨーロッパ系の人類学者は、昔はいたのかもしれない、そういう伝説もあるから、などといっている。しかし、巨人伝説と同様に、小人の伝説を持たない民族というのは、さがす方がむずかしいぐらいである。このような根拠にもとづく学説は、まったく、砂上の楼閤に等しい。むしろわたしの考えでは、小人や巨人(ワッシ民族が最大の候補)の伝説をもっている民族は、中央アフリカに出発点をもつ人々を加えているのだ。現在のバトワ民族の分布から素直に解釈して、プーントの国、または精霊の国は、ザイール盆地周辺にあった、と仮定するのが、本筋である。
ついで、ハルクーフは、「精霊の国」またはプーントの国から、2回にわたって雄ウシを持ち返ったことを、碑銘にとどめている。自分の墓の碑銘文に記すぐらいだから、これは大事なことなのである。しかも、この「雄ウシ」の位置づけについては、もっと他にも材料がある。
紀元前15世紀、トウトモーシス3世は、やはり、ミルラとともに、プーントの国から遠征隊が雄ウシ305頭を持ち帰ったこと、その後、南方の征服地から雄ウシ60頭を献上されたことなどを、神殿に記録している。
わたしは、この雄ウシ、つまり種オスの問題を、すでに予告しておいた。これは、中央アフリカのオオツノウシの系統以外の、なにものでもありえない。そうでなければ、何を苦労して遠征隊が大量のウシの群れをつれ帰り、しかも、神殿に報告したりするであろうか。逆に、オリエントやインドから牛を輸入した記録はどこにも見当らない。
この記録はそれゆえ、同時に2つのことを証明している。第一には、家畜ウシまたは聖牛の起源は中央アフリカにあることであり、第二には、プーントの国は中央アフリカにあったということである。これを否定する学者には、はっきりした反証を提出してもらう必要があるだろう。
ところで、すべての本や辞典には、ミルラは植物からとる樹脂であるとか、胃腸薬であるとか書いてある。この説明もしなくてはなるまい。
まず、貴重なミルラが、本当に植物からとれるものだったら、古代エジプト人は万難を排して、その植物の栽培をしたであろう。なにも、大遠征隊を送る必要はない。
わたしの考えでは、古代エジプトの支配階級は、当然、ミルラの秘密をかくしていた。もしかすると、神官と巫女だけの秘密になっていたのかもしれない。そして、神殿にかかげた壁画にさえ、ミルラがとれる樹木の絵をかきこませた。それほど大事な秘密だったのである。彼らの権力は、ミルラによる金属精錬、特殊合金鋼の生産能力にかかっていた。
だが、ギリシャ人やローマ人の技術者は、ミルラの秘蹟を見破ってしまった。そして、メタルとか、ミネラルとかいう、鉱物のよび名をつくりだした。
ところが、近代の学者は、プーントの国を神秘化してしまったので、ミルラそのものが、どんなものだったのかを考えようともしなかった。彼らは、再び、古代エジプト人にだまされたのだ。
最後に、プーントの位置のきめ方について、もっとも肝心なのは、その名称である。この名称は、すくなくとも1500年間、全くかわっていない。そして、プーントに類似する名前の国は、ソマリア近辺には全くない。
たしかに、地名はよくかわる。ところが、なかなか変化しにくい単語というものもある。それは人間自身のよび名だ。この「人間」という単語の系列は、どの言語族でも、明瞭なつながりを示す。そして、中央アフリカから熱帯降雨林にかけての広大な地方で、人々は、自分たちのことをバントゥとよんでいる。ここからの変化、またはエジプト訛りへの変化は、ブーントを経て、プーントである。謎の古代国家、あらゆるエジプト史学者、オリエント史学者のあこがれの国、プーントは、バントゥの国にほかならない。
「バ」は複数形の接頭辞、「ントゥ」は力を意味する。つまり、バントゥの国とは、力ある人々の国なのだ。しかも、バントゥの思想体系 [終章:「王国の哲学」で詳述] においては、その力は人間だけにあたえられたものであり、人間だけがその力を用いて、植物・動物・鉱物の中にひそむ「凍った力」を引きだすことができると規定されている。
思想は決して、頭の中から生れてくるものではない。ミルラを用いた金属精錬を、ひとつの秘蹟としてしか理解できなかった古代エジプト人の思想と、このバントゥの哲学の持主たちの思想との相異は、何を意味するのであろうか。わたしは、この謎を、最後 [終章:「王国の哲学」] にのこしておきたい。わたしの考えをのべるためには、まだまだ材料が不足している。
まず、バントゥの本拠地、アフリカ大陸の周辺に眼をむけてみよう。従来の学者たちは、つねにアフリカ大陸への、人類そのもの、そして文化・文明の外来起源説を、主張しつづけてきた。しかしその逆に、アフリカ大陸に、最初の農耕・牧畜・金属文化が発生したとすれば、それは必ずや、外側にひろがったことであろう。その痕跡は、果してとどめられているだろうか。