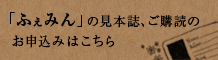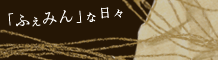- HOME
- >
- インタビュー
インタビュー
アジアを描く画家
富山 妙子さん
- 2009.12.15
- 聞き手:栗原順子
- 撮 影:落合由利子

表現することがやっと自由になった
今年の夏、新潟・越後妻有地域の廃校になった小学校で「アジアを抱いて 富山妙子の全仕事展」が開催された。国際的な「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」でのメーンイベント。炭鉱、韓国、戦争責任などをテーマとした12シリーズ、200余点の絵画作品などが展示された。
富山さんは、昨年から準備に追われ、その間に自伝と画集を出版した。米寿とは思えないほどの精力的な仕事ぶりだ。
富山さんは、大正デモクラシーの新しい風が吹いていた神戸で生まれた。10歳の時、父親の仕事の都合で満州に渡る。東京の美術学校に入学するまでの6年間をこの地で過ごした。
「満州」で見た光景は「画家となったわたしの原風景」と表現する。日本の植民地であった地での生活は、多感な少女の心を揺さぶった。
女学生になった時、西洋近代アートに感動して画家になろうと決意。しかし、戦争は年ごとに拡大し、ハルビンの女学校では、軍国教育のもと、朝鮮人生徒には創氏改名が強制された。それを拒む級友の悲しみが痛いほど伝わってきた。
極寒の冬の朝、登校中に凍死体に出合う。路上にうずくまる難民の親子、幼い浮浪児の群れ。日本の警官に泥靴で蹴られる苦力(クーリー)(港湾労働者)の姿…。戦争とともに知る植民地の悲惨さが胸に刻みつけられた。
「でも、私の頭は画家になりたい夢でいっぱいでした」
「この時代が出発点」と語る富山さんは、植民地主義を嫌悪し、贖罪の気持ちを抱きながら、日本の戦争責任を問い続ける。
女が画家になるのは難しい時代だった。「大正デモクラシーの息吹を知っている母親は、ひとり娘の私が画家になるための応援団になってくれました」
だが、敗戦で生活は一変。ハルビンにいた父親はソビエト軍に抑留され、難民になって帰国。富山さんは、芸術家同士の結婚が破綻し、2人の幼い子を抱えて飢餓の時代を生きた。
「苦しみは私を鍛えてくれたのでしょう。美術への考えも変わりました。1949年、中国革命が成功、歴史は変わると思いました。私はアジアの視座に立って、現実に根を下ろした絵を描こうと、鉱山や炭鉱をテーマに画家として出発しました」
戦後の米ソ対立の冷戦の中で、日本の美術は抽象画と純芸術(ファインアート)が主流となり、政治的な主張は排除されていく。富山さんは、美術界の異端となった。
60年代は、ラテンアメリカ、中央アジア、第三世界を題材に、70年代からは、痛烈な政治批判の詩を発表して逮捕された金芝河や、日本軍「慰安婦」などをテーマに描いてきた。
とみやま たえこ
1921年兵庫県生まれ。画家。戦後、炭鉱、韓国などをテーマに制作。「火種工房」を主宰し、映像作品も制作。著書に『アジアを抱く―画家人生 記憶と夢』(岩波書店)、画集『蛭子と傀儡子 旅芸人の物語』(現代企画室)ほか多数。- 【 新聞代 】(送料込み)
- 1カ月750円、3カ月2,250円
- 6カ月4,500円、1年9,000円
- 【 振込先 】
- 郵便振替:00180-6-196455
- 加入者名:婦人民主クラブ