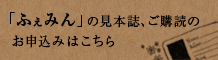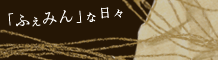- HOME
- >
- インタビュー
インタビュー
『エレーヌ・ベールの日記』の訳者
飛幡祐規さん
- 2010.12.15
- 聞き手:竹内絢
- 撮 影:落合由利子

思考停止はファシズムにつながる
日記を残したエレーヌ・ベールは、1942年当時21歳。裕福な家庭に生まれ育ち、ソルボンヌ大学の修士課程で学んでいた。日記は、42年4月から、ナチスに捕まる44年2月まで綴られている。日記を書き始めたころからユダヤ人迫害がひどくなり、42年6月には父親が逮捕されてしまう。彼女は、迫害を受け家族を失ったユダヤ系の子どもたちの世話をするなどの活動をしながらパリにとどまり続け、迫害、差別、戦争、宗教、人間についての考察を深めていく。
飛幡さんが感銘を受けたのは、エレーヌの「魂の美しさ」だ。ゆたかな感受性と冷静な論理性を持ち合わせ、全身全霊で生きようとするエレーヌ。ナチスに捕まるかもしれないという不安よりも、ユダヤ系でない人の無理解に苦しみ、多くの人は身近な人の不幸にしか心動かされない、ということに苦悩する。
「他者への真の共感とはなんだろうか。連帯感、友愛というものについての、この普遍的な問いかけに、深く心を揺さぶられました」
日本でもウーマンリブ(フェミニズム)が盛り上がってきたころ、高校生だった飛幡さんは『第二の性』を読み、「いつも思っていたことだ」と感激した。上級生の闘争に感化されたこともあり、「家庭科粉砕」(男女共修)のため討論会を開き、沖縄返還に先立つ集会で不当逮捕されたこともあった。 次第に、クラスの中では浮いた存在となり、教員からは目をつけられるように。2年生でフランス語を選択したが、文法ばかりでつまらないと語学学校の「アテネ・フランセ」に通い始めた。高校卒業後はフランスの大学に進もうと決めた。父親や親戚からは大反対されたが母親が周りを説得してくれた。 「移民の国フランスで暮らしていると、日本がいかに他者と交わらず、付き合い下手か…。90年代、国際化がいわれるようになったので、海外からの発信に興味を持つ人が増えるだろう」と、文章を書き始めた。
たかはた ゆうき
1956年東京都生まれ。文筆家、翻訳家。74年にフランスに渡り、パリ第三・第五大学で文化人類学などを学ぶ。著書に『それでも住みたいフランス』(新潮社)、訳書に『大西洋の海草のように』(河出書房新社)など多数。- 【 新聞代 】(送料込み)
- 1カ月750円、3カ月2,250円
- 6カ月4,500円、1年9,000円
- 【 振込先 】
- 郵便振替:00180-6-196455
- 加入者名:婦人民主クラブ