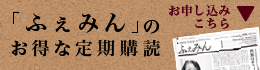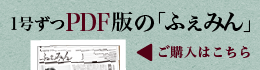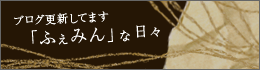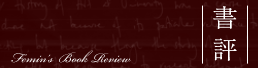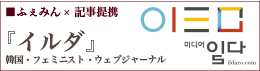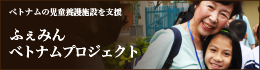- HOME
- >
- インタビュー
インタビュー
『流れゆく 遠い道』『森、すきま』監督
崔藝隣さん
- 2026.2.5
- 聞き手…中村富美子
- 撮影…宇井眞紀子

(c)宇井眞紀子
映画と通訳と社会運動で日韓を結ぶ
日本に来て3年。崔藝隣さんは、出会いに導かれるように短編映画2本を仕上げた。植民地主義という重いテーマに、日韓の市民社会の闘いを重ね、感情豊かに詩的に表現したその作品は、短編にもこんな力があるのかと再認識させる。 心のひだまですくいとる巧みな日本語を操る崔さんに、日本との関わりから聞いた。
「中学の放課後授業で第2外国語として学び始め、高校1年の時、同世代の日本人と初めて交流したんです」 日韓関係はこじれていたが、友人になれた。それが民間交流の仕事をめざすきっかけになり、大学では分野横断的に日本研究を行える日本言語文明を専攻し、様々な学生交流にも参加した。
「ところがそうした交流の場では歴史がタブー視され、韓国側が気を使って避けたり、主催側に事前に釘を刺されたり。一定以上は踏み込めない関係がもどかしかった」 その焦燥を共有する日本の学生に出会えた時はうれしかった。彼女もK‐POPへの関心から先に進まない日本の状況にもやもやしていた。
しかし2017年に革新派の政権に変わると、日本のメディアでは「反日政権」が連呼され、書店には嫌韓本がずらり。その時期、日本に出かけると、書店にいるだけで怖かった。日本語を学んだことを後悔し心が折れた。 権威のための言葉を並べ、感情や感覚などは非論理的と見下すような学界にも馴染めなかった。 もう日本語は卒業しよう。気持ちを切り替えて、複数専攻の美術に軸足を移すと、芸術が心に響き、救われた。 「じつは藝隣の名も、『いつも芸術が隣にあり、芸術を通して隣人が増えるように』と親がつけてくれた名です」
続きは本紙で...チェ イェリン
韓国・ソウル生まれ。ドキュメンタリー監督、通訳者、アクティビスト。フェミニズムの観点から歴史と記憶を現在につなぐ。『流れゆく 遠い道』(23)、『森、すきま』(25)は日韓の映画祭で上映ほか、各地で自主上映中。- 【 新聞代 】(送料込み)
- 1カ月800円、3カ月2400円
- 6カ月4800円、1年9600円
- 【 振込先 】
- 郵便振替:00180-6-196455
- 加入者名:一般社団法人婦人民主クラブ