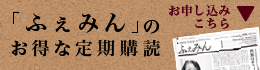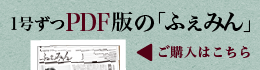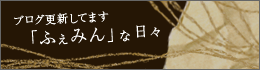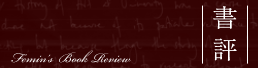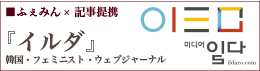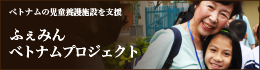その〈男らしさ〉はどこからきたの? 広告で読み解く「デキる男」の現在地
小林美香 著
|
|
その〈男らしさ〉はどこからきたの? 広告で読み解く「デキる男」の現在地
|
|
|
広告と言えば女性差別的表現が「炎上」することがあるが、男性の表現方法は話題にならない。しかし広告は「男らしい」「デキる男」で溢れている。本書は、広告の中で「男らしさ」がどう表現されているかを観察・分析し、内面化されたジェンダー規範をあぶり出す。
著者は、広告を「背景高層ビルおじさん」「おじさんだけで完結する世界」等24のカテゴリーに分類した上で、ドリンク類、スーツとパンツ、メンズ美容、選挙ポスターが拡散する「男らしさ」を解体。「デキる男」とは、仕事で有能で、異性愛規範を前提として女性(ただし美人)にモテる男。近年男性もスキンケアやメイクをし、ジェンダーレスな面もある一方、「身だしなみを整える」という新たな「男らしさ」にアップデートされるという指摘に唸った。
こんなに家父長的表現にさらされてきたかと驚くが、終章で教育・医療分野の識者との対談では「男らしさ」解体のヒントが。選挙ポスターを見るときのお供にも。(儷)

「音」の戦争と日本近代 戦時下の日常で音楽はどう鳴り響いたのか
戸ノ下達也 編著
|
- 「音」の戦争と日本近代 戦時下の日常で音楽はどう鳴り響いたのか
- 戸ノ下達也 編著
- 青弓社3600円+10%
|
|
|
日本における西洋音楽は、儀礼のための軍楽、キリスト教の讃美歌、学校教育での唱歌によって普及した。戦争への道を進む中、讃美歌の御国は皇国(どちらも“みくに”)と等化され、郷土を歌う唱歌は国家主義に、国民は特定の方向へと誘導されていく。日中戦争以降、レコード売り上げの多くは軍歌だった。音楽は、まさに軍需品として存在したのである。
こうした戦前・戦中の流れは、敗戦によって絶たれたかのように見えるが、唱歌は今なお音楽教材として残っているし、海外からの訪問賓客を接遇する際の奏楽は、かつては陸軍軍楽隊が、今日では陸上自衛隊中央音楽隊が担う。海上自衛隊の儀礼曲も、10曲のうち6曲は旧海軍のものを継承している。
あの戦争から80年、音楽自体に意思はなくとも、それを作った者、広めようとする者には明確な目的意識がある。戦争の被害と加害を語り継ぐためにも、本書は音楽のあり方を考え続けることの重要性を訴えている。(た)

その暴力は連鎖する 戦争から家庭、そして子どもへ
いのうえせつこ 著
|
- その暴力は連鎖する 戦争から家庭、そして子どもへ
- いのうえせつこ 著
- 発行 花伝社 発売 共栄書房1500円+10%
|
|
|
著者は、子どもや高齢者への虐待、女性と性、女性と新興宗教などをテーマに、長く取材をしてきた。地道な取材に裏打ちされた事実から、人の行動や思考に社会的規範や時代状況が影響を及ぼし、暴力が連鎖していくことを説く。
本書のテーマは著者が地域のNGO活動で知った児童虐待の原因を探りだしたことから始まった。暴力連鎖の要因の一つは家父長制だ。“夫に従うべき”=夫婦間レイプから、予期せぬ妊娠が児童虐待へ結びつく例が多いこと。もう一つは戦争と暴力の連続性だ。強固な性別役割分業規範(男は戦い、女は銃後)の下、戦争は暴力を肯定し、暴力が家庭内に持ち込まれ、どう影響していくのかを明らかに。
女性たちの孤独感と新興宗教への傾倒、児童虐待から高齢者虐待への連続性、戦争中の国策に沿った宗教移民の実態についてなど、関心が深まった。性は家父長制に利用され、支配の道具であることから、どう解放していくかが私たちの課題だ。(げ)