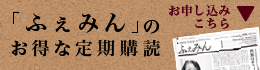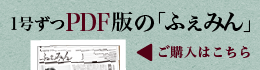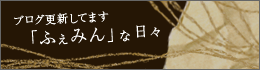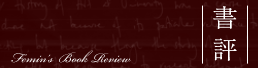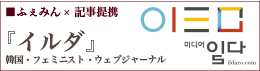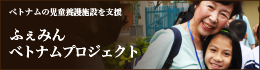- HOME
- >
- インタビュー
インタビュー
NPO法人「松代大本営平和祈念館」理事
北原高子さん
- 2025.7.25
- 聞き手・撮影…栗原順子

(c)栗原順子
戦争遺跡は平和の語り部
ヘルメットをかぶり、ガイドの北原高子さんと入り口から壕に入る。空気が冷たく、かすかな照明の中、ごつごつした岩肌が見えた。この壕は「松代大本営」と呼ばれる戦跡。アジア太平洋戦争末期、皇居にあった大本営(日本軍最高統帥機関)を移すため、「松代倉庫工事」と称して、極秘に松代町(現・長野市)に建設した地下壕の跡だ。
象山地下壕は行政の一部、舞鶴山は大本営と仮皇居、皆神山は食糧庫の予定だった。1944年秋に工事が始まり、7~8割完成していたが、使用されることなく敗戦。総延長十数キロに及ぶ地下壕の一部が見学できる。 松代大本営の記録と記憶を遺す資料館を創ろうと、2003年に設立されたのが「松代大本営平和祈念館」(以下、祈念館)。学習会や戦跡案内なども行う。北原さんは、長く同館の事務局長を務め、運動を進めてきた。
定年まで高校の国語と音楽の教員を務め、学校では人権や平和問題の担当が多く、研究会などの活動に勤しんだ。 「生徒と一緒に地域の戦跡を調べたり、戦争体験者の話を聞きに行ったりしました。松代の地下壕も、教員仲間で研究している人が多く、地元の高校生たちも保存運動を始め、1986年、祈念館の前身である『松代大本営の保存をすすめる会』が設立され、私も仲間に入りました」
ガイドをする上で大事な視点がある。朝鮮半島からの強制動員を含む6500人ほどの朝鮮人が危険な仕事に従事させられていたこと。地元の人たちは黙って協力させられて理不尽を強いられ、「慰安所」までつくらされたこと。そして、松代大本営を完成させるなどの本土決戦準備のため、沖縄では時間稼ぎのための地上戦で多くの島民が犠牲になり、今もなお苦しみが続いていること、などだ。 「沖縄の犠牲と松代大本営の構築は、戦争末期、鏡の裏表のように深くかかわって進行していました」
続きは本紙で...きたはら たかこ
1942年、長野県生まれ。教員時代から、「松代大本営の保存をすすめる会」に関わり、現在、「松代大本営平和祈念館」理事。『本土決戦と外国人強制労働 長野県で働かされた朝鮮人・中国人・連合国捕虜』(高文研)など執筆。- 【 新聞代 】(送料込み)
- 1カ月800円、3カ月2400円
- 6カ月4800円、1年9600円
- 【 振込先 】
- 郵便振替:00180-6-196455
- 加入者名:一般社団法人婦人民主クラブ