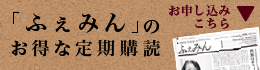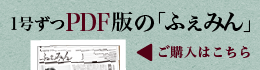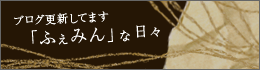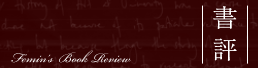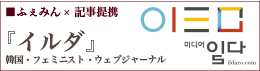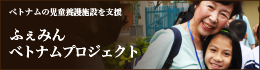- HOME
- >
- インタビュー
インタビュー
映画配給団体Shkran代表
二口愛莉さん
- 2025.7.15
- 聞き手…中村富美子
- 撮影…宇井眞紀子

(c)宇井眞紀子
ガザの現状を可能にする、この世界
映画『ガザ=ストロフ-パレスチナの吟-』の上映運動が今、静かな広がりを見せている。タイトルには1948年のイスラエル建国以来ずっとカタストロフ(大惨事)を生きてきたという含意がある。本作品の上映のために日本で配給団体Shkranを立ち上げた二口愛莉さんに、経緯から聞いた。
「共同監督の一人であるケリディン(・マブルーク)はパリで知り合った友人で、2023年10月7日のハマスによる越境攻撃から10日後、この映画の視聴リンクが送られてきたんです。『この映画を見る意義が今もあるなんて』と一言添えられて」 なるほど撮影は10年以上も前。08年末から22日間に及んだイスラエル軍によるガザへの大規模侵攻を巡る記録映画だった。
「停戦の翌日、外国人記者もまだ入れない中、監督2人は医者と偽って潜入したそうです。そしてパレスチナ人権センターの2人を案内役にガザの人々に会い、話を聞いて回った」
二口さんが映画を見ると、ガザの現在を可能にしている世界の構造がよくわかり、今見る意義を感じた。個人的な体験も関係していたかもしれない。 「大学では仏語を専攻し、卒業後に渡仏し独学で写真を始めました。9年弱住んだパリでは、仏語を通じて仏語だけではない世界にも開かれました。移民社会を知り、マグレブ(北西アフリカ)を旅する機会にも恵まれ、そこで触れたアラブ・ムスリム文化の英知が、映画の中の人々に感じられたんです」
映画配給も字幕翻訳も未知の世界だったが、「多くの人に観てほしい。とにかく上映することが大事と考え、友人3人で配給の有志団体を立ち上げ、経費を引いてプラスになったらガザに寄付しようということで始めました」
続きは本紙で...ふたくち あいり
東京都生まれ。2023年末、『ガザ=ストロフ?パレスチナの吟?』の配給団体Shkranを結成。「Education 4 Gaza /ガザに教育を」の寄付支援は今後も継続的に行う。7月25日(金)シアターキノ(札幌)にて上映+トーク。- 【 新聞代 】(送料込み)
- 1カ月800円、3カ月2400円
- 6カ月4800円、1年9600円
- 【 振込先 】
- 郵便振替:00180-6-196455
- 加入者名:一般社団法人婦人民主クラブ