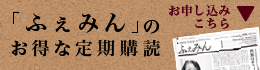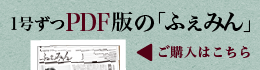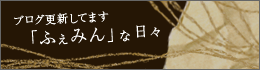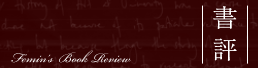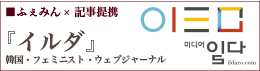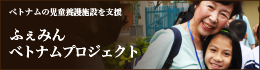- HOME
- >
- インタビュー
インタビュー
対馬丸記念館の新館長
平良次子さん
- 2024.10.5
- 聞き手・撮影…謝花直美

(c)謝花直美
思い重ねる場から新たな継承を
那覇市若狭の緑をたたえた公園を背に、対馬丸記念館が静かに佇む。当時の船の構造を再現した館。船底にあたる1階展示室へ降りると、いくつもの子どもらの遺影が来館者を見詰める。今年も、遺族から9歳の子を含む8人の写真が託された。 1944年8月、沖縄からの疎開者を乗せた対馬丸が鹿児島県悪石島沖で米潜水艦の攻撃を受け、1484人(判明分)が死亡した。「対馬丸事件」から今年80年となる。
事件の悲劇、遺族たちと元学童たちの思いを伝える記念館の新館長に戦後世代の平良次子さんが今年就任した。「館の理事を7年してきたが、館長を打診されると思ってもみなかった」。前職は南風原文化センター館長。地域の人々をつなぎ、文化と歴史を発信する理念に惹かれ、設立メンバーとして働き始めた。企画に留まらず地域の人材を育て、3年間館長も務め退職した。母は対馬丸の証言を続けた故・平良啓子さんだ。 沖縄の戦場化に備え、第32軍の提案で政府は10万人の九州・台湾疎開を決定した。計画開始直後の8月、対馬丸事件は起きた。死者の半数以上が子どもで沖縄戦の悲劇の象徴となった。
97年、海底の対馬丸が確認された。遺族は引き揚げを求めたがかなわなかった。政府は資料館整備を打ち出し、対馬丸記念会運営「対馬丸記念館」が2004年開館した。通算来館者は35万人に達した。 事件から80年目の今年。遺族や関係者400人余が参加した慰霊祭、遭難者を助けた鹿児島県宇検村の人々と沖縄の子らの交流、体験者講話、亡くなった学童の那覇市内の母校へ2基目となるモニュメント建設―。次子さんは職員たちと走り続けた。
母・啓子さんは、学校で教え、同世代の教師とともに復帰運動を闘った。家庭では子どもの服を作ったり編み物をしたり。日々忙しい啓子さんにはもう一つの活動があった。「ツシママル」という言葉。
続きは本紙で...たいら つぎこ
1962年、沖縄県大宜味村喜如嘉生まれ。大学卒業後、米国留学を経て、87年から南風原町立の南風原文化センターに勤務。地域から平和と文化を紡ぐ活動を支え、2023年までの3年間、2代目館長を務めた。24年に対馬丸記念館館長就任。- 【 新聞代 】(送料込み)
- 1カ月800円、3カ月2400円
- 6カ月4800円、1年9600円
- 【 振込先 】
- 郵便振替:00180-6-196455
- 加入者名:一般社団法人婦人民主クラブ