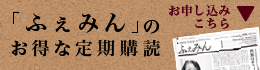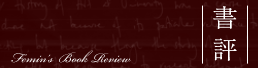- HOME
- >
- インタビュー
インタビュー
沖縄の「女性記者」として半世紀
山城紀子さん
- 2024.5.15
- 聞き手…飯田千鶴
- 提供…大城弘明

(c)大城弘明
マイノリティーの視点にこだわって
山城紀子さんは「女性記者」として、沖縄の「復帰」直後からの半世紀を駆け抜けてきた。30年勤めた沖縄タイムスを2004年に退社してからは、福祉やジェンダーを主なテーマに取材。現在は、壮絶な地上戦が行われて住民の4人に1人が犠牲になった沖縄戦や、米軍占領下におけるマイノリティーの状況をまとめたいと考える。 例えば、ハンセン病。医療や衛生、免疫力、栄養状態が向上すれば保菌者がいても感染しない。だが、正反対の状況である戦争後、沖縄で感染者が急増する。また、1943年にできた盲学校は沖縄戦で閉校。普通の学校は再建が進むのに、盲学校は6年余の空白が生じた。 「問題は深刻なのに、見えなくされている」
社会的弱者に共感して取材するマイノリティーの視点を持つ「女性記者」。その視点の芽生えは、74年の入社に遡る。現在も男性が多数を占める新聞業界では当時、新聞社が記者職として女性を募集・採用するのは珍しかった。130人ほどの記者のうち、女性は山城さんを含めて3人。同期の男性たちが希望の部署を聞かれるのに、女性である山城さんは希望を聞かれぬまま婦人欄の担当になった。
幼少期から男女平等は当たり前に育ち、入社試験でも「新聞社は男女平等」と聞いた。「みんなが女性は婦人欄を書くのが当たり前だと思っていた。私は差別的な扱いと感じたが、差別をしているという自覚のある人はゼロ。猛烈に悔しかった」と振り返る。 同期の男性記者が数年ごとに異動する中、山城さんは婦人欄の担当のまま。希望を出しても引き受けてくれるデスクがいなかった。男性と同じように社会部や政治部など様々な部署を経験し、「男並み」を目指した時期もあった。しかし、障害児や精神障害者の小規模作業所をはじめ、ケアの場を支える女性たちを取材する中で、その考えが変わっていく。「身近な家族のために立ち上がっているのは女ばかりと思ったときに、女たちがやっていることの重さや深さに気持ちが引っ張られた」
続きは本紙で...やましろ のりこ
1949年沖縄県那覇市生まれ。沖縄タイムスで73年から働き始め、74年入社。編集委員、学芸部長などを歴任。2004年に退社し、フリー。著書に『人を不幸にしない医療』(岩波現代文庫、元の記事はファルマシア医学記事特別賞)、共著に『沖縄という窓』(岩波書店)など多数。- 【 新聞代 】(送料込み)
- 1カ月800円、3カ月2400円
- 6カ月4800円、1年9600円
- 【 振込先 】
- 郵便振替:00180-6-196455
- 加入者名:一般社団法人婦人民主クラブ