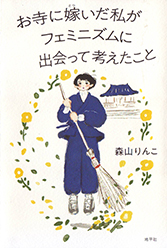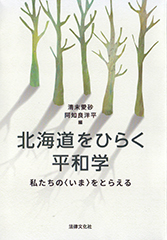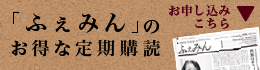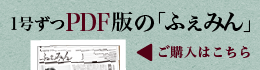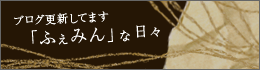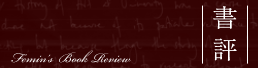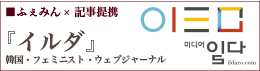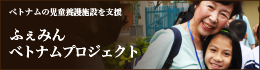生活保障システムの転換 〈逆機能〉を超える
大沢真理 著
|
命と暮らしを脅かす日本の税・生活保障制度。所得再分配が貧困を逆に深める〈逆機能〉を指摘してきた著者が、歴史と各国比較によって従来の男性稼ぎ主型システムの問題点を突き付ける。
日本の制度は、稼ぎ主の男性を支える女性が、働き、子どもを産み、育てることに「罰を科している」と説明。第2次安倍政権は社会保障費の抑制方針を打ち出し、給付総額で女性の割合が高い医療と介護に切り込む。コロナ禍では、高齢女性死者数の割合が高く、若い女性の自殺数も増加。働く女性も収入の機会を失い、就業条件が悪くなり、家事・育児などの負担も増え、「姥捨て社会」がむき出しになったと言う。
副題は「〈逆機能〉を超える」。そのために、著者は金持ち優遇ではない所得再分配機能の回復や「年金支援給付」、同一価値労働同一賃金の実現、意思決定の場で女性を増やすことを提言。少子高齢化・人口減少を促迫し、貧困を深め、格差を拡大する制度改革は待ったなしだ。(春)
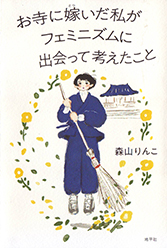
お寺に嫁いだ私がフェミニズムに出会って考えたこと
森山りんこ 著
|
- お寺に嫁いだ私がフェミニズムに出会って考えたこと
- 森山りんこ 著
- 地平社1800円+10%
|
|
|
曹洞宗の僧侶と結婚し、夫の家(寺)の暮らしの中で、仏教界の女性の立ち場などに違和感をもった著者。フェミニズムと出会い、その違和感の正体を探っていく約20年を綴ったのが本書だ。
曹洞宗では、寺に住む僧侶以外の人は「寺族」とされ、著者は結婚により自動的に「寺族」になった。しかし、これは日本特有のもの。本来、僧侶は妻帯し家族をもってはならないが、明治5(1872)年に「僧侶の肉食妻帯勝手たるべし」とした太政官布告により、妻帯仏教が急速に進む。それは、男性僧侶に都合のよい仕組みで、「寺」と「家庭(イエ)」が混ざり合い、家父長制的な構造として女性を抑圧していった。
著者が、女性と仏教に関わる講座や韓国の小説などを通してフェミニズムに出会い、女性差別の構造の中に生きていると自覚し、解放されていく過程にとても共感。仏教界でのジェンダー平等を目指して活躍している女性との対談では、仏教界も変化していると知り、興味深い。(う)
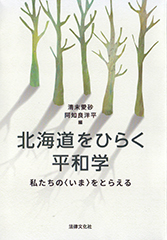
北海道をひらく平和学 私たちの〈いま〉をとらえる
清末愛砂、阿知良洋平 編
|
- 北海道をひらく平和学 私たちの〈いま〉をとらえる
- 清末愛砂、阿知良洋平 編
-
- 法律文化社2200円+10%
|
|
|
北海道には先住民・アイヌが暮らし、〈入植者植民地主義〉を体現する広大な開拓地であるという視点の本書は、“和人”の立場性を突きつける。植民地と差別、自衛隊基地との闘いや人々の連帯、日常にある暴力、という構成から成る。
戦争中に朝鮮半島から北海道へ強制動員された朝鮮人の逃亡をアイヌの人々が匿い、集落に受け入れたこともあったという事実。北海道にも暮らしていた北方少数民族ウィルタが、戦争に巻き込まれシベリアに抑留されたことは初めて知った。今後体系的な歴史の整理・保存が重要だと著者の一人は書く。陸上自衛隊矢臼別演習場をめぐる闘いからは、酪農家らの生活感を根底にした、〈何のために大地を使うのか〉という問いかけを含めて、沖縄や三里塚の闘いとの連続も読みとれた。憲法の平和的生存権の堅持を打ち出し、対話の場を作る行動には瞠目した。自民党国会議員からのアイヌの人権侵害問題も記す。地域から「平和」や「平和学」をひもとく意味を考えた。(三)