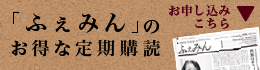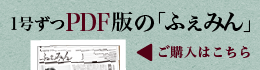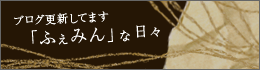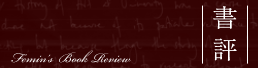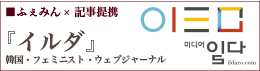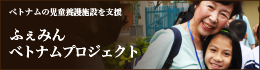平塚らいてうと現代 女性・戦争・平和を考える
米田佐代子 著
|
女性解放運動の先駆者とされる平塚らいてう研究の第一人者による論考集。戦後80年の今年、らいてうの「ただ戦争だけが敵」という平和思想と実践を伝えたい―。著者の強い信念が伝わる。
「新資料が語る『戦争の時代』とらいてう」は、一貫して平和主義だったらいてうが、中国との平和友好を願うあまり中国の抗日戦争に反対し、日本の傀儡政権支持の文章を書いたことを指摘。戦時中の負の側面から、生涯をかけて形成された平和思想に言及する。
著者自身の願いが込められる「平和とジェンダー」は、原爆投下をはじめ戦争の被害を受けた日本の女性たちが、日本が侵略戦争で加害したアジアの女性たちへの加害責任を自覚する過程を、らいてうの生き方と重ねてたどった。かつて参政権がなく、戦争に反対できなかった女性たち。参政権を得た女性に「戦争についての責任を、日本に対し、また世界に対しもっています」と訴えたらいてうの言葉を、今こそ噛みしめたい。(春)

トランスジェンダー生徒と学校 「抱えさせられる」困難と性別移行をめぐる実践
土肥いつき 著
|
- トランスジェンダー生徒と学校 「抱えさせられる」困難と性別移行をめぐる実践
- 土肥いつき 著
- 生活書院2700円+10%
|
|
|
学校の中でトランスジェンダー生徒はどのような困難を「抱えさせられる」のか。教員でありトランスジェンダー当事者である著者が10人の当事者への聞き取り調査を基に分析・研究を行った。当事者を支援や配慮が必要な「客体」でなく、変革パワーを持つ「行為主体」として位置づける。
共通するのは中学校以降に制服等を通して生来割り当てられた「性別の区分け」が強化され、「ジェンダー葛藤」が高まること。しかし著者が明らかにするのは時代や階層、家庭環境の違いを背景にした当事者の経験の多様性。だから一括りにしたマニュアル化した支援の危険性に警鐘を鳴らす。また、性別区分けの強制力の強弱や「性別カテゴリー」の幅や割り当てが、当事者と周囲の生徒との相互行為で変容していく語りが興味深い。
学校や「性別」システムの硬直性から脱し、トランス生徒を包摂するためのヒントが満載。(飆)

《新装版》無言館はなぜつくられたのか
野見山暁治、窪島誠一郎 著
|
- 《新装版》無言館はなぜつくられたのか
- 野見山暁治、窪島誠一郎 著
- かもがわ出版2000円+10%
|
|
|
1997年に開館した、長野県上田市にある「無言館」は異色の美術館だ。戦争で亡くなった画学生の作品を遺族から寄贈・寄託を受け展示している。本書は、作品収集に奔走した画家の野見山暁治さんと、文筆家で無言館館主の窪島誠一郎さんの対談が収められた約15年前の書の新装版。野見山さんは一昨年亡くなられている。
画学生の時に出征し、戦場体験をもつ野見山さんと、疎開で命が助かるも、空襲で家が焼かれ、育ての両親と敗戦後のたいへんな時期を生き抜いた窪島さんが、戦争の記憶や芸術を率直に語る。戦地では色彩に飢えていたという野見山さんは、多くの画学生が亡くなり、自身の生還に「負い目」を感じて生きてきた。その思いを受け取った窪島さんが私設の美術館を誕生させるまでの過程は感動的だ。
無言館は安易に「反戦美術館」としてはめ込まれたくないという二人。“もっと描きたかっただろう”人たちの絵を見に、丘に佇むその館にまた行きたくなった。(り)