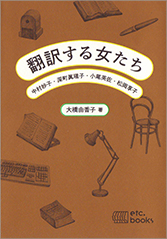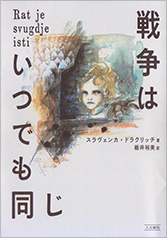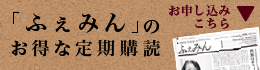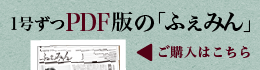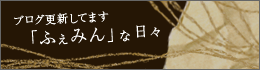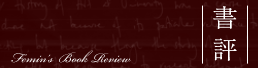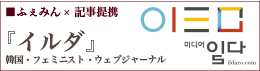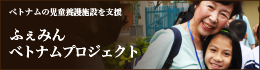「帰れ」ではなく「ともに」 川崎「祖国へ帰れは差別」裁判とわたしたち
石橋学、板垣竜太、神原元、崔江以子、師岡康子 著
|
「帰れ」ではなく「ともに」 川崎「祖国へ帰れは差別」裁判とわたしたち
- 石橋学、板垣竜太、神原元、崔江以子、師岡康子 著
- 大月書店1800円+10%
|
|
|
1910年代から朝鮮人が住み、現在も在日コリアンが集住する神奈川県川崎市桜本に、2015年から在日への差別煽動デモが襲った。著者の崔さんが地域の在日1世や次世代を守るため、前面に立って抗議をすると、「国へ帰れ」と叫ぶヘイトスピーチに遭う。ヘイトスピーチは許せないと、多くの市民や法律家たちとともに、「ヘイトスピーチ解消法」(16年)と川崎市の条例(18年)成立に尽力し、裁判で差別を認めさせ勝訴した(23年)。
凄まじいヘイトに遭う崔さんの、「私はいつか殺されます」と言う悲痛な声を受け止め、どんな差別が起き、裁判でどう闘ったのか、条例制定の方策、ヘイトスピーチを犯罪とする実効性ある「禁止法」制定へ向けた課題を関係者が示す。
差別がどれだけ人の心理を深く傷つけるか。差別を許すマジョリティにこそ責任があることを肝に命じ、最終章の崔さんの言葉をかみしめたい。(三)
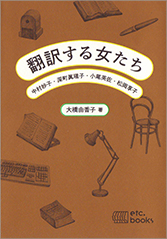
翻訳する女たち 中村妙子・深町眞理子・小尾芙佐・松岡享子
大橋由香子 著
|
- 翻訳する女たち 中村妙子・深町眞理子・小尾芙佐・松岡享子
- 大橋由香子 著
- エトセトラブックス2400円+10%
|
|
|
翻訳するのは男性がほとんどという時代があった。そんな中、1920~30年代生まれで出版翻訳を専業として活躍中の4人の女性たち(2人は逝去)のウェブ上でのインタビュー連載と後日談、書き下ろしを加えた本書。人生のどこかで4人の訳本に出合っている。
生い立ちや人となり、翻訳家になるきっかけ…語学が好きな人ばかりでないのも面白いが、翻訳に対するそれぞれの真摯な姿勢、努力、矜持が見え、翻訳とは「異なる文化のしみついた言葉を、別の異なる文化のしみついた言葉におきかえていく」繊細で創造的な営みであることを実感する。
書き下ろしは、加地永都子、寺崎あきこ、大島かおりといった、海外の女たちの動き等も訳して日本のフェミニズム運動に影響を与えた人のストーリー。特に大島が言う、家父長制文化の中で「女」が書いたものを「女」が訳す意味と意義は、今の私がどれだけ女が紡ぎ継いだ言葉で生かされ救われたかに思い至り、胸が熱くなる。(成)
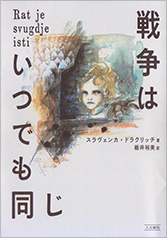
戦争はいつでも同じ
スラヴェンカ・ドラクリッチ 著 栃井裕美 訳
|
- 戦争はいつでも同じ
- スラヴェンカ・ドラクリッチ 著 栃井裕美 訳
- 人文書院2800円+10%
|
|
|
著者はユーゴスラヴィア紛争をはじめから終わりまで見届けたジャーナリスト。1991~2022年のエッセイを集めた本書は、ウクライナの戦禍を前に、「人々の苦しみはいつでも同じ」と訴える。
本書で最も堪えたのは、「戦争はいつ始まるか」という問いだ。戦争は銃弾が飛び交って始まるのではない。もっと前からゆっくりと始まっている。作家、ジャーナリスト、知識人が、「憎しみの対象」を作り出し正義のために闘うよう同胞を説得して心の準備をさせる。自民族の優越性を示す「神話」を広める。「一般人より教養があり、何が正しいかをよく見極めているはず」の彼らが「戦争へと巧みに誘導していった」
クロアチアは現在も「日常的にナショナリズムを感情的に政治利用する類の政治がのさばり続けている状況」というが、これは今どこにでもある危機だ。過去と向き合い親たちのしたことを問い質し、沈黙しないことが我々の責任だ、と著者は言う。過ちを繰り返さないために。(雪)