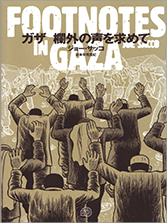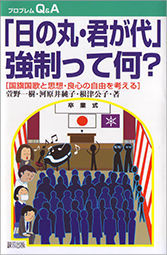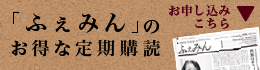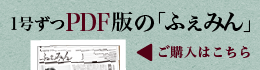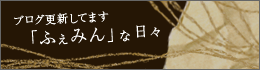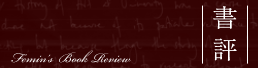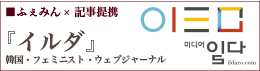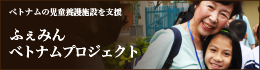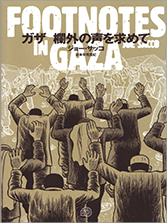
ガザ 欄外の声を求めて FOOTNOTES IN GAZA
ジョー・サッコ 著 早尾貴紀 訳
|
ガザ 欄外の声を求めて FOOTNOTES IN GAZA
- ジョー・サッコ 著 早尾貴紀 訳
- Type Slowly 2300円+10%
|
|
|
1956年、パレスチナ・ガザ地区のハーンユーニスとラファハでイスラエル兵による虐殺事件が起きた。米在住のコミック・ジャーナリストの著者は、第2次インティファーダの最中の2002~03年にガザ地区を訪れ、目撃者等の聞き取りや公文書や報道記事の発掘を通し、「大きな歴史や事件」の陰に埋もれたこの事件を詳らかにした。
現地で「今が酷いのになぜその事件を?」と訝られながら聞き取りをし、取材過程や証言者の表情、当時の光景等を類い希な絵力で大胆かつ細やかに表現。時に取材時に起きている殺戮や家屋取り壊し、1956年以外のこと(難民になった当初どのように衣食住を立ち上げたか等)も織り交ぜられる。苦痛に歪む表情や茫然自失の表情一つ一つが言葉以上に訴える。そうして全てを読み終えたとき、23年からのガザ攻撃の何もかもがこれまでの連続だと理解するのだ。なぜハマースが武力攻撃をするのかも。「停戦合意」に沸く今こそ、必読の書。訳者解説も秀逸。(暁)

台湾と沖縄 帝国の狭間からの問い 「台湾有事」論の地平を越えて
駒込武 編 呉叡人ほか 著
|
- 台湾と沖縄 帝国の狭間からの問い 「台湾有事」論の地平を越えて
- 駒込武 編 呉叡人ほか 著
- みずす書房3000円+10%
|
|
|
「台湾有事」を楯に、沖縄など南西諸島の軍事化を地元の合意もなく進めている日本。沖縄と台湾が互いの政治環境を知り、話し合い、政治的「自己決定権」を考えることをテーマに、2023年に日台の識者を集めたシンポジウムが京都で開かれた。そのまとめと各論者の論考を元に編まれた書。
論点の一つが「帝国の狭間」。中国と日本、そして米国という「帝国」に挟まれた台湾と沖縄は、一旦「有事」となれば市民が巻き込まれるのは必至。すでに台湾の上空には度々中国の戦闘機やドローンが飛ぶという。「有事」の現実感を語る台湾(呉叡人・張彩薇)と、対する沖縄(宮良麻奈美)の研究者の違いを確かめ合うような議論や、台沖の若い世代を含めた率直な鼎談に大いに刺激され、今後に期待が募る。
「社会の連帯を持って国家を制する」との呉の言葉を携え、台沖と日中の市民や研究者の対話と相互理解が平和を切り開くと信じる。(三)
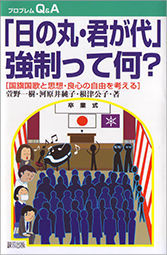
「日の丸・君が代」強制って何? 国旗国歌と思想・良心の自由を考える
萱野一樹、河原井純子、根津公子 著
|
- 「日の丸・君が代」強制って何? 国旗国歌と思想・良心の自由を考える
- 萱野一樹、河原井純子、根津公子 著
- 緑風出版2000円+10%
|
|
|
「国旗・国歌」法制定から25年。入学式や卒業式に「日の丸」や「君が代」があるのはもはや“当たり前”だ。東京都教育委員会は2003年「10.23通達」で、教職員への起立・斉唱・ピアノ伴奏を義務付け、現在までに約500人を処分、裁判も闘われている。10~11年には大阪府でも義務付けのための条例が作られ処分が常態化した。“当たり前”の背景には有無も言わせぬ強権的な教育行政がある。
度重なる処分を受け、免職の脅かしを裁判で跳ね返した東京の元教員(河原井と根津)と弁護士が記す渾身の書。「法」前史の「日の丸・君が代」強制と以後の学校の状況をつぶさに伝える。
教員が物言わなくなる中、子どもたちの変化にも心をえぐられるようだ。少数であれ強制に抗う人(子どもも!保護者も!)が今もいる。出勤闘争をする著者の姿を胸に刻んだ中学生に心打たれ、手放してはいけないものの重要さを改めて思う。(の)