ピーク・オイル:石油争乱と21世紀経済の行方
リンダ・マクウェイグ著、益岡賢訳
作品社、386ページ、上製、2400円
2005年8月31日発売
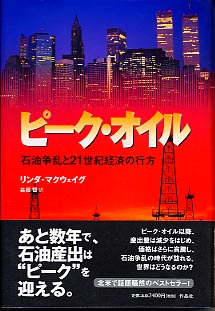 我田引水情報です。2005年8月31日に作品社から拙訳の最新刊『ピーク・オイル:石油争乱と21世紀経済の行方』が出版されました。書店にそろそろ並んでいますので、ご案内致します。
我田引水情報です。2005年8月31日に作品社から拙訳の最新刊『ピーク・オイル:石油争乱と21世紀経済の行方』が出版されました。書店にそろそろ並んでいますので、ご案内致します。
原書は Linda McQuaig, It's the Crude, Dude: War, Big Oil, and Fight for the Planet (Doubleday, CANADA, 2004) です。2005年1月末、たまたまカナダのバンクーバーで一夜を過ごした際に、町の本屋さんでベストセラー棚に並んでいたもの。
原書のタイトルから、よくある「石油地政学モノ」かなと思ったのですが、地球温暖化と石油生産ピークの問題を基調低音に幅広い視野で世界の現状に切り込む、内容的に優れた本でした。また、語りの視点が普通に楽しく生きる日常の目線に合っていて、さらに随所に興味深いインタビューを織り込んだ、読み物としても大変面白いものだったため、夜、ホテルで一気に読み切りました。
カナダの知人に聞いたところ、著者の Linda McQuaig はこれまでどちらかというとカナダの社会情勢を主題にした本を書いてきて、いずれもカナダでベストセラーとなった調査型のジャーナリストとのこと。
著者前書きの一部を以下に紹介します。
のちに明らかにするように、米国政府がかなりの程度イラクの石油を支配する欲望を[イラク攻撃占領の]動機としているという主張を裏付ける証拠は多数存在する。そしてこれは、より視野を広げると見えてくる、中東における米国の振舞いの歴史的パターンにも確かによく合致する。巨大な石油資源に米国が確実にアクセスできるよう中東地域を統制することは何十年も前から米国外交政策の一大要素であった。これについては極めて多くの文書があるにもかかわらず、こうした背景は公共的な論争からほとんど排除されてきた。本書は、マクロな歴史的パターンを考慮することで、イラクにおける米国の行為をより大切な文脈に位置づけることを目指す。また、その過程で、悪意に満ちた反米テロリスト活動の勃興を促してしまったことについて、米国の中東地域への介入がどのような役割を果たしてきたのかについても検討する。
米国のイラク侵略における石油の役割を検討することで、私たちはまた、石油に溺れている現代世界という、背景にある問題も検討することができる。石油は工業化社会の経済に必要不可欠なものである。けれども、石油資源は有限であり、この地上に残された石油は普通の人々が恐らく気付いているよりもわずかである。むろん、今まさに石油がなくなりつつあるわけではない。少なくともむこう数十年もつには十分なだけの量が残されている ----とはいえ石油がいかに私たちの生活様式の中枢をなしているかを考えるならば、数十年というのはそれほど長い時間でもない。さらに言えば、確かに、すぐに石油がなくなるわけではないが、安価な石油はもうすぐなくなるかも知れない----つまり、あまり困難なく採掘でき、したがって最近数十年私たちがなじんできた価格で市場に供せられる石油はなくなるかも知れない。二〇〇四年晩春に起きた突然の石油価格上昇は、容易にアクセスできる石油資源が世界的に減少していることをある程度反映した、持続的な石油価格上昇傾向の端緒かも知れない。これから数十年のうちに、石油価格高騰だけでなく、ますます貴重なものとなっている、残された安価な石油資源をめぐる国際競争----軍事的敵対さえ起こりうる----が激化することが予想される。
私たちの石油依存症はまた、緊急の重要性をもつもう一つの問題の中心でもある。次第に減少する石油資源をめぐる競争が激化し、国際紛争が引き起こされる恐れが出てくる中で、私たちは、石油依存症がもたらすさらに破滅的な影響----地球温暖化----に直面してもいる。したがって、私たちは奇妙に逆説的な状況に置かれていることになる。増大しつつある世界の石油消費をまかなうに十分な石油がない一方で、石油消費の増大自体が世界を破滅に陥れる脅威となっている。私たちは、フライパンと火の間で、あまり身動きのとれない場所に押し込められているかのようである。さらに驚くべきことに、私たちは、自分たちがこのような状況に縛り付けられていることを認識さえしていない。
けれども、問題は一見して思えるほど解決不可能なものでもない。驚くかも知れないが、本当に解決可能なのである:私たちの生活様式を大きく変える面倒を被る必要さえなく代替エネルギーを使うことができる見通しがある。より賢明な道をふさいでいるのは、どうやら何よりも政治的なものらしい。これは良いニュースでもあるし、悪いニュースでもある。良いニュースなのは、政治的障害ならば乗り越えることができるからである。悪いニュースなのは、恐らくその障害を乗り越えるのは容易ではないからである。変化に抵抗しているのは、米国政府や世界最大の企業など、この地球上で最も強力な組織である。
いずれにせよ、私たちの石油依存症がもたらす問題の範囲をきちんと認識することが何よりもまず大切である。イラク問題を曖昧にし続けても得るところはない。米国がイラクの石油を支配しようとしまいと----レジスタンスの激しさを考えると現在のところそれはありそうにないが----解放者のふりをしてやってきた侵略者に対して多少なりとも懐疑の目を向けることで、地上で最も爆発しやすい問題の一つである石油をめぐって、緊急に必要とされている理解を促すことができるだろう。
目次を章単位であげると:
- はじめに
- 第1章 <ピーク・オイル>----手近に実る果実はなくなった
- 第2章 手近に実る果実としての「イラク」
- 第3章 巨大石油企業による新たな中東支配構想
- 第4章 OPECを復活させた男
- 第5章 地球環境保護と巨大企業
- 第6章 ロックフェラー物語
- 第7章 石油メジャーと中東
- 第8章 OPECの闘い
- 第9章 米国の長年の夢と<ピーク・オイル>
- 第10章 21世紀の石油状況と世界の行方
ちょっと暑苦しい「いかにも」っぽい「二流自称エコノミスト事情通の地政学分析モノ系」の章見出しが並んでいますが、中身は、読み物として面白いと同時に、冷静に考えるための手がかりも流れよく盛り込まれており、私がこれまで訳してきた本と比べるといわゆる「社会問題」にさほど関心がない人も含めた幅広い人に面白く/興味深く読んでもらえるものと思います[とはいえ『ファルージャ2004年4月』は広く読んでいただければと思うのですが]。
なお、本書を読んで下さった方に、併せて、田中優著 『戦争をやめさせ 環境破壊をくいとめる 新しい社会のつくり方 エコとピースのオルタナティヴ』(東京:合同出版)をお読みになることをお勧めします。
これもまたものすごいタイトルですが(エコとピースで私はウンベルト・エーコとタバコのピースを思い出しました。実は、私はこのタイトルのために買うのをしばらく躊躇していました)、中身は明晰。とりわけ
問題を解決していくには、解決していくための戦略(ストラテジー)が必要だ(まえがきより)
問題を解決するためには、問題発生の原因と、原因に至る動機を調べなければいけない。いくら懸命に努力していたとしても、的外れな対策では解決に結びつかない。問題を解決することは、気持の問題ではないのだ。
という、自己弁護のための精神論を拒否して具体的な手続きとデータを呈示し、日常様々にできることを即物的に説明している、お勧めできる本です。よくできた料理本のようなイメージの、よくできた社会生活本で、『ピーク・オイル』を読んで「深く考えさせられた」と紋切り型で終わらず、生活に、ビジネスに、未来に繋げる一歩を颯爽と踏み出すために、楽しく参考になるでしょう。
ただし、この本(『戦争をやめさせ・・・』)に一箇所、好ましくない方向に誤った記述があるので、指摘しておかなくてはなりません。
東ティモールについて、事実関係の誤認と論理展開の問題があるのです。
まず、「インドネシアからの独立が許された」(p. 28)という誤った記述。東ティモールは国際法上インドネシアの一部であったことは一度もなく、不法占領を受けていただけですから、東ティモールがインドネシアから独立する、というのは、イラクが米国から独立する、というのと同じように、成立し得ない事態です。
とはいえ、「東ティモールのインドネシアからの独立」「石油思惑」などは、大手マスコミの他、自称「進歩派」までもが調べもせずに平然と繰り返し書いてきたことではありますが。
引用文献はル・モンド・ディプロマティークに掲載された分析の浅い甘い記事一つ。
「勢いを失ったインドネシアから石油を持つ東ティモールだけが独立を許され、それと同時にオーストラリアに有利な国境線を押しつけられようとしている」とありますが、オーストラリアはティモール海の石油欲しさに国際社会で唯一インドネシアによる東ティモール侵略と不法占領を承認した国となり、1989年には東ティモールを不法占領下においたインドネシアとの間で盗掘の契約を結び、圧倒的にインドネシアに近いところにラインを引いていて豪に有利な盗掘を進めていたのです。
この事実を考えると、「それと同時にオーストラリアに有利な国境線を押しつけられようとしている」という言明は論理的に成立し得ません。
実際、現在の東ティモールとオーストラリアとの間のティモール海交渉が、交渉されている範囲で最も東ティモールに不利に、オーストラリアに有利になったとしても、インドネシア占領下でオーストラリアが盗掘していたときよりもオーストラリアの取り分は少なくなります。また、だからこそ、インドネシアとオーストラリアが盗掘していた時代の線引きをあたかも「公平」であるかのように叫んで、オーストラリア政府は、オーストラリア国内向けに「我々は寛大に東ティモールに大きな取り分を認めている」などというプロパガンダを張ることができているのです。
さらに「独立を許され」という記述も、誰が許すのかという観点から危惧を覚えます。東ティモールの独立は、1999年8月30日の住民投票で、東ティモールの人々が、脅迫と誘拐、拷問や強姦、処刑や殺害、建物やインフラの破壊といったの多大な犠牲を払って、自ら解放を勝ち取ったものです。私はこのとき国際東ティモール連盟投票監視プロジェクトの日本事務局長を務めて日夜現地の情報を電話とメールで受け取り、また、私の連れ合いは監視員として現地に行っていましたから、この点については直接知っています。本来独立する権利を持っている人々が独立を「許され」る必要などないし、独立を「許す」ことができる立場の存在などどこにもないからです。
繰り返しますが、オーストラリアは、ティモール海の盗掘をするために親米独裁体制で国内資源の流出を認めて賄賂を受け取るスハルト政府が支配するインドネシアが東ティモールを不法占領し続けていることを望み、それを承認したのです。
さらにいうと、石油と天然ガスの生産量も埋蔵量もアチェの方が多いけれど、アチェは独立を「許され」てはいません。実際、大国と国際石油資本は、腐敗したインドネシア軍に金を払って傭兵として雇い、アチェの資源を搾取しているのです。インドネシアから石油をはじめとする天然資源を搾取する方が、東ティモールから搾取するよりもはるかに容易だ、というのが、そもそも1975年のインドネシアによる侵略を国際社会が黙認あるいは水面下で後押した理由ですし、1999年の虐殺と破壊が終わるまで手をこまねいて見ていたことも、インドネシアとの関係(つまり搾取を続けること)を重視したことが大きな理由の一つです。
それを考えると「勢いを失ったインドネシアから石油を持つ東ティモールだけが独立を許され」という言述が示唆する「石油」が「東ティモールが独立を許された」一要因だったという考察は成り立たちません。
「極力信頼できるデータを基にして」「合理的に、論理の飛躍がないように注意しながら」と前書きにあるだけに、東ティモールをめぐる記述についてのこの問題は残念です。
だめ押しになりますが、石油を動機とした様々な大国のごり押しの一例として東ティモール解放のケースを取り上げるのならば、何よりも、住民の3分に1に及ぶ20万人もの人々を死に至らしめたインドネシアによる東チモール侵略と不法占領を、インドネシアの石油・天然資源利権をはじめとする経済利権を重視して、黙認したことを挙げるべきであり、東ティモール独立を大国の石油思惑と関連づけようとするのは、事実的にも論理的にも成立しません。
さて、このように間違った論述があると、この本(『戦争をやめさせ・・・』)はトンデモ本なのでは? との疑念が生じるかも知れません。けれども、数カ所サンプリングをして簡単にクロスチェックしたところでは(全部の情報をチェックはしていません)、東ティモールに関する記述以外はとてもしっかりして信頼できるものだと判断できます。
何よりも、具体的な方向性をデータとともにきちんと書いている部分は、本当に優れたもので、読んだその日からすぐに参考になります。
[なお、著者田中さんとのやりとりで、東ティモールをめぐる記述の問題については、大変理性的にご理解いただけました。修正の機会があるときに修正して下さるとのこと]。
そんなわけで、『ピーク・オイル』と併せてお読みいただけると、一見したところ手に余るような巨大な問題と、生活の場に密着した問題とを、心情的な自己満足に浸ることによってではなく、具体的に明晰につなげていく手がかりが得られるでしょう。