�@
�@OECD�i�o�ϋ��͊J���@�\�j�ɂ����āA��i29�J�������Ō�����Ă���u�����ԓ�������v�ł��B
�A�����J��EU�i���B�A���j�̑����Њ�Ƃ��㉟������MAI�́u���ۓ����̎��R���v���� �����Ă���A�����Њ�Ƃɂ��傫�ȁu���R�v�Ɓu�����v��^������̂ł��B
�@MAI�͊C�O�ɐi�o���Ă�����{�̑��ƂɂƂ��Ă��s���̗ǂ�����ł����A���̋��� �ɂ���āA�Љ�I��҂�r�㍑�̐l�X�̐����́A�ꈬ��̑����Њ�Ƃɉ����Ԃ���Ă��܂��܂��B���E�K�͂̑勣���ɏ����߂Ɉ����ȘJ���������������A����j�Ă����Ƃɂ́A�u���R�v������Ɂu�K���v���K�v�ł��B�������AMAI�����{�����A�e�����{�⎩���̂͏Z���̐�������邽�߂̋K���������{�ł��Ȃ��Ȃ�܂��B
�@���̂悤�Ȋ�Ɨ��v�D���MAI�ɑ��A���E�e���̎s���ENGO�́uMAI���E���E�L�� ���y�[���v�𗧂��グ�܂����B���̃L�����y�[���ł́A���N4�����ɗ\�肳��Ă���MAI�̒����������������AMAI�̉e����������s����r�㍑�̎Q���̂��Ƃō���̋c�_��i�߂Ă����悤���߂Ă��܂��B
������Δ��ł��B�l�`�h
 ���ҏ��H���G �i�����w�@��w���� ���a�������j |
 �������q �i���{����ҘA���j |
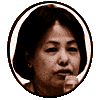 ������� �i�ߔe�s�s��c���j |
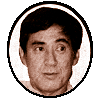 ����g�h �i��q��w�A�W�A�@ �����������j |
|---|---|---|---|
| MAI��20�N�ԁA�勣�����p������B���̊ԁA�藎�Ƃ����Љ�w�̐��� �̈��S�͒N���ۏႵ�Ă����̂��낤�H | MAI�ɂ���Ċ�Ɗ����͏���҂̋��߂���S��������悤�ɂȂ�� ���B���̂悤�ȉ��\�͒f���ċ����܂���B | MAI�ɂ���āA�������͂��߂Ƃ���Љ�I��҂̐l��������ɐN�Q����� ���ƁA����јJ���҂Ɗ��ւ̈����e�����o�邱�Ƃ��뜜���܂��B | MAI�́u�����Њ�Ƃ��������l�v�Ƃ����A�Ƃ�ł��Ȃ����E���߂����� ���肾���甽�ł��B |
�@
MAI�ʼn����ǂ��ς��H
�����ł́E�E�E
MAI�ł���ɐi�ށu�L�Z�C�J�����v
�@MAI�ł͊C�O����̓������Ăэ��ނ��߂Ɋ����J������ɘa���邱�Ƃ͋ւ��Ă���B���̈���ŁA�����Ƃ����{�ڒ�i�ł��镴�����������荞�܂�Ă���B�ƂȂ�A��i������A������j�Q����\���̂���K���Ɋւ��ẮA���炩���ߊɘa���Ă������Ƃ������ꂪ��������Ă����B
�@�܂��O����Ƃ́A��K�͓X�܂̏o�X���K�������u��X�@�v��_�n�̔������K�������u�_�n�@�v���A�����̖W���Ƃ��Ėڂ̓G�ɂ��Ă����BMAI�ɂ���āA�K���͊ɘa��������Ɍ��������낤�B�n��̎���ɑ����č��肳��鎩���̃��x���̊J���v��A�J���K�����A����ɂ���ē������W������ꍇ�ɂ͒�i�̑ΏۂƂȂ肤�邽�߁A�ɂ₩�Ȃ��̂ƂȂ炴��Ȃ��B
�@���̂悤�ɁA���ڊ���J���̊�������郋�[���łȂ��Ƃ��AMAI�ɂ���Ď����� �̕�炵�A�Љ�A�n������K�����ǂ�ǂ�ɘa����A��������l��l�����{�̑O�Ɋۗ��ɂ���Ă����B�K�������̂��߂̗��@�s�ׂ������Ƃ̒�i�ΏۂƂȂ��Ă��܂��B���b���ꕔ�̓����ƂɏW��������O���e�X�N�ȁu�L�Z�C�J�����v��i�߂Ă����A���ꂪMAI�́u���p�v�ł���B
�i�_�c�_�j�@�n�掩�����W�������FIACOD�����ǒ��j
�G�`���� vs. �J�i�_���{�c��Ɨ��v vs. ���K���@�J�i�_�ő��Ƃ���Ċ�ƃG�`���Ђ́A���Ђ̐��i�AMMT�i�L�ŃK�\�����Y���܁j�̗A ���ƍ����ړ����֎~�����J�i�_�c��̌���ɑ��A���Ђ�����������ɑ��鑹�Q�����i��315���~�j�����߂ăJ�i�_���{���i���܂����B���̂悤�Ȓ�i���\�ɂ���NAFTA�i�k�Ď��R�f�Ջ���j�́u������vs.���Ɓv�����������J�j�Y���́A�O�������Ƃ����ځA���n���{���i�ł���悤�ɂ���MAI�̐�s����ł��B
�@NAFTA�ł́AMAI�Ɠ��l�A���������{�������Ƃ̍��Y�����p�i�v���j�A�܂��͂���Ɠ��l�̌��ʂ����[�u�����{�����ꍇ�A�⏞���`���Â��Ă��܂��B���̃P�[�X�ŃG�`���Ђ����i����A�e�����K�Ȋ��E�Љ��E�[�u�����{����ۂɂ́A�ŋ��Ŋ�Ƒ�����⏞���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������ɂȂ�܂��B�����āA�⏞���č��ގ��̃P�[�X�����o����悤�ɂȂ�ł��傤�B
�@�G�`���Ђ͂܂��A���̖@�Ă��J�i�_�c���ʉ߂���6�J�����O�ɒ�i�̉\�������� ���Ă���A�����I�ɉ���j�~���悤�Ƃ��Ă��܂����BMAI�̕����������J�j�Y������������A���̂悤�ɂ��Ė���I�Ȉӎv����v���Z�X������Ƃɏ������Ă��܂��̂ł��B
�r�㍑�ł́E�E�E
�_���ɂ܂ʼn�����O���[�o�����̔g
�@���R�Ƌ������A���ݕ}���╶���A�@���d���鐶���𑗂��Ă����J���{�W�A��x�g�i���̔_���ɂ��A80�N��ɂȂ��Ďs��o�ς������炳��A�n��Љ���f����܂����B�o�ϐ����̂��߂̑�K�͊J���́A�^�}��L�͎҂����킹�܂������A�_���͓y�n��D���A�o�҂��ւ̈��͂����܂�܂����B�ݕ����Z������ƂƂ��ɁA�q����`���������A���ꂪ�u�q����E������v�݁A�s�s�̐��Y�Ƃ��g�債�Ă����܂����B�o�҂��J���҂ƂȂ����_���͓s�s�ŕs����Ȑ������������A�����������Ƃ�z�[�����X��ԂƂȂ��Ĕƍ߂̉���������Ă������̂ł��B
�@MAI�́A���������Љ�ω��ɔ��Ԃ�������ł��傤�B���D�܂������Y���������߂� ������ړ��̎��R��ۏ��ꂽ��Ƃ́A�J���҂��ٗp�s���Ɋׂ�A�ȘJ���������������܂��B�s��o�ς�����قǐZ�����Ă��Ȃ������_�����ł��A�ߑ�_�Ƃ��n��Љ�̊�Ղ�j�A�����J���Ɠs�s���ւ̐l�����o��������ł��傤�B�_��Ƃ̗]�ɂ��琶�܂�A�L���ȕ����ƎЉ�Ɉ�܂�Ă����`���Y�Ƃ��A���������Ƃ���������ƌ�������܂��ߑ�Y�ƂɈߑւ��������A���̓y�n�̐l�X�̐����╗�y�Ɛ藣���ꂽ��ʐ��Y�E��ʏ���̎d�g�݂ɑg�ݍ��܂�Ă��܂��ł��傤�B����ł������Ȃ���Ȃ�Ȃ����l�́A�����@�B���������̑��݂ɂȂ��Ă��܂��܂��B���R�������A�{���̈Ӗ��Łu�L���v�ɐ����Ă������l�́A�����̂��߁A�����ׂ̈����ɓ������݂ɕς����Ă��܂��̂ł��B�l�������Ă������߂̉��l�ς����ς����Ă��܂��̂ł��B
�i�������M�E�F���H��@���{���ۃ{�����e�B�A�Z���^�[�FJVC�j
�@
MAI�̎�ȓ��e
�������Ɠ����Ɓi�O����Ɓj�̕ی�|���n���{�����p�i�v���j���s���ہA�O����Ƃւ̕⏞���`���Â�����B�V���Ȋ��E�Љ�K���Ȃǂ���Ɗ����𐧖邱�ƂɂȂ�A��������p�Ɠ����Ɖ��߂���A���̋K���ɂ���Ƒ����𐭕{���⏞���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�B
�������̎��R���|�O����Ƃ��Q���E�ݗ�����ۂɏ��������邱�Ƃ��֎~����ȂǁB���[�J���R���e���g�i���n���B�䗦�j����A�O�݁E�f�Ջύt����A�������J�E���قȂǂ̎Q���������֎~�����B����ɂ��A�e�����{�⎩���̂͌o�ρE�J����������܂ł̂悤�ɂ͎��{�ł��Ȃ��Ȃ�B�n��Y�Ƃ͑����Њ�ƂƑΓ��ɋ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�B
�������������J�j�Y���̐ݒu�|�O����Ƃ����n���{�ڑi�����镴���������J�j�Y���̐ݒu�B���ƍ����ɂ���ĊO����Ƃɑ��z�̕⏞���s��˂Ȃ�Ȃ��Ȃ�\���������B�܂��A�O����Ƃ������@���̍���ߒ��ɉe���͂��s�g�ł���悤�ɂȂ�B
�@MAI�ɂ���ē��������̎Q���E�P�ނ̎��R�����܂�A��Ƃ̑I��������͂��g�� ���܂��B��Ƃ��C�O�ɓ����o�����Ƃ�������i�����{��A��Ƃ��Ăэ��݂����r�㍑���{�́A�@�l�ł̈��������⎩�R�f�Ջ�̗D���Ő��ɂ���Đł̈��������������s���悤�ɂȂ�܂��B
�@����A�i�o��Ƃ́A�����@���D�悳���Ԃ̑d�ŏ��i�Ԃ̓�d�ېł�E�ł̖h�~�Ȃǂ̂��߂̏��j�ɂ���āA���łɐŕ��S���y������Ă���A�����@�l�����D������Ă��܂��B�d�ŏ��ɂ�邱�̗D���[�u���c�����߁AMAI�̊�{���O�ł���u�������ҋ�(*)�v���u�Ő��v�ɂ��Ă͑ΏۊO�Ƃ���悤�ł��B�������A���������̎��R���́A�������̑�����Ɗ�������Z�������ւ̉ېł���荢��ɂ��A�l�X�ȒE�ł̋@����������˂܂���B�����MAI�͑d�ŏ��ȏ�́u�D���[�u�v�ƂȂ�܂��B
�@* �O�������E��Ƃƍ�����Ƃ��ҋ��ň�������
�i���L�K�@APEC���j�^�[NGO�l�b�g���[�N�j
�@1997�N7���^�C�̃o�[�c��@�ɒ[�����A�W�A�̒ʉ݊�@�́A�A�W�A�e���ɈÉ_�� ���������Ă��܂��B1996�N�ɐ�i���N���u�ł���OECD������ʂ������؍��܂ł�IIMF�i���ےʉ݊���j�̎x�������߂����Ƃ́A���E���ɏՌ��������炵�܂����B���̌o�ϊ�@�̂Ȃ��ŁA�A�W�A�e���͊O�݊l���̂��߂̗A�o�������������A�����ł����Ⴉ�����J���҂̒����͂���Ɉ����������A�ꕔ�̍H��͕��ɒǂ����܂�Ď��Ǝ҂���w���債�Ă��܂��B���̊�@�������炵�����{�����͊O���Ɉˑ������o�ϐ����ɂ���A�����ċ��Z�s��̎��R���ɂ���Ă����炳�ꂽ���Z���@����@����w�g�債���̂ł��B
�@�A�W�A�e���ł͑����Њ�Ƃ̓����Ȃ�тɋ��Z���@���K�����ׂ��ł���Ƃ����������܂��Ă��܂��BMAI�́A���݂�OECD�������Ԃœ��c����Ă��܂����A������͐��E���ɍL���Ă������Ƃ��Ӑ}����Ă���A�����Ȃ�ƃA�W�A�����������̌o�όv��𗧈Ă���ɂ������āA�����Њ�Ƃ̊������K�����邱�Ƃ͋���ᔽ�ɂȂ�A�Ƃ��ɓ�̍��X�͊C�O�����Ɉˑ������o�ς���E�p���铹��������邱�ƂɂȂ�̂ł��B
�i����q�@�A�W�A�����m�����Z���^�[�FPARC������\�j
| WTO / OECD vs. ���E��NGO | |
|---|---|
|
1993�N12���@ |
GATT�E���O�A�C�E���E���h�Ì��B�����֘A�̋���Ƃ��ẮA �f�Պ֘A�����[�u(TRIMs)����ƃT�[�r�X�f��(GATS)���肪���� |
|
1995�N1���@ |
WTO�i���E�f�Ջ@�ցj���� |
|
5���@ |
OECD�t�������MAI�̍쐬������ |
|
9���@ |
MAI�̌����n�܂�BOECD���Z������ƋǁiDAFFE�j�������ǂ�S���B �Ȍ�1�J�����Ɉ�x�A�����s���Ă��� |
|
1996�N3���@ |
OECD�ɂ��r�㍑���{������MAI�Z�~�i�[���J�Â����i���`�j�B �Ȍ�A�\�E���A���I�A���K�A�J�C���œ��l�̃Z�~�i�[���J�Â���� |
|
12���@ |
WTO�t����c�ő����ԓ����������낤�Ƃ��铮�������܁B NGO�ɂ��MAI�ᔻ�̐��A���܂� |
|
1997�N10���@ |
OECD�p���{���ŁuMAI�Ɋւ���NGO�Ƃ̋��c�v���J�����B ���E��NGO���uMAI���E���E�L�����y�[���v���J�n����B |
|
11���@ |
MAI�Ɋւ��āA���{���{�Ɠ��{��NGO�̋��c���n�܂� |
|
12���@ |
OECD�p���{���̑O�ŁANGO�ɂ��MAI���f�� |
|
1998�N 1���@ |
OECD�Ńr�W�l�X�Y�Ǝ���ψ���(BIAC)�ƘJ���g������ψ��� (TUAC)�Ƃ�MAI���c�J�� |
|
2���@ |
���{�ŁuMAI��NO�I�L�����y�[���v�n�܂� |
|
4���@ |
OECD�t���������MAI����������Ă��܂��c�H |
�j���[�W�[�����h�ł́c�c
�@�C�M���X�̓A�I�e�A���A�i�j���[�W�[�����h�j���x�z����ہA��Z�}�I�������Ƃ̊ԂɃ��C�^���M�������сA�}�I���̓y�n�⋙�ƁA�X�тȂǂɑ���s�N�̌�����F�߂܂����B�������V�R�����ɑ����Z�����̗D�挠��F�߂邱�Ƃ́AMAI�ᔽ�ɂȂ�܂��B���̂��߁A�}�I�������̃O���[�v��J���g���ANGO�Ȃǂ��L�͂�MAI���Ή^�����v�悵�Ă��܂��B
���܂��� ��MAI�h����E�E
�����ꂩ���MAI���Ă����ł��܂�
��������MAI���i�h�E�E�E
�@
�L�����y�[���ł͍��N4����MAI���Ɍ����āA�����O��NGO�ƘA�g���A�n�K�L�L�����y�[���A�S���L�����o���A���������A�v���X�����[�X�Ȃǂ��s���Ă����܂��B
|
�uMAI��NO�I�v�L�����y�[���̖ڎw������
|
�@
��110-0015 �����s�䓌�擌���1-20-6�ۍK�r��3�K Tel 03-3834-2436�@Fax 03-3834-2406 �d�q���[�� pf2001jp@jca.ax.apc.org �z�[���y�[�W�@ http://pf2001jp.vcom.or.jp/
�A�W�A�����m�����Z���^�[�iPARC)
��101-0051 �����s���c��_�c�_�ے�1-30�����r��303 Tel 03-3291-5901�@Fax 03-3292-2437 �d�q���[�� parc@jca.ax.apc.org �z�[���y�[�W�@ http://www.jca.ax.apc.org/parc/index-j.html
APEC���j�^�[NGO�l�b�g���[�N�iAM�l�b�g�j
��531�@���s�k�捑����1-7-14�@�������r��6�K tel/fax 06-354-6620 �d�q���[�� apecngo@mxa.meshnet.or.jp �z�[���y�[�W http://www1.meshnet.or.jp/~apec-ngo/index.html �@ �@
�@
�@
�@
�@