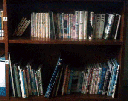 イメージ101K
イメージ101K  イメージ80K
次の項目へ
イメージ80K
次の項目へ4-2) 教育活動と捕鯨 捕鯨で栄えた町・鮎川でも、最近では捕鯨に関する教育はほとんど行われな くなっている。1992年の新聞報道によると、教科書や宮城県の副読本などから 捕鯨に関する記述がかなり前に消えたこともあり、捕鯨問題などについての関 心は低くなってきているという。また、鮎川小学校の校歌の3番(1947年に制 定されたもの)には、「極洋の果てまでも捕鯨の業に従える、日本の男児勇ま しく潮を切りて乗り出す」という部分があるが、こういったものもあまり歌わ れなくなってきているそうだ。 あるいは、鮎川の町役場隣にある牡鹿町公民館の図書室には、日本捕鯨協会 が寄贈したパンフレットが貸し出し用として用意されているが(「なぜ捕鯨か」 が 6冊、「鯨と人間」が11冊)、いずれも借りだされた形跡はなかった。また、 牡鹿町公民館図書室の棚には、鯨関連の書籍は2棚のみ。すぐ隣には、隣接す る女川町に女川原発があるせいであろう、原発関連の書籍が、4棚分保管され ていた。 以下、現在の教育活動から捕鯨に関するものを紹介する。 (1) 学校給食における鯨食 牡鹿町では、1988年より、牡鹿町内に9つある小中学校全部の学校給食で、 月1回年9回程度のペースで、鯨肉料理が提供されている。これは「鯨食文化 の維持」を目的に始められたもので、調査捕鯨によって得られたミンク鯨肉の 供給を受けたものの一部がそのために使われている。 この鯨肉給食は、日本側が外国プレスなどを招待しての牡鹿ツアーが行われ る際にも、視察対象として取り扱われることがある。 給食で出されるメニューは、鯨肉のしぐれあえ・鯨肉の竜田揚げ・鯨肉のト マトシチューなどであるという。新聞報道で報じられたメニューの中には、伝 統鯨料理に類するものは発見できなかった。もっとも、日本人の大半にとって 鯨肉は、第二次世界大戦後の食糧難の時期に非常食として出会ったものであり、 ほとんどの人は代用肉、あるいはこういった給食料理で、はじめて鯨肉を食べ たのである。そういう意味では、給食で鯨肉を食べるというのは、伝統食文化 や日本料理とは全く関係がないものの、日本におけるある種の食文化であると 言えないことはない。 (2) 牡鹿町に関する副読本 牡鹿町教育委員会は、1993年(平成 5年)から配布する小学校社会科の副読 本を 8年ぶりに改定した。新しい副読本には、牡鹿町の変貌ぶりが淡々と描写 されているという。 この副読本の編集にたずさわったスタッフは、新聞社の取材に対して、「捕 鯨再開など政治的な問題には公教育として触れられないが、現状を認識させ、 どうしたら故郷がよくなるかを、子供たちに考えさせたい」と語っている。 (3) 彫刻教室 公教育ではないが、学校が休みになる第二土曜日に、新しい鮎川の特産品を 目指す鯨木彫などを作っている「鯨友会」は、小中学生に鯨木彫づくりの指導 を行っているという。 【写真】 公民館の書棚。鯨関係の2棚(AYU36.GIF)と原発関連の4棚(AYU37.GIF)。イメージ101K
イメージ80K 次の項目へ
タイトルページに戻る。