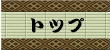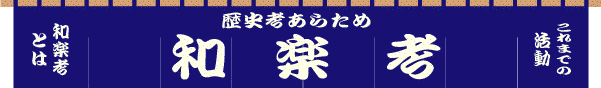
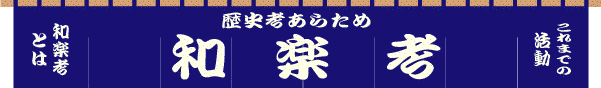
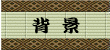 |
|
少しずつ実践せんと… 勉強を通して和の道具の思想として以下の三点を仮にまとめ上げました。 和の道具の思想 |
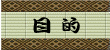 |
|
|
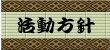 ●歴史的な研究や資料を庶民の視点に立ってまとめよう!! ●歴手的事実の探索を通して現代に生かすヒントを探そう!! ●みんなが生徒でみんなが先生、自分から勉強ししていこう!! ●勉強したことを実践しみんなに広めよう!! |
|
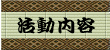 |
|
| 実際の活動内容は大きく二つあります。勉強会と発表会です。 勉強会は教科書を決めて2〜3週間に一度、朝10時ぐらいに集まって勉強しています。担当者はその項目のレジメを用意し、もちろん他のメンバーはその項目を前もって呼んでおきます。 発表会は年間3〜4回、会場を借りて一般の人に向けて開いています(予定)。 |
|
|
第一段勉強会…江戸時代の暮らしぶりを勉強しよう! 2000年4月より、9月まで『大江戸エネルギー事情』(右の図)を教科書として、三週間に一度集まって一人ずつ項目(下の項目)を分担し、担当者を中心に一回ずつ、勉強しました。 「薬」「紙」「涼む」「花」「酒」「灯り」 |
 |
|
第二段勉強会…和の道具を勉強しよう! 2000年10月より『にっぽん道具考 和風探索』(右の図)を教科書に、具体的に和の道具を勉強をはじめました。考察の視点をグループ内で統一するためにフォームを以下のように決めました。内容は現在ホームページで公開しています。 ●辞書での意味…辞書で一般的な意味を調べます。 |
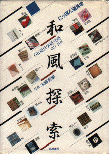 |
|
和楽考では勉強したことを多くの人に広めると言うことも重要な活動です。そのために、季節ごとに発表会を開くことに決めました。
|
 |
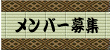 |
|
|
現在のメンバーは6名。学生からサラリーマン、職人さん老若男女で勉強しています。和楽考ではいっしょに勉強してくれる、こんなメンバーを募集しています。 ●日本のことに興味のある人…やっぱりこれはね。 年輩の方の参加を望んでおります。実際に和の道具を使ったりや当時の暮らしを体験されている『元から日本人』も方、「いっちょ『これから日本人(若い奴ら)』に教えてやるか」って気分で参加していただけませんか? |
|