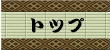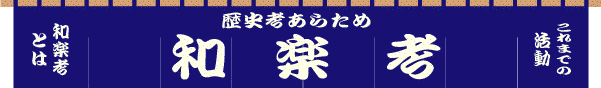
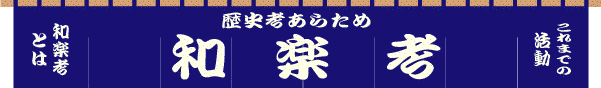
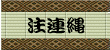 |
| しめなわ【注連縄】七五三縄、占め縄とも書く。神を祭る場所であることを示すために張る縄。 |
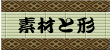 |
|
|
注連縄は、菅と呼ばれる水辺に生える植物を化粧用、つまり外側に、そして、歴史考ではすっかりご存じの稲藁をアンコ(内部)部分に使って作ります。 右の図のいわゆる縄の部分は「縄」といい、下に下がっている藁の部分は「〆の子」いい、白い紙は「紙垂」と言います。これらの部分にはちゃんと意味があります。 だそうです。稲作を中心とした農耕社会にとって、天気はその収穫には非常に重要。そんな意味からきていると言います。おもしろいものです。 農業国日本の産業廃棄物の有効利用から発達した工芸品とも言えます。 だけど農村で村おこしのいっかんで縄をなうイベントを開こうとしても、最近は縄をなえる人が、めっきり減ってしまって困っているようです。 |
|
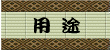 |
|
|
いわゆる神様がいる神社だけでなく、おうちにも飾ります。神棚、台所いろいろなところに飾っていたそうです。最近はあまり見なくなりましたが、車にもつけていますよね。神様は身近にいるようです。 ちなみに同じ聖域を示すモノで、中国ではお札ですが、韓国では縄を用いるそうです。 注連縄の原型となる荒縄は、いろいろな手を加えるだけで、様々な形ができる。草履、座布団、米俵…。荒縄をある程度なっておけば、いろいろな用途の道具となります。 |
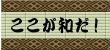 |
荒縄は現代のプラスティック以上の素材! |
|
プラスティックが世に登場した1960年代。そのキャッチコピーは“夢の素材”と言われていました。その材質は永久で、どんな形にでもなる。 でも荒縄こそ“夢の素材”でないでしょうか。太さは調節できる、どんな形でも作れます。プラスティックともっとも違うところは、一度作った縄をほどけば、また新しい形になる。まさに“夢の素材”! 今こそ荒縄の思想を見直しましょう! (担当:じゅんちゃん) |
|