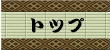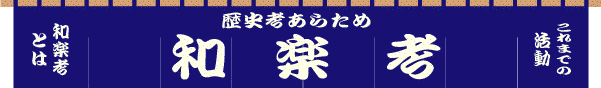
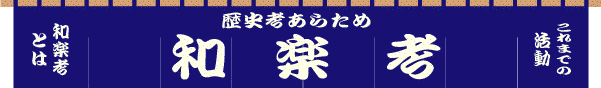
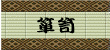 |
| たんす【箪笥】引き出し、戸のついた、衣服などの入れておくための家具。 |
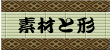 |
|
|
箪は食、笥は衣の意味。江戸時代は主に水に強いケヤキが使われていました。でも板にする技術がまだ高くなかったので、収納といえば、もっぱら行李などが重宝されていました。 それが、明治になってから西洋の洋服箪笥が入ってきて、箪笥が大型化し、右のような和箪笥の形になってきました。 関西では、着色仕上げで金具に懲り、手の込んだものが好まれ、関東では総桐(右の図)の生地仕上げが好まれました。 桐は火に強く、湿気に強いそうです。摩擦に強いため、あまりすり減らない。木製ですから傷がはいっても削れば戻る。でも全面を修復するのには結構かかるそうです。
|
|
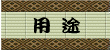 |
|
|
衣装の収納に箪笥が使われるようになったのは江戸時代中期(やっぱり現代生活の根元は江戸時代だね)。それ以前は葛籠(つづら)や行李(こうり)、長持ちなどを使っていました。 数え方が、一棹、二棹なのは、火事や運び出すのに便利なように、棹を通す金具がつけられたことからだそうです。ちょうどお殿様ののるカゴを想像して下さい。 |
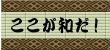 |
素材の特性を生かしたムダのないものづくり |
|
高級品から順に材料のいいとこどりをして、すそものはすそものなりの製品を作る。キリの材質の優秀性を、和の風土が育て、金持ちにも中流にも庶民にも享受できる素材活用の体系を作りだしていた。現在の伝統産業の高級品志向に一石を投じるんじゃないかな。 一方、箪笥が、明治以降、大型化したと言うことは、物を多く所有する生活スタイルに変わりはじめた象徴的に現象とも言える。 (担当:浜ちゃん) |
|