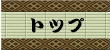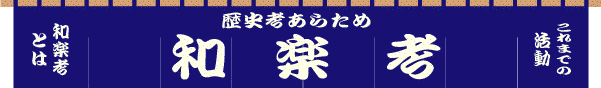
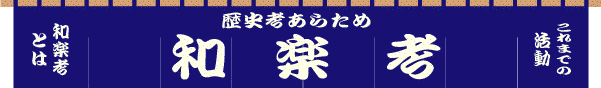
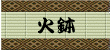 |
| ひばち【火鉢】炭火を入れて、手あぶりや湯沸かしなどに使う道具。 |
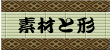 |
|
|
熱源ですが、木炭が火もちを調節するのにもっとも優れていています。 火鉢の材質は木製(箱火鉢、長火鉢)、金属製(金火鉢)、陶器製(瀬戸火鉢)があります。写真は瀬戸火鉢ですね。 瀬戸火鉢にはいろいろな色柄が楽しめます。できたのは以外にも明治期だそうです。 天端(てんば)と呼ばれる上の部分が広いほど熱が放散せず省エネだそうです。 |
|
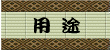 |
|
|
火鉢の中身は大きく三つの層からなります。一番下に子砂利を入れて、その上に大きめの砂、さらにその上に灰を入れます。灰の層が一番深く全体の2/3です。 炭と藁(わら)の灰を使って温度を調節するそうです。一日5〜6回は炭を継ぎ足したそうです。炭を活け、炭がたつと、また炭を活ける。 暖をとったり、餅を焼いたり、湯を沸かしたり、濡れたものを乾かしたり、火のし(アイロン)をあぶったりして使えます。一石二鳥どころか、三鳥も四鳥にもなります。 ただ実際使っていた人に話を聞くと火鉢同様に一酸化炭素中毒や火事のもとにもなっていたそうで、現在の電気を熱源とした暖房器具の方が安全だそうです。 |
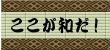 |
暖をとるだけなく、会話を埋める装置!? |
|
火鉢は部屋全体を暖めることはできませんが、目で火の色を味わうことができ、視覚、心理的な面からも暖をとることができます。 また暖や炊事、乾燥以外にも、火鉢を間に対座し会話なんかが途切れたときに、火鉢の火を見たり、炭をほぐしたりする。つまり人と人の仲立ち的な用途も日本には特に重要な用途といえるんじゃないでしょうか。今はテレビがその役割もかもしれません…。 (担当:みちこ) |
|