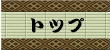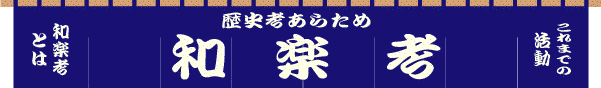
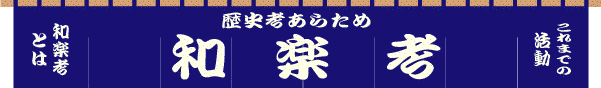
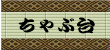 |
| ちゃぶだい【卓袱台】折りたたみのできる脚のついた、低い食卓。 |
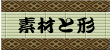 |
|
|
材料は多くの場合が木材です。戦後は合板にプラスティックで表面加工し、金属の脚の卓袱台は若い人でもピンと来る人があるかもしれません。あれも一種の卓袱台でしょう。 小さいもの(一人〜二人用)は約36ʘ〜45ʘくらい。大きいものは60ʘ〜90ʘくらいになります。高さはだいたい20ʘから30ʘが標準です。そのくらいが床座には調度いいようです。それでもって結構軽い。 脚がしまえることがテーブルにはない卓袱台の特徴です。特に一人暮らしにとってはこれからも十分利用価値があると思います。 |
|
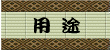 |
|
|
もちろん食事時に使います。必要のない時はたたんでしまい、茶の間は違う空間利用ができます。多くの場合は子供が勉強で利用したり、お茶を飲んだりするときにも置いていたようで、本当に必要のない時以外は、茶の間の主役として真ん中にどすんと構えていたようです、テレビがくるまでは…。 卓袱台には真ん中に15ʘ四方の穴のあいてあるものもあり、真ん中には火鉢などを置いていたそうです。その上で、鍋をしたりしたと私のおばあちゃんは言っていました。もちろんその穴にはフタもありますよ。 |
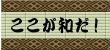 |
脚をたたんでしまう、空間転用のできる家具 |
|
卓袱台は以外にも新しい道具で、大正から戦前に普及しました。それまで日本では一人ひとつずつお膳の上にのせて食事をとっていました(ちなみに高さも違っていたそうです)。それが何と大正デモクラシーをきっかけに民主的な考え方が普及し、食卓もお膳から円卓(卓袱台)が広まっていったそうです。驚きました。 ただ西洋の思想“デモクラシー”を取り入れただけではなく和の道具の思想“たたんでしまうえる”ことはちゃんと引き継がれよね。 (担当:わか) |
|