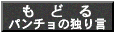
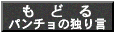
| 二人のガビー |
|
メキシコでは幾人かの気がかりな子どもたちと出会ってきました。初めてのツアーではカルメンという少女と出会いました。彼女のその後がとても気になり、いつのまにかツアー参加も四回となってしまったのです。そういった意味では、わたしにとってカルメンがメキシコの象徴なのかもしれません。 カルメンと初めて出会ったとき、彼女は路上生活を余儀なくされている子どもたちへの支援をおこなっているカサ・アリアンサというNGOの避難所で生活していました。その翌年カルメンは、カサ・アリアンサから路上へと戻りその後どこでどのような生活をしているか分らなくなりました。家に戻り、時々は路上に出てきているらしいとの噂は聞きました。もうカルメンと会うことはないでしょう。 そういった意味で今年のツアー参加は、自分にとってどうしても行きたいというものではなくなっていました。それに昨年行った沖縄への思いが強く、メキシコではなく沖縄といった気持ちで、ゆれ動いてもいましたし、7月に高熱を出したことによる自身の体力への自信のなさもありました。 それでも一昨年カサ・ダヤという、望まない子どもを産んでしまった少女たちを支援しているNGOで生活している、一人の少女(といってももう二十歳を過ぎていましたが)への強烈な思いが、四たびのメキシコ行きを決めさせました。 彼女の名はガブリエラ・カルモナ。今年(2001年)3月「ストリートチルドレンを考える会」の招聘で日本に来た少女と同名の女性です。一昨年このカサ・ダヤを訪れたとき、ガブリエラを含む3人の少女たちが自分たちの身の上話を聞かせてくれました。話すという行為により、自分の過去をもう一度自身の内部で追体験することの辛さ。その辛さがこちらにもしっかりと伝わってきました。 そんな話を聞いたあとわたしたちはカサ・ダヤの建物を出ました。そのときガブリエラがわたしを追いかけてきたのです。わたしは彼女が話をしている間、彼女の子どもを抱いてあやしていました。だからこそ追いかけてきた。そうであったからかもしれません。 彼女はわたしに向かって何かを訴えかけるように、一生懸命に話しかけようとします。けれど言葉がまったく通じないことで彼女はとてももどかしそうにおろおろし、胸で素早く小さな十字を切ったのです。 思い違いだったのかもしれません。わたしのかってな思い込みだったのかもしれません。それでもわたしは彼女がわたしに訴えかけたかったものを感じることができたと思えました。そのときわたしは彼女をしっかりと抱きしめていました。彼女と、彼女の子どもをしっかりと胸に出しきしめていました。カルメンを見つけだすことができなかったわたしが、またもう一人の少女と出会ったのです。 「わかっている。君の辛さを僕は感じようとしている。それが不可能であろうと僕はそのことを感じたい。また来る。必ず来る。君と君の息子と会うために僕は必ずまたここに来る」わたしはそう心の中でガブリエラに叫んでいました。 その年の暮れ、わたしはカサ・ダヤの少女たち全員に、クリスマスカードを送りました。そしてガブリエラにはそれとは別に個人的なカードを送ったのです。「また必ず会いに行く」と。 昨年の夏わたしはメキシコではなく沖縄にいました。沖縄でおこなわれるサミットの場に、どうしても居なければならない。そうでなければ自分が生きてきたこれまでのすべてを否定してしまうことになる。そんな強い思いがありました。 かつて高校時代ひとりの友がいました。その友は今はもういません。高校2年のとき、彼は北朝鮮と呼ばれている地域へ行き、その後消息をたちました。彼はわたしに人と一つのことを共有する「喜び」と、その「不可能性」を教えてくれました。それでもわたしは、常に何か選択を迫られたときに彼に問い続けてきました。「僕の選択は正しいだろうか?」と。 その問いの中で、昨年わたしはメキシコではなく沖縄を選びました。けれど沖縄は、わたしの予想とは異なりあまりにも平和なうちにその夏の時間が過ぎていったのです。 秋、ツアーから戻ってきた人から、ガブリエラの問いを聞かされました。「なぜコイケは来なかったのか」 そして今年早春。招聘したカサ・ダヤのスタッフからガブリエラの手紙を渡されました。知人に訳してもらった内容は、意味を読み取ることが不能なものでした。彼女がわたしになにを呼びかけようとしているのか? ガブリエラにもう一度会わなければならない。沖縄を選んだわたしは、メキシコを捨てたのではない。「場」としての沖縄がどれほど自分にとり大切なものであっても、その「場」とは、自分にとっての「喩」なのだ。現実の「人」としてのガブリエラと、「象徴」としてのカルメンを自分は捨て去ることはできない。 ガブリエラは大きく成長していました。母としても、生活者としても。カサ・ダヤの主催者ビクトリアさんも、そんなふうに成長した彼女を誇らしげにわたしたちに紹介してくれました。 彼女は縫製学校をとても優秀な成績で卒業しました。けれど彼女は手術しなければならない病気をもっているため、手術が終わるまではカサ・ダヤに居るのだとビクトリアさんは語っていました。 わたしはカサ・ダヤの少女たち一人一人に、高価ではないけれど心を込めた贈り物を持っていっていました。そしてガブリエラにも。少女たちにそのプレゼントを渡し終え、ガブリエラの横に行きました。日本人学校で教師をしている方に通訳をお願いして。 わたしは彼女の病気のことをたずねました。けれど「病名」という特殊な言葉のため、通訳の方には彼女の病名がわかりませんでした。ただ彼女は、彼女の下腹部をしきりに指していました。 わたしは彼女に自分の日本の住所を書いて紙を渡しました。そして通訳してくださっている方にこう伝えて欲しいと頼んだのです。「もしあなたが手術を無事終えてここから独立したときには、この住所に手紙を出して欲しい。僕は必ずあなたの新しい住所に連絡をとるから」 そしてもう一人のガブリエラ。今年3月日本に来たガブリエラ・ヒメネス。彼女は別れ際にわたしを呼び止め、彼女のベッドからテディ・ベアを持ってきました。そのテディ・ベアの耳には、タグが付けられたままでした。 真新しいテディ・ベア。街へ出て、わたしのために、わたしに渡すために買い求めてきたテディ・ベア。それがわたしにとってどれほどか大きな喜びだったでしょうか。彼女にとりそのテディ・ベアは、けっして安価なものではなかったはずです。 ガブリエラ・ヒメネスが日本に来たとき、わたしは彼女と、付き添いであるスタッフの責任者ギジェルミーナさんの浅草観光に同行しました。その折わたしは二人に、それぞれ好きなものを選んでもらってプレゼントしたのです。招聘したものの感謝の気持ちとしてそれは当然の行為と思いました。 ギジェルミーナもそれを素直に受け取ってくれました。ガブリエラは少し遠慮して、それでもとっても美しく可愛らしい羽子板を指差し、「ほんとうにいいの?」と目で問い掛けてきました。彼女にとりこういったプレゼントをもらう機会はほとんどなかったのでしょう。 だからこそ彼女はそのお礼としてテディ・ベアを買い求めてわたしを待っていてくれた。テディ・ベアというものではなく、彼女のその心がわたしにはたまらなく嬉しかったのです。 ビクトリアさんの愛情を受けて彼女もまた大きく成長している。「愛」というものを疑っていた少女が、素直に「愛」を受け入れることができるようになっている。ビクトリアさんや、スタッフから愛されることの喜びを知り、彼女の子どもをはじめとしたまわりの人たちを愛することの大切さをしっかりと感じられるようになっている。 水色のビニール袋に入ったテディ・ベアは、そのことをわたしに伝えてきてくれたのです。 ホテルの部屋に戻り、わたしはこう自分に問いかけました。 「お前はメキシコを忘れようとした。お前はカルメンを失ったとかってに思い込もうとした。けれどほんとうにそうなのか。カルメンは二人のガブリエラの中にもしっかりといるじゃないか。メキシコの象徴としてのカルメンをお前は失ってはならない」 「俺はメキシコの子どもたちにとって、旅人でしかないかもしれない。けれどその旅人が、子どもたちと会うために何度でも訪れる。そのことこそが子どもたちにとって大切なことなのだ。子どもたちに誠実であることが、俺にできる唯一のことなのだ」 「お前が望んでいる革命は、何世代も、何世代もの後にやってくるかもしれない。それは不可視の夢。しかしそれよりもっと大切なことは、現実にこの場に居る子どもたちへの思いを、しっかりと伝えることではないのか」 長くなりました。それでもメキシコでその他にもいくつか心に残ったことを簡単に語らせてください。 一つは知人のフリージャーナリストがはじめて書いた作品のモデルとなったマルセリーノ。彼とはやはり初めてメキシコを訪れたときカサ・アリアンサで出会いました。優しく穏やかな笑顔でわたしを見つめてくれました。日本語でしかなかったけれど「僕は君のことを知ってるんだよ」と話しかけたのです。 その彼と今年は、心身障がいを持つ子どもの施設で出会いました。彼は路上での男性からによる性的虐待により、自己の「性の混乱」に陥っているとのことでした。 もうすでに二十歳になっていたのですが、優しく穏やかな笑顔はまったく変わってはいませんでした。わたしは自分が座っていたソファーに彼に座るようにしめし、そのソファーの肘掛から彼の肩に手をかけていました。彼はおとなしくそれを受け入れてくれました。 知人の作品で描かれていた小さくかわいいマルセリーノは、今は路上で男色家からの性の対象とされ、このような施設で生活しなくてはならなくなっている。そのことでひどく気が滅入りました。そして知人さんから昨年のツアーのことで聞いたことを思い出していました。 昨年、一昨年と二度にわたり参加した中学生の少女を好きになった路上の少年がいたそうです。その少年は一年ぶりに会った中学生の少女との再会をとても喜びました。でも突然彼は泣き出してしまったのだそうです。 彼は路上で男色家に自身を売っていたのです。だから彼は泣きじゃくりながらこう言い続けたそうです。「こんな僕なんか君を愛する資格なんかない」 今わたしの横に座っているマルセリーノもまた、そうした傷みに耐えているのだ。それはあまりにもわたしにとっては受け入れることが困難なことでした。これほどにも穏やかな笑顔を見せているマルセリーノの、うちがわにある葛藤。まだ心理療法士など人的に整えることができずにいる施設の中で、マルセリーノはその葛藤とどう闘っているのでしょう。 それから昼間だけ路上の子どもたちが訪れることがえできる施設で出会った少年。少年たちは朝この施設にきてシャワーを浴び、服を着替えて一日を過ごします。そして夕方にはまた路上の自分のねぐらへと帰っていく。 メキシコには数多くの子どもたちの支援組織がある。だからどの施設も宿泊施設をもつ必要はない。それぞれの組織がそれぞれの担当を果たすことで有機的に組織同士の有効な行動をおこなう。そのようなこのNGOの姿勢に共感を持つことができました。 わたしはツアーセ責任者の配慮で、この施設に3日続けて通いました。1日目は参加者全員と。2日目は一人だけで。3日目は現地スタッフとともに路上へと。 ここにとてもおとなしそうな少年がいました。施設の責任者の話でもこの少年はもうすぐ他のNGOの定住施設に紹介することができるとのことでした。けれど彼は、ふとした瞬間に路上で見せるだろう凶暴な顔に戻るのです。 他の少年たちはそんな彼を恐れているようでした。けれど暴力で他の少年たちに自分のおこないことを強制することまではしていませんでした。路上で彼は、彼のグループの中でみなを率いているだろうことが、この昼間の施設の中でもはっきりとわかりました。 2日目はわたし一人(通訳の方を入れれば日本人は二人)だったのですが、いくつかのワークショップに参加しました。その中の一つにテレビのトークショーを模したものがありました。 各自がそれぞれ変装して実際のビデオカメラの前で自分の夢について話すのです。司会者役の施設長が一人ひとりの少年に夢について聞いていきます。そしてその少年はこう答えました。 「夢はたくさんもっていた。でもその一つとして叶いはしなかった・・・」 そしてしばらく間を開けて。施設の所長への思惑と、わたしという日本から来た人間への模範回答として、だからこそとても雄弁にこう答えたのです。「でもここに来て、きちんとした生活をして、定住施設に行くことが夢です」 その少年の答えを聞きながらわたしは6〜7年前、ブラジルの少年が語った言葉がよみがえりました。吐き出すように答えた言葉を。 「仕事を持つとか、家族を持つとかを考えたこともある。どんな仕事でもやればできる。でももう今はそんなことは考えちゃいない。夢なんてものは自分にはない。希望なんてない。いつか必ず自分も警官に殺されるだろう」 このブラジルの少年の言葉が、プラッサをはじめるきっかけとなったのです。けれどプラッサを初めて6年経った今、またこうしてメキシコでもわたしは、同じ言葉を聞いたのです。 最後にひとりの少女。デイケア施設の3日目に、職員と一緒に路上に出たとき出会った少女です。少年たちのグループの中に彼女はいました。わたしは、ツアー責任者の女性と、少女の3人でカードゲームをしていました。少女にはまだあどけない眼差しと、大人の女性のような誘うような眼差しと、その両方が備わっていました。 ゲームを終えわたしたちが地下鉄の改札に向かったとき、少女は追いかけてきて、わたしの右手首にあるミサンガをくれというのです。このミサンガは一昨年メキシコで、路上生活をしていた少年が自分で編んだものを、彼自身の手でわたしの右手首に結んでくれたものです。 だからこそこのミサンガは、日本にいる今でも、メキシコの子どもたちと自分との繋がりを常に確認せざるをえない大切なものです。そのミサンガを少女は欲しがったのです。 わたしは戸惑いました。左手首には腕時計をしています。メキシコ旅行用にと買った安物の時計ですが、デザイン的には優れていますし、ストップウオッチ機能や、アラーム機能も付き、防水機能まであります。実際幾人かの少年はこの腕時計を見入っていたりもしました。 それにもかかわらず少女はミサンガをくれというのです。2年間し続けているため、色も褪せ、編みもくたびれかけているミサンガを。なぜ。 少女は腕時計をくれといってもくれないだろうから、もっと簡単にもらえそうなミサンガを選んだのかもしれません。あるいはもっと別の理由なのでしょうか。少女の気持ちをはかりかねました。 ただわたしの気持ちはとてもあやういところに行ってしまいました。わたしは今にも泣き出しそうな顔で答えました。「これは『恋人』がくれたミサンガだからだめなんだよ」と。 少女もまた悲しそうな顔でいつまでもわたしを見つめていました。わたしはたまらなくなって改札に向かって歩き出しました。それでも少女はしばらくの間わたしを見つめていました。それから他の通行人に物乞いをはじめたようでした。 メキシコでのいくつかの光景です。メキシコから戻るたび、いつも自身に言問わざるを得なくなります。鋭く自分に突き刺さるような言問い。けっして答えを見つけることのできない言問い。 そしてだからこそ、その言問いの答えを求めるためにわたしはまたメキシコに行くだろうと感じています。二人のガビーと会うために。名も知らない少年や、少女と会うために。そう、「カルメン」と再び出会うために。
|
| 2001年8月 |