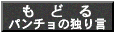
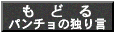
| 手首のミサンガ |
|
メキシコから戻ってきた東京は、晩夏の暑さが残っています。この残暑の中、おかわりなく過ごされていらっしゃいますでしょうか。 前回のツアーでは、カルメンという路上生活をしている少女のことと、アナと、エレーナというストリート・エデュケーターのことがとても印象に残りました。前回はみなさんが帰られた後も、仲のいい友人の女性とメキシコに残り(女性と二人だけで残ったというのに、ツアーの人の誰もがそれをいぶかったりしないということは、みんなわたしのことを男性とは見てくれていないのかもしれませんね)、メキシコシティーをぶらついていました。 ストリートチルドレンを考える会のKさんの知合いのスラムの指導者の家に行ったり、チンチャショマ神父という、路上のこどもたちの面倒を見ているスペイン人の方の施設で、こどもの面倒見ているマリオという青年と3人で、街を歩いたり。マリオもまた元路上生活のこどもだったのですが、チンチャチョマ神父のおかげで学校へも行き、お金も貯めていて、日本に行きたいと言っていました。 それからキューバへ行って、ヘミングウェイの小説「老人と海」の主人公のモデルとなったおじいちゃんと会ったり、チェ・ゲバラのモニュメントに向かい合って深く深く敬礼してみたりとしたのですが、それらのこと以上に、やはり前回は、カルメンと、アナ、エレーナのことがとても印象に残っています。 今年もまたツアーに参加した理由は、前回わたしたちがメキシコにいる間にカサ・アリアンサから路上へと戻ってしまった、カルメンを探すことが目的でした。 初日はわたしは自由行動できるという話だったので、その時に一人で街をぶらつき、カルメンを探そうと思っていました。しかし、いろいろな事情でカルメンを探す時間を作れませんでした。ただ、今年初め、ツアー責任者でもあり、フリージャーナリストのKさんがメキシコにビデオ撮影のために出かけた時、カルメンは家に帰っていて、時々路上に来ているらしいと聞かされていたので、そのことを信じるしかないです。カルメンが、シンナーや薬物で廃人になる前に家に帰ってくれているのならば。 それで今回はカルメンの話は無しです。カルメンと会えなかったことは、とても心残りではありましたけれど。 まずは、カサ・アリアンサでストリートエデュケータの人たちに、わたしたちが感想を言った時のことから話させてください。ツアー参加者の方々が現地のストリートエデュケータに、それぞれの感想を述べた時、若い女性が「わたしはこどもたちに何かをしてあげたくって来たのに、逆にこどもたちからたくさんの事柄をもらっただけでした。どうしたらいいんでしょう・・・」と言って言葉を切られてしまいました。それがとても印象に残りました。わたしもブラジルに行った時、同じことを感じたからです。 「プラッサ」を始めるきっかけとなったのは、このブラジル旅行でした。当時わたしは心筋梗塞で倒れ、手術をしたのですが、結果は思わしくなく、退職して家のそばの公民館のボランティアで日本語教室の手伝いをしていました。 そこで日系ブラジル人のTさんと出会いました。彼は生徒として日本語教室に来ていたわけではなく、やはりボランティアとして来ていたのです。Tさんはブラジルで識字運動とか、こどもたちの問題とかの活動をしていたのですが、経済的理由で日本に出稼ぎに来ています。ついこの間まで、大型トラックの運転手をしていたのですが、違反が重なり、とうとう免許取消になってしまい、つい先日帰国しました。 そんなTさんは、日本人ボランティアをどこか信用していないようでした。ちょっと距離を置いていました。それでわたしはある時Tさんに声をかけたのです。「ブラジルっていうと日本人だとリオのカーニバルを思い出すんでしょうけど、僕にとっては『ピショット』って映画なんです」。するとTさんは俄然積極的に話し出してくれました。「あんな映画は嘘っぱちなんだ。実際のこどもたちはもっとひどい情況にいるんだ」と。それから何時間も、いろいろなことを彼と話しました。それで、彼が一時ブラジルに帰国する時に、知り合いの写真家を誘って、ブラジルのこどもたちと会うための旅に出たのです。 実際にこどもたちと会うと、ことに路上に出ているこどもたちからはいろいろなことを教わりました。それからエリューダという黒人のシスターとも知合いました。彼女はサンパウロのプラッサ・ダ・セで、たった一人で子どもたちのための活動をしていたのです。 ご存じのようにその頃のブラジルでは毎日その広場でこどもが殺されていました。わたしたちがついた日も、また帰国する日も、エリューダと待ち合わせていたですが、こどもたちが警官に殺され抗議のためにエリューダは警察署に出かけ、会えないままでした。 こどもたちも当然殺伐としていました。だから、他のこどもの援助をしている組織は、プラサ・ダ・セのこどもたちの世話を避けていて、エリューダ一人だけがこどもたちの味方だったのです。 エリューダは実際、警官から暴行を受けていて腰の骨を痛めていましたし、こどもたちを自分の家に招いていると、彼女のものをこどもたちが盗むとかの、被害にも遭っていました。それでも彼女はこどもたちのことは許していました。警官にたいしてははっきりと向き合ってこどもを庇護していました。 彼女を助けてくれていたのは、サンパウロの弁護士会だけでした。直接的にではなく間接的にですが。ただ、弁護士会が彼女の後ろにいると云うことで、警官からの暴行はなんとかとどめさせていたようです。それでも脅迫は絶え間なくありました。私たちが帰国してから数ヶ月後に、彼女が所属している教会では彼女をアフリカに赴任させることにしました。これ以上彼女をプラッサ・ダ・セに置いておくことが彼女にとって、とても危険だと考えたからです。 彼女の旅費をこちらが持つことで、エリューダと一緒にブラジルの各地のNGOを回ってきました。そこではサンパウロで会ったこどもたちとはまた違ったこどもたちの顔が見えました。地方だと、まだそれほどこどもたちは殺気立ってはいませんでした。そして、わたしもまた、メキシコで若い女性がストリートエデュケーターに感想としてもらした言葉をいつのまにか漏らしていたのです。 「僕は、こどもたちから多くのものを貰った。だのに僕はこどもたちに何もあげるものがない。どうしたらいいんだ」って。 そして「プラッサ」をTさんと、一緒にブラジルに行った写真家の方と3人で初めたのです。援助とか、イベントとかを目的としてではなく、ただ日本にいる人たちに、こどもたちの状況を知ってもらうために。 ツアーの話に戻りましょう。若い人が、じっさいにこどもたちと出会って、気負ったものや頭で考えたことではなく、こどもたちと接することで大切なものを感じてもらえた。そのことがとてもうれしかったのです。 カサ・アリアンサのストリートエデュケーターの人が若い女性の方が口ごもらざるを得なかった感想への答えとして言っていました。「教育が大切だと思います」と。わたしもブラジルから帰国してそう思ったのです。わたし自身も含めてみんなで開発教育を勉強して行く場としての媒体を作ろうって。それが「プラッサ」でした。 でもやはり難しいですね。いつもプラッサを発行し続けることに、自分の中で疑問符をつけてしまっています。このことはこんどの機会にでも書かせて下さい。 ちなみに、わたしは感想として「口惜しみ」とだけ言いました。本当はなんにも言いたくなかったのです。言葉なんて無益だって思っていました。そうしたら通訳をしてくださっている方から「主語はなんですか?私ですか、それとも他の人ですか?」って聞かれてしまったのです。 通訳の方は前回、アナと、エレーナと会った時一緒にいてくれていた人なので、わかってくれていたとは思うんです。でも、仕事としての通訳では主語が必要だってこともわかります。だから一応「主語は私です」って答えたんです。 でも、本当は違うんです。主語は「私」じゃない。主語は、「望まないこどもを産んだ幼い母親」。主語は「カルメン」。主語は「路上で生活せざるをえないこどもたち」。主語は「アナ」。主語は「エレーナ」。主語は「生きるために苦しみを持っているすべての人々」。口惜しみは「私一人」の口惜しみではない。それぞれの人の、それぞれのあり方での「口惜しみ」なんだって。けれど、それを説明するのはとても難しかったのです。それで、「私」にしてしまうしかありませんでした。 そして最初に主語としてあげた、望まない子どもを産んだ幼い母親たちの支援をしている「ダヤ」というプロジェクトに、今回始めて行きました。今年のメキシコでは、カルメンと再会することはできませんでした。でも、新しい、とても忘れることのできない少女と出会いました。この「ダヤ」というプロジェクトでです。 その前にまず、日本人のツアー参加者が、ぞろぞろと少女たちの寝室を見学していた時のことから書かせてください。わたしは少女たちのプライベートな部屋を、じろじろと見て周るのが嫌で、広いリビングルームのようなところに行ってみました。そこに少女たちの妹らしい女の子たちが何人かいたからです。 その小さな女の子たちに話し掛けようとすると、もう一人日本人がいたのです。それは先ほど書いた若い女性でした。なぜ彼女が他に日本人から離れてそこにいるのかはわかりませんでした。ただ、カサ。アリアンサでの彼女の感想を聞いていたこともあり、わたしにはなんだか彼女の気持ちがわかるような気がしました。 小さな女の子たちの中に一人、とてもはにかみやの子がいました。わたしがカメラを構えると、恥ずかしそうに部屋の隅っこに隠れてしまうのです。すると彼女が「まずわたしを撮って。それをこの子に見せれば、この子も写真を撮ってもらいたくなるかもしれないから」と言いました。 そして彼女は、わざと面白い顔をしてレンズに向かいました。その写真を女の子に見せると、女の子は徐々に隅から出てきて、最後には彼女と並んでうれしそうな笑みを浮かべてカメラを見つめてくれました。 みなが少女たちの寝室を一回り見終わったところで、少女たちが自分の体験を話してくれることになりました。その場で、わたしはたまたま少女たちの席のすぐ横に座っていました。この施設では少女たちに自分の辛い体験をみなに話させることで、彼女たちに「今」という現実を見つめさせ、自分が産んだ子どもたちを愛せるようにしているようです。 三人の少女がわたしたちに体験を語ってくれたのですが、最後に話した少女など、なかなか話し出そうとしないのに、施設長の女性が促すようにして話を始めさせ出しました。 三人のうち真ん中に座っていて、かわいい男の子を抱いていた少女がいました。男の子はとっても可愛かったし、わたしのほうに手を伸ばしたりしたので、わたしもその男の子を抱き上げて、あやしたり、高い高いをしてやったりしていました。そうしながら少女たちの話を聞いていたのです。 男の子の母親は、涙ぐみながら話をしていました。だから思わずティッシュを渡してしまいました。ちょうど未開封のティッシュがあったので。そして少女たちの話を聞き終えた時、わたしはどうしようもない衝動から、少女たちの手をしっかりと握っていました。 「生きるんだよ。しっかりと、強く生きるんだよ。君たちのこどものためにも」わたしはそう叫びたかったのです。だから少女たちの手をしっかりと握り締めていました。そうする以外にわたしに何ができたでしょう? わたしたちが帰ろうとして外に出た時、例の男の子の母親が建物から飛び出してきました。そしてわたしの前に来て、何か話したそうにするのです。でも彼女は言葉を出すことができません。それは言葉が通じないからではないはずです。話したいこと、伝えたいことをどう表現していいのかわからない。だからひどく困り、いらつきながらも、わたしに話しかけようと一生懸命になっていたのです。 彼女は短い仕草で、小さくすばやく胸に十字を切りました。 「あぁ、マリア様、どうかこの日本から来た人に、私が伝えたいこの気持ちを話すことができますように。マリア様、どうかお願いします」 彼女の小さな十字には、そんな意味があるとわたしは直感的に感じました。 「だいじょうぶ。わかってる。わかってるよ」 わたしは少女にそれを伝えたかったのです。だから少女を胸に力いっぱい抱きしめてやりました。そしてそのあと少女の赤ちゃんも一緒にもう一度、強く、強く、思いっきり抱きしめてやりました。それしかできなかったのです。それだけしかできなかったのです。 いま一度の言問いです。わたしにそうする以外何ができたでしょう? あの少女には、片言であってもスペイン語で手紙を書きます。彼女に「愛」を信じてもらうために。わたしは彼女にとって父親だったのではないかと思っているのです。だからこそ、父親の「愛」を彼女に信じてもらうために。彼女が彼女のこどもをしっかりと愛することができるように。 そして帰り始めたみんなの後をわたしも歩き出しました。後ろを振り返るまいとしながら。振りかえったら、どうしようもない自分が見えてくる。無力過ぎる自分が見えてくる。抱きしめてあげることしかできなかった自分への口惜しみ。涙があふれそうでした。それをじっと我慢しながら歩いていました。 もう一つ。ストリートエデュケーターだった女性のことも話させてください。 アナというストリートエデュケータとは前回のメキシコ旅行で知合いました。路上に出る時、アナと、エレーナという二人の女性が案内役をしてくれたのです。道を歩きながらぼくはアナと、エレーナに「この仕事を辞めたいと思ったことはありませんか?」と聞きました。すると二人とも「毎日もう辞めたいと思っている」と答えたのです。それであらためて時間を作ってもらい食事しながらゆっくり話を聞きたいとお願いしたのです。 アナは、毎日路上でこどもたちと接することでノイローゼになってしまい、カサ・アリアンサのカウンセラーの女性に相談したそうです。すると答えは「あなたも大学で心理学科を出てるんでしょ。自分のことは自分で解決できるでしょ」と。 またエレーナは、未婚の母なのですが、路上で昨日まで元気だったこどもが、翌日行ってみてると死んでいたりする。それに、シンナーや薬物で自分がわからなくなっているこどもと接する時はとても危険な時もある。自分自身突然何らかの事故で死ぬ可能性もある。その時残された私のこどもはどうなるのだろうと思うとたまらない。そんな風に言っていました。 それから、カサ・アリアンサの批判もずいぶんしていました。給料自体が、幹部職員と彼女たち末端職員ではあまりにも違いすぎる。彼女らの給料は、一般の会社の中で使い走りをしている少年たちと同じぐらい。別に自分たちの給料をもっとあげろと云っているのではない。幹部の人たちの贅沢過ぎる給料を少しは減らして、その分もっとこどもたちのために使ってほしいのだと。 ただわたしの感想としては、カサ・アリアンサはそのような部分があるとしても、とても大切な組織だと思っています。グアテマラでは、今でも子どもたちが死の部隊(警官が多い)によって殺されています。ブラジルと同じです。でも、カサ・アリアンサの中米支部長のハリスさんが、体をはってそれを阻止しようとし、彼は現在グアテマラに戻れなくなっています。彼がグアテマラに戻ると、無実の罪で逮捕され、彼が告発した警官や殺し屋たちが入っている監獄に同居させられてしまいます。それは刑務所内部でのハリスさんへの暗殺を意味します。 メキシコでも、どれほど多くのこどもたちが、カサ・アリアンサのおかげで路上から、家庭や社会に戻っていけたことでしょう。ただ、組織のまずい部分はきちんと見ていかなくてはならないとは思っています。だからこそ、アナと、エレーナに会ったのです。 それはさておき、アナと、エレーナの話を聞いているうちにわたしはどうしようもなくなってしまいました。恥ずかしい話ですが、彼女たち実際に子どもたちと接している人たちの「口惜しみ」を痛感したのです。 レストランのカマレロは、涙ぐんでいるわたしを見て馬鹿にしていたことでしょう。マッチョの国です。男が女の前で泣くなんて。でも、アナはカマレロを呼んで、紙ナプキンを持ってくるように云いました。そしてそれをわたしにそっと渡してくれたのです。男が涙ぐみ、女がティッシュを渡す。それはおかしな風景だったかもしれません。 帰りも夜遅くなって、わたしがアナや、エレーナを心配すべきなのに、アナは「あんたはメキシコにはまだ不案内だから心配よ。一緒にタクシーでホテルまで送っていってあげるわよ」と言ってくれたのです。 それぞれの人の持つ「口惜しみ」と「優しさ」。 今年、アナはすでにカサ・アリアンサを辞めていました。エレーナはまだ頑張っています。それでわたしは、カサ・アリアンサの避難所でエレーナに会った時こう言いました。 「エレーナ、去年あなたたちに会った時に、あなたは路上生活のこどもたちがあなたに訴えかけてくる言葉を本にしたいって言ってたよね。こどもたちから『エレーナ、ぼくたちが言っていることをエレーナが文字にしてみんなに読んでもらってよ』と言われていたって言っていたよね。その話を外国から視察に来た人たちに話しても誰も取り合ってくれなかったって。でもぼくはあの時約束したよね。原稿がまとまったら、それを本にするための資金は絶対にぼくが何とかするって。だからエレーナ、がんばって原稿を仕上げてほしいんだ。少しずつでも進んでいるの?」 エレーナは答えました。「そうよね。でも今はとても忙しいの。もう少しすれば係長になれるから、そうすれば時間ができるわ。その時書き上げるわ」 あぁ、何という矛盾でしょうか。実際にこどもたちと接している時にはとても忙しくてものを書く時間すら作れない。それなのに、デスクワークの仕事につき、こどもたちと実際に接触することがなくなれば、原稿を仕上げる時間ができる。なんだかたまらなく「セツナイ」です。でも、エレーナにはこどもたちの本を書き上げてほしい。そう願っています。 最後に、わたしはこう思っているんです。人はそれぞれ、その心のうちで傷みを持っている。アナはアナの心の傷み。エレーナはエレーナの心の傷み。こどもたちはこどもたちの心の傷み、ツアーに参加した人にもそれぞれの心の痛み。そして、わたしはわたしの心の傷み。 その自分のうちの「心の傷み」と、しっかりと向かい合うことで、他者の傷みを理解することができるようになる。他者の傷みを、自己の中で追体験することができるようになる。そしてはじめて、ほんとうに「優しさ」を知り、持つことができるようになる。 青二才みたいなことを書いています。それでも、「追体験」を自分の中でどう受けとめていくべきなのか。高校時代からこの歳までずっと持ちつづけている、テーマなのです。 民族とは、国家とはとの「問い」と合わせて。 こうしてキーボードを叩いているわたしの右手首に、ミサンガが結ばれています。とても綺麗に編まれた紐です。なんだかいつもこのミサンガが気になってしまいます。こういった決して外してはいけないものをするのは初めてなので、うっとおしく思えることもあります。 でもこのミサンガは、一時滞在施設の男の子が結んでくれたものです。わたしの勝手な思い込みなのですが、ミサンガには少年からのメッセージが入っているって気がするんです。 「日本に帰ったって、ぼくたちとつながっているんだからね」。 帰国直後に知人の若い方にこのことを話しましたら、「それをみて『何かをしなければならないのでは?』という気持ちになるのではなく、今、本当にしたいこと、に力を注ぐためにその紐はあるのではないかしら」と、答えてくれました。 そう、それが今回の旅の答えなのかもしれません。
|
| 1999年8月 |