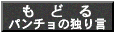
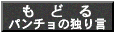
| カルメンという少女 |
|
メキシコでカルメンという少女と出会った。メキシコに着いたその日に僕は「カサ・アリアンサ」でカルメンという少女と出会った。マルセリーノとも会った。ほら、「とんでごらん」という本のの主人公の少年、マルセリーノとも。 メキシコには、現地時間で10月10日の夕方には着くはずだった。だが飛行機が大幅に遅れ、11日の午前1時ごろ僕たちはやっとメキシコシティに着いた。ホテルのベッドでのほんのちょっとした眠りの後、みんなはきっとそれぞれの思いを持ってメキシコの子ども支援現地NGO「カサ・アリアンサ」に向かったのだと思う。僕は? 僕はただ心臓の痛みを覚えただけ。心の痛みじゃない。心臓そのものの痛みだ。心臓に病気を持っている僕にとって、高地に位置するメキシコシティへ行くことはちょっと不安だった。酸素が少なければそれだけ心臓に負担を掛けることになるのだから。空気はやっぱり薄かったし、みんなと同じ早さで歩くのは辛かった。だけどそうじゃなかったのかもしれない。本当は心そのものが痛みだしていたのかもしれない。怖かったのかもしれない、子どもたちと会うことが。 メキシコまでの往復の飛行機代とホテルに泊まる金を持っている僕と「カサ・アリアンサ」にいる子どもたち。そのあまりもの違いが僕の気持ちを縛り付けている。以前ブラジルに行った時もそうだった。サンパウロ市の中央にある広場で、路上で生活せざるをえない子どもたちと会った。地方の都市の子どもたちのための施設でも、多くの子どもたちと会った。でも子どもたちにとって僕は通りすがりの人間でしかない。僕もまた日本に帰れば子どもたちのことを忘れていく。子どもたちが精一杯生きようとしていることすら、僕は忘れていってしまう。メキシコでだって同じことだろう。スペイン語のできない僕が、あるいはたとえできたとしても、僕は子どもたちとどれほども一緒にはなれないだろう。メキシコシティの薄い空気ではなく、僕のそんな思いが心臓に負担を掛けていたのかもしれない。 「カサ・アリアンサ」の所長から話を聞いた後、僕たちは子どもたちが居る食堂に行った。そこにカルメンがいた。マルセリーノもいた。でも僕にはまだそれがわからなかった。カルメンもマルセリーノも子どもたちのうちの一人でしかなかったから。僕たちは子どもたちと一緒に食事をする。子どもたちは好奇心いっぱいの笑顔で僕たちと接してくれる。その笑顔の中にマルセリーノがいた。おだやかな笑顔。「君がマルセリーノ?僕は君のことを知ってるんだ。君のことを書いた本を読んだんだ。会えるなんて思ってもいなかったよ」僕は思わず日本語で話しかける。通じようが通じまいがそんなことは関係なかった。僕はただ、お客さんとしてだけ訪れたんじゃないということを解って欲しかったんだ。それに本の著者のから、マルセリーノが今どうしているかについては日本で聞いていた。シンナーもやるようになり、カサ・アリアンサにも居つかないということを。だからよけい、マルセリーノに何かをうったえたかったんだ。でもマルセリーノは笑っているだけだった。そりゃあそうだ。僕が何を言っているのかマルセリーノにはわからないんだから。やさしい笑顔だ。それが僕にはとても辛かった。こんなやさしい笑顔をもった子が、結局はシンナーの内でしか生きることができないんだとしたら。そして僕は無力だ。あまりにも無力だ。今でも、そしてきっといつまででもマルセリーノの笑顔が浮かんでくるだろう。静かな、でも何かを諦めてしまったような笑顔を。 子どもたちは自分の写真を撮ってくれと競うようにして僕の前に来た。僕は撮りまくった。僕のような素人のコンパクトカメラであっても、写真を撮ってもらうその瞬間子どもたちは主人公になる。カメラの前で主人公になれるんだ。フィルムは残りあと一枚。そこで写真撮影は終わり。「一コマ分だけはフィルムを残しておけ。どうしても撮りたいことが起こるかもしれないから」ずいぶん以前そんなことを言われたことがある。フィルムが無くなると子どもたちは僕の回りからいなくなる。その時一人の少女だけが僕の横に残っていた。自分の写真を撮ってもらうために、他の子よりも先にカメラの前に立てなかった少女。ちょっとおてんばそうで、でもはにかみ屋みたいで。みんながいなくなったあとで僕の袖を引っ張って写真を撮ってって言っている少女。とてもかわいかった。それがカルメンだ。僕はカルメンがとっても気に入ってしまった。僕はカルメンにカメラを見せ「もうフィルムが無いんだよ」と言う。もちろん日本語で。でもカルメンは離れない。フィルムが無いということがわかっても。カルメンも僕のことを気に入ってくれたのかもしれない。マルセリーノことを書いた本の著者のが僕たちの所によってくる。「このおじさんと一緒に行く?」「いやよ」「でも、日本に行けるよ」「じゃぁ一緒に行く」こんなかわいらしい会話が二人の間で交わされる。カルメンはにっこり笑って僕の方を見る。その時僕は思ったんだ。カルメンを養女にしたいって。本の著者の冗談がふとしたきっかけを作ったのかもしれない。それまで僕はヨーロッパ人がよくやっている第三世界の子どもを養子にするという行為を否定的に見ていた。里親制度についてだって疑問符をつけていた。それなのに僕はカルメンを痛烈に養女にしたいと思ったんだ。そんなことはできっこない。それはわかりきってる。ストリートで生活してきたカルメンにとって日本での生活なんて、彼女にとっての本当の幸せにはつながらないだろう。でも僕はカルメンが日本に来ることで幸せになる。そう思ってしまったんだ。彼女を幸せにしたい。 僕にはその時はっきりとカルメンの顔が見えた。今までカメラの前にたっていた子どもたち以上にはっきりとカルメンの顔が見えた。それが大切なんだってわかった。マルセリーノの顔が見える。カルメンの顔が見える。それが大切なんだ。一人の子どもの顔をはっきり見つめることで、はじめて多くの子どもたちの顔が見えてくるんだ。たった一人の子どもも愛せなかったら、他の子どもたちも愛せやしない。しかしどんなにマルセリーノやカルメンをいとおしく思い、思いっきり抱きしめてやりたくても、それはできない。僕たちがこの地球の中で造ってしまっている大きな重しを、僕たち自身が取り除かなくてはそれができない。カルメンやマルセリーノことを思い出すと今でも涙が出てくる。悲しいからじゃない。悔しいからだ。大きな重しを取り除くためにまだまだ力の足りない自分に対して腹が立つからだ。 僕のアルバムにカルメンの写真が一枚だけある。僕はカルメンと中庭にでた。僕の同行者たちはそれぞれ中庭で子どもたちと遊んでいた。僕は一枚だけ残っていたフィルムでカルメンを撮った。「最後の一枚だけは残しておけ」その言葉の意味を初めて感じた。
|
| 1996年10月 |