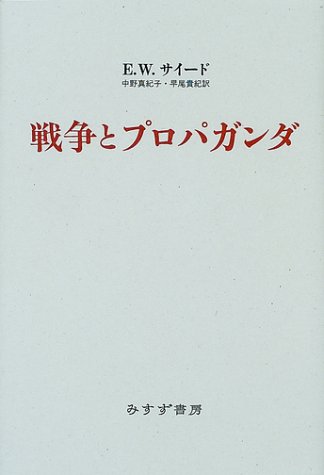
| 書 評 |
| E.W.サィード「戦争とプロパガンダ」から |
| みすず書房 |
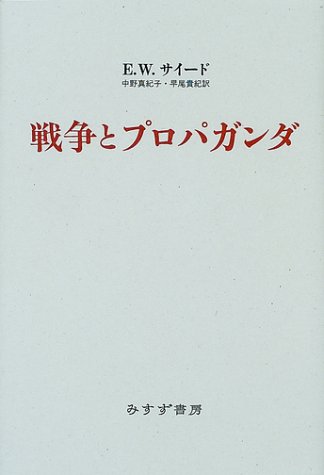
サィードって誰?
私が、初めてその名前を知ったのは、朝日新聞社の往復書簡の形で小説家大江健三郎が対談した記事を読んだときであった。1935年イギリス統治下のエルサレムに生まれたサイードは、アメリカのニューヨークに住んでいて、パレスチナ問題や、「世界の今」に対する鋭く且つ厳しい考察と未来への希望を述べていて、印象的であった。
そのサィードが、<9.11>以降、ニューヨーカーとしてどのようにアメリカをみているか、アフガニスタン侵略戦争やパレスチナ問題をどのように考えているのかを知りたかった。「戦争とプロパガンダ」では、マスコミと政治が一体になって「西洋とイスラムの文明の衝突」などと誇大な抽象概念をふりまわし、「われわれの敵に対する戦争」を正当化するアメリカ国内の集団的熱狂とブッシュ政権の人間的倫理観喪失、狂気が描かれている。
以下、その一部をサィードの言葉として紹介する
サィードは語る。
ⅰ)アメリカ内のイスラエル支持者は、「我々はいまやみなイスラエル人である」といったヒステリックな叫び声に訴えつつ、世界貿易センターおよびペンタゴンへの攻撃とパレスチナ人のイスラエルへの攻撃との関係を「世界テロ」という絶対的な結合にまでしてしまっている。そこではビンラディンとアラファトとは、相互に入れ替え可能な存在となっている。
ⅱ)ハンティントンは「今日、世界中で10億人にも達するムスリムたちは、みずからの文化の優越性を確信しているが、その一方で、支配力においては劣勢におかれているという考えに取り付かれている」という。いったい彼は多様なムスリム集団をきちんと検証しているのだろうか。欧米のめぼしい新聞や雑誌はどれをとっても、この巨大化した終末論的な語彙を増強するような論説であふれている。・・・・・
ⅲ)時局は緊張しているが、わたしたちはあくまでも、有力な共同体と無力な共同体、理性と無知とのあいだの宗教とは無縁のかけひき、正義と不正という普遍的な原則などを思考の軸にすえなければならない。広漠した抽象論に走っても、つかのまの充足が得られるだけで、自己認識にいたる事や事情を踏まえた分析を行う事は望むべくもないから。ハンティントンの「文明の衝突」理論は、「宇宙戦争」というのと同じようなイカサマの新機軸にすぎない。自己防衛的になった自尊心を補強するには役に立っても、現代の困惑するような相互依存の現実を批判的に理解するには使いものにならない。
このように述べてサイードは、アメリカ合衆国が異様な興奮状態につつまれ戦争熱が盛り上がる中で、過度の言辞と抽象化に走ることの危険を指摘し、冷静に現実に起こっている事態を見据えよと訴えている。
そして、パレスチナ解放運動に深くコミットし、もっとも強力な代弁者として、彼は、パレスチナと、イスラエルの民衆の「共生」を主張し続けているのである。

ⅳ)今日、アラブとしての私達の主な武器は軍事的なものではなく道義的なものであるとわたしは長年に渡り繰り返してきた。また、イスラエルの圧制をくつがえし自治を獲得しようとするパレスチナ人の闘争が、南アフリカにおける反アパルトヘイト闘争にように、世界の人々の想像力に訴える事が出来ない理由のひとつは、わたしたちが(パレスチナ人又はアラブやイスラームの民衆の両方の意味か...筆者注)自分たちの目標や手段をはっきり自覚しているとは思われず、自分たちの目的とすることは他者の排除でもなければ牧歌的な神話の世界への回帰でもなく、「共生」であるとうことを十分にはっきりと表明してこなかったためであると述べてきた。・・中略・・自分たちに期待することが、他者に期待すること以下であってはならない。私達の指導者がどこへわたしたちを導こうとしているのか。またいかなる理由にもとづいてそうするのかを、全ての人に立ち止まって考えてもらいたいものだ。懐疑的態度や再評価は必需品なのであって、ぜいたく品ではないのだ。
ここまで読んでくると、これは、けっして対岸の火事ではないとつくづく思うのであった。まったく戦争中の日本と同じではないか。
「過度の言辞・抽象化が集団的熱狂を生み出す」ということが、いかに戦争への道を歩む事になったか、そして「イスラエルとパレスチナに共生が必要」ということも、また日本のくらしはアジアのくらしの一部にという哲学者鶴見俊輔の言葉につながっている。
パレスチナ一般市民に無差別に砲撃を浴びせるイスラエル占領軍に、投石で対抗する少年たちを「攻撃者」と呼び、被害者を加害者にすりかえるメディア。すでに言論統制は剥き出しになって私たちの世界を覆っている。
アフガニスタン民衆の殺戮に加担する日本、合衆国メディアの受けたれ流しが進行する日本、そのような事態に断固として反対する事が人間としての道義的責任とも言うべき事なのだ。
サィードの声にもう一度耳を傾けよう。