(1) この“研究ノート”は、米国の研究者チャルマーズ・ジョンソン氏の最新刊『アメリカ帝国の悲劇(THE SORROWS of EMPIRE)』(原著2004年、邦訳2004年9月)の抜粋集である。私たちは先に、イラク戦争・占領支配の泥沼化の中で、米軍が深刻な危機に陥っていることを新シリーズで明らかにした。とりわけ米軍事力の根幹をなす地上兵力が過小兵力とベトナム戦争以来の激しい市街戦の下で、肉体的・精神的ダメージ、物質的・財政的ダメージを受けて継戦能力を維持できなくなっている実情を克明に実証した。 ※「ベトナム戦争以来のゲリラ戦・市街戦、二巡目の派兵をきっかけに顕在化した過小戦力、急激に深刻化し増大し始めた損害」(署名事務局) しかし、米軍事力はイラクでの地上兵力の異常な消耗だけで一途危機に突き進んでいくわけではない。イラク地上兵力の危機は決定的ではあるが、あくまでも米軍事構造の一部である。空軍や海軍や核戦力を持っているとともに、世界中に張り巡らされたグローバルな軍事基地網を持っている。本書は、この軍事基地帝国アメリカの全体像を解き明かしてくれる恰好の実証研究書である。私たちは、この書から米軍基地ネットワーク全体のイメージをつかむと同時に、この基地帝国がどこから、どのようにして瓦解していくのか、基地帝国が抱える諸矛盾についても明らかにするよう努めた。そして、このことを通じて、アメリカ帝国主義の軍事構造の強さと弱さを可能な限りトータルに把握する出発点としたい。 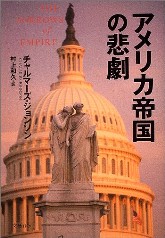 (2) チャルマーズ・ジョンソン氏は、米国の著名な国際政治学者で、「日本、中国の政治・経済研究の権威である」(「訳者あとがき」)。彼の研究歴と自己紹介は、後で紹介する『アメリカ帝国への報復』の「プロローグ--帝国を支えてきた私」に詳しく書かれている。 彼は、1967年から1973年にかけてCIAの国家評価局の顧問をしていた人物である。政府機関の中枢にいた彼は、在野に下り、一転してリベラルな立場から米軍批判、米政府批判を展開するようになる。今では、誠実で真摯な学者として、また米国の未来を憂える者として米国を告発しているのであるが、かつての地位からして内部事情に精通しており、彼の言葉は具体性と説得力に富んでいる。本書は、全世界に張りめぐらされた軍事基地のネットワークを通じて世界を支配しようとするアメリカ帝国主義の最も重要で本質的な側面についての実態を克明に暴いたものである。 著者は本書の冒頭で、沖縄訪問、沖縄体験がきっかけであった、と本書の着想を告白している。沖縄の実情に衝撃を受けただけではなく、それが“例外”“特殊”であるどころか、軍事基地帝国アメリカの“普遍”的構造であったことにより強い衝撃を受けたことが、彼にこの膨大な実証研究書を書かせたのである。 「アメリカ国民は、地球上のほかの国々に住む人々とちがって、アメリカ合衆国が軍事力で世界を支配していることに気づいていない――もしくはその事実を認めたがらない。政府の秘密主義のせいで、アメリカ国民は多くの場合、自分たちの政府が全世界に軍事基地を置いていることを知らない。南極大陸以外のあらゆる大陸にはりめぐらされたアメリカ軍基地のネットワークが、じつは新しい形態の帝国を築いていることを認識していないのである。」(「プロローグ」冒頭) 「1996年2月まで、わたしは軍隊と積極的なかかわりを持たないほかの大半のアメリカ人とおなじように、われわれの軍事基地の帝国にごくわずかな関心しか向けていなかった。わたしはそのとき、わが国が1945年以降ずっと占領してきた日本の小さな島、、沖縄にある事実上のアメリカの軍事植民地をはじめて訪れたのである。」「沖縄訪問後、わたしは沖縄駐留アメリカ軍の歴史について調査をはじめ、それについて文章を書いた...。わたしの視点はあくまで学者としてのものだった。わたしは大学教授として日本と中国の政治経済を研究することに人生を捧げてきた。アメリカの全地球的な軍事覇権主義を分析するのが仕事ではない。沖縄に住んでいない多くの日本人がそうであるように、わたしはこの島の状況を特異なものだと見なしがちだった。」「沖縄が特異ではなく典型的な例であることをわたしが理解するのには時間がかかった。」(「プロローグ」p.12~14) (3) 彼はまた、9.11事件のような事件が起こることを予想した『アメリカ帝国への報復』(原題“BLOWBACK:The Costs and Consequences of American Empire”鈴木主税 集英社刊)の著者として知られている。今回の著作はこの前書の続編として書かれたものである。その事情を著者自身が次のように述べている。 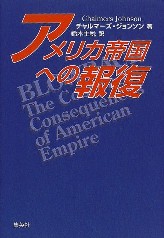 「報復(ブローバック)とは、他国に対する非公認の活動によってもたらされた思わぬ結果を意味するCIAの用語である。この本(『アメリカ帝国への報復』)の目的は、ソ連崩壊後の十年間と東アジアの変化する政治状況に特に焦点をしぼりながら、わが国の外交政策がそれまでの半世紀に行なってきたことについてアメリカの同胞に警鐘を鳴らすことにあった。本は2000年の初春に出版された。同書の中でわたしは、アメリカ政府が国外でやっていることは多くの面で、その犠牲になった国々や人々からの報復攻撃を誘っているのに等しいと主張した。二十世紀後半からの報復はまだはじまったばかりだ。」(『アメリカ帝国の悲劇』「プロローグ」p.15)
「報復(ブローバック)とは、他国に対する非公認の活動によってもたらされた思わぬ結果を意味するCIAの用語である。この本(『アメリカ帝国への報復』)の目的は、ソ連崩壊後の十年間と東アジアの変化する政治状況に特に焦点をしぼりながら、わが国の外交政策がそれまでの半世紀に行なってきたことについてアメリカの同胞に警鐘を鳴らすことにあった。本は2000年の初春に出版された。同書の中でわたしは、アメリカ政府が国外でやっていることは多くの面で、その犠牲になった国々や人々からの報復攻撃を誘っているのに等しいと主張した。二十世紀後半からの報復はまだはじまったばかりだ。」(『アメリカ帝国の悲劇』「プロローグ」p.15)「本書『アメリカ帝国の悲劇』は、わたしの前作『ブローバック』から必然的に生まれたものだ。あの本のなかでわたしはアメリカ政府が多かれ少なかれ冷戦時代と同じように機能していると考え、東アジアで紛争が起きる可能性を強調した。しかし、アメリカにおける軍国主義の程度や、ほとんど気づかれずに出現して、いまやまぎれもない地政学的現実となった巨大な基地の帝国には焦点を合わせていなかった。」(『アメリカ帝国の悲劇』「プロローグ」p.19) 「本書が対象とするテーマは、アメリカの軍国主義と、全世界に広がるその実態、大統領の私兵部隊としての「特殊部隊」の拡大、そしていっそう軍事化され、気密性の高まった組織が生きて増殖することを許す秘密主義である。」(『アメリカ帝国の悲劇』「プロローグ」p.20) 彼は左翼ではない。リベラルの立場から、米ソ冷戦の下で、軍拡競争をエスカレートさせ軍事帝国となったソ連社会主義が負担に耐えきれず崩壊した歴史的事実に衝撃を受ける。そして今アメリカ自身がこのソ連と同じ道を歩んでいることに危機感を抱き、警告を発しているのである。 「冷戦の終結後、アメリカは軍備を縮小するどころか、無謀にも帝国として世界に君臨する道を選んだ。アメリカのこうした政策は各国の怒りを買っており、21世紀にはとりわけアジアの国々から経済的・政治的な報復を受けると考えられる。本書は、アメリカの帝国主義が招いた怒りと、それに対する報復について説くものである。」(『アメリカへの報復』「プロローグ」p5) 「冷戦後のもとソ連邦に起こったことと、今世紀末におけるアメリカのありかたのあいだには共通点がある。」「アメリカの過度にふくれあがった軍事システムと兵器製造業者を支援しつづけるアメリカのシステムは、ソヴィエトのシステムの非能率と同等の意味を持っているのだ。」「すでにアメリカは、いま行われている世界的な軍事的展開とさまざまな介入の費用をまかないきれなくなっており、保護していると称する国からますます多額の『(基地)受け入れ国支援』を引き出すばかりか、『同盟国』から軍事援助に対する直接的な報奨金をせしめている。」「世紀末のアメリカ軍部は独走するシステムになりつつある。」「21世紀の世界政治を主として動かすものは、きっと世紀の後半から始まるブローバック--つまり冷戦と冷戦後の世界でアメリカが冷戦時代の姿勢をとりつづけようと決意したことの予期せぬ結果として生まれるブローバック--であろう。」(『アメリカの報復』第10章 「帝国の末路」より) そして、彼は深刻な提起をする。アメリカ帝国主義の軍事的、通貨・金融的、技術的・生産的世界覇権の歴史的没落の弁証法とでも言うべき展望である。彼はとりわけ、軍事帝国没落の背景を、ドル帝国アメリカの経済危機に焦点を当てて捉えようとしている。そして私たちが驚くのは、この展望が、9・11の1年も前に、すなわち第一期ブッシュ政権誕生の前に打ち出されたことである。(『アメリカの報復』の原著も邦訳も2000年)イラク戦争・占領の泥沼化が深刻化し、米軍の過小兵力と過剰展開の危機、基軸通貨ドルの新しい危機が絡み合って顕在化したのは、ブッシュ再選が明らかになった昨秋のことだが、著者は4年も前に、ある具体性を持って、しかも確信を持ってアメリカの歴史的没落を見通していたのである。 「歴史を振り返ってみても、衰退しつつある覇権国がその流れを逆転させたり、権力をおとなしく手放したりした例はほとんど見当たらない。・・・となれば、こう結論せざるを得ない。ブローバックがやがて危機につながり、にわかにアメリカの覇権主義的な影響力をひどく損なうか、あるいはそれを消滅させるだろう、と。帝国がアメリカの軍部にほとんど神聖と言っていいような地位を授けたことを考えれば、危機はアメリカの国内ではまず起こりそうにない。したがって、どんな改革運動も考えられないことから、最も起こりそうなのは、経済的な矛盾が頂点に達してアメリカ帝国の実態が明らかになることだろう。」(『アメリカの報復』第10章 「帝国の末路」p278) ****************
以下の抜粋集。まず見出し・項目区分は全て署名事務局の関心で付けたものである。従ってベースにした著書の目次とは異なる。各項目の最初に、私たちのノートを示し、その後に引用符(「 」)で、関連箇所の抜粋を行った。言うまでもなく、本格的な研究をやるためには、直接当該著書に当たっていただきたい。なお、縦書きの著書を横書きで引用したことに伴って、年月日と統計数値の漢数字は算用数字に切り替えた。
2005年2月24日
アメリカの戦争拡大と日本の有事法制に反対する署名事務局 [目次] ○ はじめに――世界に張りめぐらされた軍事基地ネットワーク―― Ⅰ.軍事基地帝国 (1)拡大・増殖する軍事基地ネットワーク 1)140万人の「平時の」軍隊と公称725ヵ所の海外米軍基地 2)地方総督として君臨する各方面軍の戦域最高司令官(CINC) 3)9.11後の拡大・増殖と「米本土防衛」の“北方軍”創設 4)基地帝国再編の現局面――表向きは機動性と効率の重視、その内実は石油シフトであると同時に米軍事力の限界の露呈でもある―― (2)米軍を補完する「現代版のセポイ(現地傭兵)」 (3)宇宙を軍事化して地球を支配する――世界支配の道具としてのMD―― (4)冷戦が生み出した新種の軍事帝国――その進化と9.11を契機とした全面展開―― Ⅱ.軍産複合体 (1)政府との癒着・融合と軍事予算の分け取り。戦争によって肥え太る軍産複合体 (2)軍事基地帝国に寄生するもの。軍事経済の肥大化 (3)「軍事の民営化」と「民間軍事会社」の隆盛 Ⅲ.石油支配 (1)石油獲得が死活的利害に (2)アフガン戦争も石油動機 (3)石油略奪戦略の要としてのイラク戦争 Ⅳ.軍事基地帝国の諸矛盾 (1)志願制の矛盾――貧者が富者のために戦う軍隊―― (2)人種差別と性犯罪――軍内部と基地周辺で常態化―― (3)劣化ウラン被曝を含む戦争後遺症 (4)独裁的大統領権力とファッショ的人権抑圧 (5)外交的権威の失墜と国際的孤立 (6)世界に点在する「軍事都市国家」。地元住民との矛盾・軋轢 (7)致命的な財政破綻と経済的荒廃
1)140万人の「平時の」軍隊と公称725ヵ所の海外米軍基地 ・米軍の現役兵力は、140万人弱。 陸軍48万人、海軍37.5万人、空軍35.9万人、海兵隊17.5万人。 ・予備役は、87万人プラス40.5万人超(1999会計年度)。 「現役の予備役軍人――陸軍州兵、陸軍予備役、海軍予備役、海兵隊予備役、空軍州兵、空軍予備役――」が約87万人。「非現役の予備役と非現役の州兵」が40.5万人超。 ・2001年9月時点で、現役兵力の約25.5万人を153ヵ国に派遣(民間人や扶養家族を加えると53万人強)。 ・国防総省が認めている米国外の軍事基地は725ヵ所。 実際にはこれよりもずっと多い。各種の偽装やごまかしがあり、また秘密にされている部分がかなりあるから。 ・153ヵ国に軍隊を置き、そのうち25ヵ国に大規模部隊を駐留させ、36ヵ国と軍事条約を結んでいる。 2)地方総督として君臨する各方面軍の戦域最高司令官(CINC) ・9.11までは、中東を中心にアフリカの角から中央アジアまでをフォローする「中央軍」、日本を含む43ヵ国をフォローする「太平洋軍」、ヨーロッパをフォローする「欧州軍」、ラテンアメリカをフォローする「南方軍」の4つの方面軍。2002年に米国、メキシコ、カナダ、キューバをフォローする「北方軍」を創出して5つに。 ・各方面軍の戦域最高司令官は、CINC(Commander in Chief)と呼ばれ、その司令部は「おおむね文民や軍の指揮系統の外に存在」している。「ローマ時代の地方総督に匹敵」。シンク(CINC)は、各地域の外交政策に当たる「戦域管理政策」を提出するが、「各軍の長や通常の指揮系統を飛ばして、大統領と国務長官に直接報告を行なう。」 <註> それぞれの管轄地域は「シンク帝国」と呼ばれている。「24ヵ国を統轄する米中央軍の司令官であるジニ(1998~2001)は、アメリカ史上に例を見ないほどの権力を掌握している。彼の帝国をスタッフは「シンク帝国(CINCDOM)」と呼ぶが、それはアフリカの角からアラビア半島を越え中央アジアにまでいたり、イランやイラク、アフガニスタンも彼の領土だった。」(『終わりなきアメリカ帝国の戦争』p.71/デイナ・プリースト著/原書『THE MISSION』は2003年イラク戦争直後に出版/邦訳は2003年12月・アスペクト)。この書は、イラク戦争での従軍記者たちによる翼賛報道を先取りしたような、米軍賛美の取材記であるが(特にアフガン戦争をあつかった章などは反吐が出るほどであるが)、「ワシントン・ポスト」紙の記者である著者は「本書のために四年を費やし、また一年半の休暇をとって世界十八ヵ国の戦場に潜入、国防長官にもまさる影響力の方面軍司令官三人に密着取材し、...」(「訳者あとがき」)とあるように、通常うかがい知ることのできないような事柄を多く伝えている。 ・CINCたちは、「長年のうちに、自分の担当する戦域で大使よりも大きな影響力を持つようになってきている。」国防総省は事実上、国務省の外交機能を奪い取っている。国防総省の予算は、国務省の予算の20倍である。 ・国防総省が運営する「国家安全保障局(NSA)」と「国家偵察局(NRO)」がCIAの秘密情報収集機能と競合し、陸軍特殊部隊(グリーンベレー)が秘密工作・秘密作戦でCIAを押しのけている。 3)9.11後の拡大・増殖と「米本土防衛」の“北方軍”創設 ・9.11以降、アフガニスタンとイラクでの2つの戦争をつうじて、東ヨーロッパ、イラク、ペルシャ湾岸、パキスタン、アフガニスタン、ウズベキスタン、キルギスタンで14ヵ所の新しい基地を建設。 ・9.11を契機に2002年に創出された「北方軍」は、伝統的な米国の価値観の一つについての根本的転換を画するもの。チャルマーズ・ジョンソンによれば、「第二次世界大戦でも、連邦政府はアメリカ本土防衛のための統一司令部を作らなかった。軍部の独裁の基盤になるかもしれないと懸念したからである。」ブッシュ政権の下で、9.11を契機として、米国の国内政治体制は、軍部独裁的ファシズムに向けて大きく歩を進めたのではないか。 4)基地帝国再編の現局面――表向きは機動性と効率の重視、その内実は石油シフトであると同時に米軍事力の限界の露呈でもある―― 現在、日本や韓国の米軍基地も含めた全世界的な米軍基地の再編成が行われようとしている。それについての詳しい暴露が、2004年11月11日付けでダニエル・スミス米退役大佐によって行われた。「フォーリン・ポリシー・イン・フォーカス(Foreign Policy In Focus)」に掲載された米軍再編の最新局面についての論説である。 ・主要な米軍基地は230、そのうち202が米国にあるか米国の所有。また米軍は、5,458の「世界中のさまざまに異なった控えめな軍事施設」に依存している。(2004年8月16日の国防総省と国務省共同の「Global Posture Review」に関する背景説明のブリーフィング) ・これらは3つの主要なカテゴリーに分けられる。 MOB(主要作戦基地 Main Operating Bases):恒久的に駐留する兵力と家族を伴う。 FOL(前進作戦拠点 Forward Operating Locations):「暖かい」施設と小さな軍事サポートグループを伴うが家族は伴わない。 CSL(防衛協力拠点 Cooperative Security Locations):訓練、演習、軍事交流のためだけの施設。 ・基地を上記のように3分類して、機動性と効率を追求した再編・強化を行おうとしている。総じてMOBを減らし、FOLとCSLを増やそうとしている。これは、基地帝国を維持する負担を軽減しようとするもの(したがって限界の露呈)でもあると思われる。 アジアでは、「日本と韓国の施設と司令部を統合することを構想している。」 ヨーロッパでは、ドイツのMOBを縮小して最重要なMOB以外はFOLに格下げし、MOBの拠点をイタリアに移そうとしている。「必要に応じてより急速に他の地域に展開するため」の配置を追求。 中東では、新たに獲得された軍事拠点を、FOLとして維持し拡大・強化しようとしている。 アフリカと西半球では、CSLを中心に構想されている。 ・これらの再編は、「石油資源と石油の輸送問題に結びつけられている」。米国の同盟諸国や米軍基地の所在地と、米国が石油を輸入している主な産油国(15ヵ国)との間には、一定の不一致がある。米軍の再編・再配置は、この不一致を解消する方向によりいっそう近づけようとするものでもある。 米国が石油を輸入している主な15ヵ国の内訳 : (NATO加盟国)・・・カナダ、ノルウェー、イギリス (NATO外の国)・・・(米国と基地協定を結んでいる国)サウジアラビア、クウェート、エクアドル (米国が占領中)イラク (その他)8ヵ国 「2001年9月の段階で、国防総省はアメリカ国外に少なくとも725カ所のアメリカ軍基地が存在することを認めている。実際には、その数はもっと多い。いくつかの基地は土地賃借権や非公式協定、または各種の偽装のもとに存在しているからである。しかも、この発表が行なわれてからさらに多くの基地が建設されている。」(「プロローグ」p.10) 「冷戦の終結とともに、それまでソ連の影響圏として立入禁止だったバルカン半島とパキスタンにはさまれた広大なユーラシア大陸の領土が、帝国的拡張政策の舞台として開放された。アメリカはこのきわめて重要な地方にすばやく軍隊を展開させ、じゃまをする体制といつでも戦争をはじめる構えをとった。10年ほどのこの時期に、権益や制約や計画の膨大な複合体がからみあい、ついには市民社会に匹敵する新しい政治文化が誕生した。わたしが帝国と呼んでいるこの複合体は、あきらかに――はっきりとした形さえ持って――この地上に物理的に存在する。その大部分は第二次世界大戦と冷戦時代に取得されたものだが、ソ連を封じ込めるという口実にごまかされてその真の姿に気づかれなかった。この帝国は、地球上のあらゆる大陸にある恒久的な海軍基地や軍用飛行場、陸軍駐屯地、情報収集基地、戦略的飛び地などで成り立っている。」(「第一章」p.33) 「...現在、アメリカ陸軍は48万名、海軍は37万5000名、空軍は35万9000名、海兵隊は17万5000名の兵員を有し、総計で138万9000名の男女が現役任務についている。こうした制服組の給与総額は2003年には、現役陸軍が271億ドル、海軍と空軍がそれぞれ220億ドル、海兵隊が86億ドルに達している。」(「第三章」p.102) 「1999会計年度を対象とした国防総省の『各軍における人口表示』に関する第26回年次報告は、手に入る最新の報告書だが、これによれば、常勤の現役勤務についている軍人は140万名弱である。それにくわえて、現役の予備役軍人――陸軍州兵、陸軍予備役、海軍予備役、海兵隊予備役、空軍州兵、空軍予備役――が合計で87万100名弱になる。さらに40万5000名以上の男女が非現役の予備役と非現役の州兵に入っている。1999年度に全軍は約18万4000名の新兵を採用し、かつて軍にいたことがある人間が6000名近く現役任務に戻っている。新規に任官した1万6000名以上の士官が現役任務についた。さらに1999年度には、軍隊経験のない約5万5000名の新兵と、軍隊経験を持つ8万8000名以上の兵士が予備役に編入された。1万7000名をこえる士官が州兵もしくはほかの現役の予備役部隊に入隊した。」(「第四章」p.132~133) 「2002年夏、ブッシュ政権は司法省と国防総省の弁護士たちに指示して、国内の法執行に軍が関与する能力を制限する民警団法などの法律を見なおさせた。当時、国防総省はラテンアメリカやヨーロッパ、中東、太平洋の各地域軍に相当する北アメリカ防衛の新しい地域軍を設立しているところだった。コロラド・スプリングスのピータースン空軍基地に司令部を置く北方軍は、軍をより効果的に配置して、本土近くのテロ活動に対応し、アメリカ国内に核・生物・化学兵器を持ちこませないことを目的としている。(第二次世界大戦中でも、連邦政府はアメリカ本土防衛のための統一司令部を作らなかった。軍部の独裁の基盤になるかもしれないと懸念したからである。)北方軍の管轄地域には、アメリカ合衆国、メキシコ、カナダ、キューバがふくまれる。メキシコ国民もカナダ国民も、もちろんキューバ国民も、相談は受けていない。この新しい司令部は、ほかの戦域最高司令官(CINC)の司令部と同じように、おおむね文民や軍の指揮系統の外に存在している。最高司令官は実際、ローマ時代の地方総督に匹敵する。」(「第四章」p.157) 「国防総省がいちばん勢力拡大を狙っている分野は、国務省の外交機能と、CIAの情報収集および隠密作戦機能である。」 「1997年、重要な外交政策や軍事戦略を定める責任は、公式に戦域司令官に与えられた(2002年まで戦域司令官は、総司令官または司令長官[コマンダー・イン・チーフ]、略してCINCと呼ばれていたが、彼らの拡大する権力にあきらかにおびやかされていると感じたラムズフェルド国防長官は、2002年10月彼らを「戦闘部隊司令官」と改称した)。こうした半自治権を持つ将軍や提督たちは、1990年代までは主として文民たちが扱ってきた役目をはたしている。」 「中東(中央軍)や太平洋(太平洋軍)、ヨーロッパ(欧州軍)、ラテンアメリカ(南方軍)で、最高司令官たちは情報活動や特殊作戦、宇宙資産、核戦力、兵器取引、軍事基地といった事柄を監督している。そして、彼らは「戦域管理計画」と呼ばれるものを提出する。これは基本的には各地域のミニ外交政策発表のようなもので、現地の軍事組織との緊密な関係を強化するための明確な計画もふくまれている。これはおもに、およそ7000名の特殊部隊員を150ヵ国に派遣して、現地の軍隊に「外国国内防衛」(FID)と呼ばれるものを訓練することで行なわれている――外国国内防衛とは、多くの場合、国家テロの技術を婉曲にいったものにすぎない。訓練任務はアメリカがこれらの国をスパイし、武器を売りつけ、軍隊が国防総省のつごうのいい政策を実行するよう奨励することを可能にする。すべてはごく静かに行なわれ、政治の監視の目は事実上まったく届いていない。」 「最高司令官たちは長年のうちに、自分の担当する戦域で大使よりも大きな影響力を持つようになってきている。海兵隊のアンソニー・C・ジニ大将が中央軍の司令官だったときには、20名の大使を配下にしたがえ、さらに大使級の専属政治顧問1名をかかえていた。太平洋軍(CINCPACとも呼ばれる)は43ヵ国の問題を監督している。各最高司令官は、事実上無制限の資金と自家用機、自家用ヘリ、多数の幕僚を自由に使うことができる。彼らは各軍の長や通常の指揮系統を飛ばして、大統領と国防長官に直接報告を行なう。」(「第四章」p.159~161) 「冷戦時代、一般の軍事ドクトリンでは、海外の基地に四つの任務があると考えられていた。アメリカが関心を持つ地域に通常戦力を送りこみ、必要とあらば核戦争にそなえ、攻撃に対するアメリカの反撃を確実にするための「仕掛け線」の役目をはたし(ことにドイツや韓国のような分断された「紛争地帯」で)、そしてアメリカの力の象徴になることである。冷戦終結以来、アメリカは拡張をつづける基地網をあらためて正当化するために、「人道的介入」から「イラクの武装解除」にいたる、さまざまな口実をずっと探しつづけている。」 「現在、四つの古い任務は、冷戦後の五つの任務に取って代わられたとわたしは考えている。第一に、他国に対して絶対の軍事的優勢を維持すること、この任務には、帝国の治安を維持し、帝国の一片たりとも鎖から逃げださないようにすることもふくまれる。第二に、民間人であろうが同盟国であろうが敵であろうが見境なく、その通信を傍受すること。 ...。第三に、できるだけ多くの石油資源を支配しようとすること。これは、化石燃料に対するアメリカの飽くなき欲求にこたえると同時に、その支配を石油への依存度がもっと高い地域との交渉の切札として使うためである。第四に、軍産複合体に仕事と収入を提供すること...。そして最後に、軍人とその家族が快適に暮らし、海外で勤務するあいだはじゅうぶん楽しめるようにすること。」(「第六章」p.196) 「国防総省はその帝国を維持するために、基地の建設をまねいた戦争や危機がとうに消滅したあとも、できるだけ多くの基地を手元に留めておく新たな口実をつねに発明しなければならない。上院外交委員会はすでに1970年にこう述べている。「いったんアメリカの海外基地が建設されると、基地は独自の生命を持つ。もともとの任務は時代遅れになっているかもしれないが、新しい任務が発明される。それはただ基地を維持するためではなく、しばしば実際にはそれを拡大するためである。もっとも関連がある政府省庁――国務省と国防総省――の内部では、こうした海外基地を一つでも率先して削減または廃止しようとする動きは、ほとんど見受けられなかった。」」(「第六章」p.197) 「世界中のアメリカ軍基地の多くは秘密であり、いくつかは便宜置籍国の国旗で偽装されていて、多くは複数の別個な施設で構成されている。それを思えば、アメリカの軍事帝国の規模と価値を正確に査定することなどどうやってできるだろう?」(「第六章」p.197~198) 「...国防総省の人的資源報告書は、国だけで個々の基地は列挙していない。この文書によれば、2001年9月の時点でアメリカは25万4788人の兵員を153の国に派遣していた。民間人や扶養家族をくわえると、その数は53万1227人に倍増する。」(「第六章」p.200) 「数多くの基地は、「秘密」にされているか、公式記録に載らないように考えられた方法で偽装されているが、われわれはそれがたしかに存在し、その多くがどこにあって、おおむね何をしているかをはっきり知っている。そういった基地は、国防総省が運営する、アメリカ屈指の秘密情報機関である国家安全保障局(NSA)と国家偵察局(NRO)の秘密情報収集基地か、軍石油複合体の秘密前哨基地である。当局者たちはこうした話題を決して正直に話し合おうとしないが、だからといってスパイ活動と石油が彼らの異常なまでの関心事であるという指摘が変わるわけではない。」(「第六章」p.201) (p.202~206に、2001年9月時点での「国外に派遣されていたアメリカ軍の兵員数」の表が掲載されている。各国各地域別、各軍別人数。) 「ローマや中国の漢王朝の時代から現在まで、あらゆる帝国はなんらかの恒久的な野営地や砦や基地を持ってきた。これらは征服した領土に兵隊を配置し、不穏な住民を支配下に置いて、さらなる帝国建設の足掛かりに使うのが目的だった。しかし、いま発展しているアメリカ式帝国がいちばん風変わりで興味深いのは、それが現代の段階では領土ではなく純粋に基地の帝国であって、こうした基地は何世紀もの世界征服の夢に反して、これまではまったく考えられなかった方法で地球を包囲しているということである。」 「...。現代のアメリカ帝国は、アメリカの基地建設方針、つまりわれわれが地球上に兵隊を配置する特定のやりかたをくわしく見なければ、気づくことも理解することもできない。基地取得の歴史的なパターンをたどり、全世界におけるアメリカの基地建設システムを調査することは、ごく最近まで大半のアメリカ人の目にはほとんど隠されていた帝国の活力の源をあきらかにすることである。」 「アメリカ帝国の歴史には、異国に置かれた基地が乱雑に散らばっている。アメリカの外交政策はいまや、だいたい国防総省で決定され、無数の前哨基地に引きこもって生涯を送ってきた指揮官たちによって遂行されている。これらの基地は、独自の風習や習慣、生活スタイルだけでなく、そのほかのアメリカ国民からどんどん切り離されていく独自の序列と職業上の階層によって、相互にしっかりと結びついた世界を構成している。第二次世界大戦の直前にアメリカの正規陸軍がわずか18万6000人しかいなかったことなど、思い起こすことさえむずかしい。いまや、大半の国の国家予算よりも多い国防予算にささえられた140万人の「平時の」軍隊は、外部から遮断された自給自足の基地で暮らす男女によって成り立っている。」(「第七章」p.240~242) 「こうした基地の大半が実際に米ソ戦争が起きたとき本当に重要な役割をはたしたかどうかはわからないが、基地の保有は共産主義の「封じ込め」政策の重要な一部として正当化された。また、ときには、こうした基地はただソ連の手に落ちないようにするために保有する必要があるとも主張された。封じ込めと戦略的阻止が、古くて評判の悪い植民地主義の手法に代わる新式の帝国主義の論理的根拠になった。」 「第二次世界大戦でいちばんの戦利品はドイツと日本だった。 ...」(「第七章」p.248) (このあと数ページにわたってドイツと日本(特に沖縄)の基地についてくわしく語られている。) 「ソ連崩壊後、アメリカはだんだんペースをあげて戦争を遂行し、その表向きの目的はどんどん疑わしく説得力のないものになっていった。さらにアメリカは以前にもまして、国際法の枠組みの外で全世界の反対を浴びながら武力を行使することをいとわなくなっていった。そうした戦争は、人道支援とか、女性の解放とか、非通常兵器の脅威とか、そのほかホワイトハウスや国防総省のスポークスマンがたまたま思いついた流行の専門用語で弁護されてはいても、その実態は帝国主義戦争である。戦争のたびにアメリカは、場所や規模の面からいって、要求される軍事任務には不釣り合いな新しい大軍事基地を獲得し、戦争が終わっても、その基地を手放さずに強化した。2001年9月11日のテロ攻撃のあと、アメリカはアフガニスタンとイラクで二つの戦争を遂行し、東ヨーロッパやイラク、ペルシャ湾岸、パキスタン、アフガンスタン、ウズベキスタン、キルギスタンで14ヵ所の新しい基地を手に入れた。」(「第七章」p.274~275) 「アメリカ帝国の新しい全体像はすでに浮かび上がりつつある。アメリカはラテンアメリカに対する何世紀もの支配と日本の一党支配の政権との緊密な協調を維持しているが、沖縄と韓国では心の底から嫌われている。そこでは情勢はどんどん不安定になってきている。イラクとの戦争に正当性を欠いたことで、ドナルド・ラムズフェルド国防長官が「古いヨーロッパ」と呼んで非難した国々におけるアメリカの地位はそこなわれ、アメリカはその損害をおぎなうために、ずっと貧しく、いまだに苦労をつづける東ヨーロッパの旧共産主義国に同盟国を見つけて、基地を建設しようとしている。ユーラシア大陸南部の石油資源豊かな地域では、地域全体をアメリカの覇権下に置こうとして、コソボやイラク、アフガニスタン、パキスタン、中央アジアに前哨基地を建設中である。いまのところ、イランだけがアメリカの努力の影響を受けていない。アメリカがこうしたことをするのは、テロと戦うためでも、イラクを解放するためでも、アメリカの指導者たちが持ちだすほかの口実のためでもない。わたしがこれからあきらかにするように、アメリカは石油のため、イスラエルのため、国内政治のためにそれをやったのである――われわれがみずから認めた新ローマ帝国という使命を達成するために。」(「第七章」p.275~276) 「アメリカは国連の189の加盟国のうち153の国々に軍隊を置き、そのうちの25ヵ国には大規模な部隊を駐留させている。そして、少なくとも36の国と軍事条約や拘束力がある安全保障条約を結んでいる。」(「第十章」p.370)
・国務省の「国際軍事教育訓練計画(IMET)」 1994年以降4倍の規模に。 2001会計年度に約5800万ドル、2003会計年度には8000万ドル。 1990年には96ヵ国の軍隊に軍事教育。2002年には133ヵ国に増加。 最近では、毎年約10万人の外国兵を訓練している。それもたいていは将校たち。 米国内に約150ヵ所の軍事教育施設。それにプラスして各国へ軍事教官を派遣。「そうした教官はかならずといっていいほど陸軍の特殊部隊員である。」 ・国防総省の「対外軍事融資(FMF)」 「諸外国に金を与えてアメリカの武器を買わせ、それからその使用法の訓練を提供するもの」。 2001会計年度に約36億ドル、2003会計年度には約41億ドル。(国務省のIMETに比べ2桁も違うのは、「国防総省の予算は国務省のほぼ20倍だから」。) ・1993年ニューヨークの世界貿易センター、1996年サウジアラビアの米軍高層アパート、2000年海軍の駆逐艦USSコール、そして2001年9月11日、これらは「現代版のセポイの乱だったと考えることもできる」。 「...新植民地主義的な支配はかならずしも経済的なものである必要はない。用心棒代をせびりとる国際的なゆすり行為にもとづく場合もありうる――相互防衛協定や軍事顧問団、しばしば定義があいまいであったり、誇張されていたり、または実際には存在しなかったりする脅威に対する「防衛」の名目で外国に駐留する軍隊などによって。この取り決めによって「衛星国」――外国との関係や軍備が帝国主義国家を中心に動いている、表向きは独立した国家――が作り出される。...大英帝国の自治領は衛星国の変種である。...もう一つの変種が従属国である。帝国主義国家の属国で、その資源や戦略的位置や影響力がときに支配国に政策を押しつける余地を与えることもあるが、それでも支配国の支援に大幅にたよっている国だ。その例としては、アメリカに対するイスラエル、...」(「第一章」p.43~44) 「軍部は特に冷戦終結以降、第三世界の無数の政府や将校団と緊密な関係を築き、軍同士の訓練計画に絶大な努力をかたむけている。1990年代には、二大政党の指導者たちが、多くの外交政策の目標は伝統的な経済や外交のつながりとは対照的なこうした軍同士の接触や武器取引によっていちばんよく達成できるという結論に達した。そうした政策を実行する計画の一つ、国務省の国際軍事教育訓練計画(IMET)は、1994年以降、四倍の規模に拡大している。1990年には96ヵ国の軍隊に軍事教育を提供したが、2002年にはそのすでに驚きの数字が133ヵ国にまで増えていた。国連加盟国は189しかないので、この一つの計画だけで世界の国々の70パーセントの軍隊を「教育」していることになる。最近では、アメリカは毎年約10万人の外国兵を訓練している――しかもここで話しているのは、たいていは将校たちのことであって、彼らは本国で兵士たちにアメリカ式のやりかたを伝えられるのである。2001年、アメリカ軍はラテンアメリカだけで1万5030名の将兵を教育した。国防総省は訓練生たちをアメリカ国内にある約150ヵ所の独立した軍事教育施設につれてくるか、もしくはそれぞれの国にこちらから軍事教官を派遣する――そうした教官はかならずといっていいほど陸軍の特殊部隊員である。テロとの戦いは、こうした流れをいっそう加速させた。IMETの予算は2001会計年度には5800万ドルだったものが、2003年度には8000万ドルと、38パーセントも跳ね上がっている。」(「第五章」p.172~173) 「現在、外国の軍隊を訓練する表向きのおもな意図はテロとの戦いにより多くの軍勢をかき集め、アメリカ軍部隊との合同作戦の準備をさせることである。こうした計画をささえる裏の動機は、「本土」を動揺させるかもしれない死傷者を避けるために、アメリカ軍部隊の代理を探すことにある。」(「第五章」p.174) 「国務省のIMET計画のぜいたくなライバルが、国防総省の対外軍事融資(FMF)である。これは諸外国に金を与えてアメリカの武器を買わせ、それからその使用法の訓練を提供するものだ。2001会計年度のIMETの予算は5787万5000ドルで、2003年度の予算要求は8000万ドルであるが、いっぽうのFMFの予算は10億ドル単位で、さらに増加を続けている。2001年度に国防総省は35億7624万ドルを与えられ、すぐさま2003年度の予算として41億720万ドルを要求した。二つの計画がこうもちがうのは、国防総省の予算が国務省のほぼ20倍だからである。」(「第五章」p.179) 「イスラムの武闘派は1990年代をつうじて報復をつづけ、1993年にはニューヨークの世界貿易センター、1996 年にはサウジアラビアのアメリカ軍の高層アパート、2000年には海軍の駆逐艦USSコールを攻撃した。2001年9月11日の自爆攻撃は現代版のセポイの乱だったと考えることもできる――もっとも、ブッシュ政権はあらゆる手をつくして、アメリカ国民にそういったことを考えさせないようにしているが。」(「第五章」p.182)
・1999年コソボ空爆は、軍事衛星と宇宙に配備されたGPS(全地球位置把握システム)を活用して行われた。当時の米宇宙軍司令官リチャード・B・マイヤーズ将軍は、コソボを「宇宙が可能にした戦争」であると語った。 ・宇宙軍の方針表明である『2020年へのビジョン』。 「世界経済のグローバル化はこれからもつづき、“持つ者”と“持たざる者”の格差は広がるだろう」。したがって、国防総省の任務は、しだいに危険なほど完全に反アメリカ的になっていく世界で「アメリカの権益と投資を守るために、軍事作戦の宇宙面を支配する」ことであり、方針の唯一の重要な目標は、「他国に宇宙へのアクセスを与えない」ことである。 ・レーガン政権時のSDIも現在のMDも「実際には攻撃的な概念である」。ネオコンの権威ローレンス・F・カプランいわく、「ミサイル防衛は実際にはアメリカを守ることを目的としていない。それは世界支配の道具なのだ」。 「21世紀におけるアメリカ軍国主義の一つのめずらしい側面は、政府が単に地上の強大な軍事機構によってだけでなく、宇宙の支配もつうじて世界に権勢を振るうための入念な計画をもっていることである。そうした野望の最初の徴候は、1999年3月24日から6月3日まで行われたセルビアへの爆撃に見て取ることができた。 ...。当時アメリカ宇宙軍の司令官だったリチャード・B・マイヤーズ将軍は、コソボが「宇宙が可能にした戦争」であって、未来への「新たな基準」であると語った。軍事衛星と宇宙に配備されたGPS(全地球位置把握システム)のおかげで、アメリカ軍機は兵士を危険にさらすことなく、おおむね正確な爆撃と誘導ミサイルの攻撃を行うことができた。」(「第三章」p.103) 「宇宙空間を軍事化して、さまざまな武器で武装した軌道上の戦闘基地から地球を支配しようという決意のなかには、地上のあらゆる目標や他国の衛星に指向できる高エネルギー・レーザーの配備もふくまれている。宇宙軍の方針表明である『2020年へのビジョン』は、「世界経済のグローバル化はこれからもつづき、“持つ者”と“持たざる者”の格差は広がるだろう」と主張している。したがって、国防総省の任務は、しだいに危険なほど完全に反アメリカ的になっていく世界で「アメリカの権益と投資を守るために、軍事作戦の宇宙面を支配する」ことであり、方針の唯一の重要な目標は、「他国に宇宙へのアクセスを与えない」ことである。 「一国主義的軍事覇権を確実にしようとするこうした貪欲な試みは、アメリカが1967年の宇宙条約をふくむあらゆる武器規制の合意や制約をすべてないがしろにすることを求めている。」(「第三章」p.105~106) 「弾道ミサイル防衛は、共和党関係者のなかでは、ロナルド・レーガン元大統領が戦略防衛構想(SDI)を熱心に支持したことで、ある程度の正当性を得ている。SDIは、アメリカの上にロケットとレーザーによる一種の電子的な保護屋根を築くことを目的としていた。この構想は結局、技術的に不可能であることが証明された。レーガンはまちがいなくSDIを防衛手段として考えていたが、SDIも弾道ミサイル防衛も実際には攻撃的な概念である。現在の信奉者たちが、弾道ミサイル防衛はいまやならず者国家と呼ばれている国々から自衛することだけを目的としていると示唆するのは、いい宣伝になるかもしれない。 ...。しかし、国の大小にかかわらず、アメリカに核ミサイルのような追跡可能なものを発射して自殺しようとする国があるなどとは誰も本気で信じたりはしない。ネオコンの権威ローレンス・F・カプランがいったように、「ミサイル防衛は実際にはアメリカを守ることを目的としていない。それは世界支配の道具なのだ」」(「第三章」p.110) 「彼らにとって弾道ミサイル防衛は、宇宙を武装化するために必要な広範囲の研究計画を隠蔽する手ごろな隠れ蓑であり、主要な国防下請け会社に潤沢な資金を提供するための絶好のパイプであり、そして最後に、核攻撃でアメリカを「抑止」すると脅かすかもしれないあらゆる敵の意思決定を厄介にする手段なのである。 ...。実際のところ、ミサイル防衛は防衛のためのシステムではない。それは攻撃のためのシステムであって、新たな地球的核軍拡競争に潤沢な油を注ぎ、その一方で皮肉にもアメリカの安全をいちじるしくそこなうのである。」(「第三章」p.111)
・米国は冷戦を闘う中で、植民地的領土併合の代わりに「領土の中に排他的な軍事地帯をもうけ、植民地の帝国ではなく、基地の帝国を作り上げた」。 ・それは、「拡張をつづけるアメリカの軍産複合体と結びついて」いた。 ・1979年カーター政権のもとで、ペルシャ湾岸における米国の権益を守るために「緊急展開軍」が創出され、1983年レーガン政権のもとで、「アメリカ中央軍(CENTCOM)」に改編。 ・第一次湾岸戦争から第二次湾岸戦争までの間に、「アメリカの軍事基地の帝国がペルシャ湾岸地域で大規模に拡張された」。 ・現ブッシュ政権のもとで、軍事基地帝国はその全貌を現しはじめ、9.11を契機としていっそうの自己増殖をとげた。そのイデオロギー的代弁者としてのネオコンを代表するPNACの表現によれば、国民を動員して自分たちの理論と計画を実行に移すことが可能となるような、「破滅的で触媒作用を持つ出来事――新たな真珠湾攻撃のようなもの」が、まさに9.11であった。 ・サウジアラビアのプリンス・スルタン基地は、これまで中東の代表的な基地であったが、その役割はクウェート、バーレーン、カタールにぞくぞくと建設された基地にとってかわられた。しかもオマーン、アラブ首長国連邦、トルコ、エジプト、イスラエル、ジブチに従来の基地があり、さらにアフガニスタン、パキスタン、キルギスタン、ウズベキスタンに最近基地を取得し、現在イラクに4ヵ所以上で新しい基地を建設している。 「…時代がもっと現代に近づくと、アメリカはほかの多くの帝国とちがって領土をまったく併合しなかった。そのかわりに、領土の中に排他的な軍事地帯をもうけ(ときにはたんに借り上げて)、植民地の帝国ではなく、基地の帝国を作り上げたのである。こうした基地は、指揮系統によってつながり、文民のしっかりした監視を受けることなく国防総省から指示を与えられていた。そして、拡張をつづけるアメリカの軍産複合体と結びついて、基地を取り巻く現地の文化に大きな影響を与えたが、それはほぼ例外なく悪い影響だった。こうした基地がアメリカを新種の軍事帝国へと変えたのである」(「第一章」p.34) 「2001年に現在のブッシュ政権が誕生すると、国防総省は核兵器の目標の大半をロシアから中国に変更した。さらに島の防衛をめぐって台湾と定期的なハイレベルの軍事対話をはじめ、軍の兵員と補給物資をアジア太平洋地域へ移動させるよう命じ、日本の再軍国主義化を促進するために精力的に活動した。2001年4月1日、アメリカ海軍のFP-3EエアリーズⅡ電子スパイ機一機が、海南島沖で中国の戦闘機と衝突した。このアメリカの軍機は中国のレーダー防衛を挑発して、しかるのち中国が迎撃戦闘機を誘導するのに使う無線送信と手順を記録するのが任務だった。この飛行は太平洋地域の最高司令官から命令を受けていた。各担当地域の外交政策の事実上の作者で、次第に独立性を強めているアメリカの軍事地方総督たちの一人だ。」(「第三章」p.114) 「アメリカ軍はこの戦争(アフガン戦争)を利用して、驚くべきスピードと効率で、アフガニスタンとその周辺諸国に軍事基地を持つ権利を獲得した。」(「第六章」p.233~234) 「...1979年10月、カーター政権は、ペルシャ湾岸におけるアメリカの権益を守るために、緊急展開軍と名づけられた部隊を創設した。湾岸地域に基地がなかったので、軍の司令部はフロリダ州タンパのマクディール空軍基地に置かれた。1980年1月23日、カーター大統領はホワイトハウスを去る直前にカーター・ドクトリンを発表した。「湾岸地域を支配しようとする外部の勢力の試みは、いかなる場合でも、アメリカ合衆国の極めて重要な国益に対する攻撃と見なす。そうした攻撃は、軍事力をふくむ必要なあらゆる手段によって撃退されるであろう」。その当時、これはいうのは簡単だったが、実行はきわめて困難だった。そこでアメリカはイランの代わりとなる柱を探しはじめた。1983年1月1日、レーガン政権は、まだフロリダに基地を置いていた緊急展開軍をアメリカ中央軍(CENTCOM)に改編した。これは35年ぶりに創設された戦域軍である。」(第八章」p.286) 「...二度の対イラク戦争のあいだの期間――ノーマン・シュワルツコフ将軍が攻撃を開始した1991年1月16日から、トミー・フランクス将軍が英米軍によるイラクへの侵攻開始を命じた2003年3月19日まで――には、アメリカの軍事基地の帝国がペルシャ湾岸地域で大規模に拡張された。」(第八章」p.290) 「ジョージ・W・ブッシュが大統領になると、...。彼らは九ヵ月間好機を待ちつづけた。PNACの『アメリカの防衛の再構築』の言葉を借りれば、彼らは国民を動員して自分たちの理論と計画を実行に移すことが可能になるような、「破滅的で触媒作用を持つ出来事――新たな真珠湾攻撃のようなもの」を待っていたのである。もちろん9月11日の事件はまさに彼らが求めていたものだった。」(第八章」p.294) 「石油とイスラエルと内政がどれもブッシュ政権の対イラク戦争に重要な役割をはたしたことを否定するのはむずかしいだろう。しかし、わたしは、イラクとの二度目の戦争のもっとも包括的な説明は、1999年のバルカンでの戦争や2001~02年のアフガニスタンでの戦争の説明とまったく同じであると確信している。それは帝国主義と軍国主義の容赦ない圧力である。」(第八章」p.304) 「...プリンス・スルタン航空基地...。この基地はアメリカが十年以上にわたってペルシャ湾岸地域で使用している最大の施設である。バーレーンの全国土と同じだけの広さがあり、...。」 「プリンス・スルタン基地の建設は1996年夏から2002年までつづいた。」(第八章」p.307~309) 「プリンス・スルタンはしばらくのあいだ中東に置かれた基地の代表格だった。しかし、アメリカはすでに湾岸地域で過剰なまでの軍事力を築き上げていたため、イラク戦争後、ほぼすべての兵員をサウジアラビアから撤収すると決定しても、アメリカの戦争遂行能力にはほとんど影響が出なかった。隣国のクウェートやバーレーン、カタールにぞくぞくと建設された基地だけで、アメリカが直面しそうな軍事的要求をじゅうぶんすぎるほど満たしていた。しかも、オマーンやアラブ首長国連邦、トルコ、エジプト、イスラエル、ジブチにはさらに多くの基地があり、それにくわえて、アフガニスタンやパキスタン、キルギスタン、ウズベキスタンにも最近基地を取得している。2003年が終わるまでに、たぶんイラクにはアメリカの新しい基地が四ヵ所できているだろう。」(第八章」p.311) 「問題は、いまやこうした基地自体が本来の目的となってしまったのかということである。基地が存在するがゆえに、アメリカはその使い道を探すのだろうか? イラクに対する侵攻はイラクの行動がもたらしたものなのか、 それともアメリカの持つ軍事能力がもたらしたものなのか? 21世紀の中東の騒乱の原因は、つまるところアメリカの軍国主義と帝国主義なのかもしれない――つまり、われわれの基地の帝国自体が原因かもしれないのだ。」(「第八章 イラク戦争」p.326)
・「エリートの循環」: 軍産複合体は軍高官に退役後のポストを供給し、政府は軍産複合体の幹部を国防総省の高官に任命する。 ・国防総省に群がる利益集団が予算を分け取りしている。「軍事機構はしだいに、 ...四つの主要軍種――陸軍、海軍、海兵隊、空軍――に利益をもたらすように動く巨大なカクテルになっていった。各軍種の防衛予算の配分は過去25年間にわたって二パーセント以上は変化していない。」 ・1993年クリントン政権のもとで、「より大きく、より多角化した集団に合併すれば、国防受注企業に税制上の優遇措置を与える」とした。1995年、ロッキード航空機とマーチン・マリエッタが合併して世界最大の武器メーカー、ロッキード・マーチンが誕生。このとき免税で12億ドルの利益。冷戦終結後武器製造から遠ざかりはじめていたボーイングも、税制上の優遇措置が発表されると180度方針転換。 ・軍産複合体の最大の顧客は国防総省だが、外国への武器の売り込みにも国防総省と制服の軍人が活躍している。 ・戦争は武器セールスの最大のテコ。「戦争には在庫を減らし、世界中の潜在的な顧客に新世代のアメリカの武器の性能をデモンストレーションするという望ましい特徴がある。」 「軍産複合体はさらに、軍高官にとって「退役」後のポストの豊富な供給源ともなっている。政府と契約を結んでいる防衛産業の幹部の多くが国防総省の高官に任命されるのとまったく同じである。こうした「エリートの循環」は、国防総省や防衛産業に対する議会の監督の試みを骨抜きにする傾向がある。その結果、あらゆる種類の軍事プロジェクトについやされる公金に対する説明責任はほぼ完全にはたされなくなっている。」(「第二章」p.77) 「レーガン政権時代には、際限なく増殖するアマチュア戦略家やスターウォーズ計画の信者の列がホワイトハウスを占拠するようになり、国防総省の権限ある地位に仲間をつかせようと画策した。その結果、政府の中心に、自分の利益になる機会に乗じることだけを考える、軍事的な便宜主義のようなものが発達した。 ...軍事機構はしだいに、 ...四つの主要軍種――陸軍、海軍、海兵隊、空軍――に利益をもたらすように動く巨大なカクテルになっていった。各軍種の防衛予算の配分は過去25年間にわたって二パーセント以上は変化していない。その期間にソ連は崩壊し、アメリカはパナマやクウェート、ハイチ、ソマリア、ボスニア、コソボ、アフガニスタンで様々な戦争を行なっている。軍事上の必要性が予算配分の安定を求めたわけではない。」(「第二章」p.82) 「文民軍国主義は概して「戦争の恐怖の増大」を招く。 ...。文民は職業軍人よりもイデオロギーに動かされるし、彼らは軍人と協力するときにはしばしば戦士の文化を誇示する必要性を感じる。そして彼らは本当の戦争を知らないので、戦士の文化とは相手を完膚なきまでに痛めつける無慈悲さを意味すると取っているのである。その効果は二〇〇三年のイラクに対する二度目の戦争でとくに鮮明になった。国防総省に勤務するイデオロギーに凝り固まった多くの文民たちが、戦争はおろか軍隊に勤務した経験も持っていないのに、将軍や提督たちに戦略や戦力、戦争目的を指図していたのである。」(「第二章」p.81) 「もともとの1947年のガット協定は、軍事補助金を「国家安全保障上の例外」という名目でほかの補助金とちがうものとしてあつかっていた。この扱いは、それ以降取り決められたすべての通商条約でも踏襲された。」 「1993年、クリントン政権は企業を幸せにする新たな名案を思いついた――より大きく、より多角化した集団に合併すれば、国防受注企業に税制上の優遇措置を与えるというのである。たとえば、国防総省は1995年にロッキード航空機とマーチン・マリエッタが合併して世界最大の武器メーカーであるロッキード・マーチンが誕生したとき、同社に免税で12億ドルの利益をもたらした。同様に、冷戦終結後ボーイングは武器製造から遠ざかりはじめたが、そのとき税制上の優遇措置が発表された。すると同社は針路を180度転換して、マクダネル・ダグラスとロックウェル・インターナショナルの一部を買収し、世界屈指の武器輸出メーカーになった。」(「第九章」p.356~357) 「戦争で暴利をむさぼるというと、貪欲な民間人がやることと思うのが普通だ。しかし、この見かたは外国人に武器を売ってまわるうえで制服の軍人がはたす役割を軽視している。国防総省主導の強引な売りこみがセールスを成立させた例は数知れないのである。」(「第九章」p.357) 「武器セールスの水準を維持するもう一つの方法は戦争である。戦争には在庫を減らし、世界中の潜在的な顧客に新世代のアメリカの武器の性能をデモンストレーションするという望ましい特徴がある。」(「第九章」p.359)
・戦後の米国防予算は、朝鮮戦争で急増した後、「第二次世界大戦はおろか冷戦前の水準まで減少したことは一度もない。」「軍事支出の冷戦標準」ができあがった。 ・巨額の国防支出が「正常な市民生活」の一部となった。 「カリフォルニアは防衛産業に従業する労働者の人口がどの州よりもはるかに多い。」ノースロップ・グラマン、TRW、ロッキード・マーチン、レイセオンなどが南カリフォルニアに集中。これらの企業は秘密の軍事プログラムにかかわっていて、その予算は秘密にされている。 ・「帝国を食い物にする軍高官の権益以外にもあまりに多くの権益が存在する」。軍人やその家族と軍産複合体以外に、「大学の研究開発センター、石油の精製会社と流通会社、帝国が訓練した数えきれないほどの外国将校団、スポーツ多目的車や小型武器の弾薬の製造メーカー、多国籍企業とそれが自社製品を製造するのに使っている安価な労働力、投資銀行、ヘッジファンドやあらゆる種類の投機家、そして「グローバル化」の唱道者」等々。 ・「軍事的ケインズ理論」。軍需品と戦備に政府が多額の支出をすることで経済を活性化させる。(日本において公共投資が果たしてきた役割。) 「1955年から2002年のあいだで、国防予算が第二次世界大戦はおろか冷戦前の水準まで減少したことは一度もない。...軍国主義の時代における軍事支出の冷戦標準もしくは基準線が確立された...。共和党はしばしばクリントンが軍事支出を削減したと非難したが、それは真実ではなかった。国の財政を破壊し、アメリカを世界最大の対外債務国に変えたレーガンの国防力増強のあとで、クリントンは軍事支出をすでに正常な水準となっていたところへ戻したにすぎないのである。」 「こうした巨額の国防支出が朝鮮戦争から21世紀初頭にかけて毎年つづいたおかげで、アメリカの政治経済は根本から変わってしまった。とほうもない水準の国防支出は正常な「市民」生活の一部となり、上下院のあらゆる議員が政治信条に関係なく自分の選挙区に国防関連の政府契約を持ってこようとしている。南カリフォルニアのような地域はすでに国防支出に依存していて、国防支出が「正常な」期間の一時解雇にともなう景気後退はカリフォルニア経済ではあたりまえの出来事になっている。2002年9月には、国防総省は研究開発費の4分の1近くをカリフォルニア州の各企業に注ぎこんだと見積もられている。カリフォルニアは防衛産業に従業する労働者の人口がどの州よりもはるかに多い。しかも、この数字がまだまだ少ないことはまちがいない。というのも、センチュリー・シティのノースロップ・グラマン社やレドンド・ビーチのTRW社、パームデールのロッキード・マーチン社、エル・セグンドのレイセオン社といった南カリフォルニアの多くの企業は秘密の軍事プログラムにかかわっており、その予算は同様に秘密にされているからだ。」(「第二章」p.75~76) 「新しい帝国は物理的な存在だけではない。それはシンクタンクと呼ばれる現代の愛国的修道院で働く自称『戦略思想家』たちの新たな軍勢が分析し褒めたたえる大事な対象である。それは新旧両方の特定利益集団の関心を集めている――その例が、原油の供給と価格に関心をもつ者たちと、ありえないような場所に軍事基地を建設して維持することで利益を得る者たちだ。帝国を食い物にする軍高官の権益以外にもあまりに多くの権益が存在するために、帝国の存在はあきらかに過剰に思えるほど確固としている――そのために、アメリカが進んで帝国の経営から身を引くことがあるとはとても想像できないほどだ。帝国は軍人やその家族だけでなく、軍産複合体や大学の研究開発センター、石油の精製会社と流通会社、帝国が訓練した数えきれないほどの外国将校団、スポーツ多目的車や小型武器の弾薬の製造メーカー、多国籍企業とそれが自社製品を製造するのに使っている安価な労働力、投資銀行、ヘッジファンドやあらゆる種類の投機家、そして「グローバル化」の唱道者、つまりあらゆる国々がアメリカの搾取とアメリカ式資本主義に門戸を開くように強制したいと願う理論家たちを支えている。」(「第一章」p.37~38) 「冷戦の軍事的パラノイアは米ソ両国で巨大な軍産複合体を成長させ、「軍事的ケインズ理論」をつうじて高い雇用率を維持することを助けた。軍事的ケインズ理論とはつまり、軍需品と戦備に政府が多額の支出をするということである。冷戦はさらに、軍自体や巨大な情報機関ならびに秘密機関、軍事機構の役に立つことを申し出た大学の科学研究所ならびに戦略研究所の雇用も促進した。」(「第一章」p.45)
・軍事の民営化によって民間軍事会社(民間会社だから議会の監督外にある)が興隆。「こうした民間軍事会社上位35社は、現在アメリカでもっとも利益をあげている会社に数えられる。」 ・隆盛をきわめている「民間軍事会社」というのは、従来は軍が行なっていたようなことまで請け負う会社のことである。たとえば、「ダインコープはアフガニスタンのハミド・カルザイ大統領に身辺警護を提供する仕事を請け負い、グリーン・ベレーが撤収したあとはアフガニスタン軍の訓練を引き継ぐことになっている。」 ・民間軍事会社は、「最近退役した軍高官やグリーン・ベレー隊員たちの発案で誕生したもの」がほとんどで、「この種の訓練を担当する人間は、ほぼ例外なく退役軍人である。」 「アメリカの軍部はじかにセポイたちを訓練し、装備を与えているが、それと同時に、だんだんと議会の知識も監督もおよばない民間会社を使ってそうしたことを行なうようにもなってきている。こうした民間軍事会社の上位35社は、現在アメリカでもっとも利益をあげている会社に数えられる。その大手には、...」MPRI(ヴァージニア州)、ケロッグ・ブラウン&ルート(テキサス州)、ダインコープ(ヴァージニア州)、サイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル(カリフォルニア州)、BDMインターナショナル(ヴァージニア州)、アーマー・ホールディングズ(フロリダ州)、キュービック・アプリケーションズ(カリフォルニア州)、DFIインターナショナル(ワシントンDC)、インターナショナル・チャーター(オレゴン州)など。(「第五章」p.182~183) 「ダインコープはアフガニスタンのハミド・カルザイ大統領に身辺警護を提供する仕事を請け負い、グリーン・ベレーが撤収したあとはアフガニスタン軍の訓練を引き継ぐことになっている。 ...。」 「この種の訓練を担当する人間は、ほぼ例外なく退役軍人である――傭兵、戦争愛好家、冷戦終了で職を失ったが、現役勤務当時にやっていた仕事をつづけたいと考えた人間たちだ。彼らがいま働いている会社は、最近退役した軍高官やグリーン・ベレー隊員たちの発案で誕生したものだ。」(「第五章」p.184)
・米国の海外石油依存度は年々増加。「多くの基地は、競争相手から石油採掘権を守ったり、石油パイプラインを警備したりするために外国に置かれている。」もっとも、異なる理由づけがなされているのではあるが。 ・カスピ海地域の石油と天然ガスは、かなりな程度未開発・未探査。1991年ソ連崩壊後「この地域の石油とガス資源を支配しようとする現代の競争が開始された。」 「いくつかの基地の存在理由は、アメリカが海外の石油資源に驚くほど依存していることで説明できる。しかも、その依存度は年々増加しているのである。多くの基地は、競争相手から石油採掘権を守ったり、石油パイプラインを警備したりするために外国に置かれている。もっとも、きまって「テロとの戦い」とか「麻薬撲滅戦争」とか、外国の兵士を訓練しているとか、なんらかの「人道的」介入に従事しているといった、まったく関係のないことをしていると主張しているが。」(「第六章」p.215) ソ連とイランの二ヵ国しかカスピ海に面していなかった時代には、カスピ海の石油と天然ガスはあまり開発されていなかった。「1991年のソ連崩壊後、カスピ海に面した国は突然5ヶ国――ロシア、イラン、アゼルバイジャン、カザフスタン、トルクメニスタン――に増え、この地域の石油とガス資源を支配しようとする現代の競争が開始された。その先頭に立ったのはアメリカに本部を置く多国籍企業で、すぐにアメリカ軍がそのお得意の伝統的な役割をになってあとにつづいた。 ...。1990年代と、ことにブッシュ政権が「テロとの戦い」を宣言して以降は、石油会社がふたたび用心棒をいささか必要とするようになり、国防総省は喜んでその要望に応じた。」(「第六章」p.217) 「カスピ海盆にどれだけ石油と天然ガスがあるのかは、誰も正確には知らない。これまでしっかりとした調査が行なわれたことがないからだ。」 「ここ(カスピ海盆)は世界最後の、大規模でほとんど未開発の油田とガス田であり、しばらくはヨーロッパや東アジアや北アメリカへ石油を供給するうえでペルシャ湾岸地域と競争できる場所である。ここには全世界の確定原油埋蔵量の約6パーセント、天然ガス埋蔵量の40パーセントが眠っている。」(「第六章」p.217~218)
・アフガン戦争以前の段階では、シェヴロン、ユノカル、アモコ、エクソンほか数社が「虚しい努力をつづけていた」が、「アメリカが少なくとも4ヵ国――アフガニスタン、キルギスタン、パキスタン、ウズベキスタン――に軍事基地網を建設しはじめてやっと、事態はこれらの会社に有利に動きだした」。 ・9.11とアフガン戦争以降、中央アジアでの石油と天然ガスのパイプライン敷設が急進展している。バクー=ジェイハン・パイプライン。トルクメニスタンからアフガニスタンを抜けてパキスタンのアラビア海沿岸に達する石油・天然ガス二重パイプライン。 ・石油・天然ガス二重パイプラインという「この野心的な企画の支援が、ブッシュ政権が2001年10月7日にアフガニスタンに対する攻撃を決定した最大の理由だったように思える。アフガニスタンのタリバン政権は、アメリカが援助するパイプラインの開発をかたくなにこばんでいた」。 ・1996年にタリバンが首都カブールを占領して事実上アフガニスタンを統治するようになって以降、米国はタリバンを支援した。ただし、「中央アジアの石油天然ガス資源の開発計画に協力的であるかぎり」において。 ・1990年代中期、ユノカルは、「中央アジア・ガス・パイプライン・コンソーシアム(セントガス)を設立」。これに加わったのは、トルクメニスタン政府、デルタ石油(サウジアラビア)、インドネシア石油、伊藤忠石油開発、現代エンジニアリング・アンド・コンストラクション・カンパニー(韓国)、クレセント・グループ(パキスタン)、ガスプロム(ロシア)である。 ・「1997年から中央アジアのさまざまな共和国にアメリカ軍の教官を派遣しだしたのは、パイプライン建設権の争奪戦のアメリカ代表であるユノカルを支援するというサインだった。」 「アフガニスタンに対するアメリカの攻撃以前には、この地域で活動するアメリカの大石油企業――シェヴロン(現在はシェヴロンテキサコ)、ユニオン・オイル・カンパニー・オブ・カリフォルニア(ユノカル)、アモコ(現在はブリティッス・ペトローリアム-アモコ)、エクソン(現在はエクソンモービル)ほか数社――はすべて、アゼルバイジャンとカザフスタンとトルクメニスタンから採掘権を得てパイプラインの取引をまとめようと虚しい努力をつづけていた。アメリカが少なくとも4ヵ国――アフガニスタン、キルギスタン、パキスタン、ウズベキスタン――に軍事基地網を建設しはじめてやっと、事態はこれらの会社に有利に動きだしたのである。」(「第六章」p.221~222) 「カザフスタンのパイプラインを後押しする人間たちのリストは、さながら共和党の石油族政治家の人名録を見るようだ。」(「第六章」p.222) その中には、コンドラリーザ・ライス、ディック・チェイニー、リチャード・アーミテージの名が揚げられている。 「9.11のテロ攻撃以降のバクー=ジェイハン・パイプラインを支援する軍の展開のなかで、まちがいなく一番重要なのは、2002年2月に約150名の特殊部隊員と10機の戦闘ヘリがカフカス地方のグルジア共和国に派遣されたことである。この作戦の目的は表向き、グルジア軍がグルジア北東部のパンキシ渓谷に潜伏している、アル・カーイダとつながりがあるとされるチェチェンの武装勢力と戦うための準備を整えることだと説明された。しかし、2002年2月27日、グルジアの国防省高官、ミリアン・キクナゼはラジオ自由ヨーロッパにこう語った。「アメリカ軍はわれわれの緊急即応部隊を訓練することになっています――とくに石油のパイプラインを」。」(「第六章」p.225~226) 「中央アジアではアメリカの三つ目の大プロジェクトがすでに提案されている。南のトルクメニスタンからアフガニスタンを抜けてパキスタンのアラビア海沿岸に達する、石油と天然ガスの二重パイプラインである。この野心的な企画の支援が、ブッシュ政権が2001年10月7日にアフガニスタンに対する攻撃を決定した最大の理由だったように思える。アフガニスタンのタリバン政権は、アメリカが援助するパイプラインの開発をかたくなにこばんでいたため、タリバンの排除が2001年9月11日のテロ攻撃以降の「テロとの戦い」のひそかな原因となったのである。ジャーナリストのパトリック・マーティンはこういっている。「もし歴史が9月11日をすっ飛ばし、あの日の出来事が起きていなかったとしても、たぶんアメリカはアフガニスタンで戦争に突入していただろう。しかも、ほとんど同じスケジュールで」」(「第六章」p.226) 「ユノカルもアメリカ政府も、タリバンといっしょにやっていくことは可能だし、女性と犯罪者に対するタリバンの苛酷な仕打ちは1980年代のアメリカの同盟者たちとさほど変わらないと信じていた。」 「アメリカはあらゆる手段を使って援助をはじめた。1997年から中央アジアのさまざまな共和国にアメリカ軍の教官を派遣しだしたのは、パイプライン建設権の争奪戦のアメリカ代表であるユノカルを支援するというサインだった。サウジアラビアの過激派、ウサマ・ビン・ラーディンが1996年にタリバンの「客」としてアフガニスタンに戻り、1998年8月7日にアル・カーイダがケニアとタンザニアでアメリカ大使館を攻撃したあとでさえ、クリントン政権の国務省もブッシュ政権の国務省も、アフガニスタンをテロ支援国に指定しなかった。そんなことをすれば、パイプライン建設に国際融資を受ける可能性がいっさいなくなってしまうからである。両政権とも、タリバン体制がテロを支援していたにもかかわらず、中央アジアの石油天然ガス資源の開発計画に協力的であるかぎりは、これを喜んで受け入れたのである。」(「第六章」p.228~229) 「ユノカルは1990年代中期に中央アジア・ガス・パイプライン・コンソーシアム(セントガス)を設立した。参加したのは、トルクメニスタン政府、サウジアラビアのデルタ石油、インドネシア石油、日本の伊藤忠石油開発、韓国の現代エンジニアリング・アンド・コンストラクション・カンパニー、パキスタンのクレセント・グループ、それにロシアの巨大天然ガス企業ガスプロムである。デルタがくわわったのは、同社がサウジアラビアのファハド国王に近く、ユノカルの顧問たちは国王がタリバンにユノカルを認めさせる手助けをしてくれるかもしれないと考えたからである。 ...。ガスプロムはロシアの反対をふせぐために引き込まれた。ユノカルが株の46.5パーセントを保有し、デルタが15パーセント、トルクメニスタン政府が7パーセントを保有した。中央アジアの政策については並ぶもののない権威であるパキスタンのジャーナリスト、アハメド・ラシードによれば、1996年には「パイプラインに関する戦略がタリバンに対するワシントンの関心を支える原動力となっていた」という。」(「第六章」p.230~231)
・クリントン政権末期に国防総省は対イラク戦争準備を真剣に開始。統合参謀本部の『1999年度戦略評価』は、ペルシャ湾岸で「石油戦争」が本当に起きるかもしれないことを述べている。 ・「イラクのバース党政権を倒してアメリカ寄りの傀儡政権を樹立し、そこに恒久的な軍事基地を築くという計画」が10年かけて準備されてきた。9.11直後、「ドナルド・ラムズフェルド国防長官は、ただちにイラクを攻撃するよう求めた。」 「1990年代後半、クリントン政権の第二期目に、国防総省はイラクとの新たな戦争の準備を真剣に開始した。統合参謀本部の『1999年度戦略評価』はとくに、ペルシャ湾岸で「石油戦争」が本当に起きるかもしれず、「アメリカ軍がじゅうぶんな石油供給を確保するために使われるかもしれない」とのべている。この文書は、新たな戦争がサダム・フセインの影響力をきっぱりと消し去り、彼の石油を支配し、ソ連の消滅でユーラシア大陸南部に生まれた真空地帯にアメリカの影響力を拡大することになるだろうと推測している。」 「すでに見てきたように、アジアの中部、南部、南西部に対するこの新たな関心には、アメリカ主導のコンソーシアムが天然ガスと石油のパイプライン建設の権利を手に入れるための手段として、中央アジアの独立共和国であるキルギスタンならびにウズベキスタンと軍同士の交流をはじめることや、アフガニスタンのタリバン政権を支援することがふくまれていた。しかし、この大戦略の最大の目玉は、イラクのバース党政権を倒してアメリカ寄りの傀儡政権を樹立し、そこに恒久的な軍事基地を築くという計画だった。 ...。9・11のテロ攻撃と、タリバンに対する戦争、ブッシュの「テロとの戦い」は、少なくとも十年間かけて準備されてきた計画にさらなる勢いを与えたにすぎない。」 「2001年9月11日のテロ攻撃の直後、ドナルド・ラムズフェルド国防長官は、ただちにイラクを攻撃するよう求めた。」(「第八章」p.290~291)
・ベトナム戦争後、徴兵制から志願制へ。 「強制徴兵の重点は人種的少数派や徴兵逃れの手段を持たない者たちに不当なほど置かれていた」ことへの不満がたかまって、「政府は平等に徴兵を実施するよりも徴兵制を廃止してしまうほうを選んだ。」以降、軍隊の勤務は、「それ以外の出世の道がしばしば閉ざされた人々が社会的安定を得るための道となっている。」 ・軍は新兵募集に苦労している。諸種の優遇措置で惹きつけようとしている。確実に支払われる給料、まずまずの住居、医療の恩典、職業訓練、大学教育の保証、等々。 ・「軍の新兵募集係たちは、現実の戦争で国家に奉仕するために入隊する者が事実上一人もいないことに気づいた。」入隊志願の若者のたちの「およそ5人に4人が非戦闘任務をはっきりと選択」。 「ベトナム戦争中に徴兵制度が不公平なやりかたで運用されている――大学生は免除されるいっぽうで、強制徴兵の重点は人種的少数派や徴兵逃れの手段を持たない者たちに不当なほど置かれていた――ことがあきらかになると、政府は平等に徴兵を実施するよりも徴兵制を廃止してしまうほうを選んだ。それ以降ずっと、軍隊の勤務は完全に志願制になり、それ以外の出世の道がしばしば閉ざされた人々が社会的安定を得るための道となっている。」(「第二章」p.80) 「実際のところ、新兵をひきつけるうえで唯一うまく機能していると思えるのは、軍が5万ドルまでの大学の授業料を補助する制度である。もっとも、軍に入隊した者のなかでこの計画を利用するものは結局ほとんどいないのだが。 ...。軍へ入隊するかどうかの決断に影響をおよぼすのは、人種や社会経済的な階級、アメリカの景気、そして近づく戦争の可能性なのである。 ...。イラクとの二度目の戦争の準備期間中、軍の新兵募集係たちは、現実の戦争で国家に奉仕するために入隊する者が事実上一人もいないことに気づいた。」 「新兵募集をじゃまする本当の要因は、新兵が戦闘に巻きこまれる可能性があることである。われわれの完全志願制の軍隊に入隊するアメリカの若者のおよそ5人に4人が非戦闘任務をはっきりと選択し、コンピューター技術員や人事係、出荷係、トラック整備員、気象予報員、情報分析員、コック、フォークリフト運転手になる――どれも敵と接触する危険性が低い仕事だ。民間でいい職が見つからないために入隊し、そうすることで軍が長年かかって築いてきた国家社会主義システムに避難場所を求める者も多い。確実に支払われる給料、まずまずの住居、医療の恩典、職業訓練、大学教育の保証といったものに。」(「第四章」p.127~128) 「若いアフリカ系アメリカ人たちは一つには、大都市の中心部にある人種的スラム街と、刑務所暮らしをまねくことが多い『裏経済』稼業から逃げだす目的で、ぞくぞくと軍隊に入る。第一に愛国的な動機や大衆に奉仕するという動機で入隊する者はほとんど誰もいない。ジャーナリストたちとのさまざまな会話のなかで、若い兵士や水兵たちは、民間の高い失業率、初級レベルの製造作業の海外流出による雇用のいっそうの悪化、自力で成功をつかもうとすると法とぶつかる可能性があるといった問題を口にした。」(「第四章」p.138)
・アフリカ系アメリカ人: 1999年の新兵の約20%(同年代の民間労働力では12.7%)。軍隊への定着率も高い。現役の下士官兵全体に占める割合は22.5% ・ヒスパニック: 新兵の11%(全人口比では13%)。現役の下士官兵の9.5%。この割合の低さは、「たぶん高校の退学率が高いことと――新兵は高校を卒業しているか、それに相当する資格を持っていなければならない――多くが国内で違法に暮らしている事実で説明できるだろう。」 戦闘部門では割合は高く、武器を直接扱う部隊で17.7%。 ・士官では正反対。新任士官での割合は、アフリカ系アメリカ人:約9%、ヒスパニック:4%、その他の有色人種:9%。現役将校団では、アフリカ系アメリカ人:8%、ヒスパニック:4%、その他の有色人種:5%。 ・「同じパターンは予備役にもあてはまる」。 ・戦地での上官殺し。ベトナム戦争時「手榴弾による上官殺し」が多発。「当時、自分が支持していない戦争に徴兵された下士官兵たちは、ときどき将校の宿舎に破片手榴弾を投げ込んだのである。ベトナムで報告された209件もの上官殺し事件の多くでは、手榴弾を投げ込んだり将校を射殺したりした兵士はアフリカ系アメリカ人で、被害者は大半は白人の下級野戦将校だった。軍隊内の人種差別が事件を引き起こした一因であることはあきらかである。」 イラク戦争でも「少なくとも1件の上官殺しが3月23日(2003年)に起きている。」 ・女性は、1999年度で、新兵の18%、現役予備役の新隊員の24%、現役勤務の全下士官のうち14%、新任士官の約20%、全将校団の15%を占めている。女性では上記の傾向が強まる。「軍に勤務する女性は、下士官兵だろうと士官だろうと、現役だろうと現役予備役だろうと、人種的もしくは民族的少数派グループに属している可能性が男性よりも高い」アフリカ系アメリカ人の女性は女性下士官兵の35.3%。 「性的暴行は軍のあらゆる部門に勤務する女性にとって逃れられない問題である。」 ・「犯罪と人種差別は軍隊のいたるところにはびこっている。」例外ではなく常態。世界中の軍事基地で犯罪が絶えないのは必然。 「人種や民族の面から見ると、アフリカ系アメリカ人は下士官兵のなかで平均以上の割合を占めている。1999年に現役勤務についた新兵の約20パーセントがアフリカ系アメリカ人だったが、軍務に適する年代のアフリカ系アメリカ人がアメリカの民間労働力の全体に占める割合は12.71パーセントである。さらにアフリカ系アメリカ人は軍隊の定着率も高く、現役の下士官兵全体に占める割合は22.5パーセントにまで上昇する。」 「ヒスパニックの割合は平均以下で、全人口の13パーセントを占めているのに新兵では11パーセントを構成しているにすぎない。彼らは現役の下士官兵全体の9.5パーセントを占めているが、戦闘部門では平均以上の割合を記録し、武器を直接あつかう部隊の17.7パーセントを構成している。ラテンアメリカ系の割合が平均以下なのは、たぶん高校の退学率が高いことと――新兵は高校を卒業しているか、それに相当する資格を持っていなければならない――多くが国内で違法に暮らしている事実で説明できるだろう。サンディエゴのような国境の都市では、陸軍の新兵募集係がときどき国境の向こうのティファナへ行って、グリーンカード(外国人の合法居住許可証)の発行と、陸軍での勤務が終わったら市民権を得られるかもしれないという誘いで、若いメキシコ人を入隊させようとしている。」 「士官の場合には割合がことなる。新規に任官した士官のなかのほぼ9パーセントがアフリカ系アメリカ人で、4パーセントがヒスパニック、9パーセントがそれ以外(の有色人種)だった。現役の将校団のなかでは、8パーセントがアフリカ系アメリカ人、4パーセントがヒスパニック、5パーセントがそれ以外(の有色人種)である。したがって、アフリカ系アメリカ人の士官は、下士官兵の場合よりもずっと少ない割合を占めている。同じパターンは予備役にもあてはまる。」 「...ベトナム戦争時の「手榴弾による上官殺し」を思い起こさせる。当時、自分が支持していない戦争に徴兵された下士官兵たちは、ときどき将校の宿舎に破片手榴弾を投げ込んだのである。ベトナムで報告された209件もの上官殺し事件の多くでは、手榴弾を投げ込んだり将校を射殺したりした兵士はアフリカ系アメリカ人で、被害者は大半は白人の下級野戦将校だった。軍隊内の人種差別が事件を引き起こした一因であることはあきらかである。2003年1月に国防総省で行なわれた完全志願制の軍に関する背景説明では、上官殺しの問題が持ちだされた。『気持ちのいい話ではありません』と説明を行なった国防総省の高官はのべている。それにつづくイラクでの戦争では、少なくとも1件の上官殺しが3月23日に起きている。」 「1999年度には、女性は新兵の18パーセント、現役予備役の新隊員の24パーセントを占めていた。現役勤務の全下士官兵のうち14パーセントは女性だった。新任士官の約20パーセントが女性であり、女性は全将校団の15パーセントを占めていた。もっとも特徴的なのは、軍に勤務する女性は、下士官兵だろうと士官だろうと、現役だろうと現役予備役だろうと、人種的もしくは民族的少数派グループに属している可能性が男性よりも高いということである。アフリカ系アメリカ人の女性は女性下士官兵の35.3パーセントを構成している。」 「性的暴行は軍のあらゆる部門に勤務する女性にとって逃れられない問題である。 ...」(「第四章」p.133~136) 「犯罪と人種差別は軍隊のいたるところにはびこっている。軍はきまって、報告された犯罪や人種差別事件はすべて特異な出来事であって、ごくごく少数の「腐った林檎」がしでかしたものであり、将校たちは断固とした矯正措置をとっていると説明しようとするが、世界中の軍事基地では現実はあきらかにちがっている。」(「第四章」p.139) (このあと4ページにわたって米国内と世界の軍事基地での犯罪の具体例が語られている。それは、(6)ホスト国との矛盾の内容でもある。さらにそのあと5ページにわたって新兵募集のあの手この手が語られている。これは、(1)志願制の矛盾の内容。)
・“湾岸戦争症候群”は、「前線の兵士たちだけでなく、非戦闘部隊の兵士たちにも同じくらい重くのしかかっている」。とくにPTSDと劣化ウランによる障害。 ・死傷者に4通り:1)戦死者、2)戦傷者、3)事故死者、4)戦闘行為の終了後に現れる傷病者。 第一次湾岸戦争では、従軍兵員約70万人のうち、1)148人、2)467人、3)145人、その合計は760人。だが、4)は時が経つにつれて増加し、復員軍人庁の報告によれば、2002年5月時点で死者8306人、傷病者15万9705人。 第一次湾岸戦争のあとで軍の環境浄化作業を指揮したダグ・ロッケ(元陸軍大佐、現ジャクソンヴィル大学環境科学教授)によれば、4)の傷病者26万2586人、うち死者1万617人。 「アメリカが近年行なった戦争は、意図しない深刻な影響をもたらしてきたが、そうした影響は前線の兵士たちだけでなく、非戦闘部隊の兵士たちにも同じくらい重くのしかかっている。その死傷率のもっとも重要な要素は、湾岸戦争症候群として知られる疾病である。これは死にいたることもある医学的機能障害で、1990~91年のイラク戦争で戦闘に従事した兵士たちのあいだに最初に表われた。ベトナム戦争中の枯葉剤の効果が最初、国防総省によって「心的外傷後ストレス障害」や「戦争神経症」、「弾震盪」と片づけられたのと同じように、ブッシュ政権は現在アメリカ軍によって広く使われている弾薬の有毒かもしれない副作用を真剣に受けとめてはいない。その影響は、戦場と化した自分の国で身動きがとれないアメリカの敵や民間人だけでなく、アメリカ軍自体にとっても恐るべきものだ(そしてたぶん、彼らの未来の子孫たちにとっても)。」 「最初のイラク戦争は、四通りの負傷者を出した――戦死者、戦傷者、事故死者(「友軍に対する誤射」をふくむ)、そして、戦闘行為の終了後にはじめて現われた傷病者である。1990年から1991年のあいだに、ざっと69万6778名の兵員が、<砂漠の盾>作戦と<砂漠の嵐>作戦に関係してペルシャ湾岸地域で従軍した。このうち148名が戦死し、467名が戦闘で負傷し、145名が事故で死亡した。死傷者の合計は760名で、作戦の規模を考えればきわめて少ない数字だ。しかし、2002年5月の時点で、復員軍人庁は、戦争中にこうむった軍事関連の「被曝」の結果、さらに8306名の兵士が死亡し、15万9705名が傷病者になったと報告している。さらに恐ろしいことに、復員軍人庁は、ノーマン・シュワルツコフ将軍の全軍のほぼ3分の1にあたる20万6861名の復員軍人が、1991年の戦闘で引き起こされたけがや病気にもとづいて治療や補償や年金の給付金を要求していることを公表した。各事例を再調査した同庁は、16万8011名の申告者を「傷病復員軍人」と認定した。こうした死者と障害者を考えあわせれば、最初の湾岸戦争の死傷率は実際には29.3パーセントという驚愕すべき数字になると考えられる。」 「元陸軍大佐で、ジャクソンヴィル大学で環境科学の教授をつとめるダグ・ロッケは、最初の湾岸戦争のあとで軍の環境浄化作業を指揮した人物である。 ...。ロッケは1990年以降、何千何万というアメリカ軍将兵がクウェートとその周辺に配備されており、劣化ウランに対する彼らの被曝もふくめると、死傷者数は復員軍人局の公表より多くなると考えられると指摘している。彼は、1990年8月から2002年5月のあいだに合計で26万2586名の兵士が「傷病復員軍人」になり、1万617名が死亡したと記している。彼の死傷者数で計算すると、10年間の死傷率は30.8パーセントになる。」(「第四章」p.129~130)
・事実上の改憲が進行。 憲法第一条第八節では「議会が宣戦を布告する権限を持つ」とされているが、9.11の後ブッシュ大統領は「テロとの戦争」という「戦時」を宣言し、2002年10月には、上下両院が大統領にイラクとの戦争を遂行する無制限の権限を与えた。 大統領が「敵性戦闘員」と指定すれば、アメリカ国民をも含めて、あらゆる人権を剥奪できるようになった。 ・アフガン戦争でタリバン兵として捕らえられたアメリカ市民ヤシル・エサム・ハムーディの例。大統領による「敵性戦闘員」指定によって、いっさいの市民権を剥奪された。その裁判で、ブッシュ政権と国防総省は、敵性戦闘員には弁護士と接触する権利もないと主張。さらに、裁判所は最高司令官としての大統領の絶対的な権限に立ち入ってはならないと主張。また、戦時に軍の決定を再審理するように求められたときには、裁判所は軍に従うべきであると主張。 「ブッシュと彼の政権は、政府のほかの部門と憲法を犠牲にして大統領職の権力を拡大するために精力的に働いてきた。憲法の第一条第八節は、「議会が宣戦を布告する権限を持つ」とはっきりいっている。大統領がその決断をくだすことを禁じているのである。 ...。しかし、2001年9月11日のあとブッシュ大統領は、国家がテロに対してほぼ永遠に「戦争状態にある」と一方的に宣言した。さらに、ホワイトハウスのあるスポークスマンはのちに、大統領は「自分の政策に対する反対はすべて反逆行為と同様に見なす」といっている。」 「2002年10月3日から10日にかけての議会の「恥辱の一週間」(軍事問題のアナリストのウィンズロー・T・ホイーラーの言葉)のあいだ、上下両院は投票で大統領にイラクとの戦争を遂行する無制限の権限を与えた(下院の投票結果は296対33、上院の投票結果は77対23)。大統領はさらに、イラクに対する予防攻撃に際して、彼が――彼だけが――「ふさわしい」と見なした場合にはいつでも、軍事力や核兵器をふくむあらゆる手段を使用する無制限の権限を与えられた。議論はなかった。」(「第十章」p.375) 「ブッシュ政権はさらに、アメリカ国民がテロ組織の一員であるかどうかを一方的に判断し、憲法で認められたあらゆる権利を剥奪できる権限までも不法に自分のものにしてしまった。この剥奪される権利のなかには、憲法の修正第六条で保証された、自分と同等の地位の陪審員の前で迅速な裁判を受ける権利や、抗弁のために弁護士の援助を受ける権利、自分を告発する者と対決する権利、自分自身に刑事責任を負わせるような供述を強要されない権利、そしてもっとも重要なことは、政府が被疑事実をはっきり説明して、それを公表する必要性がふくまれている。」 アフガニスタンでとらえられたヤシル・エサム・ハムーディの例。「一市民として、彼には法の適正な手続を保証した憲法の条項が適用されなければならないが、司法省は、彼が大統領によって「敵性戦闘員」に指定されたので、大統領の命令だけで弁護士抜きにいつまでも拘留することができるのだと主張した。」 「2002年6月19日、ブッシュ政権と国防総省の代表たちは、第四区巡回控訴裁判所に対して、憲法でも法律でも判例でも認められていない驚くほど独占的な大統領の権限の主張をくりひろげた。「軍は敵性戦闘員と見なした個人を捕らえ、拘留する権限を持っており、 ...そこにはアメリカの市民権を主張する敵性戦闘員もふくまれる」と彼らは主張した。「さらに、そうした戦闘員はみずからの拘留に抗議するために弁護士と接触する権利を持たない」。彼らはさらに進んで、「裁判所は軍の敵性戦闘員の決定をあとから批判してはならない」と強く主張した。なぜならそうすることで裁判所は「最高司令官としての大統領の絶対的な権限」に立ち入ることになるからである。 ...。裁判所は「戦時に軍の決定を再審理するように求められたときには」軍にしたがうべきなのだ。」(「第十章」p.376~377)
・先制攻撃と予防戦争のドクトリン。これまでに国際社会で確立されてきた国際法に縛られないことを宣言。それは、米国外交政策の権威を失墜させ、国際的な孤立を招いている。 ・常設戦争犯罪法廷としての国際刑事裁判所(ICC)。2000年にクリントン大統領が署名したものを、さかのぼって署名取消。国際法に照らして戦争犯罪である行為を、米軍は行なう(行なっている)ということの告白にほかならない。 「クリントンは「グローバル化」』の旗印を掲げて行うことで自分の政策をカムフラージュした。 ...。アメリカは世界を支配したが、支配された国々が黙って受け入れるように慎重に隠した方法でそれを行った。 「それに対して、ジョージ・ブッシュ大統領は、アメリカの比類ない軍事力の使用を基本とする正面攻撃を選択した。 ...。ブッシュはさらに予防戦争のドクトリンを支持することを公言した。アメリカはわれこそは新ローマ帝国であり、善も悪も超越し、国際社会で確立された協定には縛られないと宣言したのである。 ...。こうした政策は国際的な孤立を招き、世界の国々はアメリカの外交政策機構に対する信頼を失った。」(「第九章」p.328~329) 「世界初の常設戦争犯罪法廷である国際刑事裁判所(ICC)を骨抜きにしようとしたアメリカの試みは、この 一国主義的動機の顕著な例である。」(「第三章」p.96) この条約は1999年ローマでの多国間協議で採択され、2000年にクリントン大統領がその条約に署名し、多くの国々で批准された。しかし、現ブッシュ政権はその批准を拒んだばかりか、「さかのぼって署名を取り消すという前例のない手段をとった」。「ブッシュ政権は、自分たちの統制がおよばない国際検察官がアメリカの役人や軍人を「気まぐれに」訴追するのではないかと恐れているのだと主張している。しかし、ローマ条約には、いかなる国も自国民を戦争犯罪に問ううえで国際刑事裁判所に対し優先権を持つといった、恣意的な起訴に対する予防策がふくまれているのである。もしアメリカが個人を戦争犯罪で訴追できる法廷の設立に抵抗するとしたら、それはアメリカの帝国主義的活動がほぼまちがいなくそうした犯罪の遂行をともなうからにほかならない。アメリカは古い国際司法裁判所(これは個人ではなく国家しか裁くことができない)がテロ活動で有罪判決を下した唯一の国家である――1984年にニカラグアのサンディニスタ政権を揺るがし、葬り去ったレーガン政権の秘密工作に対して。」(「第三章」p.97)
・米軍基地は、さながら「軍事都市国家」である。「一等地を基地として収容し、地元住民に犯罪をはたらいたアメリカ兵には治外法権が認められる。基地の正門周辺にひしめきあうバーや売春宿、いつ終わるともしれない事故や騒音、性的暴行、飲酒運転による衝突事故、麻薬の使用、環境汚染」。これらは、「アメリカの若者たちに傲慢さと人種差別を教え、人種的な優越性の基本成分を植えつける。」 ・1992年、米軍はフィリピンから撤退。1995年、沖縄でレイプ事件をきっかけに反基地闘争高揚。2002年、韓国で二少女轢殺事件をきっかけに反基地闘争の一大高揚。2004年、プエルトリコから撤退。 ・韓国の米兵は、「北からの攻撃に対する「仕掛け線」として、二つのコリアのあいだの非武装地帯に何十年も配備されている」。これは、「最初の死傷者が伝えられたとき、アメリカ国民が確実に戦争を支持するほかなくなるようにすることを目的としている。」現在進行中の米軍再編で、これも変化しようとしている。 ・韓国では、二少女轢殺事件とそれへの全人民的抗議行動の中で、「韓国の世論は北朝鮮問題について劇的な変化をとげ」た。「彼らは北朝鮮が、 ...アメリカによって、ひじょうに危険な隅に追いつめられていることにも気づいている。韓国はもはや北朝鮮をそれほど恐れてはいない――少なくとも、ワシントンによって極端な行動に追い立てられていない北朝鮮は。それよりも、ワシントンが広めている戦争熱と、過去50年以上にわたって韓国に駐屯するアメリカ軍が絶えず起こしている問題のほうを恐れているのである。」 ・イギリスにある米軍基地は、議会を通さず、なし崩し的に秘密裏に拡大されてきた。「イギリスにアメリカ軍基地がいくつあるのか正確にいうことはいまも不可能である」。 ・2001年「実習船えひめ丸」事件。 「国防総省を政治的に支援してくれそうな市民団体や、国防支出に既得権益を持つ市民団体を育成しようとしてきた」国防総省のロビー活動は、「潜水艦USSグリーンヴィル艦内の致命的な怠慢事件がそれを垣間見せるまで気づかれずにいた。」2000年に太平洋艦隊だけで7836名の民間人訪問者を艦艇に同乗させていた。 「グリーンヴィルは海軍を支援する裕福な民間人16名を楽しませるだけのために出航していた」。艦長のスコット・D・ワルド中佐は、もし怠慢の廉で軍法会議にかけられたら、自分は民間人を航海につれだすよう命じられたこと、「彼らを発令所に入れることで少なくとも集中力がさまたげられた」ことを第一に主張するつもりだと語っていた。「あるテキサスの石油会社の重役は、潜水艦が海面に向かって急浮上するとき、実際に操舵席に座っていた。」 「ワルドがこの発言をもう一度くりかえして公式記録に残すことをふせぐために、海軍の審問委員会は民間の招待客を一人も証言のために召喚しなかった。そして、太平洋艦隊の司令官、トーマス・B・ファーゴ提督は彼を軍法会議にかけないことを決めた。」 ・「日本政府は長年にわたり、アメリカ軍を沖縄に封じ込めておくためにあらゆることをしてきた。」 日本の国土全体の1%以下の沖縄に、在日米軍基地の約75%。「島と日本の関係は、プエルトリコとアメリカの関係によく似ている。」「東京の政府はこの取り決めが気に入っている。国民が日本の国土にアメリカ軍の駐留を許すのは、自分たちの見えないところにいる場合だけだということを知っているからだ。」 国防総省の2001年「基地構成報告書」によれば、73箇所の米軍基地。これらの基地に、40,217人の軍人、6,431人の文民職員、42,653人の扶養家族。29,205人の日本人を兵站業務などに雇用。「日本政府はこうした役務の代価を支払うのを助けるために、毎年約40万ドルをアメリカに支払っている。したがって、日本はたぶんほかの国に金を払って自分をスパイさせている唯一の国だろう。」 「島の一等地を基地として収容し、地元住民に犯罪をはたらいたアメリカ兵には治外法権が認められる。基地の正門周辺にひしめきあうバーや売春宿、いつ終わるともしれない事故や騒音、性的暴行、飲酒運転による衝突事故、麻薬の使用、環境汚染」(「プロローグ」p.14)。 「いったん基地に入れば、アメリカの現代の地方総督とその配下の戦士たちは「地元民」ともアメリカの民間人とも接触する必要はない。こうした軍事都市国家は、19世紀のイギリスやフランスの若者に対して行なったように、アメリカの若者たちに傲慢さと人種差別を教え、人種的な優越性の基本成分を植えつける。」(「プロローグ」p.36) 「アメリカが外国に持つ軍事的な飛び地は、構造的にも法的にも概念的にも植民地とはことなるが、占領された国の司法権がまったくおよばないという点で、それ自体がミニ植民地のようなものだ。アメリカは、表向き独立した「ホスト」国とほぼ例外なく「軍事地位協定」(SOFT)を取り決めている。19世紀の帝国主義者たちが中国で獲得した『治外法権』という慣行の現代版である」(「第一章」p.49) 「...北からの攻撃に対する「仕掛け線」として、二つのコリアのあいだの非武装地帯に何十年も配備されている何千というアメリカ兵たちもいる。これはなによりも、最初の死傷者が伝えられたとき、アメリカ国民が確実に戦争を支持するほかなくなるようにすることを目的としている。」(「第三章」p.117) 「それ(2003年)に先立つ二年ほどの間に、韓国の世論は北朝鮮問題について劇的な変化をとげていた。経済的に豊かで情報も豊富な韓国の国民は、腹を空かせ、自暴自棄になり、抑圧されながら、それでも強力な軍事力を持つ朝鮮半島の同胞が、冷戦終結の皮肉と苛酷な金正日体制のせいで窮状に追い込まれていることを知っているが、同時に彼らは北朝鮮が、世界に君臨する軍事大国の役割を新たに宣言したアメリカによって、ひじょうに危険な隅に追いつめられていることにも気づいている。韓国はもはや北朝鮮をそれほど恐れてはいない――少なくとも、ワシントンによって極端な行動に追い立てられていない北朝鮮は。それよりも、ワシントンが広めている戦争熱と、過去50年以上にわたって韓国に駐屯するアメリカ軍が絶えず起こしている問題のほうを恐れているのである。」(「第三章」p.118) スパイ衛星からのデータ通信を受け取っているアメリカの主要な基地の中には、青森県三沢のアメリカ空軍基地内にある海軍航空施設が含まれている。(「第六章」p.208~209) イギリスにあるアメリカ軍基地については、「両国の政府がイギリスにおけるアメリカ軍基地の公式協定を一度も結んだことがない...。しかも、イギリス議会はこの問題について一度も票決したことがない。 ...。こういった理由から、イギリスにアメリカ軍基地がいくつあるのか正確にいうことはいまも不可能である(ただ、ある消息筋によれば、冷戦終結時には104ヵ所あったという)。」 イギリスの平和活動家リンディス・パーシーは、基地に侵入しようとして何度も逮捕されている。彼女らの活動によって、イギリス軍基地を装った米軍基地の存在がつきとめられている。彼女が最近侵入しようとしたクラウトン英空軍基地は「ある信頼すべき非公式の情報源によれば、基地の現役勤務の要員には400人のアメリカ人と109人のイギリス国防省職員が含まれるという。その役目は核爆弾搭載爆撃機を含むアメリカ空軍機との通信である。アメリカは公開の法定に「つごうの悪い証拠」が提出されるのを防ぐために、パーシーに対する訴えを取り下げた。」(「第六章」p.211~212) (2001年の実習船えひめ丸と潜水艦の衝突事件の暴露) 「マスコミのご機嫌をとってつごうのいいメッセージを伝えさせる以外に、国防総省は、国防総省を政治的に支援してくれそうな市民団体や、国防支出に既得権益を持つ市民団体を育成しようとしてきた。このロビー活動は、潜水艦USSグリーンヴィル艦内の致命的な怠慢事件がそれを垣間見せるまで気づかれずにいた。2001年2月9日、6500トンの攻撃型原子力潜水艦がホノルルの沖で緊急浮上訓練を実演して、全長190フィートの日本の高校の実習船えひめ丸と衝突、これを沈没させ、9人の日本の若者が生命を落とした。」 「グリーンヴィルは海軍を支援する裕福な民間人16名を楽しませるだけのために出航していた。 ...。彼(艦長のスコット・D・ワルド中佐)は、もし怠慢の廉で軍法会議にかけられたら、自分は民間人を航海につれだすよう命じられ、そして≪タイム≫誌に語ったように、「彼らを発令所に入れることで少なくとも集中力がさまたげられた」ことを第一に主張するつもりだといった。あるテキサスの石油会社の重役は、潜水艦が海面に向かって急浮上するとき、実際に操舵席に座っていた。」 「ワルドがこの発言をもう一度くりかえして公式記録に残すことをふせぐために、海軍の審問委員会は民間の招待客を一人も証言のために召喚しなかった。そして、太平洋艦隊の司令官、トーマス・B・ファーゴ提督は彼を軍法会議にかけないことを決めた。 ...。しかし、グリーンヴィル事件は海軍が艦艇と航空機をPRの小道具としてどれほど利用しているかをはじめてあきらかにした。2000年には太平洋艦隊だけで7836名の民間人訪問者を艦艇に同乗させている。」(「第四章」p.150~151) (p.255~259に沖縄についてのくわしい叙述がある。) 「アメリカは1945年から1972年まで、この島を国防総省が直接支配する植民地として保持した。この期間、130万人の沖縄の人々は国籍を失い、日本国民ともアメリカ国民とも認められず、アメリカ軍の中将に統治されていたのである。彼らはアメリカ軍当局が発給する特別の書類がないと、日本にもどこにも旅行できなかった。沖縄は外の世界から隔絶され、軍用飛行場や潜水艦基地、情報施設、CIAの隠れ家などがひしめく秘密の飛び地だった。こうした状況に抗議した一部の沖縄の人々は共産主義者の疑いありと決めつけられ、何百人もがボリビアに移送された。彼らはそこでアマゾン上流の人里離れた田舎に放りだされ、自給自足の生活をしいられたのである。」 「1970年代前半には、沖縄の人々は島をベトナム戦争の爆撃基地として使用することに公然と叛旗をひるがえし、軍が神経ガスや核兵器を、それにともなう危険を地元住民に警告することなく島に貯蔵していることを知って激しい怒りをぶつけていた。アメリカはしぶしぶながら、日本政府がアメリカ軍基地をひきつづき置かせてくれるのであれば、沖縄を日本の主権に形式上「復帰」させることに同意した。復帰は、沖縄の人々に対する責任を日本に転嫁しながら現状を永続させる好都合な方法だった。」 「日本政府は長年にわたり、アメリカ軍を沖縄に封じ込めておくためにあらゆることをしてきた。日本にあるアメリカ軍基地の約75パーセントがこの島に置かれているが、沖縄は日本の国土全体の1パーセント以下しか占めておらず、日本でいちばん貧しい県である。島と日本の関係は、プエルトリコとアメリカの関係によく似ている。東京の政府はこの取り決めが気に入っている。国民が日本の国土にアメリカ軍の駐留を許すのは、自分たちの見えないところにいる場合だけだということを知っているからだ。」 2001年の国防総省の「基地構成報告書」によれば、日本には73箇所の米軍基地がある。(日本の基地反対活動家たちの分析結果によれば基地の数は91である。)これらの基地は40,217人の軍人、6,431人の文民職員、42,653人の扶養家族を収容している。また29,205人の日本人を雇って兵站業務に従事させている。「…さらに、アメリカの情報機関のために、通信傍受記録だけでなく、日本語の本や雑誌も翻訳させている。日本政府はこうした役務の代価を支払うのを助けるために、毎年約40万ドルをアメリカに支払っている。したがって、日本はたぶんほかの国に金を払って自分をスパイさせている唯一の国だろう。」(「第七章」p.255~258)
・「グローバル化が第三世界の国に繁栄をもたらした例は一つも知られていない。」WTOは、「豊かな国が貧しい国に対して行使する経済的帝国主義の、欺瞞的だがきわめて効果的な道具である。しかし、システムは設立されて数年以内に分解をはじめた。」 ・「もし現在の流れがこれからもつづくならば、四つの悲劇がアメリカを見舞うことはまちがいないように思える。」 1)たえまなく戦争がつづく状態。あらゆる場所でアメリカ人に対するテロが増加。小国のあいだでは大量破壊兵器に対する依存がいっそう強まる。2)民主主義と憲法上の権利が失われる。独裁的大統領制へと変貌。3)プロパガンダや情報操作の横行。戦争や権力や軍隊に対する賛美が支配。4)財政の破綻。経済の荒廃。 ・「帝国の最後の悲劇である経済の荒廃は、 ...確実に危機につながる唯一の悲劇である。」 米軍事予算:2003会計年度、3,548億ドル。2004会計年度、3,793億ドル(エネルギー省所管の核兵器開発計画の156億ドル、沿岸警備隊の12億ドルを加えると3,961億ドル)。 「この額には国防総省が大半を管理する情報予算や、二度目のイラク戦争自体の支出、国防総省が要求するテロとの戦いのための100億ドルの特別勘定はふくまれていない。」 「アメリカのつぎに軍事に金を使っているロシアの予算はアメリカの総額の14パーセントにすぎない。第三位以下の上位27ヵ国の軍事予算を合計してやっと、アメリカの軍事支出と対等になるのである。」 ・2003年度予算にもとづく予測では、イラク戦争の出費を別にして、4,800億ドルの連邦予算赤字が見込まれている。 さらに、「国内のほぼすべての州が深刻な予算不足に直面し、連邦政府に救済措置を求めている。とくに、議会が要求する対テロ計画と民間防衛計画に政府が資金を出してくれるように要求している。」 議会予算局の見積もりでは、次の5年間に、2003年2月時点での6兆4,000億ドルの負債に加えて、1兆800億ドルの新たな連邦予算赤字が発生。 ・「アメリカの衰退はすでにはじまっている。」 「本書はこれまで、アメリカ帝国主義の軍事面をおもに取り上げてきた。ここでわたしは、世界の大半に対する経済的覇権を手に入れようとするアメリカの試みに目を向ける。 ...。皮肉なことだが、拡大しすぎたアメリカ帝国がたぶん最初に崩壊をはじめるのは、この経済面においてである。」(「第九章」p.330~331) 「グローバル化が第三世界の国に繁栄をもたらした例は一つも知られていない。 ...。グローバル化がもたらしたものはNICS(新興産業国)ではなく、約130のNNE(発展不能な国家経済)か、もっと悪い場合にはUCE(統治不能なまでに混乱した国家)である。」(「第九章」p.336~337) 「全体的に見て、1995年に誕生したWTOは、豊かな国が貧しい国に対して行使する経済的帝国主義の、欺瞞的だがきわめて効果的な道具である。しかし、システムは設立されて数年以内に分解をはじめた。9月11日のテロ攻撃以降、アメリカでは軍国主義と一国主義が強まりすぎた結果、国際法の効力は一気に弱まり、WTOの規則をささえる遵法の見せかけは浸食されている。それと同時に、アメリカの軍国主義者と経済界のグローバリストたちが衝突をはじめている。」(「第九章」p.348) 「もし現在の流れがこれからもつづくならば、四つの悲劇がアメリカを見舞うことはまちがいないように思える。 ...。まず最初に、たえまなく戦争がつづく状態がおとずれる。あらゆる場所でアメリカ人に対するテロが増加し、小さな国々のあいだではアメリカ帝国という怪物から身を守ろうとして大量破壊兵器に対する依存がいっそう強まる。第二に、民主主義と憲法上の権利が失われる。大統領が議会の重要性を完全に失わせ、みずからを政府の「行政部門」から国防総省化された大統領制のような存在へと変貌させるからである。第三に、すでにずたずたになっている真実を伝えるという原則が、プロパガンダや情報操作、戦争や権力や軍隊に対する賛美にしだいに取って代わられる。最後に、財政が破綻する。経済的資源をさらに壮大な軍事計画に注ぎ込んで、自国民の教育や健康や安全をないがしろにするからである。」(「第十章」p.366) 「帝国の最後の悲劇である経済の荒廃は、財政破綻が際限ない戦争や自由の喪失や政府の常習的な嘘ほどは憲法にとって致命的ではないかもしれないという点で、ほかの三つとはことなっている。しかしこれは、国民がどんなにおびえていても、頑として認めなくても、誤った情報を与えられていても、確実に危機につながる唯一の悲劇である。」 「世界をつねに軍事力で支配するというのは金がかかるものだ。2002年10月23日に承認された2003会計年度のアメリカの軍事予算は、3548億ドルに達した。国防総省は2004会計年度では3793億ドルへの増額を議会に求め、エネルギー省所管の核兵器開発計画の156億ドル、沿岸警備隊の12億ドルともどもそれを手に入れた。総額は3961億ドルである。この額には国防総省が大半を管理する情報予算や、二度目のイラク戦争自体の支出、国防総省が要求するテロとの戦いのための100億ドルの特別勘定はふくまれていない。 ...。アメリカのつぎに軍事に金を使っているロシアの予算はアメリカの総額の14パーセントにすぎない。第三位以下の上位27ヵ国の軍事予算を合計してやっと、アメリカの軍事支出と対等になるのである。」 「ブッシュ政権の一国主義的政策と軍事力への集中の問題は、アメリカの懐が現実にはかなり苦しいということである。2003年度予算にもとづく予測によれば、イラク戦争の出費をのぞいても、4800億ドルの連邦予算赤字が見こまれるという。国内のほぼすべての州が深刻な予算不足に直面し、連邦政府に救済措置を求めている。とくに、議会が要求する対テロ計画と民間防衛計画に政府が資金を出してくれるように要求している。議会予算局は、次の5年間に、政府が2003年2月にすでにかかえている6兆4000億ドルの負債にくわえて、1兆800億ドルというとほうもない連邦予算赤字が発生すると見積もっている。」 「同じくらい深刻なのは、わが国の貿易赤字がすでにのべたようにどんどん手に負えなくなっていることである。 ...。」(「第十章」p.393~395) 「わたしの見るところでは、 ...アメリカの衰退はすでにはじまっている。」(「第十章」p.398) (以上、『アメリカ帝国の悲劇』からの抜粋終わり) |