高校生が取り組んだメディアリテラシーの実践
報告暍本田孝義
テーマは「高校生が見たメディア」。報告者は、長年、長野県立松本美須々ヶ丘高等学校放送部の顧問だった林直哉さん。例会参加者は33名。問い合わせが少なかったので人が集まるか心配したが、結構来てくれた。
初めて参加した人が何人もいたし、pmnのメンバーで全盲の兵頭さんが京都から初参加したのもうれしかった。また、上映したビデオの製作に関わっていた、同校放送部の卒業生も2名参加した。
林さんは、放送部の活動を紹介。学校や地域の様々な行事・場面で放送部が活躍しているようだ。また、「放送部はもう一つの学校。中には授業を休んでも参加する生徒がいる。」と言っていた。そして、『テレビは何を伝えたか』というビデオを作る経緯を説明。

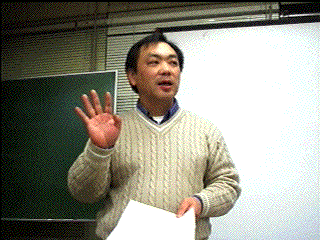
同校放送部部員の中に、河野さんの長女と共通の友人がいた生徒がいて、問題提起があったそうだ。その辺から、放送部部員たちはマスコミ報道に注意を払うようになったらしい。そして、テレビの報道に焦点を絞り、県内5局の取材を開始。事件から1年後、まずは、ラジオ番組として『テレビは何を伝えたか』が完成し、更に1年後、ビデオの『テレビは何を伝えたか』が完成。このビデオは全編テレビで放送することを企図していたが、NHK社会部(東京)が「民放にうちの記者が映るのは困る」という肝っ玉の小さい横槍で放送が不可能に。ここで諦めなかったのはすごい、と私は思った。『テレビは何を伝えたか』の上映会と、社会科の授業にメディア・リテラシーを盛り込んで、生徒が発表し始めたのだ。当初は「どうなるのかな」と林さんはひやひやしてたそうだが、授業はテレビ局や地元の大人を巻き込んで発展していく。さらに、プロの演劇にもなった。
松原さんもディスカッションで言っていたが、1本のビデオを作ることがこんなにも可能性をはらむことは、正直、驚くし、最近、放送が実現しなかったVIDEO ACT企画も「まだまだこれから」という気にさせてくれると思う。さて、この授業と演劇の報告が『メディアと共に』というビデオでした。
林さんはマスメディアは特別なものでなく、同じ人間が送り出しているのだ、ということを生徒が発見していく過程を強調していた。これは同時に、マスコミが開かれていかないとなかなか難しい、とも語っていた。そして、もう一つ、林さん自身の発見は「授業もメディア。受け手と送り手が入れ替わってみて、授業の全体像も分かる」というものでした。ディスカッションでは、メディアとは、マスメディアとは、という重要なやり取りがあった。時間があまりなく、とても大切な議論だったのに、深められなく、司会者として申し訳なく思う。例会で、こうしたテーマでやれればと思う。
また、生徒だった西沢君にも取材のやり方などの質問がとんだ。最後に私個人の感想を。林さんと生徒は、松本サリン事件以後5年間、学校で、毎日毎日、民衆のメディア連絡会と同じような議論・活動をやってたんだな、と思った。林さんのある種の自信のようなものも、生徒と切磋琢磨する中から生まれたのだと思う。日本全国の学校でこんな活動が起きるとは思えないけど、「作る・見せる・変える」活動は、学校でも必要だと思ったし、高校生だからこそ出来ることもあると思った。今後、高校生が作った素晴らしい作品をもっと見るチャンスが増えて欲しいしと思うし、交流の機会があればおもしろいと思う。
それにしても、林さんは元気な人でした。
追記:この例会がきっかけになって民衆のメディア連絡会のメーリングリストでメディアリテラシーに関連しての突っ込んだ議論に発展しています。いずれその内容も紹介・反映していきたいと思います。
トップページに戻る