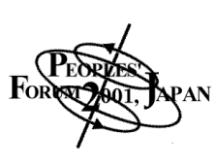
To: wto@jca.apc.org
Subject: [wto 180] 僌儘乕僶儖丒僗僞儞僟乕僪偵懳偡傞 NGO 偺帇揰
Date: Tue, 7 Sep 1999 17:05:35 +0900
From: Tomoko Sakuma <tsakuma@jca.apc.org>
仠偝傫偐傜偺偛堄尒丄偛幙栤偵懳偡傞壗傜偐偺嶲峫堄尒偵側傟偽偲巚偄丄埲壓偵嵟嬤幏昅偟偨尨峞乮傑偩敪峴偝傟偰傑偣傫偑乯傪憲晅偟傑偡丅嵅媣娫
NIRA惌嶔尋媶9寧崋尨峞
戞4復乽僌儘乕僶儖丒僗僞儞僟乕僪偵懳偡傞NGO偺帇揰乿
嵅媣娫抭巕乮巗柉僼僅乕儔儉2001帠柋嬊挿乯
梫栺丗
丂奺崙偺朄婯惂丒婎弨偺崙嵺惍崌壔偼丄婎弨愝掕幰偵傛傞
丂惗嶻梫慺丒巗応偺撈愯偲丄岞揑婡擻偺楎壔傪捠偠丄奿嵎傪
丂奼戝偟丄娐嫬攋夡傪彆挿偡傞丅懡條側暥壔傗壙抣娤丄惗懺
丂宯傪庣傞奺崙庡尃傪梚岇偟偮偮丄崙嵺揑側嵟掅幮夛婎弨乮
丂僌儘乕僶儖儈僯儅儉乯偵懳偡傞崌堄傪宍惉偡傞昁梫偑偁傞丅
杮暥
仭乽僌儘乕僶儖僗僞儞僟乕僪乿偺杮幙
丂乽僌儘乕僶儖僗僞儞僟乕僪乿偲偼丄悽奅巗応偺偁傝曽傪
婯掕偡傞條乆側梫場偵巟偊傜傟偨丄幚嵺忋偺崙嵺宱嵪婯斖
傪堄枴偡傞尵梩偩丅偦偺惉棫梫審偼丄悽奅傪堦偮偺巗応偲丄
堦偮偺壙抣娤偵摑崌偡傞偙偲偱偁傞丅偦偟偰偦偺栚揑偼丄
僌儘乕僶儖僗僞儞僟乕僪傪愝掕偡傞幰偑丄惗嶻梫慺偲巗応
傪撈愯偡傞偙偲偵偁傞丅
丂僾儘僙僗偼擇抜奒偱偁傞丅傑偢懠崙巗応偵懚嵼偡傞崙撪
朄婯惂丒婎弨傪丄杅堈丒搳帒忈暻偲偟偰庢傝彍偒丄悽奅巗
応偺摑崌乮僔乕儉儗僗壔乯傪恑傔傞丅師偵愝掕幰偵偲偭偰
搒崌偺椙偄崙嵺婎弨傪摫擖乮僗僞儞僟乕僪愝掕乯偡傞偙偲
偱丄愝掕幰偺悽奅巗応偵偍偗傞桪埵惈傪崅傔傞丅巇妡偗傞
懁偑嵟傕嫞憟椡傪敪婗偱偒傞忦審偱悽奅巗応傪摑堦偡傞偺
偱偁傞丅摑堦儖乕儖偺懚嵼偼丄摨帪偵丄奺崙偺幮夛丒宱嵪
婯惂偺偝傜側傞揚攑傪惓摉壔偡傞丅
丂僗僞儞僟乕僪愝掕偺曽朄偼戝偒偔暘偗偰擇捠傝偱偁傞丅
崙嵺婡娭傪捠偠偰柧暥壔偁傞偄偼朄揑崻嫆傪偮偔傝丄廬傢
偣傞曽朄偲丄巗応撈愯丒壡愯偵傛偭偰嫮惂偡傞傗傝曽偱偁
傞丅偄偢傟偺応崌傕丄偳偪傜偑乽杮摉偵桪傟偰偄傞偐乿丄偲
偄偆偙偲埲忋偵丄愭偵儖乕儖傗婎弨傪柧暥壔偡傞丄愭偵摿
嫋傪庢摼偡傞丄怴婯帠嬈傪奐戱偟偰巗応僔僃傾傪怢偽偡丄
偁傞偄偼媧廂崌暪偱婯柾奼戝傪恾傞丄側偳偑寛傔庤偲側傞丅
寢壥丄僌儘乕僶儖僗僞儞僟乕僪偼丄杮棃偺帺桼巗応宱嵪偺
棟憐偲偼棤暊偵丄乽旕岠棪乿傗晉偲尃尷偺廤拞傪懀偟偰偄傞丅丂丂丂丂
丂杮棃偺巗応宱嵪偵偼乽慖戰偺帺桼乿偲偄偆柉庡惈偑偁傞丅
偟偐偟丄嶻嬈娫奿嵎傗帒杮丒媄弍丒媄擻奿嵎傪惀惓偣偢丄
娐嫬丒幮夛僐僗僩傗暥壔丒惗暔偺懡條惈傪娕夁偟偨栰曻偟
偺嫞憟偼丄乽岞暯乿偱側偔丄乽帩懕壜擻乿偱側偄丅偙偺嫞憟
偵彑偰傞偺偼婎弨偺愝掕幰偩偗偱偁傝丄愝掕幰傕傑偨丄峳
攑偟偨娐嫬偲幮夛偐傜偺偟偭傌曉偟傪柶傟側偄丅
仭岞揑栶妱偺曄壔
丂岞揑栶妱偲偼丄惻惂傪捠偠偨晉偺嵞暘攝傗丄婯惂傪捠偠
偨岞惓偱帩懕壜擻側幮夛丒宱嵪偺堐帩丄僙乕僼僥傿僱僢僩
偺惍旛偵傛傞庛幰媬嵪側偳偱偁傞偲棟夝偝傟偰偒偨丅偟偐
偟崙嵺嫞憟偑寖壔偡傞拞丄偙傟傜偼嫞憟椡傪庛傔傞梫場偲
峫偊傜傟傞傛偆偵側偭偨丅惌晎偼崱丄乽崙嵺惍崌壔乮僴乕儌
僫僀僛乕僔儑儞乯乿偺棳傟偵廬偄丄愊嬌揑偵岞揑栶妱傪曻婞
偟丄戙傢傝偵丄嫮偄婇嬈僙僋僞乕偺墳墖抍偵摿壔偟偮偮偁
傞丅堦曽丄奺崙偺岞揑婡擻傪戙懼偡傞偼偢偺崙嵺惻惂丒婯
惂丒僙乕僼僥傿僱僢僩偼懚嵼偟側偄偐丄婡擻晄慡偵娮偭偰
偄傞丅杅堈帺桼壔偺棳傟傪捛偭偰丄偙偺栤戣傪峫嶡偡傞丅
仭杅堈帺桼壔偲娐嫬丒恖尃丒楯摥幰曐岇偺偨傔偺崙楢忦栺
丂僂儖僌傾僀儔僂儞僪乮UR乯埲慜偺杅堈帺桼壔岎徛偼丄娭
惻傗悢検婯惂側偳丄奺崙偺崙嫬慬抲傪懳徾偲偟偰偒偨丅崙
嫬慬抲偺掅尭偵傛傝丄桝擖検偑憹壛丄桝擖昳壙奿偑掅壓偟
偨偨傔丄奺崙偺徚旓峴摦偑曄傢傝丄嶻嬈峔憿偑夵曄偝傟偨丅
壙奿嫞憟偑寖壔偡傞拞丄僞僟偺娐嫬偼墭愼偝傟丄揤慠帒尮
偼埨偔攦偄扏偐傟丄岺応偼娐嫬婎弨傗楯摥忦審偺掅偄強偵
堏揮丄岞奞偑崙嫬傪挻偊偰奼戝偟偨丅
丂偙偆偟偨帠懺傪庴偗丄奺崙惌晎偼崙楢偺応偱偝傑偞傑側
懡崙娫娐嫬嫤掕乮MEAs乯傗恖尃婯栺丄偦偟偰婎杮揑楯摥婎
弨乮ILO嫤掕乯傪嵦戰偟偨丅偝傜偵1990擭弶摢傑偱偵偼乽崙
楢懡崙愋婇嬈峴摦婯弨乿偑憪埬偝傟丄懡崙愋婇嬈偺峴摦偵
惂栺偑壽偝傟傛偆偲偟偰偄偨丅宱嵪偺僌儘乕僶儖壔偵敽偄丄
僌儘乕僶儖側幮夛婯惂偑昁梫偲偝傟偨偺偱偁傞丅偟偐偟丄
偙偆偟偨搘椡偺峛斻側偔丄懡崙愋婇嬈峴摦婯弨偼抧媴僒儈
僢僩偺奐偐傟偨1992擭丄崙楢憤夛偱晄嵦戰偲側傝丄恖尃婯
栺傗ILO嫤掕偼懡偔偺崙偱偄傑偩斸弝偝傟偰偄側偄丅懡崙
娫娐嫬嫤掕傕傑偨丄寖壔偡傞崙嵺嫞憟偺拞偱丄宱嵪傪桪愭
偡傞奺崙偵傛偭偰夵埆偝傟偨傝丄幚岠惈偑嫼偐偝傟偰偄傞丅
仭嵟掅婎弨偑嵟崅婎弨偲偝傟傞栤戣
丂UR埲崀偺帺桼壔岎徛偱偼丄旕娭惻杅堈丒搳帒忈暻偲偟偰
崙撪朄婯惂丒婎弨傪娚榓丒揚攑偟丄崙嵺婎弨偵惍崌壔偡傞
偙偲偑庡梫側壽戣偲偝傟傞傛偆偵側偭偨丅傑偨丄偙偺僾儘
僙僗偵偍偄偰丄婇嬈娫偺帺庡婎弨傗丄幮夛婎弨偺嵟掅儔僀
儞偲偟偰嶌傜傟偰偒偨崙嵺婎弨偑杅堈丒搳帒忈暻偺嵟崅尷
搙偲偟偰埵抲晅偗傜傟傞傛偆偵側偭偰偒偨丅
丂悽奅杅堈婡娭乮WTO乯嫤掕偱偼丄奺崙偺怘昳埨慡婎弨傗
怘昳昞帵儖乕儖側偳傪僐乕僨僢僋僗埾堳夛偺掕傔傞婎弨偵
惍崌壔偡傞偙偲偑媮傔傜傟偨丅僐乕僨僢僋僗埾堳夛偲偼丄
撈帺偺怘昳婯奿傪帩偨側偄搑忋崙偺偨傔偺婎弨愝抲傪栚揑
偲偟偨崙楢婡娭偱偁傞丅偦傟傑偱偺幮夛揑擣抦偼掅偔丄偦
偺峔惉堳偼壢妛幰偲怘昳嶻嬈偑戝惃傪愯傔偰偄偨丅摉慠側
偑傜丄僐乕僨僢僋僗婎弨偼堦晹偺崙偑嶲徠偡傞嵟掅婎弨偲
尵偊傞傕偺偩偭偨丅偟偐偟丄怘椏杅堈偺忈暻偺嶍尭丒揚攑
傪栚揑偵嶌傜傟偨WTO乽塹惗怉暔専塽乮SPS乯嫤掕乿偺嫆
傝強偲偝傟偨偲偒丄偙傟偑帠幚忋偺悽奅嵟崅婎弨偵側偭偨丅
奺崙偑偙偺婎弨傛傝傕崅偄崙撪婎弨傪堐帩偟丄偦傟偑杅堈
忈暻偲偟偰採慽偝傟偨応崌丄壢妛揑崻嫆傪棫徹偱偒側偗傟
偽婎弨夵惓傗攨彏傪梫媮偝傟傞丅懡偔偺崙偑偙偆偟偨栵夘
帠傪嫲傟丄帺崙婎弨傪僐乕僨僢僋僗婎弨偵惍崌壔乮夵埆乯
偟偨丅擔杮傕摨條偱丄椺偊偽巹偨偪偼崱丄埲慜偼嬛巭偝傟
偰偄偨DDT巆棷怘昳傪怘傋傞偙偲偵側偭偨丅
丂傕偆堦偮偑乽WTO偺媄弍揑忈奞乮TBT乯嫤掕乿偱偁傞丅TBT
嫤掕偱偼丄怘昳婎弨埲奜偺慡偰偺婎弨傪懳徾偲偟偰丄偦偺
崙嵺惍崌壔傪彠椼偟偰偍傝丄彨棃丄ISO婎弨偑偦偺嵟崅婎
弨偲偝傟偰偄偔壜擻惈偑偁傞丅偦偆側傟偽丄椺偊偽ISO14000
偺僄僐儔儀儖婎弨傗帩懕壜擻側怷椦宱塩偺婎弨傛傝傕崅偄
婎弨傪奺崙丒帺帯懱偑嵦梡偡傞偙偲偼崙嵺朄堘斀偲偝傟丄
採慽丄夵惓丄攨彏丄惂嵸偺懳徾偲側傞丅偲偙傠偑ISO偲偼丄
傕偲傕偲堦晹偺柉娫婇嬈偑撈帺偵掕傔偨撪晹婯掕偺傛偆側
傕偺偩丅偟偨偑偭偰丄婇嬈偵娐嫬曐慡搘椡傪懀偡岠壥偼偁
偭偰傕丄朄揑峉懇椡傪帩偮嵟崅婎弨偵偼慡偔晄揔摉偱偁傞丅
丂摨條偵丄崙嵺捠壿婎嬥乮IMF乯偺梈帒忦審偵婛懚偺帺庡婎
弨傪庢傝崬傓偲偄偭偨働乕僗傗丄堦崙撪偺摿嫋惂搙傪崙嵺
惂搙壔偡傞側偳偺摦偒偑偁傞丅嵟掅婎弨偩偭偨帺庡婎弨偑
摉弶偺幮夛揑栚揑傪棧傟丄宱嵪妶摦傊偺曋塿偺偨傔偵嵟崅
尷搙偲偝傟丄恖椶慡偰偵嫕庴偝傟傞傋偒壢妛傗媄弍偺壎宐
偼摿嫋朄偺崙嵺壔偲嫮壔偵傛偭偰撈愯揑棙塿傪惗傓傕偺偲
側偭偨丅偦偟偰崱丄偙傟傜偺怴偟偄崙嵺儖乕儖偑丄杅堈惂
嵸傗梈帒忦審偲偄偆嫮惂椡傪敽偭偰奺崙偵墴偟晅偗傜傟傞
偙偲偵側偭偨偺偱偁傞丅
仭奺崙朄惂傪怤怘偡傞崱屻偺崙嵺惍崌壔
丂忋弎偟偨帠椺偼丄偙傟偐傜巒傑傞戝婯柾側崙嵺惍崌壔偺
戞堦曕偵夁偓側偄丅崱屻偼丄奺崙偺偁傜備傞朄婯惂丒婎弨
偑崙嵺惍崌壔偺懳徾偲偝傟傞丅偦偺愭椺偼丄嶐擭枛偵岎徛
偑懪偪愗傜傟偨OECD偺懡崙娫搳帒嫤掕乮MAI乯偵尒弌偡
偙偲偑偱偒傞丅MAI偼丄奜崙婇嬈偵懳偟丄恑弌愭偺崙撪朄
婯惂丒婎弨傪夵惓丒揚攑偡傞尃尷傪梌偊傛偆偲偟偨丅偦偺
揔梡幚懺偑奜崙婇嬈偵嵎暿揑偲敾抐偡傟偽丄婇嬈偼崙嵺朄
掛偵捈愙採慽傪峴偄丄奩摉偺朄婯惂偺夵惓丒揚攑傪敆傞偲
偲傕偵丄懝奞攨彏傪惪媮偱偒傞偲偟偰偄偨偺偩丅偦偺媡偵丄
崙壠偑崙嵺朄掛偱恑弌婇嬈傪採慽偡傞偙偲偼専摙偡傜偝傟
偰偄側偄丅MAI偺悧宆偲側偭偨杒暷帺桼杅堈嫤掕乮NAFTA乯
偱偼丄婛偵偙偺傛偆側乽搳帒壠vs.崙壠乿暣憟夝寛傪捠偠丄
僇僫僟傗儊僉僔僐偱偼娐嫬曐慡嶔偑棟晄恠側揚攑傪敆傜傟偰
偄傞丅MAI偱偼丄楯摥僗僩傗徚旓幰儃僀僐僢僩偱婇嬈偑旐偭
偨懝奞傕丄崙壠曗彏偺懳徾偲偝傟偨丅MAI偑惉棫偟偰偄傟
偽丄惌晎偼帠慜偺嶔偲偟偰僗僩傗儃僀僐僢僩傪嬛巭偟側偗
傟偽側傜側偔側偭偰偄偨偩傠偆丅
丂尰嵼WTO偱偼丄奺崙傗奺帺帯懱偺惌晎挷払偺姰慡帺桼壔
偵岦偗丄摟柧壔傗撪奜柍嵎暿側偳偺尨懃嶌傝偑恑傔傜傟偰
偄傞丅嫞憟惌嶔偺媍榑偱偼丄崙桳婇嬈傗撈愯婇嬈偑懡偄搑
忋崙巗応傪奜崙婇嬈偵奐曻偝偣傞偙偲偑庡娽偲偝傟傞丅傑
偨丄棃擭巒傑傞僒乕價僗杅堈帺桼壔偺岎徛偱偼丄岞嫟僒乕
價僗傗堛椕丒暉巸丒嫵堢側偳傪娷傓160嬈庬偑懳徾偲側傞丅
岞嫟僒乕價僗偼柉塩壔傪敆傜傟丄旕塩棙僒乕價僗偼塩棙壔
傪敆傜傟傞丅偦偆偟側偗傟偽奜崙婇嬈偵恑弌偺乽偆傑傒乿
偑側偄偐傜偩丅慡偰偺恖偵傢偗妘偰側偔採嫙偝傟偰偒偨岞
嫟僒乕價僗偑丄昻崲憌偵偼峴偒撏偐側偔側傞偐傕偟傟側偄丅
丂僌儘乕僶儖僗僞儞僟乕僪偼乽帺媼乿傗乽帺棫乿傪婎慴偲
偡傞幮夛傗乽帺棩乿揑側崙壠婡峔傪攋夡偟丄慡偰傪奜崙婇
嬈偺乽宱嵪妶摦乿偵抲偒姺偊傞偨傔偺奣擮偩丅偦偺崻掙偵
偼丄惉挿偟懕偗偹偽曵夡偡傞崱偺宱嵪帺懱偺栤戣偑偁傞丅
仭傾僇僂儞僞價儕僥傿媍榑偺栍揰
丂僌儘乕僶儖僗僞儞僟乕僪偺愝掕幰偼丄悽奅恖岥丄崙悢偺
偄偢傟偱尒偰傕悢偺忋偱偼儅僀僲儕僥傿偱偁傞丅偩偐傜偙
偦丄僌儘乕僶儖僗僞儞僟乕僪偵傛傞巗応摑崌傪捠偠偨帒杮
拁愊丄帒尮丒巗応巟攝丄媄弍丒媄擻撈愯偵傛偭偰帺傜偺抧
埵傪曐慡偡傞昁梫偑偁傝丄傑偨丄偦傟傪枩恖偵惀擣偝偣傞
偨傔偺僗儘乕僈儞傪昁梫偲偟偰偄傞丅
丂乽摟柧惈乿傗乽傾僇僂儞僞價儕僥傿乿偼偦偺揟宆偲尵偊
傞丅偙偺尵梩偼巗柉幮夛偵傕娊寎偝傟懡梡偝傟偰偄傞丅偟
偐偟摨帪偵丄惌晎偐傜宱嵪妶摦傪挷惍偡傞尃尷傪庢傝忋偘丄
帒杮傪帩偭偨姅庡傗宱塩幰偑棙弫捛媮偺偨傔偵嬑楯幰偺柦
塣傪彾埇偡傞偨傔偺曽曋偵傕巊偊傞尵梩側偺偱偁傞丅幮堳
庡懱偺乽楯摥巟攝乿宆婇嬈偼丄姅庡乮搳帒壠乯庡懱偺乽帒
杮巟攝乿宆婇嬈偵曄幙傪敆傜傟傞丅
丂傕偪傠傫丄晻寶幮夛傗晠攕傪峬掕偟偰偄傞傢偗偱偼側偄丅
偟偐偟丄悽奅巗応偑摑崌偝傟傞拞丄幮夛扨埵傗宱嵪扨埵偺
戝婯柾壔偦偺傕偺偑戝偒側晠攕傪惗傒弌偟偰偄傞丅撈愯嬛
巭朄偼岠椡傪幐偄丄朄恖惻夞旔偺梋抧傕奼戝偟偰偄傞丅僌
儘乕僶儖壔偼丄抧棟揑偵傕怱棟揑偵傕娐嫬攋夡傗昻崲偺尰
幚傪墦偞偗丄忣曬傪暋嶨壔偡傞丅傾僇僂儞僞價儕僥傿偼帒
杮偲忣曬棟夝椡傪帩偮傕偺偑丄帩偨偞傞傕偺傗嫞崌幰丄偍
傛傃幾杺幰傪捛偄棊偲偡曽曋偲側傞丅偙偆偟偨拞丄悽奅偱
嵟傕嫮戝側搳帒壠偺摟柧惈傗傾僇僂儞僞價儕僥傿偼妋曐偝
傟偰偍傜偢丄崱屻傕妋曐偝傟側偄偩傠偆丅夝寛偵偼丄尃尷
傗帒杮丄宱嵪丒幮夛婡峔偺婯柾弅彫偲暘嶶偑昁梫偱偁傝丄
揙掙偱偒側偄傾僇僂儞僞價儕僥傿媍榑偼暰奞偱偝偊偁傞丅
仭婾憰偝傟偨曐岇庡媊丗幮夛婯惂丒婎弨偺慖戰揑揔梡
丂崙嵺惍崌壔偼丄撪奜柍嵎暿傗徚旓幰棙塿偲偄偆屆揟揑側
帺桼巗応榑偩偗偱偼側偔丄摟柧惈傗傾僇僂儞僞價儕僥傿丄
娐嫬曐慡傗楯摥幰曐岇側偳偺戝媊柤暘偺壓偱恑傔傜傟傞丅
偟偐偟丄僌儘乕僶儖僗僞儞僟乕僪偺偗傫堷栶偱偁傞愭恑崙
偺懡偔偑丄偙傟傑偱崙楢偱嶌傜傟偨悢懡偔偺娐嫬嫤掕傗楯
摥婎弨丄偁傞偄偼懡崙愋婇嬈峴摦婯弨側偳偵偼擬怱偱側偔丄
帪偵偼揋懳揑偱偝偊偁傞帠幚偑暲懚偡傞丅
丂嬤擭偵側偭偰丄愭恑彅崙偼WTO偺応偱娐嫬偲楯摥偺栤戣
傪擬怱偵媍榑偟巒傔偨丅ILO嫤掕傗恖尃婯栺偺斸弝偝偊廔
偊偰偄側偄擔杮傗暷崙偑丄搑忋崙偺楯摥忦審偺埆偝傗娐嫬
婎弨偺掅偝傪偙偲偝傜偵嫮挷偡傞傛偆偵側偭偨丅偦偺栚揑
偼丄帺崙嶻嬈傪搑忋崙偺埨偄楯摥丒娐嫬僐僗僩偲偺嫞憟偐
傜庣傞偨傔偵丄偙傟傜偺婎弨偺掅偝傪棟桼偵丄搑忋崙偵杅
堈惂嵸傪壽偡偙偲偵偁傞丅偙傟傪寈夲偡傞搑忋崙惌晎偼丄
杅堈惂嵸偵儕儞僋偟偨乽杅堈偲娐嫬乿傗乽杅堈偲楯摥乿偲
偄偆壽戣愝掕帺懱偵斀敪丄怴偨側撿杒懳棫偑惗傑傟偰偄傞丅
仭栤戣惍棟
丂栤戣揰偼嶰偮偵惍棟偱偒傞丅堦偮偼丄崙嵺惍崌壔偵傛傞
崙撪幮夛朄婯惂丒婎弨偺曻婞偲偄偆崙撪朄偺栤戣偱偁傞丅
偙傟偑暥壔傗岞嫟偺偁傝曽側偳偵偍偗傞奺崙柉偺庡尃偲壙
抣娤傪怤奞偟丄懡條側惗懺宯傪曐慡偡傞偨傔偺懡條側巤嶔
傪斀屘偵偡傞丅擇偮栚偼丄奺崙偑曻婞偟偨朄婯惂丒婎弨偑
崙嵺儗儀儖偱曗姰偝傟偰偄側偄偲偄偆崙嵺朄偺栤戣偩丅偦
偟偰嶰偮栚偼丄宱嵪偺僌儘乕僶儖僗僞儞僟乕僪偺摫擖偵敽
偄丄悐戅偡傞崙撪嶻嬈傪偳偆偡傞偺偐丄偲偄偆宱嵪揑側栤
戣偱偁傞丅搑忋崙偺寽擮偲廳側傞栤戣偩丅
丂偙傟傜偺栤戣愝掕偵懳偟丄僌儘乕僶儖僗僞儞僟乕僪偼揚
攑偝傟偨崙撪朄婯惂傪曗姰偟偰偍傝丄偦偺摫擖偵傛偭偰搑
忋崙偺幮夛婯惂丒婎弨偑岦忋偡傞偺偱偼側偄偐偲偺斀榑偑
懚嵼偡傞丅偝傜偵丄搑忋崙偱偼丄摟柧惈偺岦忋偲巗応帺桼
壔偑柉庡壔傪傕偨傜偟丄崙撪宱嵪偼傛傝嫞憟椡偺偁傞嶻嬈
峔憿傊偲恑壔偡傞偲偺堄尒偑偁傞丅偟偐偟幚嵺偵偼丄偦偺
偳偪傜傕偁傑傝幚尰偟偰偄側偄丅側偤側傜丄宱嵪偺僌儘乕
僶儖僗僞儞僟乕僪偼丄傛傝掅偄杅堈丒搳帒忈暻傪媮傔傞拞丄
幮夛婯惂丒婎弨傪忈暻偲尒側偟丄嵟掅尷偺幮夛婯惂丒婎弨
傊偺惍崌壔傪恾傞偙偲傪柦戣偲偟偰偄傞乮掅埵暯弨壔乯丅乮忋
弎偺捠傝丄婾憰栚揑偱崅偄幮夛婎弨偑帩偪弌偝傟傞偙偲偼
偁傞丅乯崙壠娫偺搳帒桿抳崌愴偑偦傟傪屻墴偟偡傞丅偟偐傕丄
崙嵺壔偟偨宱嵪妶摦偵懳偡傞崙嵺惻惂傗婯惂丄崙嵺揑側庛
幰媬嵪儊僇僯僘儉偼懚嵼偟側偄偐丄幚岠惈傪嫼偐偝傟偰偄
傞丅偝傜偵丄帺桼壔偝傟偨搑忋崙巗応偱偼丄朿戝側帒杮傗
摿嫋丄婇嬈撪丒婇嬈娫僱僢僩儚乕僋偵庣傜傟丄僌儘乕僶儖
僗僞儞僟乕僪傪愭庢傝偟偨愭恑崙婇嬈偑棙弫傪壡愯偟丄偦
偺棙弫傪崙奜偵棳弌偝偣偰偄傞丅寢壥丄搑忋崙偱偼丄嵚柋
曉嵪偑懾傞堦曽丄帺桼壔偵傛偭偰崙嵺嬥梈巗応偵捈寢偝傟
偨搑忋崙巗応偱嬥梈婋婡偑敪惗偡傞壜擻惈偑崅傑傞丅幚嵺丄
嬥梈婋婡偼帺桼壔偝傟偨巗応偩偗傪捈寕偟偰偍傝丄傑偨夁
嫀廫悢擭娫偵悽奅60僇崙偑戝暆側宱嵪偺儅僀僫僗惉挿傪宱
尡偟偰偄傞乮奿嵎偺奼戝乯丅
仭僌儘乕僶儖儈僯儅儉傪媮傔偰
丂僌儘乕僶儖僗僞儞僟乕僪偲偼丄堦尒帺桼巗応宱嵪傪巙岦
偟偰偄傞傛偆偱丄幚偼摿掕偺壙抣娤偵恖乆傪屌掕偟丄偦偺
懠偺壙抣傗丄僗僞儞僟乕僪傪枮偨偣側偄戝敿偺恖乆傪攔彍
偡傞偨傔偵嶌梡偟偰偄傞丅偟偐偟丄宱嵪偺幚懺偑偙傟偩偗
僌儘乕僶儖壔偡傞拞丄巗柉幮夛傕傑偨丄偁傞庬偺崙嵺幮夛
婎弨傪愝掕偟丄崙壠偺榞傪挻偊偰栤戣偵懳張偡傞昁梫惈傪
擣幆偟偰偄傞丅偟偐偟偦偺栚揑偼丄悽奅拞偺恖傃偲偑丄朙
偐側帺慠娐嫬偺壓丄堖怘廧丒屬梡傪曐忈偝傟丄恖庬丒惈暿丒
廆嫵丒庡媊側偳傪棟桼偲偟偨偁傜備傞嵎暿傪庴偗偢偵暯榓
偵惗懚偡傞尃棙傪梚岇偡傞偙偲偵偁傞丅
丂崙楢奐敪寁夋乮UNDP乯偺乽恖娫奐敪曬崘彂乿偑梡偄偰偄
傞惗妶悈弨丄嫵堢丒屬梡婡夛側偳偺巜昗偵昞傟偰偄傞壙抣
傗丄崙楢偱嶌傜傟偰偒偨偝傑偞傑側娐嫬丒恖尃丒楯摥丒徚
旓幰曐岇偺偨傔偺嫤掕偼丄暥壔傗惗懺宯偺懡條惈傪挻偊偰丄
慡偰偺恖偑崌堄偱偒傞壙抣偺堦椺偲偄偊傞丅巹偼偦偺嵟掅
婎弨傪僌儘乕僶儖儈僯儅儉偲屇傫偱偄傞丅僌儘乕僶儖儈僯
儅儉偵忋尷偲偄偆奣擮偼側偄丅偦傟偧傟偺崙丒抧堟偑偦傟
偧傟偺懡條惈傪梚岇偡傞尃棙傪帩偭偰偄傞偲峫偊傞偐傜偩丅
偦偙偑幮夛婎弨傪忈暻偲尒側偡崱偺僌儘乕僶儖僗僞儞僟乕
僪偲崻杮揑偵堘偆偲偙傠偱偁傞丅偝傜偵丄嵟掅婎弨傪枮偨
偣側偄崙偵懳偟偰偼丄偦偺崙傪偝傜偵媷朢偝偣傞杅堈惂嵸
傗嵚柋掆巭偱偼側偔丄巗柉丒NGO傕娷傔偨憡屳棟夝偺偨傔
偺崙嵺岎棳傗憃曽岦揑側崙嵺嫤椡偑昁梫偱偁傞丅
丂崱傗宱嵪奿嵎偼撿杒偺娫偺栤戣偱偼側偔丄愭恑崙撪偱傕怺
崗壔偟偰偄傞丅娐嫬栤戣傕傑偨丄愭恑崙偺巗柉偩偗偱側偔丄
寖偟偄娐嫬墭愼丒攋夡傪栚偺摉偨傝偵偟偰偄傞搑忋崙偺巗柉
偺戝偒側娭怱帠偩丅偙偆偟偨拞丄悽奅偺巗柉塣摦偑堦抳偟偰
MAI偺惉棫傪慾傫偩偙偲偼丄僌儘乕僶儖僗僞儞僟乕僪悇恑
攈偵崻杮揑側曄峏傪敆傞幮夛揑埑椡偺崅傑傝傪昞偟偰偄傞丅
巗柉丒NGO偺崌堄傪廳帇偡傞崙傗崙嵺婡娭偑憹偊偰偒偰偄
傞偺偼丄偦偺攚屻偵壗廫壄恖傕偺晄枮偑尒偊塀傟偡傞偐傜偩
傠偆丅乽偙偺傑傑偱偼悽奅奺抧偱乮昻崲傗婹夓偵傛傞乯戝朶
摦偑婲偒傞丅乿愭斒棃擔偟偨悽嬧僄僐僲儈僗僩偺尵梩偩丅僌
儘乕僶儖僗僞儞僟乕僪傪悇恑偟偮偮丄彫庤愭偺娐嫬丒昻崲懳
嶔偱偝傜偵栕偗傞偲偄偆崱傑偱偺傗傝曽偼傕偆捠梡偟側偄丅
丂岞惓偲帩懕壜擻惈偵婎偯偔悽奅暯榓偼丄儌僲丒僇僱傪捠偠
偨憡屳埶懚偲柍尷偺宱嵪惉挿偵傛偭偰偱偼側偔丄懡條側暥壔
偺懜廳偲憡屳棟夝丄偦偟偰嫤椡傪捠偠偨恖尃梚岇丒娐嫬曐慡
偺偨傔偺僌儘乕僶儖丒儈僯儅儉偺払惉偵傛偭偰堢傑傟傞丅
NGO偼丄乽崙嵺壔偟偨巗応宱嵪偵敽傢傟傞傋偒揔愗側宱嵪丒
幮夛婯棩乿偲偄偆帇揰偐傜偺儗價儏乕偲媍榑傪媮傔偰偄傞丅
Date: Tue, 31 Aug 1999 10:58:15 +0900
To: wto@jca.apc.org
From: aosawa@jca.apc.org (OSAWA Akiko)
Subject: [wto 174] WTO 僔傾僩儖妕椈夛媍娭楢 NGO僀儀儞僩
丂奆條傊
丂埲壓偵丄WTO僔傾僩儖妕椈夛媍偵暲峴偟偰峴傢傟傞NGO偺僀儀儞僩忣曬傪偍憲傝偟傑偡丅
巗柉僼僅乕儔儉2001
戝郪乮偝偔傑偺戙棟乯
======================================================================
Citizen's Summit Program, WTO Summit Seattle, November 27 - December 2, 1999
======================================================================
The likely structure and format for NGO activities in Seattle is emerging.
A full schedule of NGO strategy, education and action parallel to the offici
al Summit itself will involve successive days devoted to particular, related
themes or substantive issues (the various critiques of and alternatives the
WTO status quo). Activists and scholars from around the world will gather i
n Seattle, and the citizen's summit will reflect and project diverse perspec
tives and critiques of the WTO, from civil society in the South and North.
Each day will follow a similar functional agenda, along these lines:
匑 8:30ish
Press briefing over breakfast
Subject: that day's themes and issues.
Interviews scheduled.
匒 10:30ish
Panels on the issues
Our opportunity to educate one another.
Reports from country-based campaigns.
匓 Noonish
Pressworthy public events --rallies, marches, demos
on the featured issue of the day, dramatizing the critique.
匔 2:00ish
Strategy Sessions of activists working on related issues.
We often do not take advantage of international events to plan forward while
in the same city: organizing international campaigns, movement building, ski
lls sharing.
匘 4:30ish
Report back on day's news.
Debrief from issue leaders.
Inside/Outside coordination.
匛5:15ish
Adjourn and Dispatch
All clear for concerts, cocktail parties, chasing negotiators
Several appropriate venues for all these functions were reserved month ago,
all within a few blocks of the official Summit venue, the Trade and Conventi
on Center, and without the assistance of the corporate SHO coalition. The l
argest is the United Methodist Church which sits 1200 in the sanctuary and 4
00 in the Press Room below. Back-up venues are identified.
---------------------------------------------------------------
Schedule of events:
---------------------------------------------------------------
仛FRIDAY & SATURDAY November 26 & 27
* International Forum on Globalization (IFG) Teach-In
(Benaroya Symphony Hall, Downtown Seattle)
Contact: 415.771.3394 or www.ifg.org
仛MONDAY November 29
* Environment and Health
(United Methodist Church)
Contact: Mary Bottari, Public Citizen --202.546.4996 (health)
Dan Seligman, Sierra Club -- 202.547.1141 (environment)
* International Interfaith Service
(United Methodist Church)
Contact: Michael Ramos, Washington Association of Churches --
206.625.9790 or www.thewac.org
仛TUESDAY November 30
* Livelihoods/Labor Rights/Standard of Living/Human Rights
(United Methodist Church)
Contact: Medea Benjamin, Global Exchange --510.548.0370 or www.globalexchang
e.org
Contact: Marianne Mollman, Public Citizen-- 202.546.4996 (human rights)
* Massive Rally and March on the WTO
(The Streets of Seattle)
Contact: EVERYONE YOU KNOW!!!
仛WEDNESDAY December 1
* Women/Domocracy/Sovereignty/Development
(United Methodist Church)
Contact: Alexandra Spieldoch, Center of Concern -- aspieldoch@coc.org
* No Patents on Life: Biotech in the Global Economy
(Plymouth Congregational Church)
Contact: Phil Bereano -- 206.543.9037 or phil@uwtc.washington.edu
仛THURSDAY December 2
* Food & Agriculture: Food Safety and Security
(United Methodist Church)
Contact: Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) --
612.870.0453 or www.iatp.org, or rvanstaveren@iatp.org
仛FRIDAY December 3
*Who Rules? Corporate Accountability
(Gethsemane Lutheran Church)
Contact: David Korten, people-Centered Development Forum
pcdf@econet.org or http://iisd.ca/pcdf
--------------------------------------------------------------------
Organizing committees for each of these days have been formed or are in the
process of being formed. Contact the organizations listed after each day to
get involved or to learn more about the details of the planning of the vario
us days. Each organizing group aims to be as inclusive and incorporating as
possible, including international, national and local participants.
--------------
戝郪徎巕<aosawa@jca.apc.org>
巗柉僼僅乕儔儉2001
仹110-0015丂搶嫗搒戜搶嬫搶忋栰1-20-6丂娵岾價儖3奒
TEL. 03-3834-2436 FAX. 03-3834-2406
http://www.jca.apc.org/pf2001jp/
To: wto@jca.apc.org, oda@jca.ax.apc.org
Subject: [wto 157] 悽奅偺僂僄僢僽僒僀僩埬撪乮揮憲乯
Date: Wed, 11 Aug 1999 18:39:32 +0900
From: Tomoko Sakuma <tsakuma@jca.apc.org>
WTO丄擾嬈丄GMO丄APEC丄娐嫬丄壏抔壔丄怷椦丄僂儔儞丄愇桘丄恖尃丄愭廧柉丄斀愴側偳偵娭楢偡傞悽奅偺僂僄僢僽僒僀僩偺儕僗僩傪揮嵹偟傑偡丅
嵅媣娫抭巕
--------------------------------------------------------
This list is posted on the web by Brian Jenkins,
Australian Stop-MAI! Coalitiom
http://www.nettrek.com.au/~brian/andreas.htm
--------------------------------------------------------
Millenium Round // Rodada do Milenio // Ronde Millenaire
-> UPDATE 05.08.99 <-
====================
"OFFICIALS":
(neolib's blah blah)
====================
World Trade Organization:
http://www.wto.org
WTO Seattle
http://www.wto.org/wto/minist/seatmin.htm
Seattle Business welcomes WTO:
http://www.wtoseattle.org
European Commission:
http://europa.eu.int/comm/dg01/dg1newround.htm
TABD Mid Year Report:
http://www.tabd.org/about/MYMExecSummary1.html
and the annex: http://www.tabd.org/about/MYMTechnicalAnnex.html
CANADA'S DEPT. OF FOREIGN AFFAIRS AND INT'l TRADE
http://www.dfait-maeci.gc.ca/menu-e.asp
CANADIAN INT'l TRADE TRIBUNAL
http://www.citt.gc.ca/
US INTERNATIONAL TRADE COMMISSION
http://www.usitc.gov/
US Trade Representative
http://www.ustr.gov/
===================================================
"INOFFICIALS":
===================================================
============================================
WTO - MILLENNIUM ROUND - GLOBAL TRADE - MAI
============================================
(* frequently updated)
Adbusters: The big Question / en
http://www.adbusters.org/campaigns/economic/splash.html
American Lands / en
http://www.americanlands.org/forestweb/newwto1.htm
A SEED Europe / en *
http:// www.antenna.nl/aseed
Trade and Investment:
http://www.antenna.nl/aseed/trade/
ATTAC / en /fr *
http://attac.org/ang/
(in french): http://www.attac.org
ATTAC Brasil: http://www.attac.org/brasil/
Brian Jenkins anti-MAI page (Australia) / en *
http://www.nettrek.com.au/~brian/
"Citizens on the Web" / Toronto en *
http://www.interlog.com/~cjazz/action7b.htm
home: http://www.interlog.com/~cjazz/
Corporate Europe Observatory / Amsterdan en *
http://www.xs4all.nl/~ceo
WTO-special Issue:
http://www.xs4all.nl/~ceo/observer4/
Council of Canadians / en *
http://www.canadians.org/
Ej巖cito Zapatista de Liberaci梟 Nacional / es
http://www.ezln.org
Encontro Americano pela Humanidade e Contra o Neoliberalismo
http://www.encontroamericano.com.br/
"Infos zum MAI" / de
http://userpage.fu-berlin.de/~timor/mai/
"Millennium Round" (an URL of EP Green Party) / en *
http://www.millennium-round.org
"Model-WTO '99" (Oikos) / en (?)
http://www.stud.unisg.ch/~OIKOS/model-wto/
180 Movement for Democracy and Education / en
http://www.corporations.org/democracy/wto.html
home: http://www.corporations.org/democracy/
No2WTO Listarchive / en *
http://no2wto.listbot.com/cgi-bin/view_archive?Act=view_archive&list_id=no2wto
"MAI niet gezien" / Leiden nl *
www.stelling.nl/mai
Observatoire de la Mondialisation / Paris fr
http://www.ecoropa.org/ob
Ontario PIRG's MAI-not Project / Ottawa en *
http://mai.flora.org
Peoples Global Action (PGA) / en fr es de ru *
Acci梟 Global de los Pueblos/ Action mondiale des peuples AGP/AMP
http://www.agp.org
PGA in Seattle / en
http://members.aol.com/mwmorrill/pga.htm
List archive:
www.listbot.com/cgi-bin/view_archive?Act=view_archive&list_id=WTOSeattleDiscussion
People For Fair Trade / Seattle en
http://www.peopleforfairtrade.org
Polaris Institute (Canada) / en
http://www.nassist.com/mai/
Public Citizens Global Trade Watch / en *
http://www.tradewatch.org
List archive: http://lists.essential.org/mai-intl/
"Road To Seattle" (Newsletter) / en *
www.newsbulletin.org/bulletins/getcurrentbulletin.cfm?bulletin_id=67&sid=
Seattle Citizen Committee/ en
http://www.seattlewto.org
"SHUTDOWN SEA-TOWN" / Seattle en
http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/8771/nowto.html
Third World Network / en *
http://www.twnside.org.sg/souths/twn/trade.htm
WEED World Economy, Ecology & Development / de *
http://www.weedbonn.org
WEED on WTO: http://www.weedbonn.org/info/wto2000.htm
Germanwatch on WTO: / de
http://www.germanwatch.org/pubzeit/z29home.htm
==============================================================
some more
European Groups involved in the Stop Millennium Round Campaign
(without special WTO websites)
==============================================================
BUND (Friends of the Earth Germany) / de
http://www.snafu.de/~bund
or http://www.bund.net
Center for Environmental Public Advocacy (Slovakia) / sk
http://www.changenet.sk/cepa
Friends of the Earth Europe / en
http://www.foeeurope.org
Friends of the Earth Czech /cz
http://www.duhafoe.cz
Friends of the Earth UK / en
http:://www.foe.co.uk
Trade, Environment and Sustainability:
http://www.foe.co.uk/foei/tes
KEPA Finland / fi
http://www.kepa.fi
Movimiento contra la Europa de Maastricht / es
http://www.nodo50.org/maast
Oxfam Belgium / fr en
http://www.oxfamsol.be
World Development Movement (UK) / en
http://wwengineered alternative to the well-known biotech TNCw.wdm.org.uk/
=====================================
AGRIGULTURE FOOD - - GENETICS - TRIPs
=====================================
BUKO Agrar Koordination / de (?)
http://www.bukoagrar.de
Coordination paysanne europeenne - CPE / (fr)
http://www.confederationpaysanne.fr/cpe.htm
Confederation Paysanne France / (fr)
http://www.confederationpaysanne.fr/
Food First (USA) / en
http://www.foodfirst.org
Genetic Resources Action International (Spain) / en es fr
http://www.grain.org
Genetix Snowball (UK) / en
www.gn.apc.org/pmhp/gs
Global Forum on Sustainable Food and Nutritional Security (Brazil)
contact: agora@tba.com.br (URL ?)
Institute for Agriculture and Trade Policy (USA) / en (?)
http://www.iatp.org/
Inter Continental Caravan / en
http://http://stad.dsl.nl/~caravan/
MST (Brasil)
http://www.mst.org.br/
"Mutanto" - a genetically engineered alternative to the well-known biotech
TNC
http://freespace.virgin.net/david.curtin/nonsanto/nonsanto.htm
Rural Advancement Foundation Int'l
http://www.rafi.org
Via Campesina / (fr)
http://www.confederationpaysanne.fr/via.htm
=========
ANTI APEC
=========
Aotearoa/New Zealand APEC Monitoring Group / en
http://www.apec.gen.nz/
APEC Alert! Vancouver / en
http://www.cs.ubc.ca/spider/fuller/apec_alert/
No to APEC / en
http://www.trican.com/~rsantos/front.htm
=====================================
ENVIRONMENT - SUSTAINABLE DEVELOPMENT
=====================================
CIEL - Center for International Environmental Law / en
http://www.igc.apc.org/ciel/
CUTS - Centre for International Trade, Economics & Environment (India) /
en
http://www.cuts-india.org (under construction)
Eco-Action / en
http://www.eco-action.org/
Les 僣o-Guerriers (Earth First! France) / fr
http://wwwusers.imaginet.fr/~onafor/ecoguerrier.html
Earth First! Australia / en
http://www.green.net.au/ozef_update/
Earth First! UK / en
http://www.k2net.co.uk/ef/
Friends of the Eath international / en
http://www.foe.org
GroenFront! (Eart First! netherlands) / nl
http://groenfr.huizen.dds.nl/
International Center for Trade and Sustainable Development / en (?)
http://www.ictsd.org
International Institute for Sustainable Development / en (?)
http://iisd1.iisd.ca/
National Center for Sustainability / Vancouver en
http://www.islandnet.com/~ncfs/ncfs/
Raingow Keepers (Earth First! Russia)/ ru en
http://www.ecoline.ru/KOI/SEU/KOLLEKT/RK/INDEXE.HTM
Sacred Earth Network / ru en
http://www.igc.apc.org/sen/
russian: http://www.ecoline.ru/sen/
SEAC - Student Environmental Action Coalition / en
(an A SEED linked group in the US)
http://www.seac.org/
SURGE - Students United for a Responsible Global Environment
http://www.unc.edu/~dmarkato/surge.html
Transatlantic Environment Dialogue (TAED) (sponsored by TABD ???)
contact: taed@eeb.org (URL ?)
West Coast Environmental Law BC Canada / en
http://www.vcn.bc.ca/wcel/
Zeme predevsim! (Earth First! Prague) / cz
http://www.geocities.com/RainForest/Canopy/1651
http://www.ecn.cz/zemepredevsim
---------------------------------------------
CLIMATE
---------------------------------------------
"Climate Action Now"
http://www.imaja.com/change/environment/can/can.html
---------------------------------------------
FOREST
---------------------------------------------
Rainforest Action Network
http://www.ran.org/
--> see also "American Lands!"
---------------------------------------------
MINING - URANIUM
---------------------------------------------
Jabiluka (Australia)
http://www.jabiluka.net/
---------------------------------------------
OIL
---------------------------------------------
"Delta" (Nigeria) / en
http://www.oneworld.org/delta/
Oilwatch / es en
http://www.igc.apc.org/ecuanex/oilwatch/main.html
Project Underground / en
http://www.moles.org/ProjectUnderground/
==============================
HUMAN RIGHTS - RACISM - FACISM
==============================
CARF - Campaign against Racism and Facism UK/ en
http://www.carf.demon.co.uk/
CARF - Uniting against Globalisation
http://www.carf.demon.co.uk/global/
Colombia Support Network /
http://www.igc.apc.org/csn/
News Ahency New Colombia
http://home3.swipnet.se/anncol/
East Timor Action Network
http://www.etan.org/
East Timor Human Rights Centre
http://www.gn.apc.org/ethrc/
Human Rights/ de en
http://www.humanrights.de/
"The Hunger Site"
http://www.thehungersite.com/
UNPO - Unrepresented Nations and Peoples Organisation
http://www.unpo.org/
==================================================
INDIGENIOUS NETWORKS
(closed related to "environment" & "human rights")
==================================================
TAIGA ressource network / en
http://www.snf.se/TRN/
U'wa Project / en
http://www.solcommunications.com/uwa.html
=========
ANTI-WAR:
=========
AIM - Alternative Information Network in former Yugoslavia / en
http://www.aimpress.org/
Le Courrier des Balkans / fr
http://bok.net/balkans/
Global Network against Weapons and Nuclear Power in Space / en
http://www.globenet.free-online.co.uk/
Institute for War & Peace Reportung UK / en
http://www.iwpr.net/
Iraq Action Coalition / en
http://www.leb.net/iac/
Network for Peace in the Balkans UK/ en
http://www.BalkanPeaceNetwork.freeserve.co.uk/
Peace Action / en
http://www.peace-action.org/
Stop Cassini Earth Flyby / en
http://www.nonviolence.org/noflyby/
Transnational Foundation for Peace and Future Research / en
http://www.transnational.org
Trident Ploughshares 2000
http://www.gn.apc.org/tp2000/
War resister's international:
http://www.gn.apc.org/warresisters/
==========
OTHERS
==========
Alliance for Democraty (USA) / en
http://www.afd-online.org/
A SEED Japan / jp en
http://www.jca.ax.apc.org/~aseed/
C.A.D.T.M. (Belgium) / en fr es
http://users.skynet.be/cadtm/
Corporate Watch / en
http://www.corpwatch.org
Critical Mass Seattle / en
http://www.oz.net/~nic/cm.html
Critical Mass Tokyo
http://www.jca.ax.apc.org/~aseed/bicycle2.htm
Ending Corporate Governance / en
http://www.ratical.com/corporations/
EuroDusnie / Leiden nl en
http://stad.dsl.nl/%7Erobbel/
Eyfa - European Youth For(est) Action / en
http://antenna.nl/eyfa/
Food Not Bombs Seattle / en
http://www.scn.org/activism/foodnotbombs
Global Policy Forum NYC / en
http://www.globalpolicy.org/
http://www.globalpolicy.org/globaliz/
GASPP (GLOBALISM AND SOCIAL POLICY PROGRAMME) / en (?)
http://www.stakes.fi/gaspp/
Halifax Initiative (Canada) / en
http://www.sierraclub.ca/national/halifax/
IBON Foundation (Philippines) / en
http://www.ibon.org/
International Coalition for Development Action (Belgium) / en
http://www.icda.be
International Forum on Globalization / en
http://www.ifg.org
Institute for Global Communications (IGC)
http://www.igc.org/
June 18th international day of actions / en
http://www.j18.org
http://www.infoshop.org/june18.html
LabourNet Austria / de
http://ourworld.compuserve.com/homepages/LabourNetAustria/
Les Peripheriques vous parlent / Paris fr
www.globenet.org/periph
Multinational Corporations Human Rights / en (?)
(Erasmus University Project, Rotterdam)
http://www.multinationals.law.eur.nl/
PICIS Korea / jp en
http://www.jinbo.net/~picis/top_e.html
REAS - r巗eau de l'巆onomie alternative et solidaire / fr (?)
http://w1.neuronnexion.fr/~reas/
"Reclaim the Streets!" (rts) / en
http://www.gn.apc.org/rts
reclaim Madrid (June 18th) / es
http://www.nodo50.org/reclaim
rts New York City / en
http://reclaimthestreetsnyc.tao.ca/
rts Toronto / en
http://rts.toronto.tao.ca/
Socio-Ecological Union - SEU / ru
http://www.ecoline.ru/seu
SEU Newsletter:
http://www.igc.org/gadfly
TOES - The Other Economic Summit (USA) / en
http://pender.ee.upenn.edu/~rabii/toes/
Transnational Corporate Research / en
http://www.trufax.org/menu/resource.html
Transnational Institute / Amsterdam en
http://www.tni.org
Tusovka (Bulgaria) / ru en
http://www.savanne.ch/tusovka/en
WEED - World Economy, Ecology & Development / de en
http;//www.weedbonn.org
"50 Years are enough!" (IMF/ WB) / en
http://www.50years.org/
ZNet - A community of people concerned about social change
http://www.zmag.org/
============================
Organizations and Treaties - more ore less pushing Globalization
============================
----------------------------
FREE TRADE AREAS
----------------------------
APEC
http://www.apec.org
Secretariat
http://www.apecsec.org.sg/
ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)
http://www.asean.or.id/
FTAA (Free Trade Area of the Americans)
http://www.ftaa-alca.org/Alca_e.asp
MERCOSUR
http://www.americasnet.com/mauritz/mercosur/
WEF Santiago Summit, May 1999:
http://www.weforum.org/Activities/Regional/Mercosur/live99/
trade and investment report:
http://www.mercosurinvestment.com/
NAFTA Secretariat
http://www.nafta-sec-alena.org/
NAFTA-NET INT'L TRADE SITE
http://www.nafta.net/it.htm
SAFTA (South Asian Free Trade Agreement)
South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)
http://www.south-asia.com/saarc/
----------------------------
INDUSTRIAL LOBBY GROUPS
----------------------------
ERT (European Round Table of Industrialists)
http://www.ert.be/
ICC (International Chamber of Commerce)
http://www.iccwbo.org
Keidanren (Japan)
http://www.keidanren.or.jp/
UNICE (Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe)
without any URL (?); infos about at:
http://www.firewall.brainstorm.co.uk/CBI/public/UNICE.html
USCIB (US Council for International Business)
http://www.uscib.org/
Expo 2000:
http://www.expo2000.de/
----------------------------
FAO (Food and Agricultural Organization)
http://www.fao.org
IMF (International Monetary Fond)
http://www.imf.org
OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)
http://www.oecd.org
TABD (Trans-Atlantic Business Dialogue)
http://www.tabd.org
Trilateral Comission
http://www.trilateral.org/
UNCTAD (UN Conference on Trade and Development)
http://www.unicc.org/unctad/
WBCSD (World Business Council for Sustainable Development)
http://www.wbcsd.ch/
WEF (World Economic Forum)
http://www.weforum.org
World Bank
http://www.worldbank.org/
WORLD BANK/WTO TRADE AND DEVELOPMENT CENTER
http://www.itd.org/
----------------------------
----------------------------------------------------------
Tomoko Sakuma
People's Forum 2001, Japan
Maruko-bld. 3F 1-20-6 Higashi-ueno
Taito-ku, Tokyo 110-0015 Japan
TEL +81-3-3834-2436
FAX +81-3-3834-2406
Email : tsakuma@jca.apc.org or pf2001jp@jca.apc.org
Website: http://www.jca.apc.org/pf2001jp/
----------------------------------------------------------
To: wto@jca.apc.org
Subject: [wto 144] WTO 師婜岎徛 UPDATE
Date: Wed, 28 Jul 1999 17:11:24 +0900
From: Tomoko Sakuma <tsakuma@jca.apc.org>
WTO-ML偺奆偝傑丄
嶐擔丄偲偁傞夛崌偱巊偭偨儗僕儏儊偱偡丅WTO師婜岎徛偵娭偡傞7寧枛傑偱偺尰忬傪堦墳傑偲傔偰傒偨傕偺偱偡丅丂Just
For Your Information.
嵅媣娫
WTO師婜岎徛偵偮偄偰
1999.7.27
嵅媣娫抭巕乮巗柉僼僅乕儔儉2001乯
I. WTO師婜岎徛傪弰傞媍榑
仭岎徛曽朄丂亄丂挷報曽朄
仱屄暿暘栰岎徛乮暷崙偑庡挘乯亄丂憗婜廂妌曽幃乮屄暿岎徛偱惉棫偟偨暘栰偐傜師乆偵挷報偡傞曽幃乯
仱曪妵揑岎徛乮擔杮丄EU偑庡挘乯+丂堦妵庴戻曽幃乮曪妵揑岎徛偺寢壥傪堦妵偟偰挷報偡傞曽幃乯
仱嵦梡偝傟傞壜擻惈偑崅偄岎徛曽朄丟丂曪妵揑岎徛傪峴偄丄挷報偼嵟廔揑偵慡偰偺暘栰偺岎徛廔寢屻偵堦妵庴戻曽幃偱丅偟偐偟挷報慜偱傕崌堄偑惉棫偟偨暘栰偐傜巄掕揑偵幚巤偟偰偄偔丅岎徛婜娫偼栺3擭偱崌堄丅
仭娭惻堷偒壓偘偺曽幃
丂
仱僼僅乕儈儏儔曽幃丟慡偰偺崙偑奺崙偺偦傟偧傟偺尰峴娭惻棪偐傜堦掕妱崌傪堦棩嶍尭偡傞乮儌僲偺娭惻堷偒壓偘偱巊傢傟偨偑丄僒乕價僗岎徛偱傕偙偺曽幃傪梡偄傞偙偲傪暷偑採埬乯
仱僛儘丒僛儘乮Zero for Zero乯曽幃丟奺崙偑崌堄偱偒傞摿掕晹栧偵偮偄偰憡屳偵娭惻傪揚攑偡傞乮APEC偐傜帩偪墇偝傟偨ATL乮椦嶻暔丄悈嶻暔側偳9暘栰傗峼岺嬈惢昳暘栰乯偵揔梡丠乯
仱僞儕僼丒僺乕僋偺堦棩嶍尭丟奺暘栰偺嵟戝娭惻棪傪堷偒壓偘傞乮擾嬈暘栰丠乯
仱娭惻暘椶偺娙慺壔丟慡偰偺娭惻偵偮偄偰丄3偮偵暘椶偟丄偦傟偦傟偺暘椶偛偲偵娭惻棪傪堦棩壔乮EU採埬乯
仱僞儕僼丒僄僗僇儗乕僔儑儞偺揚攑丟尨椏傛傝傕壛岺昳偺曽偑崅偔側傞娭惻惂搙傪巭傔傞
仭岎徛懳徾暘栰
仱價儖僩僀儞丒傾僕僃儞僟乮僂儖僌傾僀丒儔僂儞僪岎徛偱2000擭偐傜偺岎徛嵞奐偑掕傔傜傟偰偄傞暘栰乯丗擾嬈乮AOA乯丄僒乕價僗乮GATS乯
仱僯儏乕丒僀僔儏乕乮堦晹愭恑崙偑怴偨偵岎徛偺懳徾偵偟傛偆偲偟偰偄傞暘栰丄懳徾偲偝傟傞偐偳偆偐偼枹掕乯丗惌晎挷払丄嫞憟惌嶔丄搳帒丄杅堈偲娐嫬丄杅堈偲楯摥
仱僔傾僩儖妕椈夛媍傑偱偵岎徛偑恑傔傜傟傞暘栰乮ATL丟Acceralated Tariff Liberalization乯丟椦嶻暔丒悈嶻暔側偳傪娷傓丄峼岺嬈惢昳乮儌僲偺暘栰乯偺娭惻揚攑岎徛丅妕椈夛媍偱偺挷報傪栚巜偡丅
仱掕婜揑儗價儏乕崁栚丗抦揑強桳尃乮TRIPs丟2000擭乯丄杅堈娭楢搳帒慬抲乮TRIMs丟1999擭乯
仭岎徛偺徟揰
仜僔傾僩儖妕椈夛媍傑偱偵岎徛偑恑傔傜傟傞暘栰
仱峼岺嬈惢昳乮偙偺暘栰偺娭惻棪偑掅偄擔杮偑愊嬌巔惃丅偨偩偟椦栰挕偼丄椦丒悈嶻暔偵偮偄偰偼峼岺嬈惢昳偺榞偐傜奜偟丄暿搑岎徛偡傞偙偲傪媮傔偰偄傞丅巻僷儖僾偼椦嶻暔偱偼側偔峼岺嬈惢昳偺埖偄偵側傞梊掕丠乯
仜價儖僩僀儞丒傾僕僃儞僟
仱擾嬈乮暷崙偺嵟戝偺壽戣丅EU偼曗彆嬥偺寴帩傪栚巜偡丅僶僫僫丄媿惉挿懀恑儂儖儌儞丄堚揱巕慻傒懼偊乮GMOs乯怘昳丄僟僀僆僉僔儞墭愼怘昳側偳丄暷乕EU娫偺懳棫偑偡偱偵寖壔偟偰偄傞暘栰乯
丂--杅堈帺桼壔乮暷崙丒働傾儞僘僌儖乕僾側偳乯丟桝弌曗彆嬥偺揚攑丒嶍尭丄悢検惂尷丒桝擖嬛巭傪娭惻妱摉乮Tariff
Rate Quotas)偵堏峴丄TRQs偺奼戝丄崙壠杅堈婇嬈偺揚攑丄娭惻堷偒壓偘丄巗応傾僋僙僗偺夵慞乮摿偵搑忋崙偐傜愭恑崙巗応偵懳偟偰乯丄摿暿僙乕僼僈乕僪偺揚攑
丂--怘昳埨慡惈丄擾嬈偺懡柺揑婡擻乮娐嫬乯丄怘椏埨慡曐忈乮EU丄擔杮丄僲儖僂僃乕丄儌乕儕僔儍僗丄僇儕僽彅崙側偳乯丟擏媿丒擕媿傊偺儂儖儌儞嵻搳梌偺栤戣丄GMO乮堚揱巕憖嶌乯怘昳偺庢傝埖偄乮SPS嫤掕亖僐乕僨僢僋僗埾堳夛怘昳婯奿乯丄娐嫬丒抧堟幮夛曐慡偺偨傔偺曗彆嬥偺堐帩乮僌儕乕儞丒儃僢僋僗偺堐帩丒奼戝乯丄摿暿僙乕僼僈乕僪偺堐帩
丂--搑忋崙傊偺摿暿偐偮嵎堎偺偁傞懸嬾乮Special and Differentiated Treatment ); 摿宐娭惻偺夵慞傑偨偼LDCs偐傜偺慡桝擖昳偵懳偡傞娭惻揚攑側偳丅
仱僒乕價僗乮EU丄暷崙偑愊嬌揑丅擔杮偼杊屼丠亖擾嬈帺桼壔偲僩儗乕僪丒僆僼偺娭學丅岞嫟僒乕價僗丄旕塩棙暘栰偑柉塩壔丄塩棙壔傪敆傜傟傞偙偲偑嵟戝偺栤戣乯
丂僄僱儖僊乕側偳岞嫟僒乕價僗暘栰丄揹婥捠怣暘栰丄曎岇巑丒夛寁巑丄昦堾丒夘岇丄棳捠側偳傊偺撪崙柉懸嬾丄崙嵺婎弨偺摫擖丄揹巕彜庢堷偵偮偄偰偼娭惻傪愝偗側偄偲偺巄掕崌堄傪堐帩乮暷丒EU乯
丂幚柋乮曎岇巑丒夛寁巑丒僐儞僺儏乕僞娭楢丒尋媶奐敪丒晄摦嶻丒儗儞僞儖乛儕乕僗乯丄捠怣乮梄曋丒攝払丒揹婥捠怣丒僆乕僨傿僆價僕儏傾儖乯丄寶愝娭楢乮價儖丒搚栘丒愝抲乛慻棫丒巇忋偘乯丄棳捠乮栤壆丒壍丒彫攧丒僼儔儞僠儍僀僘乯丄嫵堢乮弶拞崅摍丒惗奤乯丄娐嫬乮墭悈張棟丒攑婞暔張棟丒岞廜塹惗乯丄嬥梈乮曐尟丒嬧峴丒徹寯乯丄寬峃娭楢乮昦堾丒夘岇乯丄娤岝丒椃峴乮儂僥儖丒儗僗僩儔儞丒椃峴戙棟揦丒椃峴僈僀僪乯丄儗僋儕僄乕僔儑儞丒暥壔丒僗億乕僣乮屸妝丒曬摴丒恾彂娰丒攷暔娰丒僗億乕僣乯丄塣桝乮奜峲奀塣丒撪棨悈塣丒峲嬻丒塅拡桝憲丒揝摴丒摴楬桝憲丒僷僀僾儔僀儞乯丄峀崘丄揹巕彜庢堷側偳丄寁160嬈庬
仜僯儏乕僀僔儏乕
仱惌晎挷払乮暷崙偼11寧偺妕椈夛媍傑偱偵摟柧惈側偳偵娭偡傞尨懃傪岎徛丄妕椈夛媍偱偺挷報傪栚巜偟偰偄傞偑...乯
丂忣曬偺摟柧壔丄崙丒帺帯懱丒巗挰懞側偳偁傜備傞儗儀儖偺惌晎挷払偵懳偟偰撪奜柍嵎暿傪揙掙乮摿偵搑忋崙乯
仱嫞憟惌嶔乮暷崙偺斀僟儞僺儞僌棎敪傪巭傔偝偣偨偄EU丄擔杮丅偟偨偑偭偰暷崙偼偙偺僀僔儏乕偵徚嬌揑丅搑忋崙偵傛傞崙撪嫞憟惌嶔偺惍旛傪巟墖偡傞偙偲偑媍戣偲側傞丠乯
丂撈愯嬛巭朄側偳偺嫞憟惌嶔偑偄傑偩惍旛偝傟偰偄側偄崙偱偺嫞憟惌嶔偺惍旛媊柋偯偗丄搑忋崙偺惂尷揑儖乕儖乮僷僼僅乕儅儞僗梫媮側偳乯偺揚攑丄嬈奅抍懱側偳偵傛傞惂尷揑彜姷峴偺揚攑丄奜崙婇嬈偺崙撪巗応偱堦掕偺儅乕働僢僩傾僋僙僗妋曐
仱搳帒乮EU丄擔杮偼慜岦偒丅暷崙偼崙撪乮媍夛乯偐傜偺斸敾傪嫲傟偰徚嬌揑丅僀儞僪丒僷僉僗僞儞偼斀敪乯
丂WTO偱岎徛偝傟傞偲偟偰傕丄OECD偱偲傫嵙偟偨MAI偲偼堘偭偨傾僾儘乕僠乮儃僩儉丒傾僢僾曽幃亖奺崙偑帺桼壔偱偒傞暘栰傪帺屓怽惪偟偰岎徛偡傞傗傝曽乯傪庢傞偙偲偼傎傏娫堘偄側偟丅偙偺曽幃傪嵦梡偡傞偺偱偁傟偽丄怴偨偵搳帒嫤掕傪嶌傜側偔偰傕丄TRIM偲GATS偺嵞岎徛偵傛偭偰傕摨條偺岠壥偑摼傜傟傞丅暷崙偼屻幰傪婓朷丅
仱娐嫬偲杅堈乮EU慜岦偒丅暷惌晎偼徚嬌揑偩偑暷媍夛偼慜岦偒丠僀儞僪埲壓傎偲傫偳偺搑忋崙偼乽婾憰偝傟偨曐岇庡媊乿偵巊傢傟傞偲斀敪乯
丂懡崙娫娐嫬嫤掕偺杅堈惂尷慬抲傪WTO儖乕儖偵埵抲偯偗傞偙偲丄僄僐儔儀儖側偳偺PPMs偵婎偯偔慬抲傪梕擣偝偣傞偙偲丄娐嫬丒怘偺埨慡偵偮偄偰偼乽梊杊尨懃乿偵懃傞偙偲側偳丅
仱娐嫬偲楯摥乮EU慜岦偒丅暷惌晎偼帣摱楯摥偲杅堈惂嵸偺儕儞僋傪峫埬拞丠乯
丂乽婾憰偝傟偨曐岇庡媊乿偲偺搑忋崙偺斀敪傪旔偗傞偨傔乽婎杮揑楯摥婎弨偺弲庣乿偵偼僾儔僗偺僀儞僙儞僥傿僽傪梌偊傞偲偄偆懪奐嶔偑EU偐傜採埬偝傟偰偄傞丅
仱偦偺懠丄杅堈偺墌妸壔乮杅堈庤懕偒偺娙慺壔乯丄暣憟夝寛庤懕偒偺儗價儏乕側偳
II.丂嵟嬤偺僩儗儞僪
仭搑忋崙傗NGO偐傜偺斸敾傪堄幆偟偨怴偨側庢傝慻傒乮奐敪丒娐嫬傊偺攝椂丄摟柧惈丒NGO嶲壛乯
丂--杅堈偲奐敪埾堳夛乮CTD乯丄杅堈偲娐嫬埾堳夛乮CTE乯側偳偱偺媍榑乮1995擭乣乯
丂--奐敪偍傛傃娐嫬偵娭偡傞僴僀儗儀儖丒僔儞億僕僂儉偺奐嵜
丂--1996擭12寧偺僔儞僈億乕儖妕椈夛媍傛傝NGO偺僆僽僓乕僶嶲壛梕擣
丂--NGO偲偺旕岞幃嫤媍偑憹壛乮WTO丄奺崙乯
丂--EU偑儈儗僯傾儉丒儔僂儞僪偺乽帩懕壜擻側奐敪傊偺塭嬁昡壙乿傪奜晹偵埾戸
仭奐敪丄娐嫬偺媍榑傪媡庤偵庢偭偨愭恑崙偺愴棯
丂乕NGO偐傜偺忣曬廂廤乮僸傾儕儞僌乯偺妶敪壔(暷崙丄EU丄擔杮乯
丂乕巗柉嶲壛偺懀恑偵傛傝丄帺崙偺婇嬈傗娐嫬NGO傪暣憟夝寛偱妶梡偟傛偆偲偟偰偄傞暷崙
丂乕搑忋崙偺偨傔傪憰偭偨乽巗応傾僋僙僗乿媍榑偲丄娐嫬偺偨傔傪憰偭偨乽曐岇庡媊乿偺暪懚
仭尰嵼弌偝傟偰偄傞娭楢偺採埬丟
丂--屻敪奐敪搑忋崙乮LDCs乯偐傜偺桝弌昳偵懳偟丄2003擭傑偱偵愭恑崙偑娭惻傪揚攑乮EU採埬乯
丂--搑忋崙偵懳偡傞WTO朄棩巟墖僙儞僞乕偺愝棫乮僶儞僌儔僨傿僢僔儏丄僐儘儞價傾丄崄峘丄僆儔儞僟丄僲儖僂僃乕丄僼傿儕僺儞丄撿傾僼儕僇丄僞儞僓僯傾丄僠儏僯僕傾丄僩儖僐丄僀僊儕僗乯
丂--惗嶻僾儘僙僗庤抜乮PPM乯偵婎偯偔僄僐儔儀儖傪梕擣偝偣傞乮EU乯
丂--杅堈儖乕儖偵偍偗傞乽梊杊尨懃乮Precautionary Principle乯乿偺妋棫乮EU乯
丂--婎杮揑楯摥婎弨偺弲庣偵懳偡傞杅堈柺偱偺乮惂嵸偱偼側偔乯僀儞僙儞僥傿僽傪愝偗傞乮EU乯
丂--僟儞僺儞僌棪偑2亾埲壓傪斀僟儞僺儞僌擣掕偺懳徾偐傜偼偢偟偰偄傞偑丄偙傟傪搑忋崙偵懳偟偰偼5亾傑偱懳徾奜偲偡傞丅傑偨丄僟儞僺儞僌偝傟偨桝擖昳偑憤桝擖偺3亾埲壓偺応崌傕懳徾奜偲偟偰偄傞偑丄偙傟偵偮偄偰傕搑忋崙偵懳偟偰偼5亾傑偱懳徾奜偲偡傞乮僀儞僪採埬乯
丂--愭恑崙偺僞儕僼丒僺乕僋乮嵟戝娭惻棪乯傪擾嬈丄慇堐丄堖椏丄旂妚惢昳側偳搑忋崙偑斾妑桪埵傪桳偡傞暘栰偵偍偄偰尰峴偺350亾偐傜堷偒壓偘傞乮墷廈媍夛乯側偳
III. NGO偺庡挘丒採埬
仭抧媴娐嫬栤戣偺夝寛嶔偲崙嵺宱嵪儖乕儖偺柕弬
丂--丂懡崙娫娐嫬嫤掕乮MEAs乯偑枹敪払側拞偱偺媫懍側宱嵪偺僌儘乕僶儖壔乮杅堈丒搳帒儖乕儖偺帺桼壔丄柍婯棩側帒杮堏摦偺憹戝乯
仛巗応宱嵪偵偼娐嫬丒幮夛惌嶔偑敽傢傟偹偽側傜側偄仛
仭崙撪惌嶔偲崙嵺宱嵪儖乕儖偺柕弬
丂--丂撪奜柍嵎暿尨懃偑弞娐宆宱嵪乮帒尮偺抧堟弞娐乯傗丄抧堟幮夛宱嵪妶惈壔偺偨傔偺惌嶔傪慾奞
乮搑忋崙偺敪揥傕慾奞乯
丂--丂壢妛揑崻嫆偺捛媮偑乽梊杊尨懃乿偍傛傃崙柉庡尃乮崙柉偺朷傓惌嶔偺幚巤乯偲柕弬
丂--丂娐嫬曐慡傗楯摥幰曐岇傪憰偭偨杒偺乽曐岇庡媊乿偵搑忋崙偑斀敪乮堦曽揑杅堈慬抲乯
丂--丂撿傪憰偭偨懡崙愋婇嬈偵傛傞乽巗応傾僋僙僗乿梫媮偑奺崙偺娐嫬丒屬梡惌嶔偵媦傏偡埆塭嬁
丂--丂惗暔摿嫋偺妋棫偲抦揑強桳尃偺揔梡婜娫偺墑挿偵傛傞峴偒夁偓偨摿嫋曐岇乮帺桼壔偵媡峴丠乯偑婇嬈偵傛傞庬昪傗壢妛媄弍偺撈愯傪彽偔
仭宱嵪偺僌儘乕僶儖壔傗丄偦偺寢壥偱偁傞嬥梈丒宱嵪晄埨偐傜惗偢傞娐嫬栤戣
丂--丂桝弌偺偨傔偺揤慠帒尮偺廂扗寖壔丄擾栻懡搳丄戝婯柾娏燆側偳偵棅傞旕帩懕宆擾嬈丒梴怋偺奼戝
丂--丂怷椦偺弅彫傗怉椦偵傛傞強桳尃偺曄壔側偳偵傛傞丄揱摑揑從偒敤擾嬈偺帩懕晄壜擻壔
丂丂--仺丂寢壥偲偟偰偺嵐敊壔丄搚忞楎壔丒棳弌丄増娸晹偺楎壔丄惗暔懡條惈偺徚幐
丂--丂撿杒奿嵎丄崙撪奿嵎偺奼戝
丂 丂--仺丂搒巗壔偲僗儔儉壔丅怘椏暘攝偺栤戣丄塹惗丄攑婞暔丄岞奞側偳
丂--丂庬巕傗惗栻側偳偺惗暔帒尮偺攔懠揑撈愯尃偑妋棫偝傟傞偙偲偵傛傞丄擾嬈惗暔懡條惈偺憆幐丄堚揱巕慻傒懼偊惗暔偺奼嶶丄彫婯柾擾壠偺宱塩埑敆丂仛怘椏偲悈偺妋曐丒暘攝偺栤戣丄娐嫬丒塹惗偺栤戣仛
仭惌嶔偺僌儘乕僶儖壔偵敽偆栤戣
丂--丂堄巚寛掕偺応偑墦戅偔偙偲偑恖乆傪柍婥椡丄柍娭怱偵偟偰偄傞栤戣乮暘尃偵柕弬丠乯
丂--丂暋嶨惈偑憹偡偙偲偵傛傝丄愱栧壠偩偗偺媍榑偵偝傟偰偟傑偆栤戣乮廧柉嶲壛丒忣曬岞奐偵柕弬丠乯
丂--丂晛曊惈偑捛媮偝傟傞偙偲偱丄暥壔丄壙抣娤丄惗暔偺懡條惈偑娕夁偝傟偑偪偱偁傞栤戣乮儅僀僲儕丂僥傿偺尃棙偵柕弬丠乯
丂--丂崙嵺儗儀儖偱嶰尃暘棫偑幚尰偟偰偄側偄栤戣乮柉庡庡媊偵柕弬丠乯
丂仛僌儘乕僶儖壔偼丄忣曬丒帒尮丒擻椡偺廤拞偡傞崙壠傗僙僋僞乕偵傛傞乽憖嶌乿傪梕堈偵偡傞仛
仭壽戣惍棟
丂--丂仛Welfare State乮暉巸崙壠亖崙柉崙壠乯偐傜Welcome State乮桿抳崙壠亖婇嬈崙壠乯傊偺曄幙仛
乮崙壠傗帺帯懱偺岞揑婡擻乮惻惂亖強摼偺嵞暘攝丄婯惂亖娐嫬丒幮夛婯惂丄庛幰媬嵪側偳乯偑斲掕偝傟傞堦曽丄崙嵺儗儀儖偱偙偺婡擻偑戙懼偝傟傞傛偆偵偼側偭偰偒偰偄側偄乯--仺僒乕價僗杅堈帺桼壔偵傛傝偙傟傜岞嫟僒乕價僗偍傛傃旕塩棙帠嬈偑柉塩壔丒塩棙壔偝傟傞婋尟惈乯
丂--丂仛偁傜備傞崙撪惌嶔偺崙嵺惍崌壔乮僴乕儌僫僀僛乕僔儑儞乯偵傛傞暥壔丒惗懺宯偺懡條惈偺憆幐仛乮惗懺宯偛偲偵堎側傞娐嫬曐慡惌嶔傪嵦戰偡傞偙偲丄廧柉偺朷傓敪揥僷僞乕儞傪慖戰偡傞偙偲丄廧柉偺壙抣娤傪朄惂搙偵斀塮偡傞偙偲側偳傪慾奞乯
仭昁梫偲偝傟傞巤嶔
丂--丂抁婜帒杮堏摦偺梷惂乮崙嵺婯惂丒惻惂乯偲帩懕壜擻側幚懱宱嵪傊偺帒嬥娐棳丄娐嫬曐慡傊偺桿場
丂--丂懡崙愋婇嬈峴摦婯惂
丂--丂崙嵺惻惂丒崙嵺嫞憟朄丒崙嵺娐嫬朄偺惍旛丄廩幚
丂--丂崙壠丄抧堟偺庡尃偺妋擣
仭嬶懱揑側曽朄
丂--丂仛巗柉丒NGO側偳丄旕惌晎丒旕塩棙僙僋僞乕偵傛傞憡屳偺岎棳丄嫤椡丄楢実仛傪捠偠丄怣棅忴惉丄柉庡壔丄娐嫬曐慡丄奐敪惌嶔側偳偵娭偡傞悈暯揑側崙嵺嫤椡傪柾嶕
丂--丂堦斒巗柉丄抧堟廧柉偵懳偡傞仛忣曬岞奐傪挻偊偨乽愊嬌揑峀曬乿仛偵傛傝丄岞揑婡擻傊偺棟夝傪懀恑
仭WTO偵偮偄偰偺採埬
仜WTO惂搙堦斒偵偮偄偰
1.丂WTO偺僐儞僙儞僒僗曽幃偼婡擻偟偰偄側偄丅偄偔偮偐偺慜採忦審傪晅偗偨忋偱乽搳昜曽幃乮棟憐揑偵偼柍婰柤搳昜乯乿傪嵦梡偡傞丅
2.丂偨偡偒偑偗惂嵸偼攑巭偡傞丅僱僈僥傿僽丒僐儞僙儞僒僗曽幃傕攑巭偡傞丅
3.丂搑忋崙偑書偊傞嵟戝偺栤戣偼丄崙嵺岎徛偵懳墳偱偒傞帒嬥丒抦幆丒恖嵽偑埑搢揑偵晄懌偟偰偄傞偙偲偱偁傞丅栺懇偝傟偰偄傞帒嬥丒媄弍巟墖傪懍傗偐偵幚巤偡傞偲嫟偵丄暣憟夝寛僔僗僥儉傪棙梡偱偒傞傛偆偵巟墖偡傞丅乮仺WTO朄棩巟墖僙儞僞乕愝棫採埬乯
4.丂乽巗応傾僋僙僗偺岦忋乿偼寢壥庡媊偺娗棟杅堈偱偁傞偨傔丄慜採偲偟側偄丅偨偩偟丄屻敪搑忋崙側偳偐傜偺桝弌昳偵偮偄偰偼暿搑桪嬾慬抲傪島偠傞乮GSP偼娭惻棪偑尙暲傒掅壓偡傞拞丄廫暘婡擻偟側偔側偭偰偄傞偙偲偵攝椂偡傞乯丅乮仺2003擭傑偱偵LDCs偐傜偺桝擖偵懳偟愭恑崙偺娭惻傪揚攑偡傞採埬乯
5.丂乽帺桼乿偱偼側偔乽岞惓乿偲乽帩懕壜擻惈乿傪杅堈儖乕儖偺尨懃偲偡傞丅偦偺偨傔偵昁梫側崙嫬慬抲傪堐帩丒嵞峔抸偟偰偔偙偲傪梕擣偝偣傞乮僗僞儞僪丒僗僥傿儖丄儘乕儖僶僢僋椉忦崁偺攑巭乯丅
6.丂娐嫬丒怘椏埨慡曐忈側偳偺尨懃傪妋棫偡傞丅偨偩偟丄搑忋崙偵懳偟偰偼嵎堎偺偁傞慬抲傪島偠傞丅
7.丂暣憟僷僱儖傊偺巗柉嶲壛乮暷崙偑庡挘乯偼丄愭恑崙婇嬈偺僷僱儖夘擖傪壜擻偲偡傞偨傔丄慜採忦審傪尩偟偔偡傞側偳偺攝椂偑昁梫丅
8.丂娐嫬曐慡傗楯摥幰曐岇側偳偺栚揑偱偁偭偰傕丄堦曽揑側杅堈惂嵸偼堦愗擣傔側偄丅MEAs偵傛傞杅堈慬抲偼MEAs偺儐僯僶乕僒儕僥傿側偳偵偮偄偰偺忦審晅偒偱梕擣偟偰偄偔丅乮懡崙娫庡媊偺堐帩乯
仜師婜岎徛偵偮偄偰
9.丂師婜岎徛偱偼乽偝傜側傞帺桼壔乿偱偼側偔丄僂儖僌傾僀丒儔僂儞僪崌堄乮WTO嫤掕乯偑幮夛丒宱嵪丒娐嫬丒奐敪偵梌偊偨塭嬁偺昡壙儗價儏乕傪傑偢峴偆偙偲偑昁梫偱偁傞丅偦偺寢壥偵廬偄丄WTO嫤掕偺夵掶嶌嬈偵擖傞偙偲偑偱偒傞丅
10.丂搳帒丄僒乕價僗丄惌晎挷払丄嫞憟惌嶔側偳偺暘栰偵偮偄偰偼丄廫暘側棟夝偲尰忬擣幆偑懚嵼偣偢丄摿偵搳帒丒僒乕價僗偵偮偄偰偼媫惉挿暘栰偱偁傞偨傔偵尒捠偟偑晄摟柧偱偁傞丅傑偨丄岞嫟僒乕價僗傗旕塩棙僒乕價僗帠嬈側偳丄塩棙壔偵偼側偠傑側偄暘栰傕娷傑傟偰偄傞偨傔丄偙傟傜岞嫟丒旕塩棙僒乕價僗偺暘栰偺岎徛偵偼墳偠側偄丅搳帒丄惌晎挷払丄嫞憟惌嶔偵偮偄偰傕岎徛奐巒傛傝傕慜偵丄奐偐傟偨媍榑偺愊傒廳偹偑晄壜寚偱偁傞丅
10.丂擾嬈曗彆嬥偺椺奜偲偟偰乽怘椏埨慡曐忈儃僢僋僗乿傪怴愝丄壙奿巟帩傗旛拁惌嶔側偳傪梕擣偝偣傞丅怘椏桝擖崙偺桝擖昳栚偺崙撪惗嶻偺彠椼丄帺崙撪徚旓偺偨傔偺娐嫬曐慡宆擾嬈偺彠椼傪捈愙強摼曐忈偺忦審偲偡傞偙偲丅乮搑忋崙偐傜偼乽奐敪儃僢僋僗乿偑採埬偝傟偰偍傝丄怘椏桝弌崙偲桝擖崙偺嬫暿偲偄偆峫偊曽偼堦斒壔偟偰偄側偄丅堦曽乽懡柺揑婡擻乿偼EU偺桝弌曗彆嬥傪庣傞偨傔偺鎘曎偩偲偟偰搑忋崙偐傜晄昡傪攦偭偰偄傞丅乯
11.丂惌晎曗彆嬥偑巟媼偱偒側偄弮怘椏桝擖搑忋崙傪懳徾偵丄WTO埲奜偺僼僅乕儔儉偱乽彫婯柾擾柉曐岇婎嬥乿傪憂愝丄愭恑崙偺擾嬈曗彆嬥偺堦掕妱崌傪嫆弌偡傞丅
To: wto@jca.apc.org
Subject: [wto 143] WTO 娭楢忣曬丂 6寧丂 Vol.2
Date: Tue, 27 Jul 1999 19:01:47 +0900
From: Tomoko Sakuma <tsakuma@jca.apc.org>
WTO娭楢忣曬丂6寧丂Vol.2
栚師丗
仭WTO怴儔僂儞僪偵娭偡傞妕椈媺夛媍偑僽僟儁僗僩偱奐偐傟傞
仭 暷惌晎僸傾儕儞僌丟僼儘儕僟偺擾壠偑帺桼壔偵斀敪丅儈僱僜僞偺擾嬈抍懱偼GMO栤戣偲堦師嶻昳壙奿掅柪偵寽擮傪昞柧
仭 僔儔僋暓戝摑椞偑儊儖僐僗乕儖乮撿晹撿暷嫟摨巗応乯丄僠儕偲EU偺杅堈宱嵪嫤椡嫤掕偺岎徛偵僗僩僢僾
仭 WTO堦斒棟帠夛偺夛崌偵僀儞僪惌晎偑WTO師婜岎徛偵岦偗偨採埬傪採弌
仭娯崙偑WTO偺搳帒儖乕儖偵拲暥
仭WTO怴儔僂儞僪偵娭偡傞妕椈媺夛媍偑僽僟儁僗僩偱奐偐傟傞
丂5寧28擔丄僽僟儁僗僩偱WTO怴儔僂儞僪偵娭偡傞妕椈媺夛媍偑奐偐傟偨丅嶲壛偟偨偺偼18僇崙乮傾儖僛儞僠儞丄僆乕僗僩儔儕傾丄僽儔僕儖丄僇僫僟丄僠儕丄僐僗僞儕僇丄僠僃僐丄僴儞僈儕乕丄僀儞僪丄擔杮丄娯崙丄儊僉僔僐丄儌儘僢僐丄僯儏乕僕乕儔儞僪丄僔儞僈億乕儖丄僗僀僗丄僞僀丄暷崙乯偲崄峘偍傛傃EU偱偁傞丅妕椈傜偼丄尰嵼WTO偵壛柨怽惪傪峴偭偰偄傞崙乆偑師婜岎徛奐巒傑偱偵WTO偵壛柨偱偒傞傛偆搘椡偡傞偙偲偱堦抳偟偨丅師夞夛崌偼10寧偵僗僀僗偱奐嵜偝傟傞丅
丂嶲壛偟偨妕椈偺傎偲傫偳偑丄宱嵪敪揥儗儀儖偺堘偆慡偰偺壛柨崙偺娭怱偑斀塮偝傟傞傛偆丄峀斖偐偮僶儔儞僗偺偲傟偨師婜岎徛傪栚巜偡偙偲偵巟帩丄偦偆偱側偄尷傝價儖僩僀儞丒傾僕僃儞僟乮擾嬈丒僒乕價僗乯偵偍偄偰傕戝暆側帺桼壔偼払惉偱偒側偄偲偟偨丅偟偐偟堦晹偺崙偐傜偼丄婛懚偺WTO嫤掕偺幚巤偵崲擄傪棃偟偰偄傞崙乆偵攝椂偟丄岎徛斖埻傪峀偘偡偓側偄傛偆拲暥偑弌偝傟偨丅
丂 傑偨丄搑忋崙丄摿偵屻敪奐敪搑忋崙偺娭怱傊偺攝椂傪桪愭偡傞偙偲丄偍傛傃偦偺嬶懱嶔傪専摙偡傞偙偲偵崌堄偑宍惉偝傟偨丅WTO嫤掕偵崌傢偣偨崙撪朄偺夵掕丄恖嵽傗僀儞僼儔柺偱偺崙嵺嫤椡傗丄杅堈娭楢偺媄弍巟墖嶔側偳偱偁傞丅
丂師婜岎徛偺拞恎偵偮偄偰偼丄價儖僩僀儞傾僕僃儞僟埲奜偺岎徛壽戣偲偟偰丄峼岺嬈惢昳乮儌僲偺杅堈乯偺娭惻堷偒壓偘傪庢傝忋偘傞偙偲偑傎傏崌堄偝傟偨丅偦偺懠偵搳帒傗嫞憟惌嶔丄杅堈庤懕偒偺娙慺壔側偳偑嫇偑偭偨偑丄崌堄偵偼帄傜側偐偭偨丅
丂傎偲傫偳偺妕椈偑岎徛曽幃偵偮偄偰乽堦妵彸擣丒庴戻乿宍幃偲3擭娫偺岎徛婜尷傪巟帩丄師婜岎徛偺奣梫傪掕傔傞乽僔傾僩儖妕椈愰尵乿偼夝庍偺僘儗偑惗傑傟側偄傛偆丄柧妋偐偮娙寜側暥彂偲偡傋偒偩偲庡挘偟偨丅僔傾僩儖偱偼丄暣憟夝寛偵娭偡傞椆夝偵偮偄偰偺嵞岎徛偺寢壥傗丄屻敪奐敪搑忋崙偺奜崙巗応傊偺傾僋僙僗偺夵慞嶔側偳丄徻嵶側寛掕帠崁偵偮偄偰暿搑暥彂傪嶌惉偡傞偙偲傕傎傏崌堄偝傟偨丅
丂妕椈偺懡偔偼丄巗柉幮夛偺棟夝傪懀恑偡傞偨傔偵WTO偺摟柧惈傪岦忋偡傞偙偲丄巗柉幮夛偲偺懳榖傪懀恑偡傞偙偲傪巟帩偟偨丅
丂
彺栿丗Friends of the New Round Declaration, June, 4 1999, Inside US Trade
仭暷惌晎僸傾儕儞僌丟僼儘儕僟偺擾壠偑帺桼壔偵斀敪丅儈僱僜僞偺擾嬈抍懱偼GMO栤戣偲堦師嶻昳壙奿掅柪偵寽擮傪昞柧
丂 擾嬈偑娤岝偵師偖庡梫嶻嬈偱偁傞僼儘儕僟廈偱暷擾柋徣乮USDA乯偲暷捠彜戙昞乮USTR乯偑WTO師婜岎徛偵娭偡傞僸傾儕儞僌傪奐嵜偟偨丅嶲壛偟偨擾壠偺傎偲傫偳偑乽擾嬈杅堈偺帺桼壔乿偵斲掕揑側尒夝傪昞柧丄暷巗応岦偗偵桝弌傪峴偭偰偄傞奜崙偺娐嫬丒楯摥婎弨偺掅偝傗丄嬥梈婋婡偵傛傞捠壿愗傝壓偘偵傛傝丄偝傜偵埨壙偲側偭偨桝擖怘椏偲嫞憟偱偒偢偵暷擾壠偑懝奞傪旐偭偰偄傞帠懺偑柧傜偐偵偝傟偨丅
丂 偐傫偒偮椶偺惗嶻僐僗僩偼1億儞僪偁偨傝僽儔僕儖偱偼48僙儞僩側偺偵懳偟丄僼儘儕僟偱偼76僙儞僩偱偁傞偑丄偦偺棟桼偼暷崙偑尩偟偄楯摥丒娐嫬婎弨傪嵦梡偟偰偄傞偨傔偱偁傞偲偄偆丅偦偺偨傔丄EU傗暷崙偺擾壠偼丄擾嬈杅堈傪帺桼壔偡傞嵺偵偼EU傗暷崙偺楯摥丒娐嫬婎弨偲摨摍偺婎弨傪懠崙傕嵦梡偡傞偙偲偑忦審偲偝傟傞傋偒偩偲峫偊偰偄傞丅
丂 11,500擾壠傪戙昞偡傞僼儘儕僟偐傫偒偮椶憡屳夛幮偺戙昞偼丄僽儔僕儖嶻偺偐傫偒偮椶偺99亾偑桝弌梡偱偁傞堦曽丄暷崙嶻偱桝弌偝傟偰偄傞偺偼慡懱偺10亾偵夁偓側偄偲偟偰丄僽儔僕儖偐傜偺偐傫偒偮椶桝擖偵懳偡傞娭惻堷偒壓偘偼乽帺嶦峴堊乿偩偲庡挘偟偨丅
丂 僺乕僫僣惗嶻幰傜偐傜偼丄NAFTA乮杒暷帺桼杅堈嫤掕乯傗GATT偑惉棫偟偰傕暷崙偐傜偺僺乕僫僢僣桝弌偼憹壛偟偰偄側偄偲偟偰丄帺桼壔偦偺傕偺偵懳偡傞媈栤偑掓偝傟偨丅
丂 堦曽丄僩僂儌儘僐僔惗嶻幰傗戝敒儌儖僩惗嶻幰傜偑嶲壛偟偨儈僱僜僞廈偱偺僸傾儕儞僌偱偼丄掅柪偡傞堦師嶻昳壙奿偲丄奀奜偐傜斀敪偑嫮傑偭偰偄傞堚揱巕慻傒懼偊(GMO)嶌暔偺栤戣偵堄尒偑廤拞偟偨丅傑偨丄丄EU偑暷僶僫僫夛幮偵傛傞拞撿暷彅崙偐傜偺僶僫僫桝弌傪婯惂偟偰偒偨審偵偮偄偰暷崙偑WTO偵採慽丄彑慽偟偨審偵偮偄偰傕丄抧尦NGO偐傜偼丄暷崙撪偱嬛巭偝傟偰偄傞壔妛昳傪巊梡偟偰惗嶻偝傟偨僶僫僫傪EU偑桝擖偟側偄偺偼摉慠偱偁傞偲偺尩偟偄堄尒偑弌偝傟偨丅
丂 偁傞僒僂僗僟僐僞廈媍堳偼丄WTO妕椈夛媍偺暷惌晎戙昞偵丄扤偵懳偟偰傕愑擟傪晧傢側偄懡崙愋庬昪丒擾壔妛婇嬈偺戙昞偱偼側偔丄慡暷擾嬈幰楢崌乮National
Farmers Union乯偺戙昞傪擖傟傞傛偆梫惪偟偨丅
丂偙傟偵懳偟偰USDA懁偼丄WTO妕椈夛媍偱偼擾嬈暘栰偺嵞曇惉傗掅柪偡傞堦師嶻昳壙奿丄GMO昞帵側偳偵偮偄偰偼榖偟崌傢傟側偄偩傠偆偲曉摎偟丄WTO嫤掕偺撪梕愢柧偵廔巒偟偨丅
嶲峫丗USTR,USDA hear concerns on trade talks, US agenda alarms Florida farmers,
By Kevin G. Hall, Journal of Commerce, June 8,1999
The fires burn in Europe; Taking stock of US policy in the World Trade Organization,
By Steve Sprinkel, An ACRES, USA, Special Edition, June 7, 1999
仭僔儔僋暓戝摑椞偑儊儖僐僗乕儖乮撿晹撿暷嫟摨巗応乯丄僠儕偲EU偺杅堈宱嵪嫤椡嫤掕偺岎徛偵僗僩僢僾
丂 6寧4擔偵働儖儞偱奐偐傟偨EU僒儈僢僩偱丄僔儔僋暓戝摑椞偼2000擭12寧傑偱偺奐巒偱崌堄偝傟偰偄傞撿暷5僇崙偲偺杅堈丒宱嵪嫤椡嫤掕偺岎徛偵斀懳傪昞柧丄僒儈僢僩偺嫟摨惡柧偐傜撍擛丄偙偺審偵娭偡傞暥尵偑嶍彍偝傟偨丅偙偺嫤掕偵偮偄偰偼6寧28擔丄29擔偵儕僆僕儍僱僀儘偱奐偐傟傞墷廈丒撿暷夛媍偵戝偒側塭傪棊偲偡偙偲偵側傞丅偙偺儕僆丒僒儈僢僩偼僔儔僋巵帺恎偑採埬偟偨傕偺偱偁傞丅僔儔僋戝摑椞偼丄WTO師婜岎徛偵偍偗傞擾嬈暘栰偺埖偄偑柧傜偐偵側傞傑偱丄懠偺杅堈岎徛傪奐巒偡傋偒偱偼側偄偲庡挘偟偨偑丄偦傟偵懳偟丄懠偺EU庱擼偼撿暷巗応偑暷崙偵撈愯偝傟傞偲斀敪偟偨丅
嶲峫丗Spanish paper reports 'fiasco' as Chirac 'blows apart' EU-Mercosur agreement,
BBC summary of world broadcasts, June 8, 1999
仭 WTO堦斒棟帠夛偺夛崌偵僀儞僪惌晎偑WTO師婜岎徛偵岦偗偨採埬傪採弌
丂 6寧7擔丄8擔偵峴傢傟偨WTO堦斒棟帠夛偺夛崌偵僀儞僪偑採弌偟偨儁乕僷乕偼丄斀僟儞僺儞僌嫤掕乮幚巤偵娭偡傞嫤掕戞5忦乯丄曗彆嬥偍傛傃憡嶦娭惻偵娭偡傞嫤掕丄塹惗怉暔専塽偵娭偡傞嫤掕乮SPS嫤掕乯丄偍傛傃杅堈娭楢搳帒慬抲乮TRIMs乯嫤掕偺夵惓傪採埬偟偰偄傞丅
丂斀僟儞僺儞僌嫤掕偵偮偄偰偺採埬偼丄懳徾奜偲偝傟偰偄傞桝弌妟偺2亾傪壓夞傞僟儞僺儞僌棪傪丄搑忋崙偐傜偺桝弌偵偮偄偰偼5亾偲偡傞偙偲丄偍傛傃懳徾奜偲偝傟偰偄傞桝擖偵愯傔傞僟儞僺儞僌桝擖偺妱崌傪尰峴偺3亾偐傜丄搑忋崙偵尷偭偰5亾偵堷偒忋偘傞偙偲偱偁傞丅偝傜偵丄摨堦昳栚偺僟儞僺儞僌挷嵏傪嵞奐偡傞偲偒偵偼丄慜夞偺挷嵏廔椆帪傛傝1擭娫偺婜娫傪嬻偗傞偙偲丄偍傛傃帠幚擣掕偺偨傔偺崙儗儀儖偱偺挷嵏偺寢壥偵懳偟偰懠崙偑斀榑偡傞偙偲傪擣傔傞傛偆梫惪偟偨丅
丂嵟嬤偺WTO擭師曬崘偵傛傟偽丄1997擭偵奐巒偝傟偨斀僟儞僺儞僌挷嵏偼丄僆乕僗僩儔儕傾42審丄EU41審丄撿傾僼儕僇23審丄暷崙16審偱偁傝丄偦偺懳徾偲偝傟偨偺偼EU59審丄拞崙31審丄戜榩16審丄娯崙16審偲側偭偰偄傞丅傑偨丄1997擭帪揰偵敪摦偝傟偰偄傞斀僟儞僺儞僌慬抲偼崌寁偱880審偱偁傝丄偦偺34亾偑暷崙偵懳偟偰丄16亾偑EU偵懳偟偰丄10亾偑僇僫僟丄9亾偑儊僉僔僐偵懳偟偰敪摦偝傟偰偄傞丅
丂 曗彆嬥偵娭偡傞僀儞僪偺採埬偼丄搑忋崙偑桝弌幚愌偵墳偠偰巟弌偝傟傞曗彆嬥丄偁傞偄偼崙撪惢昳傪桪嬾偡傞曗彆嬥側偳傪WTO儖乕儖偱梕擣偡傞偲偄偆傕偺偱偁傞丅偝傜偵丄憡嶦娭惻偺揔梡偺懳徾奜偲偝傟偰偄傞桝弌壙奿偺3亾傑偱偺曗彆嬥傪丄搑忋崙偵偮偄偰偼7亾傑偱堷偒忋偘傞傛偆梫惪偟偨丅僀儞僪偼丄婛懚偺曗彆嬥儖乕儖偑愭恑崙宆偺曗彆嬥偩偗傪椺奜埖偄偲偟丄搑忋崙宆偺曗彆嬥傪嵎暿揑偵埖偭偰偄傞偙偲傪旕擄偟偰偄傞丅
丂SPS嫤掕偵偮偄偰偺僀儞僪偺採埬偼丄尰嵼搑忋崙偵梌偊傜摼偰偄傞丄SPS嫤掕偵婎偯偔崙撪朄惍旛偺幚巤桺梊偺婜娫傪墑挿偡傞偙偲丄偍傛傃崙嵺婎弨偺嶔掕僾儘僙僗偵搑忋崙偑嶲壛偱偒傞傛偆偵偡傞偙偲偱偁傞丅
丂TRIMs偵娭偟偰偼丄搑忋崙偑奜崙偐傜恑弌偟偨婇嬈偵懳偟偰崙撪僐儞僥儞僩梫媮乮崙撪嶻偺晹昳傪堦掕妱崌巊梡偡傞偙偲傪梫媮乯傗桝弌梫媮乮惗嶻検偺堦掕妱崌偺崙奜桝弌傪梫媮乯傪2000擭1寧傑偱偵揚攑偟側偗傟偽側傜側偄偲偡傞尰峴儖乕儖傪夵惓偟丄偙傟傜偺堐帩傪梕擣偡傞傛偆媮傔偨丅
嶲峫丟India urges revision of WTO agreements on antidumping, subsidies, investment,
International Trade Reporter, Volume 16 Number 23m June 9, 1999
仭娯崙偑WTO偺搳帒儖乕儖偵拲暥
丂 6寧3擔丄4擔偵奐嵜偝傟偨WTO杅堈搳帒嶌嬈晹夛乮WGTI乯偵偍偄偰娯崙惌晎偼丄搳帒儖乕儖偺岎徛奐巒偼巟帩偟偮偮傕丄偦偺拞恎傪惂尷偡傞撪梕偺採埬傪採弌偟偨丅偦偺撪梕偼丄尨懃帺桼壔偱椺奜崁栚儕僗僩傪奺崙偑採弌偡傞偲偄偆乽僩僢僾丒僟僂儞曽幃乿偺OECD丒MAI僞僀僾偺嫤掕偱偼側偔丄WTO偺GATS乮僒乕價僗杅堈嫤掕乯偑嵦梡偟偨儃僩儉丒傾僢僾曽幃傪嵦梡偡傞偙偲偱敪揥儗儀儖偺堘偆奺崙偺帠忣傪斀塮偱偒傞傛偆偵偡傞偙偲丄偍傛傃懳徾斖埻傪惢憿嬈暘栰偵尷掕偡傞偙偲偺2揰偱偁傞丅
丂 尰嵼丄WTO偱搳帒嫤掕傪岎徛偡傞偙偲偵偼僀儞僪丄僷僉僗僞儞丄ASEAN彅崙偑擄怓傪帵偟偰偍傝丄暷崙偼媍夛傗NGO偺斀敪傪嫲傟偰偙偺審偵偼岥傪偮偖傫偱偄傞丅搳帒嫤掕偺岎徛偵慜岦偒偺巔惃傪帵偟偰偄傞偺偼EU丄擔杮丄僽儔僕儖丄僇僫僟丄僗僀僗側偳偱偁傞丅
嶲峫丗South Korea urges limited talks on investment in next WTO round, International
Trade Reporter, Volume 16 Number 23, June 9, 1999
To: wto@jca.apc.org
Subject: [wto 140] WTO 娭楢忣曬丂 6寧丂 Vol.1
Date: Fri, 23 Jul 1999 21:55:53 +0900
From: Tomoko Sakuma <tsakuma@jca.apc.org>
WTO娭楢忣曬丂6寧丂Vol.1
仭 OECD妕椈棟帠夛丟MAI偺幐攕傪惓幃偵擣傔傞丅
仭 暷惌晎偑崙壠杅堈婇嬈偵偮偄偰4儢崙偵幙栤
仭僼傿儞儔儞僪椢偺搣偑WTO師婜岎徛偑怴偨側暘栰偵庢傝慻傓偙偲偵斀懳傪昞柧
仭僆儔儞僟惌晎丄怴偨側搳帒嫤掕偱偼側偔婛懚偺TRIMs乮杅堈娭楢搳帒慬抲偵娭偡傞嫤掕乯偺嫮壔傪庡挘
仭僶乕僔僃僼僗僉暷捠彜戙昞丄僒乕價僗杅堈偺戝暆帺桼壔傪採埬
仭 OECD妕椈棟帠夛丟MAI偺幐攕傪惓幃偵擣傔傞丅
丂OECD僷儕杮晹偱枅擭4寧乣5寧偵奐偐傟傞妕椈棟帠夛偑崱擭偼5寧26擔丒27擔偵奐嵜偝傟丄壛柨29僇崙偐傜杅堈憡偲嵿柋憡偑嶲壛偟偨丅崱夞偺徟揰偼WTO師婜岎徛偩偭偨偑丄偦偺撪梕偵幚幙揑側恑揥偼尒傜傟側偐偭偨丅傑偨丄嵦戰偝傟偨妕椈惡柧偼丄暷惌晎偐傜偺梫惪傕偁傝丄搳帒嫤掕偺崱屻偺壜擻惈偵偮偄偰偼尵媦偟偰偄側偄丅
丂崱夞偺妕椈棟帠夛偱偼丄偙偺媍榑埲奜偵傕丄悽奅宱嵪偺揥朷傗帩懕壜擻側奐敪偵娭偡傞OECD偺挷嵏丄揹巕彜庢堷傊偺壽惻僔僗僥儉偺奐敪傗僶儖僇儞敿搰偵偍偗傞愴屻暅嫽偵OECD偑壥偨偟偆傞栶妱側偳偵偮偄偰榖偟崌傢傟偨丅
丂 壛柨奺崙偼11寧偺WTO妕椈夛媍偱價儖僩僀儞丒傾僕僃儞僟乮擾嬈丒僒乕價僗乯偺嵞岎徛傪奐巒偡傞偙偲丄偍傛傃師婜岎徛偱偼搑忋崙偑廳梫側栶妱傪扴偆偙偲偵偮偄偰偼崌堄偟偨偑丄怴偨偵偳偺暘栰傪岎徛偵壛偊傞偐偵偮偄偰偼慡偔崌堄偵帄傜側偐偭偨丅
丂 WTO師婜岎徛傪3擭埲撪偵廔寢偡傞偙偲偲丄堦妵庴戻曽幃傪嵦梡偡傞偙偲偵偮偄偰偼傎傏崌堄偑宍惉偝傟偨丅妕椈棟帠夛屻偺婰幰夛尒偵墳偠偨僌儕傾丒儊僉僔僐嵿柋憡偵傛傟偽丄揹巕彜庢堷偲惌晎挷払偵偮偄偰偺婯棩偼丄師婜岎徛偑奐巒偝傟傞傛傝傕憗偔崌堄偵帄傞壜擻惈偑崅偄偲偄偆丅
丂 妕椈惡柧偼崙嵺楯摥婎弨偺弲庣傪姪崘偟偰偄傞偑丄偙偺栤戣偼WTO師婜岎徛偵娭偡傞抜棊偱偼庢傝忋偘傜傟偰偄側偄丅杅堈儖乕儖偵幮夛忦崁乮楯摥婎弨弲庣婯掕乯傪娷傔傞偙偲傪庡挘偟偰偄傞楯摥慻崌偼丄偙傟傪巟帩偡傞僼儔儞僗側偳偲偲傕偵儘價乕傪揥奐偟偨偑丄搑忋崙傪戙曎偡傞儊僉僔僐丄娯崙丄擔杮偑斀懳偟偨偺偱偁傞丅
丂 僆乕僗僩儔儕傾偺僼傿僢僔儍乕杅堈憡偼丄崑惌晎偺挷嵏曬崘乽悽奅杅堈夵妚乿傪敪昞丄奺崙偺娭惻棪傪堦棩偵50亾堷偒壓偘傟偽枅擭4000壄僪儖埲忋傕杅堈妟偑奼戝偟丄娭惻偑慡攑偝傟傟偽摨條偵7500壄僪儖偺杅堈奼戝偑幚尰偡傞偲偺挷嵏寢壥傪曬崘偟偨丅
丂 OECD壛柨奺崙偼崙嵺嬥梈僔僗僥儉偺嫮壔偲嬥梈婋婡偺梊杊傪栚揑偲偟偨乽僐乕億儗乕僩丒僈僶僫儞僗尨懃乿傪嵦戰丄偙傟偑崱夞偺妕椈夛媍嵟戝偺惉壥偲側偭偨丅偙傟偼嶐擭偺OECD妕椈夛媍偺姪崘傪庴偗偰OECD偑弨旛偟偰偒偨尨懃惡柧偱偁傞丅妕椈傜偼丄偙偺尨懃惡柧偑OECE奺崙丄偍傛傃悽嬧丒IMF傪捠偠偰搑忋崙偵偍偄偰傕愊嬌揑偵妶梡偝傟傞傛偆婜懸傪帵偟偨偑丄偙偺尨懃惡柧偼懠偺崙嵺忦栺偲堘偭偰朄揑峉懇椡傪帩偨側偄丅
嶲峫丟Trade Agenda Left Unresolved At Conclusion of OECD Ministerial Meeting, International
Trade Reporter, Volume 16 Number 22, June 2,1999.
OECD Final Communique and Communique of OECD Council Meeting at the Ministerial Level
(www.oecd.org)
仭 暷惌晎偑崙壠杅堈婇嬈偵偮偄偰4儢崙偵幙栤
丂 暷惌晎偼丄崙壠杅堈婇嬈乮STEs乯偵懳偡傞崙嵺婯斖嶌傝傪WTO師婜岎徛偺栚昗偺堦偮偵宖偘偰偄傞丅偙偺審偵偮偄偰暷惌晎偼5寧26擔偺WTO夛崌偺応偱丄儊僉僔僐丄僲儖僂僃乕丄僩儖僐丄擔杮偺4儢崙偵偦傟偧傟幙栤傪弌偟丄師夞夛崌傑偱偵曉摎偡傞傛偆梫惪偟偨丅尰嵼偺WTO儖乕儖偱偼STEs偺堐帩偼梕擣偝傟偰偄傞偑丄偦偺塣塩偼柍嵎暿尨懃偲巗応庡媊偵婎偯偄偰偄側偗傟偽側傜側偄偲偝傟偰偄傞丅
丂 儊僉僔僐偵懳偟偰偼丄STE偱偁傞CONASUPO偑暡擕偺桝擖儔僀僙儞僗傪壡愯偟偰偄傞棟桼偵偮偄偰丄僲儖僂僃乕偵懳偟偰偼崙壠崚暔夛幮偑攔懠揑撈愯摿尃傪堐帩偟偰偄傞幚懺偵偮偄偰丄僩儖僐偵懳偟偰偼惌晎偺僞僶僐岞幮乮TEKEL乯偺柉塩壔偑拞巭偝傟偨偙偲偵偮偄偰丄偦偟偰擔杮偵懳偟偰偼4寧偺僐儊娭惻壔埲屻偺怘椘挕偺暷桝擖偺幚懺偵偮偄偰丄偦傟偧傟曉摎偑媮傔傜傟偰偄傞丅
彺栿丟U.S. Presses WTO Members to Explain Activities of State Trading Enterprises,
International Trade Reporter, Volume 16 Number 22, 1999
仭僼傿儞儔儞僪椢偺搣偑WTO師婜岎徛偑怴偨側暘栰偵庢傝慻傓偙偲偵斀懳傪昞柧
丂5寧31擔丄僿儖僔儞僉偱峴傢傟偨NGO僙儈僫乕偺応偱丄僼傿儞儔儞僪椢偺搣媍挿偑敪尵丄WTO師婜岎徛偵偍偄偰怴偨側暘栰乮僯儏乕丒僀僔儏乕乯偺帺桼壔岎徛傪奐巒偡傞偙偲偵斀懳偺巔惃傪柧傜偐偵偟偨丅偦傟傛傝傕丄尰嵼偺WTO僔僗僥儉慡懱偵偮偄偰昡壙傪峴傢偹偽側傜側偄偲偄偆庡挘偱偁傞丅僼傿儞儔儞僪椢偺搣偼尰嵼丄梌搣楢崌偺堦妏傪扴偭偰偄傞丅堦曽丄偳偆僙儈僫乕偵嶲壛偟偰偄偨曐庣攈偺奜柋戝恇偼丄偵傘乕丒僀僔儏乕傪娷傔偨儈儗僯傾儉丒儔僂儞僪楬慄乮岎徛暘栰奼戝楬慄乯傪寴帩偟偨丅
仭僆儔儞僟惌晎丄怴偨側搳帒嫤掕偱偼側偔婛懚偺TRIMs乮杅堈娭楢搳帒慬抲偵娭偡傞嫤掕乯偺嫮壔傪庡挘
丂僆儔儞僟惌晎偑5寧28擔偵敪昞偟偨乽怴儔僂儞僪乮'The New Round'乯乿偵傛偭偰丄僆儔儞僟偺WTO師婜岎徛偵岦偗偨億僕僔儑儞偑柧傜偐偵偝傟偨丅拲栚偡傋偒側偺偼丄OECD偱MAI乮懡崙娫搳帒嫤掕乯岎徛僌儖乕僾偺媍挿崙傪柋傔偰偄偨摨崙偑丄WTO偱傕憗媫偵搳帒嫤掕傪岎徛偟偰偄偙偆偲偟偰偄傞EC乮墷廈埾堳夛乯傪斸敾丄偦傟傪旔偗偰婛懚偺TRIMs嫤掕傪嫮壔偟偰偄偔曽朄傪庡挘偟偰偄傞揰偱偁傞丅僆儔儞僟偼WTO僔僗僥儉偺嫮壔傪朷傫偱偍傝丄偦偺偨傔偵杅堈偵娭楢偟偨嫞憟惈嶔傗搳帒偺暘栰偵偍偗傞婯棩嶌傝傪廳帇偟偰偄傞丅偟偐偟丄偙偆偟偨僯儏乕丒僀僔儏乕偵岎徛斖埻傪峀偘傞偙偲偵斀敪偑峀偑偭偰偄傞帠懺傪庴偗丄傛傝尰幚揑側楬慄傪柾嶕偟偰偄傞偲尵偊傞丅
丂偦偺堦曽丄嬥梈婋婡側偳偱乽帺桼杅堈乿傊偺媈擮偑峀偑偭偰偄傞偙偲偵懳偟丄偝傜側傞帺桼壔偩偗偑偙偺婋婡傪扙偡傞曽朄偩偲庡挘丄娭惻庤懕偒傗斀僟儞僺儞僌慬抲丄曗彆嬥側偳偺旕娭惻忈暻偺嶍尭傪栚巜偡偲偟偰偄傞丅傑偨丄懡偔偺搑忋崙偑僂儖僌傾僀丒儔僂儞僪崌堄偺幚巤崲擄傪庡挘偟偰偄傞偙偲偵懳偟偰傕丄偙偺崌堄偵偮偄偰嵞岎徛偡傞偙偲偼晄壜擻偩偲愗傝幪偰丄働乕僗丒僶僀丒働乕僗偱懳墳偡傋偒偩偲偟偨丅
丂懡崙娫娐嫬嫤掕乮MEAs乯偲WTO儖乕儖偺柕弬揰偵偮偄偰偼MEAs偺杅堈惂尷慬抲傪WTO儖乕儖偺壓偱梕擣偡傞偙偲傪巟帩偟偨丅傑偨丄梊杊尨懃偲墭愼幰晧扴尨懃乮PPP乯偵偮偄偰傕庴偗擖傟偰偄偔曽恓傪帵偟偨偑丄偦偺採埬偼嬶懱惈傪寚偄偰偄偨丅偝傜偵丄EU撪偺擾嬈廬帠幰偑捈柺偟偰偄傞乮崅偄娐嫬側偳偺婎弨側偳偵傛傞乯崅偄惗嶻僐僗僩傪掅尭偡傞偨傔偺娐嫬曗彆嬥傪偳偆埖偆傋偒偐偵偮偄偰偼尵媦偟偰偄側偄丅
彺栿丗Latest Development in the Netherlands, by Erik Wesselius, June 3,1999
仭僶乕僔僃僼僗僉暷捠彜戙昞丄僒乕價僗杅堈偺戝暆帺桼壔傪採埬
丂僶乕僔僃僼僗僉暷捠彜戙昞偼6寧1擔丄儚僔儞僩儞D.C.偵偍偗傞悽奅僒乕價僗嶻嬈戝夛偺応偱島墘偟丄師婜WTO岎徛偵偍偗傞僒乕價僗杅堈偺戝暆帺桼壔偵堄梸傪帵偟偨丅摨戙昞偼丄僂儖僌傾僀丒儔僂儞僪偱掲寢偝傟偨僒乕價僗杅堈嫤掕乮GATS乯偺岎徛宍幃乮儕僋僄僗僩丒僆僼傽乕曽幃亖奺崙偛偲偵帺桼壔偱偒傞晹栧傗偦偺掱搙偵偮偄偰帺庡怽惪偟丄岎徛偡傞傗傝曽乯偼岠棪揑偱側偄偲偟偰丄儌僲乮峼岺嬈惢昳乯偺娭惻堷偒壓偘岎徛曽幃乮奺崙偑帺庡怽惪偟偨椺奜晹栧傪彍偒丄尨懃慡偰偺晹栧傪堦棩偵帺桼壔偡傞曽幃乯傪僒乕價僗暘栰偵傕嵦梡偡傋偒偩偲偟偨丅
丂偝傜偵丄奺崙偑崌堄偱偒傞摿掕晹栧偵偮偄偰偼娭惻傪揚攑偡傞乽僛儘丒僛儘曽幃乿傗丄慡偰偺崙偑奺崙偺尰峴娭惻偐傜堦掕妱崌傪堦棩嶍尭偡傞乽僼僅乕儈儏儔曽幃乿傪僒乕價僗杅堈岎徛偱傕愊嬌揑偵妶梡偟偰峴偔傋偒偲偺尒夝傪帵偟偨丅暷崙偼丄偙傟傜偺曽幃傪慻傒崌傢偣偰丄摿偵嬥梈丄揹婥捠怣乮僥儗僐儉乯丄塣桝丄僆乕僨傿僆丒價僕儏傾儖丄寶愝丄嫵堢丄寬峃丄娤岝丄偍傛傃愱栧怑嬈偵偍偗傞戝暆帺桼壔傪栚巜偟偰偄傞丅
丂摨戙昞偵傛傟偽丄GATS偺壓偱丄僆乕僨傿僆丒價僕儏傾儖晹栧偱帺桼壔傪栺懇偟偰偄傞偺偼14儢崙偵夁偓偢丄傑偨丄僯儏乕僗偺廂廤丒攝怣傪帺桼壔偟偨搑忋崙偼奆柍偱偁傞丅偝傜偵丄儌僲偺杅堈帺桼壔偵晄壜寚偱偁傞塣桝僒乕價僗偺帺桼壔傪栺懇偟偰偄傞崙偼50儢崙偵枮偨側偄偲偄偆丅僂儖僌傾僀儔僂儞僪廔寢埲屻偵掲寢偝傟偨嬥梈僒乕價僗嫤掕傗婎杮僥儗僐儉嫤掕偵偼偦傟偧傟70儢崙偟偐嶲壛偟偰偍傜偢丄摨戙昞偺栚揑偼巆傝偺栺60儢崙偺WTO壛柨崙偵偙傟傜屄暿嫤掕傪庴偗擖傟偝偣傞偙偲偱偁傞丅
丂婎杮僥儗僐儉嫤掕偱偼丄崙撪婯惂偵堦棩偵壽偝傟傞崙嵺婯棩乮尨懃乯傪嵦戰偟偨丅暷崙偼丄崱屻偺僒乕價僗岎徛偵偍偄偰傕丄偙偺傛偆側崙嵺婯棩傪嶌傝偨偄偲偟偰偄傞丅僶乕僔僃僼僗僉捠彜戙昞偼丄GATS偺嵞岎徛偵傛偭偰丄媄弍奐敪偑懀恑偝傟丄晄岞惓側忈暻偑揚攑偝傟傞偙偲傪婜懸偡傞偲岅偭偨丅摨戙昞偼傑偨丄寬峃嶻嬈側偳傕揹婥捠怣傪夘偟偰僒乕價僗傪採嫙偱偒傞晹栧偱偁傝丄嵎暿揑側埖偄傪庴偗傞傋偒偱偼側偄偲庡挘偟偨丅
丂摨戙昞偼傑偨丄惌晎挷払偺摟柧惈傪妋曐偡傞偨傔偺嫤掕傪丄僔傾僩儖WTO妕椈夛媍傛傝傕慜偵掲寢偡傞偙偲丄偍傛傃僀儞僞乕僱僢僩傪夘偡傞揹巕彜庢堷偵娭惻傪壽偝側偄偲偺巄掕崌堄偺婜尷傪墑挿偡傞偙偲傪暷惌尃偼栚巜偟偰偄傞偲弎傋偨丅偝傜偵丄暷崙偲拞撿暷彅崙偑岎徛偟偰偄傞暷廈帺桼杅堈嫤掕乮FTAA)偱偼僒乕價僗杅堈帺桼壔偵娭偡傞憪埬偑9寧偵偼姰惉偡傞梊掕偱偁傝丄傑偨暷崙偲EU偺娫偱榖偟崌傢傟偰偄傞戝惣梞娫宱嵪僷乕僩僫乕僔僢僾乮TEP乯偱偼愱栧怑嬈僒乕價僗偺帒奿婯掕偺憡屳擣徹偑榖偟崌傢傟偰偍傝丄偦偺椉曽偺寢壥偑WTO師婜岎徛偺峴曽偵傕戝偒側塭嬁傪梌偊傞偩傠偆偲岅偭偨丅
彺栿丗Barshefsky reveals U.S. push to broaden WTO service talks, Inside US Trade,
June 4 , 1999
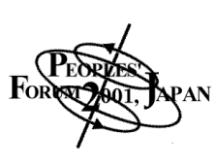
To: wto@jca.apc.org
Subject: [wto 135] WTO 娭楢忣曬丂 99/5丂 Vol.2
Date: Wed, 21 Jul 1999 15:06:42 +0900
From: Tomoko Sakuma <tsakuma@jca.ax.apc.org>
WTO娭楢忣曬丂99/5丂Vol.2
栚師丗
仭WTO僔傾僩儖妕椈夛媍偵岦偗丄暷嶻嬈奅偑傾儞働乕僩挷嵏
仭EU杅堈戝恇夛崌偑WTO師婜岎徛偵岦偗偨嫟捠億僕僔儑儞偵偮偄偰嫤媍
仭暷崙偺怘昳壛岺嬈奅偑壛岺怘昳桝弌傪愴棯暘栰偵埵抲偯偗傞傛偆暷惌尃偵梫惪
仭WTO師婜岎徛偵娭偡傞崙嵺彜嬈夛媍強乮ICC乯偺梫惪
仭墷廈媍夛偑俤倀擾嬈曗彆嬥偺嶍尭傪姪崘
仭暷崙偺傾僌儕價僕僱僗偺楢崌偑WTO師婜岎徛偵拲暥
仭 乽梊杊尨懃乮Precautionary Principle乯乿偑崱屻偺岎徛偺僇僊丠
仭WTO僔傾僩儖妕椈夛媍偵岦偗丄暷嶻嬈奅偑傾儞働乕僩挷嵏
丂暷嶻嬈奅偼崱擭11寧偺WTO僔傾僩儖妕椈夛媍偵岦偗偰乽杅堈奼戝偺偨傔偺暷崙楢柨乮U.S.Alliance
for Trade Expansion乯乿傪慻怐丄僔傾僩儖偺慡暷惢憿嬈楢崌乮NAM乯偵帠柋嬊傪偍偒丄枅廡夛崌傪奐嵜偟偰偄傞丅夛崌偱偼丄崙嵺杅堈偵娭傢傞彈惈楢崌乮WIIT乯偑幚巤偟偨傾儞働乕僩偺廤寁寢壥偑敪昞偝傟偨丅埲壓偺寢壥偼暷媍夛偲峴惌晎丄偍傛傃儊僨傿傾傗悽榑挷嵏夛幮偵憲晅偝傟傞丟
1.丂暷崙恖偺傎偲傫偳偑丄杅堈栤戣偵偮偄偰徻偟偔側偄側偑傜傕丄杅堈嫤掕偼乽憡屳庡媊乿偵婎偯偔傋偒偩偲峫偊偰偄傞丅
2.丂84亾偺恖偑丄奜崙巗応偑暵嵔揑偱偁傞尷傝丄暷崙偺杅堈偼奼戝偱偒側偄偲摎偊偨丅
3.丂70亾偺恖偑丄杅堈嫤掕偼椙偄傕偺偱偁傝丄WTO僔傾僩儖妕椈夛崌偵偍偄偰暷崙偑巜摫椡傪敪婗偡傞偙偲傪朷傫偱偄傞丅
4.丂楯摥慻崌堳偺壠掚偲丄偦偆偱側偄壠掚偲偱偼夞摎偺撪梕偵庒姳偺堘偄偑偁偭偨丅
仭EU杅堈戝恇夛崌偑WTO師婜岎徛偵岦偗偨嫟捠億僕僔儑儞偵偮偄偰嫤媍
丂5寧9擔丒10擔丄EU媍挿崙偱偁傞僪僀僣偺宱嵪扴摉憡偺媍挿偺壓丄儀儖儕儞偱EU杅堈戝恇夛崌偑奐嵜偝傟偨丅WTO師婜岎徛偵岦偗偨EU偺嫟捠億僕僔儑儞偵偮偄偰榖偟崌偆嵟屻偺妕椈媺夛崌偱偁傞丅偙偙偱丄WTO師婜岎徛偺岎徛婜娫偵偮偄偰偼3擭埲撪丄岎徛曽朄偼乽曪妵揑乿偐偮乽堦妵庴戻乿丄懳徾暘栰偵偮偄偰偼峼岺嬈惢昳偺娭惻堷偒壓偘丄搳帒儖乕儖丄嫞憟惌嶔丄杅堈偲娐嫬丄偍傛傃杅堈偲幮夛忦崁乮楯摥婎弨乯側偳偺僯儏乕丒僀僔儏乕傪丄婛偵岎徛偡傞偙偲偵崙嵺揑崌堄偺偁傞擾嬈偲僒乕價僗乮價儖僩僀儞丒傾僕僃儞僟乯偲偲傕偵岎徛偟偰偄偔偙偲偱婎杮崌堄偝傟偨丅偨偩偟搳帒傗嫞憟惌嶔側偳偵偮偄偰偼丄師婜岎徛偺娫偵彮側偔偲傕尨懃偵娭偟偰崌堄傪宍惉偟丄偦偺屻偺嬶懱揑岎徛偵偮側偘傞偲偟偨丅
丂摿偵搳帒儖乕儖偵偮偄偰偼丄OECD偱偺MAI乮懡崙娫搳帒嫤掕乯偺幐攕傪庴偗偰丄MAI偲偼慡偔堘偆丄怴偟偄搳帒儖乕儖傪僛儘偐傜嶔掕偟偰偄偔傋偒偩偲偟偨丅嬶懱揑偵偼丄MAI偺偲偒偺傛偆側僩僢僾僟僂儞宍幃乮尨懃帺桼壔丄椺奜儕僗僩傪採弌乯偱偼側偔丄儃僩儉傾僢僾宍幃乮帺桼壔偱偒傞暘栰傗昳栚偵偮偄偰偩偗儕僗僩傾僢僾乯偱岎徛偡傞偙偲丄敪揥抜奒偵墳偠偨嵎堎偺偁傞懸嬾丄偍傛傃幚懱宱嵪偵娭傢傞搳帒偩偗傪懳徾偲偡傞乮帒杮堏摦傪娷傔側偄乯偙偲側偳偱偁傞丅
丂嫞憟惌嶔偵偮偄偰偼丄WTO壛柨奺崙偵偍偄偰嫞憟惌嶔傪惍旛偟偰偄偔偨傔偺僀儞僙儞僥傿僽傪愝偗傞偙偲偲丄摟柧惈丒柍嵎暿丒懳徾偲偝傟傞姷峴側偳偵偮偄偰婎杮尨懃傪掕媊偡傞偙偲傪採埬偡傞丅EU偼偙傟偵傛傝丄奺崙偼WTO尨懃偵斀偡傞峴堊偵偮偄偰奩摉崙傪採慽偡傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵側傞偲偟偰偄傞偑丄暷崙撪偺斀僩儔僗僩朄傪奜崙偵揔梡偡傞偙偲偑惂栺偝傟傞偲偟偰暷崙偑斀敪偡傞偙偲偼昁帄偱偁傞丅
丂峼岺嬈惢昳偺娭惻偵偮偄偰偼丄嵟戝娭惻棪乮僞儕僼丒僺乕僋乯傪壓偘傞偙偲偲丄宱嵪敪揥偺搙崌偄偵墳偠偨抜奒揑側僞儕僼丒僺乕僋傪媮傔偰偄偔丅傑偨丄娭惻惂搙傪摑堦壔偡傞偨傔偵丄慡偰偺昳栚傪3偮偺僇僥僑儕乕偵暘椶偟丄偦偺暘椶偛偲偵堦妵偟偰娭惻堷偒壓偘棪傪掕傔偰偄偔偙偲傪採埬偡傞丅偙偆偟偨惂搙傪嵦梡偡傞偙偲偵傛傝丄EU傗暷崙丄擔杮偺娭惻偼慡懱暯嬒偱40亾掱搙堷偒壓偘傜傟傞偲偟偰偄傞偑丄搑忋崙偵懳偟偰偼丄傛傝崅偄娭惻傪堐帩偱偒傞傛偆偵崅傔偺暯嬒儗儀儖傪愝掕偡傞偲偟偰偄傞丅
丂EU偼傑偨丄娭惻憡摉妟偺嵏掕曽朄傗丄嫋擣壜惂搙丄尨嶻抧婯掕丄崙嵺惍崌壔側偳偺悈暯揑壽戣乮偁傜備傞暘栰偺杅堈偵傑偨偑傞栤戣乯偱傕愊嬌揑偵媍榑傪儕乕僪偟偰偄偔偲偟偰偄傞丅
丂娐嫬偺栤戣偵偮偄偰偼丄懡崙娫娐嫬嫤掕偲WTO儖乕儖偺惍崌惈偺栤戣偵壛偊丄徚旓幰偺娐嫬堄幆傪杅堈儖乕儖偵斀塮偡傞偙偲丄偍傛傃儔儀儖偵惗嶻曽朄傪婰嵹偡傞偙偲傪梕擣偡傞昞帵儖乕儖傪妋棫偡傞偙偲傪栚巜偟偰偄傞丅奐敪偺栤戣偵偮偄偰偼丄EU偼廬棃傛傝丄2003擭傑偱偵愭恑岺嬈崙偑屻敪奐敪搑忋崙乮LDCs乯偐傜偺桝擖偵懳偡傞娭惻傪揚攑偡傞偙偲丄偍傛傃LDCs偺WTO傊偺幚幙揑側嶲壛傪壜擻偲偡傞偨傔偺媄弍巟墖傪嫮壔偡傞偙偲傪庡挘偟偰偒偰偄傞丅LDCs偐傜偺桝擖偵懳偡傞娭惻揚攑偵偮偄偰偼丄5寧12擔偺墷廈媍夛偱傕EU偺億僕僔儑儞偲偟偰丄僇儕僽丒拞撿暷彅崙偲帺桼杅堈寳傪宍惉偟偰偄偔審偲偲傕偵彸擣偝傟偰偄傞偑丄摨擔偵暵枊偟偨巐嬌杅堈戝恇夛崌乮搶嫗乯偱偼崌堄偵帄傜側偐偭偨丅
丂抦揑強桳尃偵娭偡傞杅堈儖乕儖偵偮偄偰傕婯掕傪嫮壔偟偰偄偔偙偲偑崌堄偝傟偨丅擾嬈偵偮偄偰偼丄CAP偺夵掶斉偱偁傞傾僕僃儞僟2000偑EU偺岎徛億僕僔儑儞偦偺傕偺偱偁傞偙偲偑嵞妋擣偝傟丄擾嬈偺帩偮乽懡柺揑婡擻乿偵攝椂偟偰偄偔偙偲偵傎偲傫偳偺戝恇偑崌堄偟偨丅
丂奺崙暿偱偼丄儀儖僊乕暃庱憡偲僀僞儕傾杅堈憡偼乽僌儘乕僶儖壔偑恖乆偵梌偊傞塭嬁乿傪峫椂偡傋偒偩偲庡挘丄儀儖僊乕偼摿偵楯摥丄暥壔偺懡條惈丄娐嫬丄徚旓幰曐岇傊偺攝椂傪嫮挷偟丄僀僞儕傾偼搑忋崙偺棙塿丄偍傛傃巗柉偺惗妶悈弨偺岦忋傊偺攝椂傪嫮挷偟偨丅僼儔儞僗偼WTO偲ILO乮崙嵺楯摥婡峔乯偺崌摨嶌嬈晹夛偑敪懌偟偨偙偲傪娊寎偟丄WTO偵偍偄偰楯摥栤戣偑偒偪傫偲埵抲偯偗傜傟傞傋偒偩偲庡挘偟偨丅
嶲峫丗Informal Council in Berlin on 9 and 10 May to prepare European Stance for next
multilateral negotiations on basis of commission paper - Globalization, respect for
reform of the Cap, resuming negotiations on investments 'from scratch', Agence Europe,
May 6,1999
European trade ministers back a global round of WTO negotiations to be concluded
quickly, Agence Europe, May 10,1999側偳
仭暷崙偺怘昳壛岺嬈奅偑壛岺怘昳桝弌傪愴棯暘栰偵埵抲偯偗傞傛偆暷惌尃偵梫惪
丂慡暷壛岺怘昳惢憿幰楢崌乮Grocery Manufacturers of America乯偼丄嬤擭丄彫敒傗僩僂儌儘僐僔側偳偺堦師嶻昳偺桝弌崅傪忋夞偭偨壛岺怘昳傪丄堦帪巆昳桝弌偲摨條偵暷崙偺杅堈愴棯暘栰偲偟偰埵抲偯偗丄懠崙巗応偺奐戱偵椡傪擖傟傞傛偆梫惪偡傞暥彂傪戝摑椞埗偵採弌偟偨丅暷崙偺怘昳壛岺嬈奅偼丄堚揱巕慻傒懼偊怘昳偵懳偡傞昞帵媊柋偯偗偵岦偗偨懠崙偺摦偒偵恄宱傪偲偑傜偣偰偍傝丄偦傟偵娭楢偟偰丄WTO偺塹惗怉暔専塽偵娭偡傞嫤掕乮SPS嫤掕乯偺夵惓傪庡挘偡傞EU偺摦偒傪墴偝偊崬傒偨偄偲峫偊偰偄傞丅尰峴偺SPS嫤掕偱偼丄怘昳埨慡惈傗摦怉暔曐岇偺偨傔偺崙撪慬抲偼杅堈忈暻偲側傞偨傔丄乽壢妛揑崻嫆乿偵婎偯偄偰偄側偗傟偽側傜側偄偲偟偰偄傞丅丂摨嬈奅偼丄峼岺嬈惢昳偵壽偝傟傞奺崙偺娭惻偺悽奅暯嬒偑4亾偱偁傞偺偵懳偟丄堦師嶻昳偲壛岺怘昳偵壽偝傟偰偄傞娭惻偺暯嬒偼40亾偱偁傞偲偟偰丄堦師嶻昳偲壛岺怘昳偵傕峼岺嬈惢昳暲偺娭惻棪傪揔梡偡傞傛偆庡挘偟偰偄偔偲偟偰偄傞丅摨嬈奅偺帋嶼偱偼丄2005擭傑偱偵壛岺怘昳桝弌偑暷崙偺擾嶻暔丒怘昳桝弌偵愯傔傞妱崌偼75亾偵払偡傞偲偄偆丅偙偺妱崌乮壛岺怘昳偲壛岺怘昳嵽椏偺崌寁乯偼1975擭偵偼(B24亾偩偭偨偑丄1988擭偵偼婛偵61亾偵払偟偰偄傞丅
嶲峫丗US food must be higher on tfade talks agenda-group, Reuter Financial Report,
May 17,1999
仭WTO師婜岎徛偵娭偡傞崙嵺彜嬈夛媍強乮ICC乯偺梫惪
丂G8僒儈僢僩傪1儢寧屻偵峊偊偨5寧20擔丄懡崙愋婇嬈偺楢崌懱偱偁傞崙嵺彜嬈夛媍強乮ICC乯偼G8偺媍挿傪柋傔傞僔儏儗乕僟乕撈庱憡偲夛崌傪峴偄丄WTO師婜岎徛偵娭偡傞梫惪傪峴偭偨丅偦偺撪梕偼丄岎徛婜娫偵偮偄偰偼丄慜夞偺僂儖僌傾僀丒儔僂儞僪偺挿婜壔偑悽奅宱嵪偵埆塭嬁傪梌偊偨偲偟偰丄媫懍偵曄壔偡傞價僕僱僗娐嫬偵抶傟傪庢傞偙偲側偔丄嶻嬈奅偺梫惪偵墳偊傞傛偆丄師婜岎徛偺憗婜懨寢傪媮傔偨丅傑偨丄師婜岎徛偱偼丄婇嬈偑悽奅巗応偱暯摍側忦審偺壓丄帺桼偵嫞憟偡傞偙偲傪壜擻偲偡傞丄傛傝峀媊偺乽巗応傾僋僙僗乿偺妋曐偑徟揰偲偝傟偹偽側傜側偄偲偟偨丅偙傟偼偮傑傝乽崙壠偺朄婯惂偵娭偡傞懡崙娫偺婯棩傪嫮壔偡傞偙偲偱偁傞乿丅嬶懱揑偵偼丟
匑僒乕價僗杅堈偺偝傜側傞帺桼壔丄
匒擾嶻暔杅堈偵偍偗傞曐岇庡媊揑忈暻偺幚幙揑嶍尭丄
匓娭惻偺堷偒壓偘偲揚攑丄
匔挿婜帒杮搳帒傪娷傓奀奜捈愙搳帒乮FDI乯偺曐岇丄
匘懡崙娫娐嫬嫤掕乮MEAs乯偵婎偯偔杅堈慬抲傪WTO儖乕儖偵惍崌偡傞偨傔偺婎弨嶌傝丄
匛帠幚忋偺杅堈忈暻偲側偭偰偄傞僄僐儔儀儖偺栤戣傊偺懳張丄
匜捠娭庤懕偒側偳偺杅堈娭楢庤懕偒偺娙慺壔偲嬤戙壔丄側偳傪梫惪偟偨丅
丂ICC偼悽奅137儢崙偵ICC埾堳夛傪梚偟偰偍傝丄G7奺崙偱慻怐偝傟偰偄傞ICC埾堳夛傕偦傟偧傟G7奺崙惌晎偵梫惪暥傪採弌偟偰偄傞丅
彺栿丗Settle rows and launch new trade round, business tells G7, May 20
(慡暥偼Web; www.iccwbo.org乯
仭墷廈媍夛偑俤倀擾嬈曗彆嬥偺嶍尭傪姪崘
丂墷廈媍夛偼5寧4擔丄WTO慡壛柨崙偑2005擭傑偱偵屻敪奐敪搑忋崙偐傜偺桝擖偵懳偡傞慡偰偺娭惻傪揚攑偡傋偒偲偺寛媍傪嵦戰偟偨丅偙偺寛媍偱偼丄僂儖僌傾僀丒儔僂儞僪偺寢壥偑搑忋崙偵偲偭偰晄棙偵摥偄偰偄傞尰忬傪夵慞偡傞傛偆媮傔偰偄傞丅偝傜偵丄愭恑崙偵傛傞曗彆嬥晅偒桝弌偵傛傝丄搑忋崙撪偱偺怘昳壛岺偑怢傃擸傫偱偄傞幚懺傪摜傑偊丄EU偺乽旕岠棪偱偁傝丄曐岇偝傟偡偓偰偄傞乿EU偺擾嶻暔暘栰傊偺曗彆嬥傪嶍尭偟側偗傟偽側傜側偄偲偟偰偄傞丅
丂墷廈媍夛偼傑偨丄WTO暣憟夝寛儊僇僯僘儉偺壓偱偺學憟偑懡敪偟偰偄傞偙偲偵傛傝丄搑忋崙傊偺晧壸偑戝偒偔側偭偰偄傞偙偲傗丄挷掆偵傛傞夝寛傊偺摴偑傎傏暵偞偝傟偰偟傑偭偨揰偵寽擮傪昞柧偟偨丅偟偨偑偭偰丄搑忋崙偵懳偡傞乽摿暿偐偮嵎堎偺偁傞懸嬾乮SPDs乯婯掕乿傪嵞専摙偡傞偙偲偑師婜WTO岎徛偺戝慜採偲偝傟傞傋偒偱偁傞偑丄摨帪偵丄SPD偺晅梌偵偁偨偭偰偼丄崙嵺楯摥婎弨偺弲庣偑忦審偲偝傟傞傋偒偩偲偄偆偺偑墷廈媍夛偺庡挘偱偁傞丅
丂嬶懱揑偵偼丄師婜岎徛偵偍偄偰偼丄擾嬈丄慇堐丄堖椏丄旂妚惢昳側偳丄搑忋崙偑愭恑崙偵懳偟偰斾妑桪埵傪桳偡傞摿掕暘栰偵偍偗傞僞儕僼丒僺乕僋乮嵟戝娭惻棪乯傪尰峴偺350亾偐傜堷偒壓偘傞偙偲傪庡娽偲偡傋偒偩偲偟偨丅
嶲峫丗EU Parliament Endorse Duty Benefits For Least Developed Nations in WTO Talks,
International Trade Reporter, Volume 16 Number 19, May 12,1999
仭暷崙偺傾僌儕價僕僱僗偺楢崌偑WTO師婜岎徛偵拲暥
丂暷崙偺70埲忋偺崚暔桝弌僌儖乕僾傗傾僌儕價僕僱僗偑WTO僔傾僩儖妕椈夛媍偵岦偗偰寢惉偟偨僔傾僩儖墌戩擾嬈埾堳夛乮Seattle
Round Agriculture Committee; SRAC乯偼暷惌晎偵懳偟丄壙奿巟帩偵婎偯偔廬棃偺擾嬈曗彆嬥傪堐帩偡傞偙偲丄偍傛傃崙撪嶻嬈偵塭嬁偺戝偒偄堦師嶻昳桝擖偵懳偡傞娭惻妱摉惂搙乮TRQs丟堦掕検偺桝擖偵懳偟偰掅偄娭惻棪傪揔梡偟丄偦傟傪挻偊偨暘偵偮偄偰偼崅娭惻傪壽偡曽幃乯偺揔梡斖埻傪奼戝偟側偄偙偲傪梫惪偡傞惡柧傪嵦戰偟偨丅SRAC偺儊儞僶乕偵偼慡暷擾嬈價儏乕儘乕傗慡暷柸壴埾堳夛丄僇乕僊儖丄僐僫僌儔丄慡暷壛岺怘昳嬈楢崌側偳偺傾僌儕價僕僱僗戝庤偑娷傑傟偰偄傞偑丄30枩恖傕偺壛柨幰傪梚偡傞慡暷擾嬈幰楢柨偼嶲壛偟偰偍傜偢丄摨楢柨偼撈帺偵採尵傪採弌偡傞梊掕偱偁傞丅SRAC偺儊儞僶乕帺懱偑偝傑偞傑側棙奞傪撪曪偟偰偄傞偨傔丄惡柧暥偱傕棙奞偑懳棫偡傞晹暘偵偮偄偰偼偐側傝偁偄傑偄側昞尰偑巆偝傟偨丅
丂暷傾僌儕價僕僱僗偺娫偵偼丄暷崙偑懠嶻嬈傪曐岇丒怳嫽偡傞偨傔偵暷崙偺擾嬈暘栰偑 媇惖偵偝傟偰偒偨偲偺擣幆偑偁傞丅傑偨1996擭偵惉棫偟偨暷擾嬈朄偵傛偭偰暷崙偺擾嬈偼偡偱偵帺桼壔傊偺堏峴婜娫偵偁傞偵傕偐偐傢傜偢丄幚嵺偵偼抜奒揑偵尭傜偝傟偰偄傞晄懌暐偄偱偼榙偄偒傟側偐偭偨暘偑嬞媫媬墖嬥偲偟偰巟媼偝傟偰偄傞帠懺偵寽擮傪書偄偰偄傞丅偙傟偵懳偟偰暷媍夛嬝偼丄椺奜揑偵埨抣偩偭偨嶐崱偺堦師嶻昳壙奿偑崱屻傕懕偔偼偢偼側偄偲偟偰丄嬞媫媬墖偑峆忢揑側傕偺偱側偄偙偲傪嫮挷偟偰偄傞丅
丂巗応傾僋僙僗傪夵慞偡傞偨傔偺巤嶔偲偟偰丄SRAC偼娭惻堷偒壓偘偲桝弌崙偺儊儕僢僩岦忋偵帒偡傞TRQs偺夵慞傪姪崘偟偨偑丄尰嵼丄柸壴傗偝偲偆偒傃丄僺乕僫僢僣丄僠乕僘丄媿擏側偳偵揔梡偝傟偰偄傞暷崙偺TRQs偺揔梡斖埻傪奼戝偡傞偙偲偼媮傔偰偄側偄丅堦曽偱SRAC偼丄TRQs偺榞傪挻偊偨桝擖昳偵懳偡傞朄奜側崅娭惻傪屳宐揑偵揚攑偟偰偄偔傛偆媮傔偰偄傞丅
丂SRAC偼桝弌曗彆嬥偺慡攑傪昗炘偟偰偄傞偑丄偦偺払惉偼崲擄偲偟偰丄彮側偔偲傕桝弌曗彆嬥偺棎梡乮椺偊偽EU偺崙撪岦偗僠乕僘惢憿偵懳偡傞曗彆嬥側偳偑丄幚嵺偵偼桝弌曗彆嬥偲摨條偺婡擻傪壥偨偟偰偄傞偵傕偐偐傢傜偢丄尰峴偺WTO儖乕儖偱偼桝弌曗彆嬥偲偼擣幆偝傟偰偍傜偢丄偦偺嶍尭懳徾偵娷傑傟偰偄側偄乯傪杊偖尩奿側儖乕儖傪嶌傞傋偒偩偲庡挘偟偰偄傞丅
丂摨條偵丄SRAC偼崙壠杅堈婇嬈乮STEs乯偺尨懃揚攑傪朷傫偱偄傞偑丄摨帪偵丄傛傝尰幚揑側梫媮偲偟偰丄STEs偺塣塩偺摟柧惈偺岦忋偲丄巗応偛偲偵愝掕壙奿傪曄偊傞嵎暿揑壙奿愝掕偺攑巭傪媮傔偰偄傞丅
丂僶僀僥僋惢昳偺庢傝埖偄偵娭偡傞SRAC偺庡挘偼丄SPS嫤掕偵婎偯偒乽揔惓壢妛乿偲乽揔惓側儕僗僋昡壙乿傪婎慴偲偡傞尰峴偺傗傝曽傪堐帩偡傋偒偱偁傝丄摨帪偵丄婛懚偺SPS嫤掕偺夵惓傪捠偠偰丄偁傞偄偼怴偨偵僶僀僥僋惢昳偵娭偡傞嫤掕傪掲寢偡傞偙偲偵傛偭偰丄僶僀僆僥僋僲儘僕乕偺恑曕傪懀恑偡傋偒偩偲偟偰偄傞丅
丂WTO嫤掕偺暣憟夝寛偵娭偡傞椆夝12忦8崁偱擣傔偰偄傞乽惗慛怘昳偵娭偡傞暣憟夝寛庤懕偒偺乪恦懍壔乫慬抲乿偵偮偄偰丄SRAC偼丄學憟椉崙偺崌堄傪梫審崁栚偐傜偼偢偡傛偆媮傔偨丅SRA俠偼傑偨丄杅堈惂嵸偺懳徾昳栚偵怘椏傪娷傔側偄偙偲傪WTO偱崌堄偡傞傛偆媮傔偰偄傞丅娐嫬傗楯摥偲杅堈儖乕儖偲偺娭學偺栤戣偵偮偄偰偼丄暷惌尃偑偙偺栤戣偵惓柺偐傜庢傝慻傑側偗傟偽乽堦妵彸擣庤懕偒乮僼傽僗僩丒僩儔僢僋乯朄埬乿偑彸擣偝傟側偄偲偟偰丄杅堈傪惂尷偟側偄宍偱偙偺栤戣偵庢傝慻傓傋偒偩偲偟偨丅
丂師婜岎徛慡斒偵偮偄偰偼丄岎徛斖埻偼曪妵揑偱偁傞傋偒偲偟偰丄擾嬈偲僒乕價僗暘栰偵尷掕偟側偄傛偆梫惪偟偰偄傞丅岎徛曽幃偵偮偄偰偼丄椺奜傪擣傔偢慡偰偺擾嬈暘栰偵偮偄偰堦妵岎徛偡傞乽僼僅乕儈儏儔曽幃乿偲堦妵彸擣曽幃傪庡挘丄岎徛婜尷偼3擭埲撪偲偟偨丅
彺栿丟Agriculture Coalition Sets Priorities For WTO, Sidesteps Radical Reform, May
21, 1999, by Mark Ritchie(IATP)
仭 乽梊杊尨懃乮Precautionary Principle乯乿偑崱屻偺岎徛偺僇僊丠
儗僆儞丒僽儕僞儞EC暃埾堳挿偼EU丄暷崙偲娐嫬NGO偺崱屻偺嫤椡娭學傪嫮壔偡傞偙偲傪栚揑偵奐偐傟偨僽儕儏僢僙儖偱偺夛媍偺応偱乽梊杊尨懃偼変乆偑捈柺偟偰偄傞嵟傕崲擄側惌嶔壽戣偱偁傞乿偲偟偰丄崱屻偙偺尨懃偵偝傑偞傑側夝庍偑偮偗傜傟丄棎梡偝傟偰偄偔壜擻惈傪帵嵈偟偨丅OECD偑嶌傝忋偘偨梊杊尨懃偲偄偆奣擮偼丄92擭抧媴僒儈僢僩偱嵦戰偝傟偨儕僆愰尵偺乽壢妛揑崻嫆偺寚擛偑娐嫬栤戣傊偺懳嶔傪抶傜偣傞尨場偵側偭偰偼側傜側偄乿偲偄偆暥尵偵昞傟偰偄傞捠傝丄娐嫬栤戣偵懳張偡傞嵺偺尨懃偲偟偰搊応偟偨丅僽儕僞儞暃埾堳挿偼偙偺梊杊尨懃偑晄昁梫偐偮夁忚側惌嶔傪惓摉壔偡傞偙偲偱丄杅堈惂尷慬抲傪壏懚偡傞尵偄栿偵巊傢傟傞偙偲傪寽擮偟偰偄傞丅堦曽丄娐嫬NGO偼丄嶐崱偺杅堈岎徛偵偐傜傓媍榑偺拞偱丄椺偊偽搳帒娐嫬惍旛乮奀奜搳帒曐岇偺偨傔偺儖乕儖嶌傝乯偑乽梊杊尨懃乿偵懃偭偰恦懍偵恑傔傜傟傞傋偒偩丄偲偄偆傛偆側宍偱娐嫬曐慡偱偼側偄暘栰偱棎梡偝傟巒傔偰偄傞偙偲傪斸敾偟偰偄傞丅
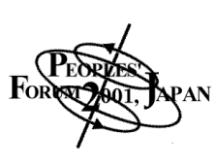
To: wto@jca.apc.org
Subject: [wto 112] FW: NGO Registration to attend Seattle WTO Ministerial Conference
Date: Tue, 13 Jul 1999 01:07:23 +0900
From: Tomoko Sakuma <tsakuma@jca.ax.apc.org>
MIME-Version: 1.0
Sender: owner-wto@jca.apc.org
X-Sequence: wto 112
Precedence: bulk
Reply-To: wto@jca.apc.org
WTO僔傾僩儖妕椈夛媍偵NGO僆僽僓乕僶乕偲偟偰嶲壛偡傞偨傔偺庤懕偒偺埬撪偱偡丅愭擔丄AM僱僢僩偺愳忋偝傫傕WTO-ML偵揮嵹偟偰偔傟偰偄傑偟偨偑丄儕僋僄僗僩偑偁傝傑偟偨偺偱丄嵞搙揮憲偟傑偡丅
嵅媣娫
> For those NGOs interested in NGO accreditatioin to the WTO
> Ministerial Conference in Seattle, please see the information below
> which describes the necessary procedure. You may also wish to visit
> the WTO website at <http://www.wto.org>, and click on
> "Non-Governmental Organizations".
>
> ______________________________________________________________
>
>
> NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
> FACILITIES PROVIDED TO ATTEND
> THE THIRD WTO MINISTERIAL CONFERENCE
>
>
> As time is running and representatives from Non Governmental
> Organizations need to prepare for their attendance at the third
> Ministerial Conference of the WTO to be held in Seattle from 30
> November to 3 December 1999, WTO Members have agreed on 15 June 1999
> to renew the same procedures for registration adopted for the two
> previous Ministerial Conferences held in Singapore (December 1996)
> and in Geneva (May 1998).
>
> Applications from NGOs to be registered will be accepted on the basis
> of ArticleV, paragraph2 of the WTO Agreement, i.e. such NGOs
> "concerned with matters related to those of the WTO".
>
> When addressing their request for registration to attend the Seattle
> Ministerial Conference, NGOs have to supply in detail all the
> necessary information showing how they are concerned with matters
> related to those of the WTO.
>
> To speed up the process for those NGOs who have been duly registered
> for and attended one of the following meetings: previous Ministerial
> Conferences (Singapore '96, Geneva '98) or the Symposia organized by
> the Secretariat in March 1999, their requests can be accompanied only
> by a shorter presentation of their activities and how they relate to
> those of the WTO. The reference of the meeting for which they have
> been granted registration and attended has to be mentioned.
>
> Requests for registration accompanied by the presentation of the NGO
> activities have to be sent by mail before 16August 1999 to:
>
> External Relations Division
> Centre William Rappard
> 154 rue de Lausanne
> 1211 Geneva 21
> Switzerland
>
> Please note that all registration forms are numbered and cannot be
> copied. They should be returned by mail with all the information
> requested and recent passport size photos attached to the External
> Relations Division as soon as possible and in any case not later
> than 15 September 1999. Incomplete requests will not be accepted.
>
>
> Confirmation of registration will be sent to NGOs as from 1 October
> 1999 after the list of NGOs having requested registration has been
> circulated to WTO Members.
>
> Upon confirmation of registration, badges will be made available in
> Seattle for entrance to the Plenary Sessions, entrance to the NGO
> Conference Centre, where facilities will be provided to all
> registered NGOs and participation in social events.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Observer status for international IGOs at the Seattle Ministerial
> Conference
>
>
> WTO Members have agreed on 15 June to invite International
> Intergovernmental Organizations (IGOs) as observers to the third WTO
> Ministerial Conference to be held in Seattle from 30November to
> 3December 1999 on the basis of the same guidelines adopted for the
> two previous Ministerial Conferences (Singapore '96 and Geneva '98):
>
> (a) organizations that are observers to the General Council will be
> automatically invited;
>
> (b) organizations that are observers to subsidiary bodies will be
> invited if they request to attend; and
>
> (c) consultations will be held to determine which other organizations
> that are not observers to the WTO and that request attendance at the
> Ministerial Conference should be invited.
>
>
> As provided in the Rules of Procedure for observer status of IGOs "if
> for any one-year period after the date of the grant of observer
> status, there has been no attendance by the observer organization,
> such status shall cease. In the case of sessions of the Ministerial
> Conference, this period shall be two years".
>
> Pursuant to this provision all organizations which have attended the
> Singapore and the Geneva Ministerial Conferences will upon request
> automatically be granted observer status at the 1999 Seattle
> Ministerial Conference.
>
> .
>
>
>
----------------------------------------------------------
Tomoko Sakuma
People's Forum 2001, Japan
Maruko-bld. 3F 1-20-6 Higashi-ueno
Taito-ku, Tokyo 110-0015 Japan
TEL +81-3-3834-2436
FAX +81-3-3834-2406
Email : tsakuma@jca.apc.org or pf2001jp@jca.apc.org
Website: http://www.jca.apc.org/pf2001jp/
----------------------------------------------------------
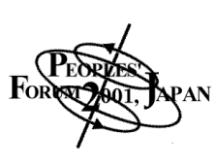
X-Sender: aosawa@po.jca.apc.org
Mime-Version: 1.0
Date: Fri, 2 Jul 1999 23:29:34 +0900
To: wto@jca.apc.org
From: aosawa@jca.apc.org (OSAWA,Akiko)
Subject: [wto 101] 僶僀僆僥僋僲儘僕乕娭楢忣曬 7/2
Sender: owner-wto@jca.apc.org
X-Sequence: wto 101
Precedence: bulk
Reply-To: wto@jca.apc.org
偙傟偐傜偱偒傞偩偗丄GENET儊乕儕儞僌儕僗僩偵棳傟偨拞偐傜彺栿偟偰棳偟偰偄偒偨
偄偲巚偄傑偡丅婎杮揑偵WTO偵娭學偡傞忣曬偵偟傑偡偑丄偦傟埲奜偱傕戝偒側塭嬁偺
偁傞摦偒偵偮偄偰偼庢傝偁偘傑偡丅
丂崱夞偼GOOD僯儏乕僗偲BAD僯儏乕僗偑奺2屄偱偡丅
丂丂傕丂偔丂偠
仛EU丄GMO乮堚揱巕慻傒姺偊嶌暔乯偺怴婯擣壜傪搥寢仛
仛惗暔懡條惈忦栺丄僞乕儈僱乕僞乕丒僥僋僲儘僕乕偵懺搙傪寛傔傜傟偢仛
仛僐乕僨僢僋僗埾堳夛丗媿惉挿儂儖儌儞乮rBGH乯偺崙嵺婯弨丄嵦戰偝傟偢仛
仛乽娐嫬偵傗偝偟偄乿堚揱巕慻傒姺偊僽僞丠丠両仛
------------------------------------------
仛EU丄GMO乮堚揱巕慻傒姺偊嶌暔乯偺怴婯擣壜傪掆巭仛
丂乧GMO嬛巭偵岦偗偨寛掕懪丅擔杮偺怴暦傕偐側傝曬摴偟偰偄傑偟偨丅
------------------------------------------
丂EU偼6寧24擔丄尩偟偄娐嫬婎弨偑摫擖偝傟傞傑偱偼丄儓乕儘僢僷堟撪偱崱屻偄偭偝
偄丄怴偨側彜嬈梡GMO傪擣壜偟側偄偙偲傪寛掕偟偨丅崅傑傞徚旓幰偺晄埨偵墳偊丄梊
杊尨懃偵傕偲偯偄偨敾抐偩丅寛掕偵偁偨偭偰偼僼儔儞僗丄僪僀僣偑婙怳傝栶偵側傝丄
僀僞儕傾丄僨儞儅乕僋丄儖僋僙儞僽儖僌側偳偑愊嬌揑偵巟帩偟偨丅偙偺擣壜掆巭偼丄
彮側偔偲傕2002擭傑偱堐帩偝傟傞偲僌儕乕儞僺乕僗偼尒偰偄傞丅側偍丄尰嵼怽惪拞偺
GMO偼偡傋偰丄EU偺擣壜僾儘僙僗偺梫審傪枮偨偟偰偄側偄偙偲偱丄僗僩僢僾偝傟偰偄傞丅
丂儕僢僩丒價僄儖僑乕EU娐嫬扴摉埾堳偼丄偙偺慬抲偵娭偟偰偨偲偊WTO偱朄揑偵慽偊
傜傟偰傕丄EU偼彑偮偲帺怣傪尒偣偰偄傞丅
乮嶲峫丗"Tell the World we have a GMO Moratorium!", Steve Emmott, 6/24/99)
------------------------------------------
仛惗暔懡條惈忦栺丄僞乕儈僱乕僞乕丒僥僋僲儘僕乕偵懺搙傪寛傔傜傟偢仛
------------------------------------------
丂6寧拞弡偵儌儞僩儕僆乕儖偱奐嵜偝傟偨丄惗暔懡條惈忦栺偺曗彆婡娭乽SBSTTA乮壢
妛揑媦傃媄弍揑彆尵偺偨傔偺曗彆婡娭乯乿夛崌偱丄僞乕儈僱乕僞乕丒僥僋僲儘僕乕乮
壓婰嶲徠丅惗暔懡條惈忦栺偱偺惓幃柤偼丄乽GURTs丗Genetic Use Restriction Techn
ologies乿乯偵娭偡傞寛媍偑嵦戰偝傟偨丅偟偐偟丄寛媍偼旕忢偵庬昪夛幮婑傝偺撪梕
偲側傝丄NGO懁偼僔儑僢僋傪塀偣側偄偱偄傞丅
丂岎徛偱偼傑偢僲儖僂僃僀惌晎偑丄GURTs偺幚尡嵧攟偍傛傃彜嬈壔偵懳偡傞儌儔僩儕
傾儉寛媍傪採埬丅偙傟偵懳偟丄傾僕傾丄傾僼儕僇丄拞撿暷偺崙乆偑巀惉丄傾儊儕僇偲
僇僫僟偼嫮峝偵斀懳偟偨丅偦偺屻丄僀僊儕僗偑懨嫤埬亅亅儌儔僩儕傾儉偱偼側偄偑丄
寢壥揑偵彜嬈壔偺嬛巭偵偮側偑傞埬亅亅傪弌偟偨丅偙偺擇偮偼偦傟側傝偵昡壙偱偒傞
傕偺偩偑丄彮悢偺僌儖乕僾偱偺枾幒偱偺岎徛偺偺偪丄側偤偐嵟廔揑偵寛媍偼丄奺崙惌
晎偼幚尡嵧攟偲彜嬈壔偺嬛巭傪峴偭偰傕傛偄乮偟偐偟杮摉偵嬛巭偡傞偲丄WTO儖乕儖
偺壓偱杅堈忈暻偱偁傞偲傒側偝傟傞嫲傟偑偁傝儕僗僋偑崅偄乯丄偲偄偆丄儃儔儞僞儕
乕儀乕僗偺撪梕偵傑偱堷偒壓偘傜傟偰偟傑偭偨丅枾幒偱偼丄僆乕僗僩儕傾側偳偺GMO
桝弌崙僌儖乕僾乽儅僀傾儈丒僌儖乕僾乿偑丄寛媍偺撪梕傪崪敳偒偵偟偨偲巚傢傟偰偄傞丅
丂僞乕儈僱乕僞乕丒僥僋僲儘僕乕偵懳偡傞斀懳塣摦傪揥奐偟偰偄傞NGO丄RAFI乮崙嵺
擾懞敪揥嵿抍乯偼丄乽亀帺崙偺揤慠帒尮偵懳偡傞崙偺庡尃亁乮摨忦栺15忦-1乯傪曐忈
偟偰偄傞惗暔懡條惈忦栺偑丄偦偺庡尃傪怤奞偡傞GURTs偵懳偟偰偒偪傫偲棫応傪昞柧
偱偒側偄側傜丄偄偭偨偄懠偺偳偙偑偱偒傞偺偐丠乿乽偙偺寛媍偼丄摨忦栺偺怣棅惈傪
挊偟偔棊偲偟偨乿偲斸敾偟偰偄傞丅乮嶲峫丗"Biodiversity Convention's Terminato
r Decision Fails Biodiversity and Fails Farmers",RAFI,6/29/99)
仸僞乕儈僱乕僞乕丒僥僋僲儘僕乕
丂撆慺堚揱巕傪慻傒崬傓偙偲偵傛偭偰丄庬昪夛幮偐傜攦偭偨庬巕偐傜偱偒偨庬巕傪擾
壠偑帺壠嵦庬偟偰嵞傃傑偄偨偲偒偵偼丄敪夎偟側偄傛偆偵偡傞媄弍丅暷婇嬈偺僨儖僞
仌僷僀儞儔儞僪幮乮屻偵儌儞僒儞僩偑攦廂乯偲暷擾柋徣偺嫟摨奐敪偱惗傒弌偝傟丄偦
偺屻丄摨條偺媄弍傪僀僊儕僗偺僛僱僇幮傕奐敪偟偨丅
丂婇嬈偺庬巕巟攝偺嫮壔乮摿偵帺壠嵦庬偑懡偄搑忋崙偺擾柉傊偺塭嬁偑戝乯傗丄惗懺
宯傊偺塭嬁偑偁傞偲偟偰丄NGO偺嫮偄斀懳偑婲偒偰偄傞丅乮僶僀僥僋偲椢偺妚柦偺悇
恑懁偱偁傞儘僢僋僼僃儔乕嵿抍偱偡傜丄偮偄嵟嬤丄儌儞僒儞僩偺棟帠夛偵懳偟丄偙偺
媄弍偺彜嬈壔僾儔儞傪曻婞偡傞傛偆媮傔偰偄傞丅乯
------------------------------------------
仛僐乕僨僢僋僗埾堳夛丗媿惉挿儂儖儌儞乮rBGH乯偺崙嵺婯弨丄嵦戰偝傟偢仛
------------------------------------------丂
丂乧EU偺rBGH媿擏桝擖嬛巭堐帩乮[wto 97]乯偵懕偔僌僢僪僯儏乕僗丅
丂儘乕儅偱奐嵜偝傟偨僐乕僨僢僋僗埾堳夛偵偍偄偰丄rBGH偺嵟戝巆棷検傪掕傔傞崙嵺
婯弨偺嵦戰偑尒憲傜傟偨丅偙傟偵傛偭偰丄奺崙偑傛傝掅偄婎弨抣傪撈帺偵掕傔偨傝桝
擖嬛巭偟偨傝偡傞偙偲偑壜擻偵側傞丅
丂偙傟傑偱丄僐乕僨僢僋僗偱婯弨傪嵦戰偡傞偙偲傪傾儊儕僇偑嫮偔庡挘偟偰偍傝丄崱
夞傕EU偲偺娫偱挿偄榑憟偑峴傢傟傞偲梊應偝傟偰偄偨丅偟偐偟崱夞傾儊儕僇偼丄僐儞
僙儞僒僗偑摼傜傟側偄偲憗乆偵敾抐偟丄乽婯弨傪嵦戰偟側偄乿偙偲傪採埬丄奺崙傪嬃
偐偣偨丅110儢崙245偺徚旓幰抍懱偐傜側傞崙嵺徚旓幰婡峔乮CI乯偼丄乽傕偟婯弨偑嵦
戰偝傟傟偽丄rBGH偺埨慡惈偑徹柧偝傟偨偙偲偵側傝丄尰嵼奺崙偑峴偭偰偄傞rBGH巊梡
偺擕惢昳偺桝擖嬛巭偑杅堈忈暻偱偁傞偲偟偰WTO偵帩偪崬傑傟傞偲偙傠偩偭偨乿偲丄
偙偺寛掕傪娊寎偟偰偄傞丅
乮嶲峫丗"Countries free to set own standards on BST residues in food",
Consu
mer International, by Michael Hansen, 6/30/99丂傛傝徻偟偄忣曬偼営http://www.
consumersinternational.org/campaigns/food乯
仸媿惉挿儂儖儌儞乮rBGH乯
丂傾儊儕僇偱巊梡偝傟偰偄傞崌惉儂儖儌儞嵻丅媿偺旍堢懀恑丒擏傪傗傢傜偐偔偡傞丒
擕検憹壛側偳傪栚揑偵巊傢傟傞丅摨帪偵峈惗暔幙傪戝検偵搳梌偡傞偙偲傗丄儈儖僋偵
rBGH偑崿偠傝丄堸傫偩恖偵傾儗儖僊乕傗儂儖儌儞堎忢傪堷偒婲偙偡側偳偺栤戣偑偁傞
丅EU偩偗偱側偔丄僇僫僟傕嵟嬤丄儌儞僒儞僩偺rBGH擣壜怽惪傪媝壓偟偰偄傞丅傾儊儕
僇偺擾壠偺15%偑巊梡丅擔杮偱偼側傫偺婯惂傕側偄丅乮嶲峫亀堚揱巕慻傒姺偊怘昳Q&A
亁埨揷愡巕挊乯
丂
------------------------------------------
仛乽娐嫬偵傗偝偟偄乿堚揱巕慻傒姺偊僽僞丠丠両仛
------------------------------------------
丂僇僫僟偺壢妛幰偑丄儅僂僗偲僶僋僥儕傾偺堚揱巕傪慻傒偙傫偩丄儓乕僋僔儍乕庬偺
乽娐嫬偵傗偝偟偄僽僞丗Enviropig乿傪奐敪偟偨偲敪昞偟偨丅
丂偙偺僽僞偺暢偼丄廬棃偺僽僞偺暢偵斾傋偰丄壨愳墭愼偺尨場偲側傞儕儞偺娷桳検偑
20乣50%彮側偄偲偄偆丅娐嫬栤戣傪夝寛偡傞偙偲傪栚揑偵偮偔傜傟偨堚揱巕慻傒姺偊
摦暔偼丄偙傟偑弶傔偰偲巚傢傟傞丅偟偐偟丄傕偪傠傫恀偺慱偄偼丄乽尰嵼丄儓乕儘僢
僷丄傾僕傾偺堦晹丄杒暷偱丄僽僞偺帞堢悢偺憹壛傪朩偘偰傞偺偼儕儞偵懳偡傞婯惂丅
儕儞偑50%彮側偄暢傪弌偡僽僞側傜丄廬棃偺攞偺摢悢傪帞堢偟偰傕娐嫬婎弨傪僋儕傾
偱偒傞乿偲偄偆偲偙傠偩乮奐敪偟偨Guelp戝妛偺僕儑儞丒僼傿儕僢僾嫵庼帺恎偺尵梩
乯丅帠幚丄偙偺奐敪帒嬥27枩僪儖傪採嫙偟偨偺偼乽僆儞僞儕僆梴撠擾壠巗応楢柨乿偱
丄摨楢柨偑乽Enviropig乿偺撈愯儔僀僙儞僗尃傪帩偭偰偄傞丅彜嬈壔偵偼丄嵟掅4擭娫
偐偐傞傒偙傒丅
(嶲峫丗"Environmental Friendly Pigs???",from Yahoo News: http://dailynews.ya
hoo.com/headlines/sc/story.html?s=v/nm/19990624/sc/canada_pigs_1.html, 6/24/99乯
--------------
戝郪徎巕<aosawa@jca.apc.org>
巗柉僼僅乕儔儉2001
仹110-0015丂搶嫗搒戜搶嬫搶忋栰1-20-6丂娵岾價儖3奒
TEL. 03-3834-2436 FAX. 03-3834-2406
http://www.jca.apc.org/pf2001jp/
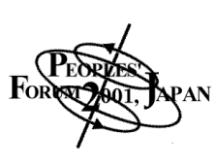
To: wto@jca.apc.org
Subject: [wto 97] WTO 娭楢忣曬丂 99/5丂 Vol.1
Date: Fri, 2 Jul 1999 14:12:02 +0900
From: Tomoko Sakuma <tsakuma@jca.ax.apc.org>
MIME-Version: 1.0
Sender: owner-wto@jca.apc.org
X-Sequence: wto 97
Precedence: bulk
Reply-To: wto@jca.apc.org
憡曄傢傜偢忣曬偑彮偟屆偔偰嵪傒傑偣傫丅
偲偙傠偱丄嶐擔憲晅偟偨擾嬈丒椦悈嶻嬈偵娭偡傞擔杮採埬偺崪巕偼丄PDF僼傽僀儖偵側偭偰偄傞偨傔丄夋憸偲偟偰庢傝崬傑傟偰偍傝丄暥帤偲偟偰擣幆偱偒傑偣傫丅傾僋儘僶僢僩偲偄偆夝撉僜僼僩偑昁梫偱偡乮偙傟偼擾悈偺僂僃僢僽懠丄懡偔偺僂僃僢僽偱柍椏偱僟僂儞儘乕僪偱偒傑偡乯丅偱偡偐傜丄偙偪傜偐傜偼揧晅偺PDF僼傽僀儖偲偄偆曽朄埲奜偼儊乕儖偡傞庤抜偑側偐偭偨偨傔丄旕忢庤抜偲偟偰偙偺傛偆側傗傝曽傪偟傑偟偨丅偙偪傜偐傜偺揧晅帒椏傕丄擾悈偺僂僄僢僽偺傕偺傕偆傑偔奐偗側偄丄偁傞偄偼暥帤壔偗偟偰偄傞丄偲偄偆曽偱丄偳偆偟偰傕擖庤偟偨偄曽偼丄擾悈徣崙嵺宱嵪壽偵捈愙梄憲偟偰傕傜偆傛偆偍婅偄偟偰傒偰偼偳偆偱偟傚偆偐丅
嵅媣娫
WTO娭楢忣曬丂99/5丂Vol.1
栚師丗
仭墷廈楢崌乮EU乯丄惉挿儂儖儌儞媿擏偵懳偡傞桝擖嬛巭傪宲懕
仭儀儖僊乕丄僀僞儕傾丄僨儞儅乕僋偺奐敪NGO偑EU偺怘椘惌嶔傪斸敾
仭偦偺懠偺NGO偺摦偒
仭墷廈楢崌乮EU乯丄惉挿儂儖儌儞媿擏偵懳偡傞桝擖嬛巭偺堐帩傪敪昞
丂惉挿儂儖儌儞媿擏偼敪僈儞惈暔幙偱偁傞偲偺EU壢妛埾堳夛偺堄尒傪庴偗丄EU偼5寧4擔丄媿惉挿儂儖儌儞傪巊梡偟偰旍堢偝傟偨媿擏偺桝擖嬛巭慬抲偺宲懕傪寛掕偟偨丅EU壢妛埾堳夛偼丄6庬偺儂儖儌儞乮17庬偺僄僗僩儘僎儞丄2庬偺揤慠儂儖儌儞丄3庬偺崌惉儂儖儌儞乕Zeranol,
Trenbolone, Melengestrol acetate乯偵偮偄偰帋尡傪峴偄丄17庬偺僄僗僩儘僎儞乮Beta oestradiol乯偑柧傜偐偵乽敪僈儞惈暔幙乿偱偁傞偲寢榑偯偗偨丅埾堳夛偼丄暷崙偵偍偗傞擕僈儞傗慜棫態僈儞偺敪徢棪偲暷崙嶻媿擏偵巆棷偡傞儂儖儌儞偲偑憡娭偟偰偄傞壜擻惈傗丄偙傟傜偺儂儖儌儞偑堚揱巕傗柶塽宯丄恄宱宯偵埆塭嬁傪梌偊傞壜擻惈傕巜揈偟偨丅
丂偙偺桝擖嬛巭慬抲偼WTO忋媺埾堳夛乮僷僱儖乯偺嵸掕乮1998擭1寧乯偵傛偭偰揚夞傪敆傜傟偰偄傞偨傔丄堦扷嵸掕偑弌偨學憟働乕僗偵偮偄偰丄怴偨側壢妛揑崻嫆偑弌偰偒偨応崌偵丄偦偺幚巤媊柋傪偳偆夞旔偡傞偐偑崱屻偺墷廈媍夛偺壽戣偲側傞丅
丂偙傟偵懳偟丄暷捠彜戙昞晹乮USTR乯偺擾嬈扴摉岎徛姱丄僺乕僞乕丒僔儍乕巵偼丄WTO忋媺埾堳夛偺嵸掕偵偟偨偑偭偰EU偑桝擖嬛巭傪揚夞偟側偗傟偽丄塿900枩僪儖婯柾乮栺10壄墌乯偺曬暅娭惻傪壽偡偲偄偆巔惃傪夵傔偰柧妋偵偟丄EU懁偑暷崙偵懳偡傞懝幐曗彏傪恀寱偵専摙偟偰偄側偄偲偟偰偄傜偩偪傪尒偣偨丅乮偦偺屻丄暷崙偼WTO暣憟夝寛僷僱儖偵202枩僪儖乮栺2壄4000枩墌乯偺曬暅慬抲傪媮傔偰採慽丄7寧拞偵嵸掕偑弌偝傟傞梊掕丅乯僔儍乕巵偼丄偙偺EU壢妛埾堳夛偺挷嵏寢壥偵偮偄偰丄暷媍夛偺岞挳夛偵偍偄偰乽僀儞僠僉乿偱偁傞偲徹尵偟丄僌儕僢僌儅儞擾柋挿姱偲僶乕僔僃僼僗僉捠彜戙昞偺嫟摨惡柧偱傕摨條偺尒夝偑帵偝傟偰偄傞丅
丂EU偼4寧28擔丄偙偺桝擖嬛巭偺懳徾偵6寧15擔傛傝暷崙偐傜偺儂儖儌儞丒僼儕乕乮儂儖儌儞傪巊梡偟偰偄側偄乯媿擏傕娷傔傞偲敪昞偟偨丅EU懁偺僒儞僾儖挷嵏偵傛傞偲丄儂儖儌儞丒僼儕乕偲偟偰EU偵桝擖偝傟偰偄傞暷崙嶻媿擏偺栺12亾偐傜儂儖儌儞巊梡偺嵀愓偑敪尒偝傟偰偍傝丄崱屻偼僒儞僾儖挷嵏傪100亾偵奼戝偡傞傛偆搘椡偡傞偲偟偰偄傞丅暷崙偼EU偵懳偟丄惉挿儂儖儌儞媿擏偺嬛桝偵懳偡傞曗彏偲偟偰丄儂儖儌儞丒僼儕乕媿擏偵懳偡傞婜娫尷掕偺悢検婯惂榞偺奼戝傪媮傔偰偒偨丅傾儞僨傿丒僜儘儌儞捠彜戙昞晹峀曬扴摉偼EU偺敪昞傪庴偗偰摨擔丄EU偲暷崙偼乽EU偑暷崙偐傜栺2500枩僪儖偵憡摉偡傞儂儖儌儞丒僼儕乕媿擏偺桝擖傪懕偗傞乿偲偺壖崌堄偑偁傞偲敪昞偟丄偙偺栤戣偼乽怘椏埨慡惈傗寬峃偺栤戣偲偼壗偺娭學傕側偄乿偲弎傋偨丅EU懁偼偙偺壖崌堄偺懚嵼傪斲掕偟偰偄傞丅
丂EU偼尰嵼丄惉挿儂儖儌儞媿擏偵懳偟偰儔儀儕儞僌傪媊柋偯偗傞偲偄偭偨懪奐嶔傪採埬偟偰偄傞偑丄乽桝擖偑嬛偠傜傟偰偄傞惢昳偵偮偄偰儔儀儕儞僌傪専摙偡傞偺偼柍堄枴乮僶乕僔僃僼僗僉捠彜戙昞乯乿偲偟偰暷崙偼偙傟偵墳偠偰偄側偄丅
嶲峫丗UE: pas de lavTe de l'embargo sur le boeuf auz hormones, Le Monde, Mardi 4,
1999
Agriculture U.S. Sees Little Chance of Setting Dispute With EU Over Beef Imports
as Talks Collapse, by Gary G. Yerkey and Bengt Ljung, International Trade Report,
Vol 16 No.18 May 5, 1999, The Bureau of National Affairs, Inc., Washington, D.C.
仭仭儀儖僊乕丄僀僞儕傾丄僨儞儅乕僋偺奐敪NGO偑EU偺怘椘惌嶔傪斸敾
丂4寧15-17擔偵僽儕儏僢僙儖偱奐嵜偝傟偨墷廈奐敪NGO憤夛偼丄WTO傗CAP乮EU嫟捠擾嬈惌嶔乯丄儘儊嫤掕側偳偵偍偗傞EU偺惌嶔傪斸敾偟丄NGO懁偺梫朷傪傑偲傔偨愰尵傪嵦戰偟偨丅梫朷偺撪梕偼埲壓偺捠傝丟
1.丂愭恑崙偺擾嬈桝弌偵懳偡傞曗彆嬥傪嬛巭偡傞偙偲丅偙偺傛偆側曗彆嬥偼朙偐側杒偺崙乆偑梋忚怘椘傪奀奜偵僟儞僺儞僌桝弌偡傞偙偲傪彆挿偟丄悽奅偺怘椏壙奿傪掅柪偝偣丄寢壥偲偟偰搑忋崙偺彫婯柾擾壠偵懡戝側旐奞傪梌偊傞丅
2.丂乽僨僇僢僾儕儞僌乿強摼曗彏傪娷傓丄偁傜備傞宍偺僟儞僺儞僌傪嬛巭偡傞偙偲丅偙傟偵傛傝晄岞惓側崙嵺嫞憟丄傑偨偼帩懕晄壜擻側惗嶻僷僞乕儞傪夞旔偡傞偙偲偑偱偒傞丅
3.丂擾嬈惗嶻偺婯柾偵墳偠偰曗彆嬥傪弌偡側偳偺CAP偺桝弌巜岦傪惓偟丄幮夛丒娐嫬丒宱嵪柺偐傜彫婯柾偱帩懕壜擻側擾嬈傪昡壙偟丄怳嫽偡傞傛偆惌嶔傪曄峏偡傞偙偲丅
4.丂EU巗応偵懳偡傞搑忋崙偺傾僋僙僗傪夵慞偡傞偙偲丅搑忋崙偵懳偟丄峆忢揑側掅娭惻傪曐忈偟丄悢検婯惂丒婫愡揑婯惂丒偦偺懠偺旕娭惻忈暻丒壛岺昳偵懳偡傞崅娭惻乮僞儕僼丒僄僗僇儗乕僔儑儞乯傪揚攑偟丄偝傜偵2000擭傛傝嵟昻崙偐傜偺擾嶻暔傪娷傓慡偰偺桝擖昳傪旕娭惻偲偡傞偙偲丅
5.丂搑忋崙偍傛傃弮怘椏桝擖崙偵懳偟丄擾嬈僙僋僞乕偺曐岇傪捠偠偨帺媼棪偺岦忋傪梕擣偡傞偙偲丅偮傑傝偼丄WTO偺儈僯儅儉丒傾僋僙僗梫媮丄娭惻壔丄娭惻堷偒壓偘偺揔梡傪柶彍偟丄帺媼棪偺岦忋偺偨傔偺崙撪擾嬈巟帩傪梕擣偡傞偙偲丅
6.丂WTO偵偍偗傞嵟昻崙偺曐岇丅嵟昻崙偑岎徛偡傞庡尃傪懜廳偟丄怘椏弮桝擖崙偱偁傞嵟昻崙偵偮偄偰偺儅儔働僔儏墖彆嫤掕傪幚峴偵堏偡偙偲偱丄嵟昻崙偑崙撪偺彫婯柾擾壠傪墖彆偡傞擻椡傪崅傔傞偙偲丅
7.丂嵟昻崙偵懳偟偰偼丄儘儊嫤掕偺傛偆側屳宐揑偱偼側偄摿宐懸嬾偺晅梌傪梕擣偡傞偙偲丅
8.丂偮傑傝乮TRIPs27忦3B側偳偱婯掕偟偰偄傞乯惗暔摿嫋乮僶僀僆丒僷僀儔僔乕乯丄偍傛傃嵞惗晄擻側庬巕乮僞乕儈僱乕僞乕媄弍乯偺奐敪傪嬛巭偡傞偙偲偱丄堚揱巕帒尮偵懳偡傞奺崙偺庡尃傪曐忈偡傞偙偲丅
9.丂崙嵺婎弨傛傝傕崅偄婎弨傪崙柉偑朷傫偩応崌偵偼丄惌晎偑摦怉暔偺惗柦偵娭偡傞崅偄崙撪婎弨傪掕傔傞偙偲傪梕擣偡傞偙偲丅
10.丂娐嫬丒幮夛揑偵帩懕晄壜擻側宍偱乮偐偮楯摥幰偺尃棙傪側偄偑偟傠偵偟偨乯惗嶻偵傛偭偰丄惗嶻僐僗僩傪壓夞傞埨偄壙奿偱峴傢傟傞彜庢堷傪WTO儖乕儖偵傛偭偰慾巭偡傞偙偲丅
11.丂抧堟巗応偵偍偗傞抧堟撪偺擾嬈惗嶻偺嫞憟傪彠椼偟丄偙傟傪堦帪揑偵崙嵺嫞憟偐傜曐岇偡傞偙偲丅
12.丂慡偰偺恖乆偑怘椏傪摼傞偲偄偆婎杮揑尃棙乮怘椏庡尃乯傪曐忈偡傞崙嵺朄惂搙傪嫮壔偡傞偙偲丅
13.丂WTO偺堄巚寛掕偵搑忋崙惌晎偑幚幙揑偐偮岞暯側宍偱嶲壛偱偒傞傛偆丄偦偟偰NGO傗楯摥慻崌丄擾柉慻怐丄彈惈抍懱側偳偺幮夛丒柉廜塣摦抍懱偺嶲壛傪懀偡偙偲偱丄WTO傪柉庡壔偡傞偙偲丅
14.丂CAP夵妚偑搑忋崙偵梌偊傞塭嬁傪揔愗偵昡壙偟丄偦偺埆塭嬁傪庴偗傞搑忋崙偵懳偟偰巟墖傪峴偆偙偲丅
15.丂ACP乮傾僼儕僇丒僇儕僽丒懢暯梞廈偺彅崙乯偵懳偟丄傾僕僃儞僟2000偵傛傞CAP夵妚偱旐傞懝奞傪曗彏偡傞偙偲丅
16.丂搑忋崙偺怘椏埨慡曐忈偲偄偆栤戣偑WTO儖乕儖偵揔愗偵斀塮偝傟傞傛偆丄APC彅崙傗偦偺懠偺搑忋崙惌晎偲偺嫤媍傪奐巒偡傞偙偲丅
17.丂EU擾嬈帎栤埾堳夛偍傛傃擾嬈惌嶔寛掕儊僇僯僘儉偵丄奐敪丒娐嫬丒徚旓幰丒彫婯柾壠懓擾壠偺岞幃偍傛傃旕岞幃側戙昞傪擖傟傞偙偲丅
晹暘栿丗EU policies on agricultural trade (WTO, CAP and Lom Food Security must come
before commercial interests, The General Assembly of European Development NGOs' meeting
in Brussels on 15,16 and 17 April 1999
仭偦偺懠偺NGO偺摦偒
1.丂奐敪抍懱偵娭偡傞悽奅嫵夛楢崌乮APRODEV乯丗4寧18乕22偵擾嬈偲杅堈惌嶔丄偦偟偰WTO偲儘儊嫤掕偑嵟昻崙偺怘椏埨慡曐忈偵傕偨傜偡塭嬁偵偮偄偰榖偟崌偆廤夛傪奐嵜丅傾僼儕僇丄傾僕傾丄拞撿暷丄偍傛傃墷廈偺57儢崙偐傜偺嶲壛幰傜偑嵦戰偟偨愰尵暥偱偼乽WTO擾嬈嫤掕偺曪妵揑側塭嬁昡壙傪幚巤偡傞偨傔偵崱屻彮側偔偲傕2擭娫偼丄師婜岎徛傪搥寢偡傞乿傛偆梫媮偟偰偄傞丅
乮Contact; Robert W.F.Van Drimmelen 亙aprodev@skynet.be亜)
2.丂僔僄儔僋儔僽偲慡暷栰惗惗暔楢柨乮NWF乯丗暷惌尃偵懳偟偰乽White Paper on Environmentally
Responsible Trade Negotiating Authority乿乮娐嫬柺偱偺愑擟傪壥偨偣傞杅堈岎徛尃尷偵娭偡傞敀彂乯傪敪峴丄柉庡揑偐偮愢柧愑擟傪壥偨偟偆傞杅堈岎徛尃尷偺怴偨側偁傝曽偵偮偄偰採埬偟偰偄傞丅偦偺拞偱偼丄暷媍夛偑乽崙嵺杅堈偵娭偡傞摿暿埾堳夛乿傪憂愝偟丄杅堈栤戣偵娭偡傞岞挳夛傪奐嵜偱偒傞傛偆偵偡傞偙偲傪採埬偟偰偄傞丅偙偺摿暿埾堳夛偵偼丄崙嵺彜庢堷偺懀恑傪扴摉偟偰偄傞楢朚惌晎晹嬊偩偗偱側偔丄娐嫬曐慡傗徚旓幰偺曐岇偲埨慡丄偍傛傃楯摥幰尃棙側偳傪扴摉偟偰偄傞晹嬊傕嶲壛偝偣傞傛偆媮傔偰偄傞丅
乮Contact; John Audley at NWF 亙audley@nwf.org亜
3.丂崙嵺帺桼楯楢乮ICFTU乯丗1999擭3寧偵WTO杮晹偱奐嵜偝傟偨僴僀儗儀儖丒僔儞億僕僂儉偱偼乽Development,
Environment and Trade乿偲偄偆惡柧傪敪昞丄WTO偵懳偟偰楯摥婎弨偺弲庣傪杅堈儖乕儖偺拞偵埵抲偯偗傞傛偆梫惪偟懕偗偰偄傞丅
乮Contact; James Howard at Employment and International Labour Standards, International
Confederation of Free Trade Unions 亙howard@icftu.org亜
4.丂撿丒搶傾僼儕僇杅堈忣曬丒岎徛僀僯僔傾僥傿僽乮SEATINI乯丟撿晹偍傛傃搶晹傾僼儕僇彅崙偺杅堈岎徛扴摉幰傜偑廤傑傝丄尰峴偺杅堈儖乕儖傗崱屻偺杅堈岎徛偵娭偡傞忣曬丒堄尒岎姺傪峴偭偰偄偔拞偱傾僼儕僇彅崙偺嫟捠億僕僔儑儞傪扵偭偰偄偔帋傒丅戞擇夞夛崌偼3寧4乕9擔偵僂僈儞僟偺庱搒僇儞僷儔偱奐嵜偝傟偨丅
乮愰尵暥傪婓朷偺曽偼嵅媣娫傑偱亙tsakuma@jca.apc.org亜丄Contact; Dr.Yash Tandon at
International South Group Network <ytandon@harare.iafrica.com>
5.丂僌儘乕僶儕僛乕僔儑儞偵娭偡傞崙嵺僼僅乕儔儉乮IFG乯丗悽奅偺妶摦壠丄妛幰丄宱嵪妛幰丄尋媶幰丄嶌壠側偳60柤偐傜側傞摨僼僅乕儔儉偼丄僌儘乕僶儖壔傪墴偟恑傔偰偄傞尰嵼偺崙嵺惌帯宱嵪偺偁傝曽偵懳偟偰丄偦傟偵戙傢傞怴偨側巚憐傗嫟摨峴摦丄巗柉嫵堢側偳傪幚巤偟偰偒偨丅偦偟偰WTO僔傾僩儖妕椈夛媍偺婜娫拞偵偄偔偮偐偺僀儀儞僩乮僙儈僫乕丄僔儞億僕僂儉丄愴棯夛媍側偳乯傪婇夋偟偰偄傞丅
乮Contact; 亙ifg@ifg.org亜乯
----------------------------------------------------------
Tomoko Sakuma
People's Forum 2001, Japan
Maruko-bld. 3F 1-20-6 Higashi-ueno
Taito-ku, Tokyo 110-0015 Japan
TEL +81-3-3834-2436
FAX +81-3-3834-2406
Email : tsakuma@jca.ax.apc.org or pf2001jp@jca.ax.apc.org
Website: http://www.jca.apc.org/pf2001jp/
----------------------------------------------------------
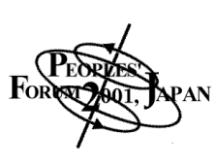
To: wto@jca.apc.org
Subject: [wto 88] WTO 師婜岎徛偵懳偡傞擔杮惌晎偺棫応
Date: Wed, 30 Jun 1999 19:05:29 +0900
From: Tomoko Sakuma <tsakuma@jca.ax.apc.org>
MIME-Version: 1.0
Sender: owner-wto@jca.apc.org
X-Sequence: wto 88
Precedence: bulk
Reply-To: wto@jca.apc.org
6寧17擔偵婰幰敪昞偝傟偨擔杮惌晎偺WTO師婜岎徛偵懳偡傞億僕僔儑儞乮擾嬈丄椦嶻暔丒悈嶻暔乯偑擾悈徣偺僂僄僢僽忋偱僟僂儞儘乕僪偱偒傑偡丅亙http://www.maff.go.jp/wto/wto00.html亜丂偨偩偟丄媄弍揑側儈僗偵傛傝丄僱僢僩僗働乕僾偱偼偦偺儁乕僕偩偗峴偔偙偲偑偱偒側偄忬懺偵側偭偰偄傑偡丅
擾嬈偺乽採埬崪巕乿偵偮偄偰偼PDF僼傽僀儖傪揧晅偟傑偡丅
嵅媣娫
----------------------------------------------------------
Tomoko Sakuma
People's Forum 2001, Japan
Maruko-bld. 3F 1-20-6 Higashi-ueno
Taito-ku, Tokyo 110-0015 Japan
TEL +81-3-3834-2436
FAX +81-3-3834-2406
Email : tsakuma@jca.ax.apc.org or pf2001jp@jca.ax.apc.org
Website: http://www.jca.apc.org/pf2001jp/
----------------------------------------------------------
揧晅彂椶傪曄姺: Macintosh HD:WTO990~2.PDF (TEXT/dosa) (000095C5)
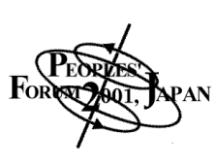
To: wto@jca.apc.org
Subject: [wto 87] StopWTORound 儊乕儕儞僌儕僗僩偺偛埬撪
Date: Wed, 30 Jun 1999 17:57:22 +0900
From: Tomoko Sakuma <tsakuma@jca.ax.apc.org>
MIME-Version: 1.0
Sender: owner-wto@jca.apc.org
X-Sequence: wto 87
Precedence: bulk
Reply-To: wto@jca.apc.org
WTO師婜岎徛偺奐巒偵斀懳偡傞巗柉丒NGO偺儊乕儕儞僌儕僗僩偲偟偰崱寧巒傑偭偨儊乕儕儞僌儕僗僩偺徯夘偱偡丅乮扐偟丄崙嵺ML側偺偱撪梕偼慡偰塸暥偱偡乯丅
嵅媣娫
StopWTORound [English] [For People Over 10] [moderated]
This mailing list has been created to facilitate a global campaign opposing a Millenium
Round
or a new Round of comprehensive trade negotiations within the World Trade Organisation.
Signatories are calling for a moratorium on negotiating any new issues, whilst the
existing
agreements are reviewed and rectified. The mailing list's primary purpose is to facilitate
strategy development and information exchange between signatories to and sympathisers
with the"STATEMENT FROM MEMBERS OF INTERNATIONAL CIVIL SOCIETY OPPOSING A MILLENNIUM
ROUND OR A NEW ROUND OF COMPREHENSIVE TRADE NEGOTIATIONS." To transfer to the
joint statement please click on the informational link address.
For more information, http://antenna.nl/aseed/trade/index.html
----------------------------------------------------------
Tomoko Sakuma
People's Forum 2001, Japan
Maruko-bld. 3F 1-20-6 Higashi-ueno
Taito-ku, Tokyo 110-0015 Japan
TEL +81-3-3834-2436
FAX +81-3-3834-2406
Email : tsakuma@jca.ax.apc.org or pf2001jp@jca.ax.apc.org
Website: http://www.jca.apc.org/pf2001jp/
----------------------------------------------------------
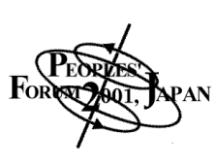
To: wto@jca.apc.org
Subject: [wto 86] 2/16WTO 堦斒棟帠夛媍帠榐乮塸暥乯
Date: Wed, 30 Jun 1999 13:07:21 +0900
From: Tomoko Sakuma <tsakuma@jca.ax.apc.org>
MIME-Version: 1.0
Sender: owner-wto@jca.apc.org
X-Sequence: wto 86
Precedence: bulk
Reply-To: wto@jca.apc.org
1999擭2寧16擔偵WTO杮晹偱奐嵜偝傟偨堦斒棟帠夛偺媍帠榐偱偡丅岞幃暥彂偱偡偺偱丄梫栺傑偨偼彺栿偼偁傝傑偣傫偑丄揮嵹偟傑偡丅
嵅媣娫
WORLD TRADE ORGANIZATION
RESTRICTED
WT/GCIW/1 17/Rev.1 -25 January 1999
General Council 16 February 1999
REVIEW OF PROCEDURES FOR THE CIRCULATION AND DERESTRICTION OF WTO DOCUMENTS
Note by the Secretariat on Proposals made by Delegations - Revision
This note reflects the present state-of-play of the discussions and
reproduces the written proposals of US/Canada (WT/GC/w/106), the European
Communities (WT/GC/W/92), and Mexico (WT/GC/W/113), as well as the oral
proposals for changes in the Procedures for the Circulation and
Derestriction of WTO Documents (WT/L/160/Rev.1) which have been made by
delegations in the course of discussions during the October General Council
meeting.
I. GENERAL
(a) Mexico
Making it clear in the main text of the General Council Decision that if
they are to be derestricted, documents must be available in Spanish, French
and English. Giving greater meaning and operability to footnote 2 of the
General Council Decision.
(b) United States and Canada
WTO documents initially issued as restricted documents, but subject to
automatic derestriction after a determined time-period (e.g. minutes),
should be clearly marked on the first page of the document with the
anticipated date of derestriction. In the exceptional case where a document
is to remain restricted beyond the period foreseen, the Secretariat should
issue a notice to this effect.
(c) Indonesia on behalf of ASEAN Members
Transparency meant access to information without undermining confidentiality
principles. In attempting to enhance transparency, Members should ensure
that the intergovemmental and contractual nature of the WTO was not
compromised.
(d) Switzerland'
In favour of unrestricted circulation of WTO documents to the greatest
extent possible, provided that delegations had the opportunity to protect
politically sensitive documents, which was presently the case.
(e) Japan
A balance had to be struck between the effort to improve the transparency of
the organization and the need to preserve its intergovernmental character as
a forum for negotiation.
II. PARAGRAPH 7
(a) United States and Canada
As with the original 1996 Decision, the anticipated revised Decision should
be reviewed again after: two years.
III. APPENDIX
1. Item (a)
(I) Secretariat Background Notes
(a) United States and Canada
Paragraph (a) of the Annex to the 1996 Decision should be modified to
provide that Secretariat background notes, except for those which purport to
portray the views of WTO Members, shall normally be circulated as
unrestricted documents. Recognizing that there may be exceptional cases in
which a WTO body, when requesting the Secretariat to prepare a background
note, considers it essential that the note be initially considered on a
restricted bases, provisions should be made for exceptional restriction of
such notes, provided that a maximum time-period (e.g. 6 months) should be
established for its automatic derestriction if there are no exceptional
circumstances.
(b) European Communities
Secretariat background notes are intended to provide factual information and
not to represent the collective views of WTO Members. All such notes should
therefore be circulated on a non-restricted basis. There may be exceptional
cases in which a WTO body, when requesting the Secretariat to prepare a
background note, considers it essential that the note be initially
considered on a confidential basis. This may be allowed, as an exception to
the general rule of derestriction, provided that a maximum time period (e.g.
6 months) is established for its automatic derestriction.
(c) Indonesia on behalf of ASEAN Members
Secretariat background notes, when they provided factual information and did
not represent collective or individual views of Members, could be circulated
as unrestricted documents. However, a Secretariat background note could be
circulated as restricted if there was a consensus thereto.
(d) Argentina
Secretariat background notes could be derestricted 15 days after circulation
if no request to the contrary had been received by the Secretariat.
(e) Switzerland
Present procedures should continue to apply to working documents of the
WT/BFA/SPECA series and Balance-of-Payments documents.
(f) Japan
Provisions to maintain the necessary confidentiality of these documents
would have to be made clear.
(ii) Documents Submitted by Members
(a) United States and Canada
Recognizing that paragraph (g) of the Appendix to WT/L/I 60/Rev. 1 already
provides that documents submitted by Members for circulation should normally
be issued as unrestricted documents, the General Council should decide to
amend paragraph (a) of the Appendix to provide that this shall also be the
normal practice in the case of documents from Members circulated in the W
series. Of course, in both cases, we should preserve the possibility for the
Member making the submission to make an exceptional request for restricting
the submission, but for a period not, in principle, to exceed six months.
(b) European Communities
Documents submitted by a WTO Member should be circulated as unrestricted,
including those which are currently classified as working documents. On an
exceptional basis, a Member may indicate to the Secretariat that a document
be circulated on a restricted basis. In such case, however, the document
should be automatically derestricted after the expiry of a period of time
(e.g. 6 months).
(c) Indonesia on behalf of ASEAN Members
With regard to documents submitted by WTO Members, procedures under
paragraph (a) of the Appendix of WTIL/160/Rev.1 could be modified to allow
for the same rules as in paragraph (g), according to which documents
submitted by WTO Members, other than in the W" series, were circulated as
unrestricted unless otherwise stated by the Member concerned, and would be
considered for derestriction at the end of each six-month period.
(d) Japan
Provisions to maintain the necessary confidentiality of these documents
would have to be made clear.
(iii) Meeting Agendas
(a) European Communities
Meeting agendas should be immediately derestricted.
(b) Indonesia on behalf of ASEAN Member States, and Egypt
Agendas of meetings should be derestricted only after adoption by Members.
(iv) Other working documents
(a) European Communities
Working documents of a draft nature, such as decisions and proposals:
Consideration could be given to procedures to facilitate earlier
derestriction of such documents after the expiry of a reasonable period of
time.
2. Item (b)
(a) Mexico
Adding, in subparagraph (b) of the Appendix to the General Council Decision,
documents relating to the modification of schedules of commitments under
Article XXI of the General Agreement of Trade in Services (GATS).
3. Item (c)
(a) United States and Canada
Paragraph (c) of the Appendix to WT/L/160/Rev.l should be modified so as to
provide that minutes of meetings of all WTO bodies, including Summary
Records of Sessions of the Ministerial Conference and Secretariat-produced
notes of discussions should be considered for derestriction three months
after their circulation in all three WTO languages.
(b) European Communities
Minutes are prepared under the responsibility of the Secretariat and provide
essential information about WTO activities. Minutes should therefore be
circulated on an unrestricted basis. Exceptions would be made for a limited
number of WTO bodies which, by their very nature, require a certain degree
of confidentiality in proceedings.
(c) Indonesia on behalf of ASEAN Members
<Members approved> minutes of meetings in their final version could be
derestricted after procedures for achieving final Member-approved minutes of
meetings should be defined. This rule would not apply to certain WTO bodies
which, by their nature, required a certain degree of confidentiality in
their proceedings.
(d) Switzerland
Possibility of restricting such documents, as provided in WT/L/160/Rev.1,
should remain.
(e) New Zealand
Once categories of documents like minutes had been circulated to Members in
the three WTO languages, there were no compelling reasons for maintaining
any additional period for derestriction.
4. Item (e)
(a) European Communities
Documents relating to Working Parties on Accession submitted by the acceding
country could be subject to earlier derestriction if the acceding country so
indicates to the Secretariat.
5. Item (h) (footnote 1)
(a) United States and Canada
As soon as the "Findings and Conclusions" portion of a completed final
panel
report is prepared in all three official languages of the WTO, a final
report shall be issued to the parties to the dispute and the "Findings and
Conclusions" portion shall be circulated for information purposes as an
unrestricted document. In addition, at the same time, pending its
translation into the other two official languages of the WTO, the
"Descriptive" portion of the final report, shall be made available as an
unrestricted document in the original language of the panel report. This
decision is without prejudice to the Dispute Settlement Understanding and
the working practices concerning dispute settlement procedures agreed by the
Dispute Settlement Body and contained in document WT/DSB/6.
(b) European Communities
Panel reports should be immediately derestricted upon their circulation to
all WTO Members. Other aspects relating to transparency in WTO dispute
settlement should be considered within the framework of the DSU review.
(c) Egypt
Final panel reports should be derestricted once available in all official
languages.
(d) Argentina
Agree with the US/Canada proposal but for practical reasons, Members should
find a formula to ensure that the parties had such information at least a
few days or a few hours before the press, so that they could inform their
governments appropriately and explain to the public and to their national
institutions the meaning of the different decisions.
(e) Jamaica and Colombia
With respect to the distribution sequence of final panel reports, thought
should be given to the role of third parties.
IV SCOPE OF THE PROCEDURES
(a) European Communities
It should be noted that procedures for derestriction only apply to official
WTO documents. The procedures do not apply either to the Plurilateral Trade
Agreements, although the Community would favour their adoption by the
competent bodies.
(b) Australia
Other useful WTO documents, such as for example those with "job numbers"
and
papers from the Committee on Agriculture's Analysis and Information Exchange
Process were currently outside the scope of the procedures. Arrangements
could be made to enable appropriate circulation of these documents as well.
In the course of the review of the DSU a number of proposals which have a
bearing on the subject of derestriction and circulation were made. They are
reflected in the Compilation of comments submitted by Members prepared by
the Secretariat (Job No.6289). The relevant texts are reproduced on the
following
--------------
Texts referred to in footnote 1
(a) EC: "As of today, when the panel and Appellate Body reports are issued
to the WTO Membership, they are also made available to the general public.
One possibility might be to make public at that stage not only the reports,
but also the documents in the file before the panel or the Appellate Body
(e.g. analysis and background notes prepared by the WTO Secretariat,
submissions of participating parties which the parties had cleared for
publication or non-confidential summaries, thereof, etc.). This suggestion
might permit a significant shortening of the reports, by eliminating or
substantially shortening the arguments section. In developing the precise
modalities, the availability in all three official WTO languages of the
documents necessary to fully understand individual cases should be ensured.
(Paragraph 159 of the Compilation)".
(b) Japan: "With a view to encouraging the parties to the dispute to provide
a non-confidential summary of the information contained in their submissions
(i.e., a public version of the submission) and to improving transparency of
the dispute settlement process, a deadline of providing public versions
requested by any Members should be set out in the DSU. In this regard, the
timing of derestricting final panel reports should be also considered.
(Paragraph 174 of the Compilation)".
(c) Norway: "Early derestriction of the parties' submissions - or the
non-confidential parts thereof, at the latest at the same time as the
derestriction of the panel report itself, may promote a better understanding
in the public of the dispute settlement system of the WTO. This may
alleviate the need for extensive inclusion of the submissions in the panel
reports themselves, which should be guided by the usually short summaries of
arguments given in judgments of national courts. (Paragraph 166 of the
Compilation)".
(d) The Compilation of comments submitted by Members also contains in
paragraph 170 and the footnote 22 thereto a cross-reference to the proposal
by the US and Canada which appears in item 3(d) of this note
----------------------------------------------------------
Tomoko Sakuma
People's Forum 2001, Japan
Maruko-bld. 3F 1-20-6 Higashi-ueno
Taito-ku, Tokyo 110-0015 Japan
TEL +81-3-3834-2436
FAX +81-3-3834-2406
Email : tsakuma@jca.ax.apc.org or pf2001jp@jca.ax.apc.org
Website: http://www.jca.apc.org/pf2001jp/
----------------------------------------------------------
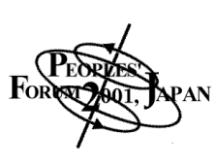
To: wto@jca.apc.org
Subject: [wto 83] WTO 娭楢忣曬丂 99/4丂 Vol.3
Date: Thu, 24 Jun 1999 18:51:16 +0900
From: Tomoko Sakuma <tsakuma@jca.ax.apc.org>
MIME-Version: 1.0
Sender: owner-wto@jca.apc.org
X-Sequence: wto 83
Precedence: bulk
Reply-To: wto@jca.apc.org
WTO娭楢忣曬丂99/4丂Vol.3
栚師丗
仭暷擾柋徣挿姱丄WTO師婜岎徛偵偍偗傞楢実傪僇僫僟偵梫惪
仭暷婇嬈偵峀偑傞堚揱巕慻傒懼偊嶌暔儃僀僐僢僩偵暷崙惗嶻幰偺晄埨崅傑傞
仭WTO妕椈夛媍偵岦偗偨弨旛僾儘僙僗偑戝崙偺懳棫偵傛偭偰掆懾
仭暷惌尃丄怴偨偵7審偺WTO採慽傪専摙拞
仭暷擾柋徣挿姱丄WTO師婜岎徛偵偍偗傞楢実傪僇僫僟偵梫惪
丂僟儞丒僌儕僢僌儅儞暷擾柋徣挿姱偼丄WTO師婜擾嬈岎徛偵懳偡傞僗僞儞僗偵偮偄偰僇僫僟惌晎偲偺崌堄傪宍惉偡傞偨傔偵僆僞儚傪朘栤偟偨丅偟偐偟挿姱偑丄僇僫僟偺擾嬈曗彆嬥惂搙傪斸敾偡傞偲丄僇僫僟惌晎懁偐傜傕暷崙偺摨條偺惂搙偵斸敾偑忋偑傞側偳丄懡偔偺揰偱椉崙偺僗僞儞僗偑堦抳偡傞偙偲偼崲擄側忬嫷偵偁傞偙偲偑柧傜偐偲側偭偨丅
丂僌儕僢僌儅儞挿姱偼丄WTO師婜岎徛偺擾嬈岎徛偵偍偗傞暷崙偺嵟戝偺栚昗偵偮偄偰丄娭惻丒桝擖妱摉側偳偺乽杅堈榗嬋揑慬抲乿傪嶍尭偡傞偙偲偱偁傝丄摿偵僇僫僟偺彫敒儃乕僪乮斕攧埾堳夛乯側偳偺乽崙壠杅堈夛幮乿偺揚攑傪廳帇偟偰偄傞偲弎傋偨丅僇僫僟彫敒儃乕僪偼僇僫僟惣晹偐傜桝弌偝傟傞慡偰偺彫敒丄戝敒傪庢傝埖偭偰偍傝丄偦偺検偼悽奅偺彫敒杅堈偺栺5暘偺堦傪愯傔偰偄傞丅挿姱偼偙偺儃乕僪偺曗彆傪庴偗偨僇僫僟偐傜偺彫敒偑巗応壙奿傪壓夞偭偰偄傞偨傔丄僇僫僟彫敒偺悽奅巗応僔僃傾偑奼戝偝傟丄巗応壙奿偑掅柪偡傞偲旕擄偟丄傑偨丄偙偺儃乕僪偑暷崙偺崚暔彜幮偵斾傋偰晄摟柧偱偁傞偲斸敾偟偨丅偟偐偟僇僫僟懁偼丄偙偺儃乕僪偼擾柉偐傜挜廂偝傟偨帒嬥偱塣塩偝傟偰偍傝丄惌晎偐傜偺曗彆傪庴偗偰偄側偄偲斀敪偟丄媡偵暷崙偺崚暔彜幮偲摨摍偵摟柧惈偑妋曐偝傟傟偽儃乕僪傪堐帩偡傞偙偲傪擣傔傞偐偲栤偄曉偟偨丅偙傟偵偮偄偰挿姱偼柧尵傪旔偗偨丅
丂暷崙偑桝弌曗彆嬥側偳偺杅堈忈暻偺嶍尭岎徛偱儕乕僟乕僔僢僾傪敪婗偟偰偄偔偲偺挿姱偺敪尵偼僆僞儚偺挳廜偐傜攺庤傪帩偭偰庴偗擖傟傜傟偨偑丄摨帪偵丄暷崙偑棪愭偟偰帺崙偺桝弌曗彆嬥傪嶍尭偡傋偒偱偼側偄偐偲偺挳廜偐傜偺堄尒偵懳偟偰傕戝偒側攺庤偑姫偒婲偙偭偨丅WTO師婜岎徛偱偺暷崙偺戞擇偺栚昗偼丄杅堈惂尷揑側朄惂搙乮悢検婯掕傗桝擖嬛巭側偳乯傪慡偰娭惻妱摉惂搙乮TRQ;
Tariff Rate Quotas乯偵抲偒姺偊偰偄偔偙偲偱偁傞丅偙偺応崌丄怘椏偵懳偡傞娭惻偼嵟戝300亾傑偱偲偝傟傞丅暷崙偼尰嵼丄偙偺TRQ傪僺乕僫僢僣偲柸壴偵揔梡偟偰偍傝丄僇僫僟偼棌擾惢昳偲棏丄偍傛傃寋擏偵揔梡偟偰偄傞丅挿姱偼戞嶰偺栚昗偲偟偰丄奺崙偺崙撪擾嬈曗彆嬥偵懳偡傞婯惂傪尩偟偔偡傞偙偲偩偲弎傋偨丄暷崙偼嶐擭丄嬞媫帪偺曗彆嬥偲偟偰60壄僪儖埲忋偺捛壛巟弌傪掕傔傞朄棩傪惉棫偝偣偰偄傞偑丄挿姱偵傛傞偲偙偺曗彆嬥偼乽杅堈榗嬋揑乿偱偼側偄忋丄WTO偱掕傔傜傟偨曗彆嬥偺尷搙撪偵廂傑偭偰偄傞偲偄偆丅偟偐偟暷崙偼丄曗彆嬥嶍尭偺嶼掕婎弨擭偵擾嬈曗彆嬥傪戝暆奼戝偡傞偙偲偱丄曗彆嬥嶍尭傪幚幙揑偵峴傢側偔偰嵪傓傛偆憖嶌偟偰偄傞偲偄偆帠幚偑偁傞丅
嶲峫丗Journal of Commerce, Wednesday, April 21,1999
仭暷婇嬈偵峀偑傞堚揱巕慻傒懼偊嶌暔儃僀僐僢僩偵暷崙惗嶻幰偺晄埨崅傑傞
丂4寧16擔丄僇乕僊儖幮偑堚揱巕慻傒懼偊嶌暔偺攦偄庢傝傪掆巭偡傞偲偺曬摴偑偁偭偨丅摨幮偺峀曬扴摉偼偙傟傪斲掕偟偨偑丄儌儞僒儞僩幮偺儔僂儞僪傾僢僾側偳偺摿掕偺擾栻偵懴惈傪帩偮堚揱巕慻傒懼偊僩僂儌儘僐僔偺惗嶻幰偺娫偵偼晄埨偑峀偑偭偰偄傞丅偦偺棟桼偼丄暿偺戝庤崚暔彜幮丄ADM乮傾亅僠儍乕丒僟僯僄儖僘丒儈僢僪儔儞僪乯幮偑4寧16擔埲崀丄摨幮偺壛岺岺応傗挋憼巤愝偱偼EU偵桝弌偱偒側偄堚揱巕慻傒懼偊僩僂儌儘僐僔傪庴偗擖傟側偄偲敪昞偟偰偄傞偙偲偱偁傞丅慡暷偱嶰斣栚偺婯柾傪屩傞僩僂儌儘僐僔壛岺嬈幰丄AE僗僞乕儕乕幮傕摨條偺寛掕傪偡偱偵敪昞偟偰偄傞丅
丂暷崙偺崚暔彜幮僌儖乕僾偺悇寁偵傛傞偲丄崱擭偺暷崙嶻僩僂儌儘僐僔偺栺4乣6亾偑儔僂儞僪傾僢僾丒儗僨傿擾栻懴惈堚揱巕慻傒懼偊僩僂儌儘僐僔偩偲偄偆丅崚暔彜幮偼丄EU岦偗偺僩僂儌儘僐僔揵暡帞椏偵丄EU偑桝擖嬛巭偲偟偰偄傞庬椶偺堚揱巕慻傒懼偊僩僂儌儘僐僔偑娷傑傟偰偄傞偲敾柧偟偨応崌偵丄懳EU桝弌偵巟忈偑弌傞偙偲傪怱攝偟偰偄傞丅
丂僇乕僊儖幮偵傛傟偽丄堚揱巕慻傒懼偊嶌暔傗偦偺壛岺昳傪EU岦偗偵桝弌偱偒側偄偙偲偵寽擮傪書偄偰偼偄傞偑丄崙撪巗応岦偗偵堚揱巕慻傒懼偊嶌暔傪崙撪惗嶻幰偐傜攦偄忋偘傞偙偲偼崱屻傕懕偗偰偄偔偲偄偆丅摨幮偼傑偨丄暷崙撪偺庬昪儊乕僇乕傗惗嶻幰僌儖乕僾偵懳偟丄EU偵桝弌偱偒側偄摿掕偺堚揱巕慻傒懼偊僩僂儌儘僐僔偺庬椶偵偮偄偰廃抦揙掙偡傞僾儘僌儔儉傪巟墖偟偰偄傞偲偄偆丅
彺栿丗Resource News International, April 21,1999
仭WTO妕椈夛媍偵岦偗偨弨旛僾儘僙僗偑戝崙偺懳棫偵傛偭偰掆懾
丂WTO師婜岎徛偺懳徾暘栰傗岎徛曽朄傪弰偭偰懳棫偑懕偔拞丄偙傟傜偵崌堄偑惉棫偡傞偺偼憗偔偲傕7寧崰偲側傝丄幚幙揑側弨旛僾儘僙僗偼廐偵廤拞偡傞偙偲偵側傞丅摉弶偺僗働僕儏乕儖捠傝偵恑傫偱偄側偄嵟戝偺棟桼偼丄暷崙偺懺搙偑偼偭偒傝偟側偄偙偲偵偁傞丅6寧24擔傑偱懕偔暷崙撪偺僸傾儕儞僌丒僾儘僙僗偑廔椆偡傞傑偱偼岞幃側億僕僔儑儞偑弌偣側偄偙偲偵側偭偰偄傞偨傔偱偁傞丅堦曽EU偱傕丄EC乮墷廈埾堳夛乯偵岎徛尃尷偑梌偊傜傟偰偄側偄拞丄岞幃側億僕僔儑儞傪採帵偱偒偢偵偄傞丅EC偵岎徛尃尷偑梌偊傜傟傞偺偼憗偔偲傕WTO僔傾僩儖妕椈夛媍屻偵側傞偲巚傢傟傞丅擔杮偼6寧拞弡偵擾嬈岎徛偵懳偡傞億僕僔儑儞傪娷傔偨徻嵶側採埬傪採弌偡傞梊掕乮6寧17擔偵乽擾嬈乿偍傛傃乽椦丒悈嶻暔乿偺暘栰偺採埬偑岞昞偝傟偨乯偩偑丄僇僫僟偺採埬採弌偼廐偵側傞偲偄偆丅
丂僕儏僱乕僽偺WTO杮晹偱偼偦傟埲奜偺奺崙偐傜採埬偑忋偑偭偰偒偰偄傞丅僆乕僗僩儔儕傾偼丄僔傾僩儖妕椈夛媍偵偍偄偰乽擾嬈杅堈乿偵乽儌僲偺杅堈乿偲摨偠尨懃傪揔梡偡傞偲偄偆栚昗傪宖偘傞偙偲傪採埬偟偨偑丄偙傟偵偮偄偰暷崙側偳偺戝崙偐傜偺堄尒偼弌偝傟偰偄側偄丅偙偺僆乕僗僩儔儕傾偺採埬偼丄嬶懱揑偵偼擾嬈桝弌曗彆嬥偺揚攑傪堄枴偟偰偍傝丄摨崙偼偙偺曗彆嬥嶍尭偲丄搑忋崙偵懳偡傞摿暿偐偮嵎堎偺偁傞埖偄傪擾嬈岎徛偺拞怱揑壽戣偵娷傔傞偙偲傪媮傔傞嬶懱揑側採埬傕暿搑採弌偟偰偄傞丅
丂搑忋崙悢僇崙傕偡偱偵採埬傪弌偟偰偍傝丄偦偺傎偲傫偳偑婛懚偺WTO嫤掕偐傜搑忋崙偑壎宐傪庴偗傜傟傞傛偆偵偡傞偙偲偲丄偙偺嫤掕偺幚巤妋曐偑桪愭偝傟偹偽側傜偢丄偦傟傑偱偼價儖僩僀儞丒傾僕僃儞僟乮BIA;
僂儖僌傾僀儔僂儞僪廔寢帪偵2000擭偐傜偺嵞岎徛偑崌堄偝傟偰偄傞暘栰乯埲奜偺暘栰偵傑偱峀偘偨岎徛傪峴偆偙偲偵偼斀懳偡傞偲偄偆庯巪偱偁傞丅偟偐偟暷崙偼3寧23-24擔偺堦斒棟帠夛偱丄乽嫤掕幚巤偺崲擄惈傪崕暈偡傞偙偲乿偼丄師婜帺桼壔岎徛偺懳徾傪奼戝偟丄BIA埲奜偺暘栰傪娷傔傞偙偲偲柕弬偟側偄偲庡挘偟偰偄傞丅暷崙偼崱傑偱傕搑忋崙偑WTO嫤掕傪弲庣偡傞偨傔偺崙撪朄惍旛偑抶傟偰偄傞晹暘偵偮偄偰暣憟夝寛偵帩偪崬傫偱偒偰偍傝丄崱屻傕偙偆偟偨幚巤偺栤戣偼働乕僗僶僀働乕僗偱懳墳偡傞偲偟偰偄傞丅堦曽僷僉僗僞儞側偳偼慇堐暘栰偺帺桼壔偑愭恑崙僒僀僪偱恑傫偱偄側偄偙偲傪乽幚巤乿忋偺栤戣偲偟偰夵慞傪梫媮偟偰偄傞丅
丂搑忋崙偵偲偭偰丄暋嶨偐偮峀斖側悽奅杅堈岎徛偵懳墳偡傞偩偗偺愱栧惈偲抦尒傪旛偊偨恖嵽偑晄懌偟偰偄傞偙偲丄岎徛僗僞儞僗傪寛傔傞偨傔偺撈帺偺暘愅傪峴偊偰偄側偄偙偲側偳偑戝偒側忈奞偵側偭偰偄傞偲偺嫟捠偟偨擣幆偑懚嵼偡傞偵傕偐偐傢傜偢丄傑偨偦傟偵懳偡傞帒嬥丒媄弍巟墖偑栺懇偝傟偰偄側偑傜廫暘偵幚巤偝傟偰偄側偄偙偲傕戝偒側栤戣偲擣幆偝傟偰偄傞丅
丂師婜帺桼壔岎徛偵愊嬌揑側崙偼僇僫僟丄擔杮丄僆乕僗僩儔儕傾丄儊僉僔僐丄娯崙丄拞撿暷彅崙丄搶撿傾僕傾彅崙偱偁傞丅僀儞僪丄僷僉僗僞儞丄僄僕僾僩偺3儢崙偼師婜岎徛偦偺傕偺偵斀懳偱偁傝丄儅儗乕僔傾偼岎徛僗働僕儏乕儖偵斀懳偟偰偄傞丅暷崙偼崌堄偑惉棫偟偨暘栰偛偲偵掲寢偡傞乽憗婜廂妌乿曽幃傪採埬偟偰偄傞丅
嶲峫丗"WTO Ministerial Preparations Slowed By Major Trading Partners",
Inside US Trade, April 23,1999
European Commission Reviews Preparation of Millennium Round - Global Talks, areas
of negotiation, Positions of Participants, Brussels April 23,1999, Agence Europe
仭暷惌尃丄怴偨偵7審偺WTO採慽傪専摙拞
丂暷惌尃偼尰嵼丄EU偵懳偟偰2審丄娯崙偵懳偟偰2審丄僇僫僟偵懳偟偰1審側偳丄崌寁7審偺WTO採慽傪専摙偟偰偄傞丅暷崙偼偙傟傑偱丄崌寁44審偺採慽傪峴偄丄偦偺撪偺20審偱彑慽偟偰偄傞丅
丂崱夞採慽偺懳徾偵偼丄峲嬻娗惂僔僗僥儉偺奐敪偵娭偡傞EU婇嬈偺嫟摨僾儘僕僃僋僩偵懳偡傞僼儔儞僗惌晎偺曗彆嬥偑娷傑傟偰偄傞丅娯崙偵懳偡傞採慽偺懳徾偼丄桝擖媿擏偵懳偡傞娯崙惌晎偺桝擖娗棟惌嶔偍傛傃嵟掅壙奿愝掕丄偦偟偰暷崙嶻媿擏偵偲偭偰乽嵎暿揑乿側崙撪棳捠僔僗僥儉乮彜姷峴乯偱偁傞丅娯崙偵懳偡傞傕偆堦審偺採慽偺撪梕偼丄嬻峘寶愝偵娭偡傞娯崙惌晎偺惌晎挷払偑崙撪嬈幰傪桪愭偟偰偍傝丄WTO偺惌晎挷払嫤掕偵堘斀偟偰偄傞偲偄偆傕偺偱偁傞丅
丂僇僫僟偵懳偟偰偼TRIPs乮杅堈娭楢抦揑強桳尃乯嫤掕偵婎偒丄婛懚偍傛傃怴婯偺摿嫋偵懳偟偰20擭娫偺曐岇傪梌偊偹偽側傜側偄偲偙傠傪丄1989擭10寧埲慜偵怽惪偝傟偨摿嫋偵偮偄偰偼17擭傑偱偟偐擣傔偰偄側偄揰傪WTO堘斀偱慽偊傞丅
丂暷崙偼傾儖僛儞僠儞偵懳偟偰傕丄崚暔斕攧嫋壜傪摼傞偨傔偵傾儖僛儞僠儞惌晎偵採弌偝傟偨暷惢栻夛幮偺旕岞奐偺帋尡僨乕僞偺楻塳偵偮偄偰丄TRIPs堘斀偱偁傞偲偟偰採慽偺弨旛傪恑傔偰偄傞丅暷崙偼EU偵懳偟偰傕丄EU偑擾嶻暔偲怘昳偵壽偟偰偄傞尨嶻抧昞帵媊柋偑丄TRIPs偺掕傔傞彜昗曐岇偵堘斀偟偰偄傞偲偟偰採慽傪峴偆梊掕偱偁傞丅傑偨丄僀儞僪偵懳偟偰偼TRIMs乮杅堈娭楢搳帒慬抲乯嫤掕偵乽堘斀乿偟偰偄傞帺摦幵嶻嬈奅偺彜姷峴偵偮偄偰慽偊傞偲偟偰偍傝丄僇僫僟偵懳偟偰偼丄僆儞僞儕僆廈朄偑摨廈偲暷儈僱僜僞廈偵傑偨偑傞屛偵偍偄偰暷嫏柉偵嵎暿揑側慬抲傪掕傔偰偄傞偲偟偰暷捠彜朄301忦偵婎偯偄偨挷嵏傪奐巒偡傞丅
彺栿丗Administration To Bring Seven Trade Complaints To WTO, Congress Daily April
30,1999
----------------------------------------------------------
Tomoko Sakuma
People's Forum 2001, Japan
Maruko-bld. 3F 1-20-6 Higashi-ueno
Taito-ku, Tokyo 110-0015 Japan
TEL +81-3-3834-2436
FAX +81-3-3834-2406
Email : tsakuma@jca.ax.apc.org or pf2001jp@jca.ax.apc.org
Website: http://www.jca.apc.org/pf2001jp/
----------------------------------------------------------
仧偍栤偄崌傢偣
巗柉僼僅乕儔儉2001帠柋嬊
丂 仹110-0015丂搶嫗搒戜搶嬫搶忋栰1-20-6丂娵岾價儖3奒
TEL.03-3834-2436丂FAX.03-3834-2406
E-mail; pf2001jp@jca.apc.org