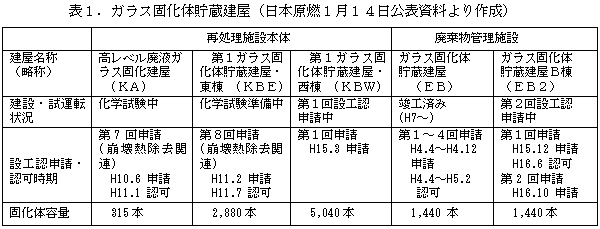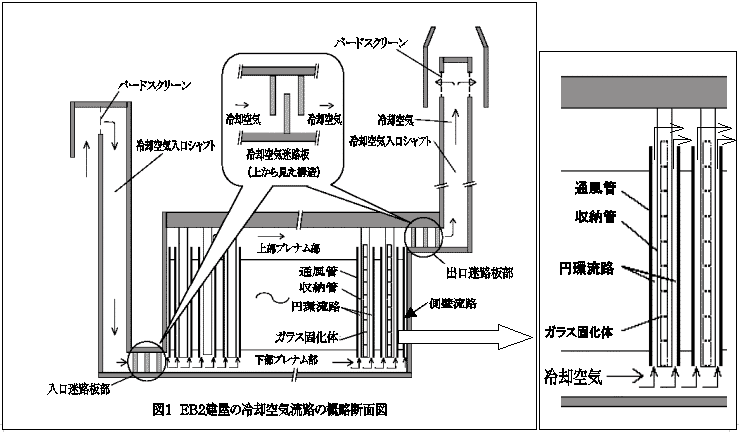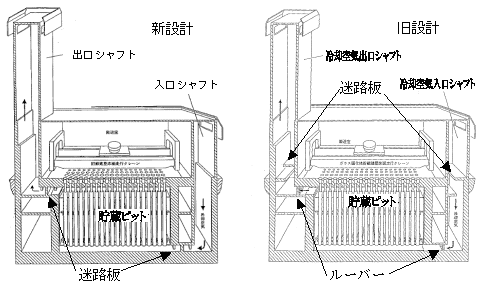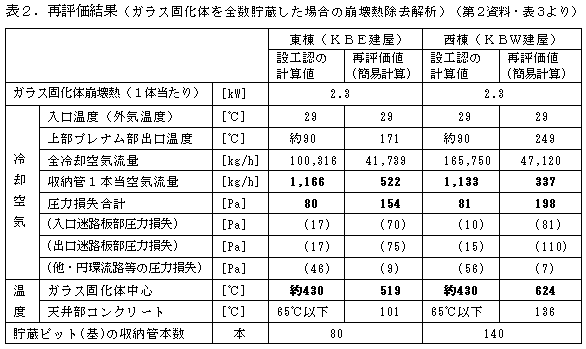六ヶ所・ガラス固化体貯蔵建屋の怪
設計変更で上がるはずの固化体温度が、変更前とまったく同じとは?
2005年4月20日 美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会 今年1月28日に、日本原燃はガラス固化体貯蔵建屋の温度解析に誤りがあったことを認め、誤りの解析結果と修正した再評価結果を公表しました。それは、1月28日公表の第2資料「特定廃棄物管理施設のガラス固化体貯蔵建屋B棟及び再処理施設においてガラス固化体を貯蔵する類似の冷却構造を有する設備における崩壊熱の除去解析の再評価結果報告書」(以下第2資料と引用)の特に表3に集約されています。なぜそのような誤りを犯したのかについて、原燃は「文献式の解釈誤り」だと称し、同様の誤りがないことはすべて調査確認済みだとしています。この判断の妥当性について、原子力安全・保安院は1月28日付見解で何も評価しないまま、他方では、設計をやり直す方針は妥当だとしました。そこで原燃は4月18日に、2つのガラス固化体貯蔵建屋に関する「設計及び工事の方法の変更許可申請」を保安院に提出しました。ウラン試験最終段階の「総合確認試験」では、これら貯蔵建屋がからむため、その時点までに工事をやり直す必要があるからです。 問題は、原燃の解析誤りとはどんなものかということです。実はこれは解析誤りなどではなく、建設費を安く上げるための意図的な虚偽の解析、虚偽の申請ではないかという疑いがきわめて濃厚なのです。そのような虚偽が他にないことは、もちろんまだ調査されていません。 この問題の性格を端的に見るために、第1ガラス固化体貯蔵建屋・西棟に焦点を当てることにしましょう。ガラス固化体貯蔵建屋は表1に示すように5つありますが、解析誤りが生じたのは現に使用中のEB建屋を除く4建屋です。その誤りは、基本的に1996年(H8)に、冷却空気の流路にある迷路板の構造を変えるよう設計変更し、空気の流れを悪くしたときに生じたものです。そして、西棟だけはそればかりでなく、2001年(H13)にさらに別の設計変更を行いました。固化体をギュウギュウ詰めにして「貯蔵を効率化」したのです。 ところが西棟では、これら2回の設計変更により解析対象が変わったのに、固化体の温度は1991年(H3)に計算した値からまったく変わらないままで申請しています。これは誰が考えてもおかしなことです。ある種の虚偽が行われたとしか考えられません。特に第2の設計変更のときになぜ温度が変わらなかったのかについては、これまで誰からも問題にされず、原燃も一言も説明していません。原燃の第2資料にある経過説明でも、奇妙なことに、この問題にはまったく触れていないのです。同様の「虚偽」が他の施設にないことはもちろん調査すらされていません。 そこで、原燃の虚偽性を明らかにするため、西棟に焦点を当てて以下に見ていきましょう。
1.ガラス固化体の放射能と発熱 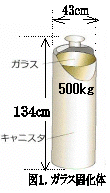 まず、建屋に貯蔵されるガラス固化体とはどんなものかを見ておきましょう。原発の使用済み核燃料からプルトニウムとウランを抽出した後の高レベル放射能廃液をガラス材と混ぜて固めたもので、ステンレス製のキャニスタに入っています(数え方を収納管と区別するため、ここでは1個2個とします)。 まず、建屋に貯蔵されるガラス固化体とはどんなものかを見ておきましょう。原発の使用済み核燃料からプルトニウムとウランを抽出した後の高レベル放射能廃液をガラス材と混ぜて固めたもので、ステンレス製のキャニスタに入っています(数え方を収納管と区別するため、ここでは1個2個とします)。100万kWの原発を1年間運転して生じる使用済み核燃料からの放射能はガラス固化体30個に納まるほどに、固化体内の放射能はすさまじいものです。六ヶ所再処理施設内の3つの貯蔵建屋には8,200個が貯蔵でき、「約8年間に発生するガラス固化体を貯蔵できる」とされています(1996年(H8)4月変更申請6-7-4-23頁)。 貯蔵中には、キャニスタを突き抜けて出る放射線(ガンマ線と中性子線)及び放射能による発熱(崩壊熱)が問題になります。 ■ガラス固化体1個の放射能:原燃が公表しているイギリスのBNFL社製の場合、 ・総ベータ・ガンマ放射能 4.5×1016 Bq(1秒間に1兆の45,000倍本のガンマ線をだす) ・総アルファ放射能 3.5×1014 Bq ■ガラス固化体1個の発熱量:BNFL製では最大2.5kW、コジェマ製では2.0kWとされている。六ヶ所再処理施設からの固化体では2.3kWだが、バラツキを考慮すると最大で2.8kWとされている(例えば1996年(H8)4月変更申請書6-7-4-8頁)。 2.ガラス固化体貯蔵建屋での空気冷却 1996年(H8)以後の設計によるガラス固化体貯蔵建屋は下図のようになっています。ガラス固化体9個(KA建屋だけは7個)が1本の収納管に縦積みされています。収納管は炭素鋼製で厚さ1㎝、外径45㎝、長さ16m(4階建の高さほど)で、これによって1個500㎏、表面温度300℃近いガラス固化体9個が40~50年間も支えられる予定です。その外側に通風管があり、収納管と通風管の間にある幅12㎝の円環領域を空気が通るようになっています。 図2.ガラス固化体貯蔵建屋(1996年(H8)の迷路板設計変更以後:第2資料・図1より) 3.放射線防護と空気冷却との矛盾─迷路板の必要性 ところが図2を見ると、入口シャフトから下部プレナム部への入口部分と上部プレナム部から出口シャフトへの出口部分に迷路板が取り付けられています。それを上から見た図を見ると、その部分で空気は狭い領域を横向きにジグザグ行進しなければならないため、明らかに流れが妨げられます。それだけ空気冷却の能力が落ちることになります。それなのに、なぜわざわざ迷路板を取り付けなければならないのでしょう。 それはガラス固化体が発する膨大な放射線(ガンマ線と中性子線)が空気流路を通って外部に出るのを防ぐためです。放射能自体はステンレス製のキャニスタ内に閉じ込められているため、よほどのことがないと外に漏れ出ることはありませんが、放射能が発する放射線のうち、ガンマ線と中性子線はステンレス製キャニスタやその外の炭素鋼製収納管などを貫いて飛び出してきます。ガンマ線だけで前に見たように、毎秒1兆の4万5千倍本もが1個のガラス固化体から放出されます。ちょうど蛍光灯から光がでるように、縦に並んだ収納管のあらゆる箇所から放射線が放出され、壁などで反射されながらあちこちに散乱していきます。空気の流路には何も障害物がないため、流路の壁で反射されながら進んでいってついに外部にまで出てしまうのです。これを防ぐためには、放射線がまっすぐ進むのを妨げるように板などで流路を遮断する必要があります。 このようにして、放射線の外部への漏れを防ぐためにはどうしても空気流路を塞ぐ必要があるものの、それは空気の流れを妨げるので冷却を妨害するというように二律背反の矛盾が生じます。その矛盾の妥協点が迷路板の設置だというわけです。 4.迷路板の設計変更(1996年・H8年)にも係わらず固化体温度は不変 原燃は1996年(H8)に、第1ガラス固化体貯蔵建屋・東棟及び西棟などで迷路板の設計変更を行いました。変更点は、次の図3から分かります。図3の左側が変更後で、図2とは左右が入れ替わっていますが、同じ構造になっています。ガラス固化体を貯蔵する部屋は「貯蔵ピット」と呼ばれますが、迷路板はその下部プレナム部の入口と上部プレナム部の出口についています。図2右側の図は変更前で1991年(H3)の変更申請によるもので 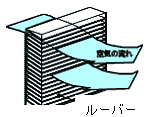 す。迷路板は入口シャフトと出口シャフトに2枚ずつ"ひさし"のような形に付けられています。また、別にルーバーがありますが、これは放射線遮蔽用で、右図のように、薄い金属板製で窓のブラインドを水平に開いたような構造をしています(これは1989年(H1)の最初の申請書ではなかったものです)。 す。迷路板は入口シャフトと出口シャフトに2枚ずつ"ひさし"のような形に付けられています。また、別にルーバーがありますが、これは放射線遮蔽用で、右図のように、薄い金属板製で窓のブラインドを水平に開いたような構造をしています(これは1989年(H1)の最初の申請書ではなかったものです)。なぜこのような設計変更を行ったかと言えば、「施工性を高めるため」ということです。変更前の設計どおりにひさし状にコンクリートを取り付けるのは難しいため、費用と時間がかかります。実はこの変更が行われた1996年(H8)は、さまざまな面で費用の節減が行われた年でした。同年1月には、再処理施設の建設費が、それまでの8,400億円から一挙に1兆8,800億円へと2.2倍に膨らむことが明らかになりました。そのためこのときの変更申請で、精製施設の2段階精製を1段に変更し、高レベル廃液貯蔵タンクの数などを大幅に減らしたりしています。経費削減の大きな圧力の中で、迷路板の「施工性」を高める必要も起こったに違いありません。
ところが驚くべきことに、1996年(H8)の変更申請書には1991年(H3)の変更申請書とまったく同じ温度が書かれているのです。1996年(H8)の変更申請書には、第1ガラス固化体貯蔵建屋の貯蔵ピットでは、東棟と西棟の区別なく、ガラス固化体の表面温度は約280℃、同中心温度は約430℃、冷却空気の円環流路出口温度は約90℃と書かれていますが、この記述は1991年(H3)の変更申請書と寸分変わっていないということです。 いまでは、原燃はこれを誤りと認め、その「原因」は、空気流量に対する迷路板の影響を計算する際に、「文献式の解釈を間違えた」ためとしています。しかし、何らかの計算間違いがあったとしても、温度が以前とまったく同じ値になることは一般にあり得ないことです。 5.西棟では第2の設計変更でも固化体温度は不変 さらに驚くべきことが、第1ガラス固化体貯蔵建屋・西棟で起こります。別の設計変更をしたのに、またもやガラス固化体の温度に何らの変化もなかったということです。 図4は、2001年(H13)7月17日付の原燃の記者発表ですが、そこのはじめの部分に設計変更の動機が書かれています。ガラス固化体収納管の間隔を縮めて「貯蔵を効率化」すること、それにより建屋が小型化できることです。確かに、西棟の横幅が以前の74mから東棟と同じ56mに小型化されています。したがって、建設費用が安くつくということでしょう。 どのように貯蔵を効率化するのかを、もう少しくわしく見ていきましょう。図4は建屋1階の床面を示していますが、その下の地下1階と2階を貫くように貯蔵ピットがあります。貯蔵ピットは、変更前には東棟でも西棟でも同じで20本の収納管が4列で構成されており、それが東棟では4基、西棟では7基ありました。 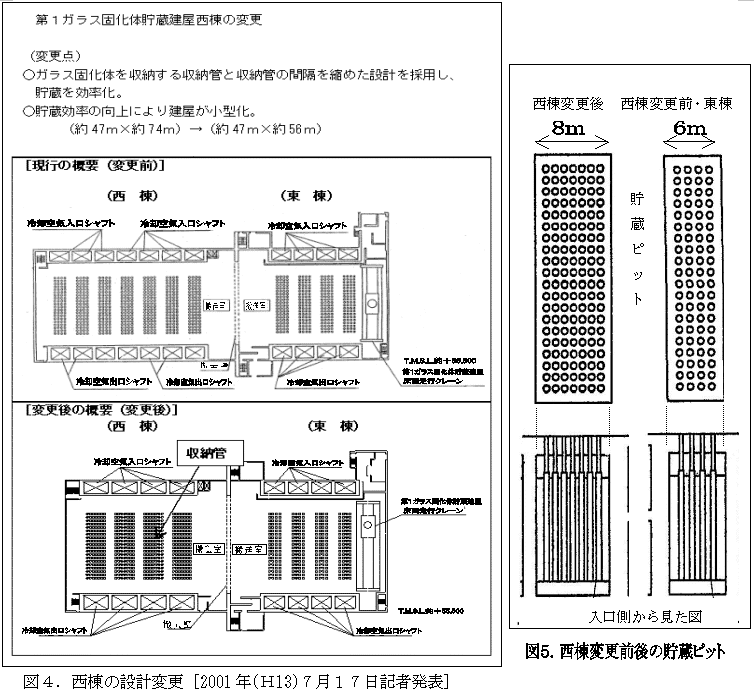 ところが2001年(H13)の設計変更により、図5のように西棟では貯蔵ピットが7列×20本で、4基になりました。収納管の全本数及びガラス固化体数に変更はありません。 ここで重要なことは、空気流量や温度の解析は貯蔵ピットごとに行われることです。ガラス固化体が設計変更前と同じに冷却されるためには、収納管と通風管の間を通る空気の流れが同じでなければなりません。それが貯蔵ピットの設計変更によってどう変わるでしょう。 貯蔵ピットには、設計変更前には4×20=80本の収納管があり、空気の入口幅(貯蔵ピットの幅)は約6mでした(図5)。それが設計変更により、収納管本数が7×20=140本に増え、空気の入口幅は約8mに変わりました。収納管本数は1.75倍に増えたのに、空気入口幅は1.33倍にしか増えていないのです。西棟建屋の幅を74mから56mに減らし、「貯蔵を効率化」したのだからこれは当然の結果です。貯蔵ピット当たりの固化体数が1.75倍に増え、1.75倍の熱が発生するため、それだけ多くの冷却空気が必要です。また固化体の熱は空気を動かす原動力であるため、多くの熱は空気流量を高めようとします。ところが、空気流の入口は1.33倍にしかならないのだから、空気流に対する抵抗が相対的に増えて、結局、必要な空気流量が確保されなくなります。すなわち、この設計変更で固化体温度が高まるのは必然です。 ところが、実に驚くべきことに、2001年(H13)の変更申請書では、1996年(H8)当時の温度、したがって1991年(H3)当時の温度の記述が、そのまま何の変更もなく再録されているのです。 ここまで2度も同じことを見せられると、誰しもどうも変だなと思わざるを得ません。設計変更にはそれなりの動機があって、要するに安上がりに建設するために行うわけです。そしてそのように設計変更すれば、ガラス固化体の温度が上昇することになるのは必然です。しかし、その温度上昇をそのまま認めれば、設計上の温度限界である500℃を超えるので、目的の安上がり設計変更は不可能になります。それならいっそ温度は元のままにしておきたいという動機が強く働くことは想像に難くありません。 しかし、このような意図的なことを犯せば、必ずどこかにその痕跡が残り、どこかで矛盾が生じているに違いありません。そのことを以下で少し詳しく調べてみましょう。 6.解析の虚偽性はどこに現れているか 原燃の解析間違いに気づいたのは原子力安全基盤機構で、申請中のEB2建屋の温度解析をクロスチェックしてみたからです。その指摘を1月14日に保安院から受けて、原燃が計算をやり直した結果が第2資料の表3に集約されています。そのうち東棟(KBE)と西棟(KBW)の分だけを、以下の表2としてまとめました。 これまで述べてきた設計変更との関係を西棟に即して整理しましょう。2001年(H13)の設計変更までは、図4のように、西棟は東棟と同じ規格の貯蔵ピットで、温度解析の対象が同じだったので、両者を区別する必要はなかったのです。それゆえ、表2の東棟に関する数値は同時に、1996年(H8)変更時の西棟の数値だと見なすことができます。他方、表2西棟の数値は、2001年(H13)設計変更以降なので2回分の設計変更が含まれているものです。以上により、表2は実は、西棟に関する1996年(H8)と2001年(H13)の設計変更に係わる数値だと解釈できます。 なお、再評価値の計算では、「簡易計算」と書かれているとおり、壁際を流れる空気量が無視されています。それゆえに、"全冷却空気流量=収納管1本当空気流量×収納管本数"という関係が成り立っています。収納管本数が80本と140本というのは、ちょうど西棟の2001年(H13)変更前後の貯蔵ピットでの本数と一致しています(「設工認の計算値」の場合は、壁際流も考慮されているので、上の等式は成り立っていません。注:設工認=「設計及び工事の方法の認可申請」)。 以下、仮に再評価値は正しいとして、表2について気づいた点を記述していきましょう。
東棟(KBE)での2つの数値(設工認と再評価値)を比べると、収納管1本当たりの空気流量が1,166から522に減少しています。1996年(H8)の解析では、本当は522しか流れないものを、勝手に1,166も流れると虚偽の記述をしていたということです。 今度は、東棟(KBE)の設工認と西棟(KBW)の設工認を比較します。1本当たり流量が1,166と1,133でほぼ同じです。これは2001年(H13)の設計変更でギュウギュウ詰めにしたにも係わらず空気流量に変更はなかったと虚偽の記述をしたことを意味しています。このときのギュウギュウ詰め変更により、再評価値の522が337に減少するという、それ位の影響が本当はあったはずなのに、これを無視したということです。この2001年(H13)の変更問題はまだまったく問題にされていません。 (2) ガラス固化体中心温度 温度の計算値は、1991年(H3)当時からまったく変わっていないことを何度も強調してきました。そのことは表2の設工認の計算値欄にある3つの温度に表されています。例えば、ガラス固化体中心温度は東棟(KBE)と西棟(KBW)で同じ約430℃となっていますが、これは2001年(H13)の設計変更で温度計算値を変えなかったことを意味しています。 東棟(KBE)の2つの数値を比べると、1996年(H8)の設計変更で本当は519℃になるべきところを430℃のままにしたことが分かります。2001年(H13)の設計変更では519℃が624℃に変わる程度の影響があったのに、それを無視して前のままの温度にしたことが分かります。 つまり、1996年(H8)の設計変更の影響をまともに計算していたら、設計上の温度限度である500℃を超えてしまうために、そのような設計を採用することができなかったわけです。それでは経費削減にならないので、温度は前のままにしておこうということにした疑いが濃厚です。さらに、次の2001年(H13)の変更ではさらに温度が上がるので、まともに計算したのではとてもギュウギュウ詰めにできない。だから温度は前のままにしておこうとなったのに違いありません。 (3) 圧力損失 次に、虚偽の解析、虚偽の申請をしたに違いないという証拠を示す必要があるでしょう。もし温度は変えないことを再優先して、解析はなんとなくそれらしい数値を後で付け加えただけならば、表2の数値の間に矛盾が生じるはずです。それは、表2の冷却空気流量を用いて圧力損失を計算してみることによってチェックできます。 「圧力損失」というのは、空気の流れを妨げるように迷路板などから働く抵抗力のことで、それを流れと逆向きの圧力で表したものです。圧力損失を計算するために原燃が用いた計算式が第2資料15頁に出ているので、それと同じ式を用いて計算してみます(詳しい説明は後述)。 問題になるのは原燃が虚偽の解析をしたのではと疑われる設工認の計算値です。このときの「文献式の解釈誤り」がどのようなものかは15頁に書かれているので、その通りに間違った計算をしてみます。そのようにして、原燃のいう「間違い」が本当かどうか調べてみるわけです。 外気温29℃のときの空気密度を理科年表より1.17kg/m3とします。迷路板が設置されている貯蔵ピットへの入口ダクトの断面の高さを、図より目算でb=1.3mとします。同じ断面の横幅は貯蔵ピットの横幅で、これは変更申請書に書かれていて、2001年(H13)の変更前(つまり東棟と同じ)でa=6m、変更後(西棟)はa=8mです。これらを用いて15頁の式で入口迷路板部の圧力損失を計算すると、東棟で10.9θ^2、西棟で16.75θ^2となります。ここでθ^2は、迷路板の構造を現す数値が公表されていないので直ちに数値で示すことができませんが、1より小さい数値であることは分かっています(図から目算で決めると大体0.7程度だと思われます)。それゆえ、東棟の圧力損失は10.9より小さい値になります。ところが、表2のそれに該当する数値は17なので、明らかに矛盾しています。西棟の場合は、圧力損失が10で16.75より小さいので直ちに矛盾しているとは言えないですが、他方、西棟のθ^2は東棟のθ^2より大きいので、16.75θ^2>10.9θ^2 となるはずなのに、表2では逆になっていて、やはり矛盾しています。 これらの矛盾は、迷路板部の構造を表す数値を原燃が公表すればさらにはっきりするでしょう。 7.結論 ここでは、設計変更が2回行われた第1ガラス固化体貯蔵建屋・西棟に目をつけて、設計変更の内容を調べてきました。2回とも、明らかに冷却空気の流れを悪くする方向の変更であることは直感的に明らかです。それにも係わらず、温度の解析値を1991年(H3)以来まったく変えていないのはどう考えても虚偽としか思えません。仮に何らかの解析間違いを行ったとしても、温度の数値が2回ともまったく変わらないなどはあり得ないことです。結局、前の温度をただそのまま引き写しただけに違いありません。 事実、原燃が「文献式の解釈間違い」だと言い訳をしている第2資料・表3(ここでの表2)の数値には矛盾が含まれています。温度を変えないことを大前提としたものの、実際の迷路板の構造は温度が上がるように変化しているのだから、どこかで矛盾が露呈するのは当然のことです。 原燃のやることはまったく信用できません。他の設備や施設でも同様の虚偽が行われている疑いが濃厚です。直ちにウラン試験をやめて、虚偽について徹底調査すべきです。その虚偽の責任が社会的に厳しく問われるべきです。 [補足:圧力損失の計算―原燃第2資料・15頁より] 15頁の流量 W は、1時間(h)当たりに断面積 S(m2) を通って流れる空気の体積(m3)である。流速 u=W/S は単位断面積(1m2)当たり、1時間当たりに 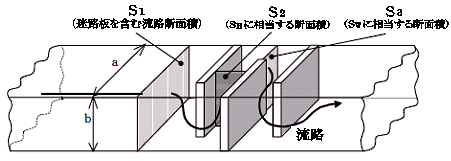 流れる空気の体積(m3)を表している。表2の全冷却空気流量は単位がkg/hとなっているので、1時間当たりに流れる空気の重量を表しているが、これは空気密度ρを用いてρWで表される(密度×体積=重量だから)。u=W/SをΔPの式に代入して整理すると、 流れる空気の体積(m3)を表している。表2の全冷却空気流量は単位がkg/hとなっているので、1時間当たりに流れる空気の重量を表しているが、これは空気密度ρを用いてρWで表される(密度×体積=重量だから)。u=W/SをΔPの式に代入して整理すると、ΔP=θ^2・(ρW/S)^2/ρ となる。 空気密度ρは、理科年表の式よりρ=1.2932/(1+0.00367t)(tは温度(℃)で100℃程度まで妥当)より決まる。Sは流路の断面積で、「文献式の解釈間違い」に基づく場合は、迷路板が存在しないとした場合の流路全体の断面積をとることになっているので、S=S1=ab(aは流路幅、bは流路の高さ)で決まる。 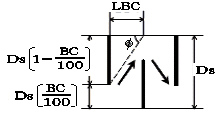 θ=sinφでφは15頁の図に示されているが、直角三角形の垂線/斜辺で決まる。斜辺の長さをピタゴラスの定理(三平方の定理)を用いて決めると、結局、θ^2=1/(1+(d/Ds・r)^2)となる。ただしd=LBC
は2つの迷路板の距離、r =1‐BC/100は迷路板幅/流路幅を表す。 θ=sinφでφは15頁の図に示されているが、直角三角形の垂線/斜辺で決まる。斜辺の長さをピタゴラスの定理(三平方の定理)を用いて決めると、結局、θ^2=1/(1+(d/Ds・r)^2)となる。ただしd=LBC
は2つの迷路板の距離、r =1‐BC/100は迷路板幅/流路幅を表す。Ds は「文献式の解釈誤り」に基づけば、Ds=2ab/(a+b)で決まる。それゆえ、東棟では θ^2=1/(1+0.22(d/r)^2)、西棟では θ^2=1/(1+0.20(d/r)^2)となる。d/r は東棟と西棟でほぼ同じ値をとると考えられるので、θ^2は両者であまり違わないだろう(西棟の方が多少であれ大きい値となる)。大体の値を図から読み取ると、θ^2はおよそ0.7 程度の値だと思われる。 |