六ヶ所再処理工場海洋汚染―海藻類による被ばくの再評価
|
2003年9月12日 小山英之(美浜の会代表) はじめに 2002年11月23日発行の美浜の会とグリーンピース・ジャパン共著のパンフレット「六ヶ所再処理工場は人々の安全を脅かす」の中で、海洋汚染による被ばくについて、事業許可申請書の評価を批判的に検討している。その場合、批判の最も重要なポイントになっているのが海藻類の汚染による被ばくである。その被ばくの程度は、放出口から北13km地点(泊漁港沖合い)での海水の放射能濃度によって決まるようになっている。 同パンフレットでは、その北13km地点での濃度評価をした結果、事業許可申請書の計算結果よりも約5.8倍高い濃度になると結論している。その結論は、事業許可申請書の計算方法についてのある解釈に基づいており、その方法を修正することによって得られたものであった。事業許可申請書では概して説明が簡略化されているため、その内容を評価するときに、推察せざるを得ない点が多々あるのである。 ところが、その北13km地点濃度に関する申請書の計算方法について、パンフ著者の解釈が間違っていたことがその後明らかになった。そのことは、申請書の計算方法について日本原燃や経産省原子力安全・保安院に質問書を出して問い合わせた結果明らかになったことである。また他にも、肝心の拡散の程度に決定的な影響を与えるパラメータ(拡散係数)の設定についても、パンフでは申請書と違う取り方をしていたことも判明した(くわしい内容は以下で説明)。 そこで、申請書内容の基礎になっている下記の文献に依拠して、前記誤りを修正するとともに、改めて申請書内容を批判的に検討したい。その結果、泊濃度は前回の約5.8倍から約3.3倍に下方修正される。それに基づき、かつ前と同じくラ・アーグとの比較を考慮して、海洋汚染による被ばく線量を再評価すれば、約60μSvとなる(約80μSvから下方修正)。海洋汚染によるだけで50μSvを超えるという点では、前回パンフの主旨を変える必要はない。すなわち、日本原燃は、被ばく線量が22μSvで50μSvを超えないから安全だと主張しているが、この安全性の根拠が崩れることに変わりはない。 大気放出による被ばく、さらにラ・アーグの燃焼度より1.5倍高い燃焼度の使用済み燃料を扱っていることなどを考慮すれば、被ばく線量は100μSvを超えるものと予測される。 なお、軽率にも間違った内容をパンフで宣伝したことについて、美浜の会代表として各方面にお詫びしたい。下記の参考文献2の入手についてお世話になった水口憲哉氏に感謝したい。 参 考 文 献 1.「廃液海洋拡散予測モデルの開発」、平成元年3月、電力中央研究所報告:U880702. 海洋科学基礎講座1、海洋物理Ⅰ、pp.331-335、東海大学出版会。 3. 宇野木早苗著、「沿岸の海洋物理学」、東海大学出版会、第9章。 4. T.Kobayashi, S-H.Lee and M.Chino, Development of Ocean Pollution Prediction System for Shimokita Region Model Development and Verification. J. Nuclear Science and Technology, 39, pp.171-179. 1.なぜ、放出口北13km地点での放射能濃度を問題にするのか 事業許可申請書に書かれているとおりの計算式とデータを用いて計算した結果によると、5つの経路による被ばく線量の合計の中で、海産物摂取による被ばくは約88%を占めている。そのうちの12%(全体の10.7%)が海藻類摂取による寄与である。5つの被ばく経路で他に重要なのは魚網からの被ばくで全体の約11%を占めている。 海藻類以外の海産物の放射能を決めるのは、放出口周辺のむつ小川原港港湾区域(漁業権消滅区域)の海水の平均濃度である。この区域内での放射能を吸収した魚介類を同区域周辺で採取すると想定しているからである。ところが海藻類は、放出口周辺では採れずに、泊漁港付近で採れるとしており、放出口から北13km地点の海水濃度によって決まると仮定している。なお、魚網の放射能は、むつ小川原港港湾区域周辺の最大濃度によって決まるとしている。 ここでなぜ北13km地点での濃度を問題にするかと言えば、第1に、申請書では泊方向に向かう海流を過小評価しているように思えること、第2に、ラ・アーグ再処理工場での海洋放出実績と比較すると、海藻類によく吸収濃縮される放射能(核種)があまり放出されないように想定しているからである。そのため、ここでは海藻類に限って申請書の評価を批判的に検討したい。 2.事業許可申請書の濃度評価方法 放射能濃度の評価方法は、前記参考文献1の電力中央研究所の論文でくわしく検討されている。ただし、そこでも、いろいろな量の定義や説明が非常に雑にしかなされていない。いろいろな場合の計算結果が書かれているが、それがどのような条件のもとでなのかが明記されていない。したがって、言葉の端々から推察しなければならない点が多々ある。また、明らかに間違いだと思われる説明もなされている。 解析は大きく分けて2段階になっている。第1段階は深さ約50mの海底放出口から放出された廃液が攪拌されながら海面近くまで浮上する過程(「近傍領域」)である。この解析は別の論文で行われており、その結果は「仮想放出口条件」として集約され、文献1での解析の出発点となっている。第2段階は、その仮想放出口条件を前提として、廃液が海流に乗って拡散していく過程(「遠方領域」)の解析である。この遠方領域の解析では、次の3種類の量が必要となる。第1は海流速度、第2は廃液固有の速度である。第3は、これら海流速度+廃液速度によって廃液が流されながらどのように濃度が拡散していくかという解析である。なお、事業許可申請書では、これらのうち第2の廃液流動の解析を省略しているので、ここでもそれは無視することにしたい(廃液固有の流れは、海流の速度をわずかに高めるだけだから)。 以下、仮想放出口、海流速度、廃液濃度の拡散について順に説明しよう。数学的な内容がどうしてもからむのだが、それについては付録にゆだねることにしたい。 (1) 仮想放出口条件について (1-1)仮想放出口とは 仮想放出口とは、遠方領域での廃液拡散の出発点(初期条件)となるための廃液分布のことである。これは海底の放出口から放出された廃液が攪拌されながら海面近くにまで浮上したときの分布によって決まる(図1)。仮想放出口は海流に直交するように広がり、縦の厚みH0、幅B0の広がりをもち、その範囲では濃度C'0は一定であると仮定されている。その際、浮上する過程で海流によって流されたりするので、海流をどう想定するかが問題になる。 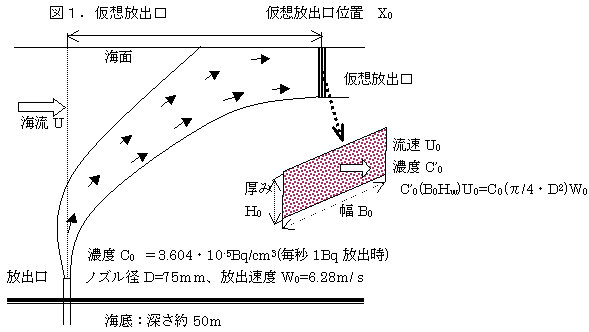 (1-2)海流速度の想定 海流の速度は下北海域の観測によって決まるものである。観測点が21地点におかれ、1年間に渡って海流の向きと流速が測定された。ただし、放出口付近以外での観測は、2月、6月、8月、11月に限られている。そのデータは事業許可申請書に掲載されているものと同じである。その結果から文献1では、次のようにして流速と向きの頻度を割り出している。 まず、21地点から「代表的と思われる」7地点を選び出した(文献1図-19)。その7地点とは、水深10m地点が1点、水深50m地点が2点、水深100m地点が4点である。そこでの観測結果から(多分平均をとって)、南向き流(南流)、北向き流(北流)および憩流の起こる頻度として次表の上段に示す結果を導いた(憩流とは流速5cm/s未満の流れとされている)。表の下段は、放出口における年間を通じた観測結果から導かれている。これらは、年間を通じて南流、北流および憩流がどのような頻度で起こるかを示している。これは、単に放出口付近だけでなく、下北海域の流れを全体的に規定するものと考えられている。 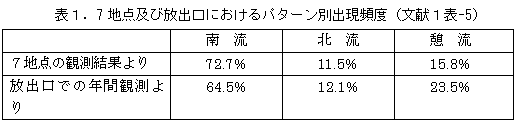 さて、この表を見ると、7地点観測結果では南流の出現頻度が高いが、これは当然の結果である。なぜなら、下北海域では水深が深くなるほど南流が起こる傾向が強いから。水深10m付近では南流と北流の起こる頻度はほとんど50対50に近い。ところが、7地点のうち水深100mの地点を4地点選び、水深10mはたったの1地点だけしか選んでいないのである。 しかし結局は、基本的に放出口でのデータに基づき、「総合勘案した」次の結果をもって下北海域の流向と流速の頻度を規定した。ここで憩流には、南流(いっせいの南向きに流れ)と北流(いっせいの北向き流れ)以外のすべてのパターンを含めている。例えば、沖合いで南向きかつ沿岸で北向きなるパターンは憩流に含めている。この方式の批判は、後で行うことにする。 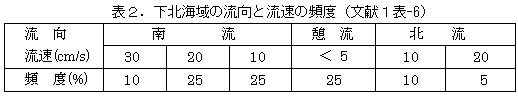 このような流速と流向を基礎にして、ある種の解析を行った結果、前の図に示した仮想放出口条件を特徴づけるいろいろなパラメータの値を下表のように導いている。 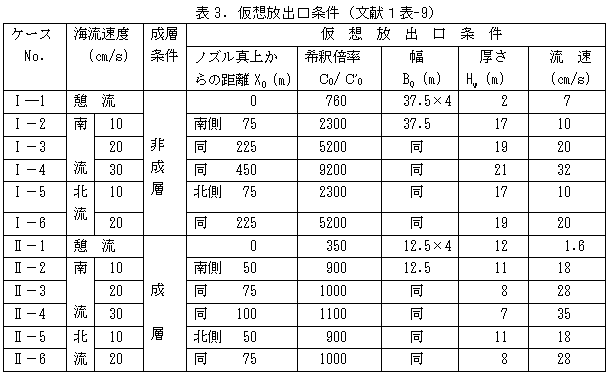 注:元の表では、海域流動の単位がm/sになっているが、cm/sに修正した。また、希釈倍率の値は元表のままの値を書いたが、これはかなり雑な値である。 注:成層期は6~9月に起こり、非成層期はその他の季節に起こるとしている。それゆえ、成層期は4/12=1/3の頻度で、非成層期は8/12=2/3の頻度で起こるとしている。 (1-3)放出口北13km地点での濃度を規定する海流速度 前回作成した我々のパンフでは、放出口北13km地点での濃度を評価する場合の放出口条件としては上記の表3を適用しているものと解釈していた。ところが、日本原燃や原子力安全・保安院への質問書への回答を通じて明らかになったのは、次のようなとり方をしているということだった。つまり、放出口北13kmは放出口からかなり離れているので憩流の影響はほとんど及ばないと考える(この扱いには疑問があるが)。そのため、憩流の起こる頻度を南流と北流の起こる頻度に割り振って加える。具体的に言えば、表2より、憩流の起こる頻度は25%であるが、これを南流頻度60%対北流頻度15%に割り振ると、南25×60/75=20%、北25×15/75=5%となるが、これに若干北側におまけを付けて、南18%対北7%にする。これらを元来の頻度南60%と北15%に加えると南78%、北22%(憩流0%)となるというわけだ。 そうすると結局、北13km地点での濃度を評価するための仮想放出口条件は次のようになる。例えば、非成層期で10cm/sの北流が起こる頻度は、非成層期頻度2/3×北流の起こる頻度22%×北流のうち10cm/sの起こる頻度10/15(表2より)=9.78%。このような計算を北流について行うと次の表4の結果になる。 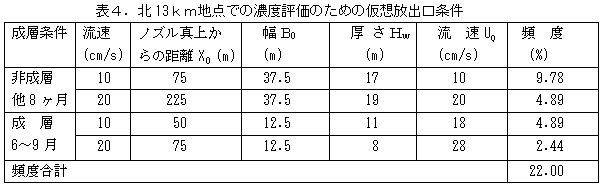 (2) 海流の解析 次に、文献1では海流についてどのように取り扱っているかを見ておこう。その前に、そもそも下北海域の海流はどのように特徴づけられているかについて概観しておきたい。 ここの海流を特徴づけているのは、第1に津軽暖流である。これは日本海に入り込んだ黒潮の末裔であり、津軽海峡西側の海面が高いために東側に向かって噴出してくる。夏場には、勢いよく噴出すために、それに引きずられるようにして沿岸沿いの流れが起こる。津軽海峡より南側の下北海岸沿いには北向きの、北海道側沿岸では南向きの流れになる。海上保安庁のデータで見ると、このような傾向が起こるのは7月から10月のようである。その他の季節では津軽暖流は噴出しが弱いために、出口付近からそのまま南に下がるように流れる。 特徴づけの第2は、親潮と親潮前線によって津軽暖流の流れが制約されていることである。津軽暖流の流れる海域が、親潮前線によって制約され、全体的には南に流れる傾向になっている。さらに第3には、この海域の地形によって制約される。しかし、下北の海岸はほぼ直線状に南北に走っているのでそれほど複雑なことはなく、等水深線もほぼ海岸線に平行に走っている。ただし、むつ小川原港の突堤によっては、海岸寄りの海流はかなり影響を受けているようである。 それでは文献1では、このような特徴をもつ海流をどのように扱っているのだろうか。そこでは、放出口を含むかなり広い海域を計算領域としてとり、その中で一般的な方程式群を数値的に解いている。このような方程式群の解は、初期条件と境界条件を与えないと決まらないが、境界条件は下北海域の海流測定値とは何の関係もない一般的なものを与えている。初期条件は、定常状態の場合を解いているので関係しない。ただし、水深が浅いところでは、海底からの摩擦によって流速が弱まるので、地形が問題になるが、水深については実際の値をインプットしているようである。そうすると、結局ここでの方程式群の解は、下北海域と同様の地形の海域ならどこでも当てはまる一般的な海流なのであって、下北海域の海流を特徴づけたものとは言えない。 計算結果を見ると、特に北向き流については、沿岸付近で実際の観測値より小さい値が出ている。それは当然で、津軽暖流の噴出しに伴って沿岸沿いに北向き流が発生するなどという特徴は、方程式や境界条件のどこにもインプットされていないからである。 しかしどちらにせよ、結局は、このような解析は放出口北13kmでの濃度評価を行うのには何も関係していない。次に説明するように、そのために必要な海流は、上記表4で与えられている流速に対応する頻度だけなのである。 (3) 北13kmでの濃度を決める拡散 文献1では、北13kmでの濃度を決めるのに憩流は関係しないとして、年間を通じた全体の流れを北向き流と南向き流に分けてしまった。このうち、南向き流はもちろん北方面には影響しないので、結局北13km地点での濃度は、表4の頻度で起こる北向き流によって決まることになる。 海底の放出口から毎秒1Bqの放射能が継続的に放出されるとしよう。それはまず図1の長方形をした仮想放出口に到達して、そこをくぐる。それが例えば流速10cm/sの流れに乗って北に向かうとしよう。もし拡散がまったくなく、そのままで進むなら北13km地点に到達しても仮想放出口での濃度と変わらない。ところが、小さな渦や乱流が絶えず起こっているために、廃液は全体とし北に進みながら、南北にも東西にも拡散する。拡散の度合いが大きければ大きいほど、廃液が横向き(東西方向)に散らばるため、北13km地点での濃度は小さくなる。 このようにして、北13km地点での濃度は拡散の度合いを決めるパラメータ(拡散係数)をどのようにとるかによって大きく影響されることになる。文献1では、拡散係数の決め方について文献2が挙げられている。リチャードソンの4/3則が採用されているのであるが、それは拡散係数が「拡散幅」の4/3乗に比例するというモデルである。そして、文献2によると、結局拡散係数は時間の2乗に比例するのと同等になっている(くわしくは付録参照)。 その比例係数などのこともあるので、日本原燃と原子力安全・保安院に拡散係数をどう決めたかと質問したが、明確な答えがなかった。私の推察では、文献1では拡散係数が時間の2条に比例するというモデルは採用していないようである。なぜかと言えば、文献1では憩流以外については定常状態を扱っているが、係数が時間に関係する場合は定常状態にならないからである。恐らく、例えばt=x/uのような関係を用いて時間を場所変数に変えているのではないかと思われる。しかし、それでは別の方程式を扱うことになる。 文献1では、もうひとつ不確かな点がある。文献1の仮定では、仮想放出口から出発してから時間とともに拡散の度合いを示す拡散係数が大きくなるように、つまり次第に拡散の度合いが高まるように想定されているのだが、やがて廃液が海岸線にぶつかるので、その辺りで拡散係数を一定にとることにしている。そこまで到達するのにおよそ1日程度かかるという記述があるが、実際にどのように数値を決めたのかが書かれていない。 そこで試しに、文献1の図-10にある計算結果と、拡散係数が全域で一定とした場合の解とを比較してみよう。図-10で扱っているのは、ここでの表3で言えば、非成層の南流の場合(ケースNo.I-2, I-3, I-4)である。恐らく定常状態と仮定して、計算領域をメッシュに分けて数値的に解いている。拡散の中心線上(放出口から真南に向かう線上)の値が図-10で示されている(下記の数値は図-10から物差しで読み取ったもの)。 この場合には、水深50mの線に沿った値であるため、海底による摩擦はほとんど影響しない。そうすると、流速一定、拡散係数一定の場合の解は解析的に求められるので我々はそれを使うことにする(海岸線による反射の影響はほとんど効かないことは実際に確かめている)。そのようにして図2の結果が得られる(計算式は付録で記述)。 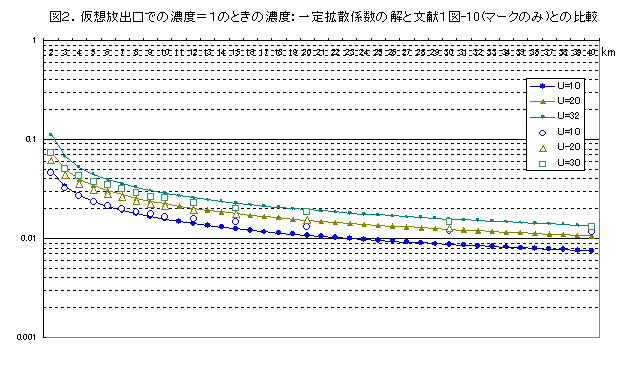 これを見ると、流速U=20,30cm/sの場合は、距離が大きいところで、拡散係数一定とした当方の計算値(拡散係数値は文献1の値を採用)と図-10(△と□)とはほぼ完全に一致している。ところがU=10cm/sの場合はむしろ距離の小さいところで一致しているが、距離の大きいところではずれている。しかしよく見ると、U=10の値○がU=20の値△よりも上に行くという非常に不自然な挙動を示しているので、この点についてはU=10の値は信用できないと見なすべきである。 南方向か北方向かは、この計算では違いがないので、文献1では放出口北13kmでの濃度として、ほぼここで決まる値を使っていることが分かる。その濃度値は、当方の計算結果では0.013(U=10)及び0.019(U=20)となる。ただし、ここでの値は仮想放出口での濃度=1と基準化した場合の数値である。事業許可申請書では、放出口で毎秒1Bqを継続的に放出した場合の濃度値を記述しているので、それに直す必要がある。 図1を参照し、海底の放出口から1秒間に1Bqが放出されたとしよう。その放射能はすべて仮想放出口(面積B0Hw)を通り1秒間では流速Uの距離に及ぶので、1Bqの放射能が体積B0HwUの中に存在することになる。したがって、仮想放出口での濃度はC'0=1/(B0HwU)となる。それゆえに、放出口で毎秒1Bq放出するときの濃度は、仮想放出口での濃度=1としたときの濃度を、B0HwUで割れば得られることになる。 以上は、非成層の場合であるが、文献1では成層の場合のグラフは別の種類で非常にわかりにくいものしかない。そのため、とりあえず拡散係数一定の場合の計算を成層の場合にもあてはめて、表4に基づいて計算した結果が表5である。成層のU=18, U=28のときの濃度値には、B0やHwの値の違いも効いてくる。仮想放出口で濃度=1の場合の計算値を、それぞれの場合のB0HwUで割った値が、放出口で毎秒1Bq放出のときの濃度になっている。それらにそれぞれの頻度(確率)をかけて加えれば、濃度の年間平均値(期待値)が得られる。 結局、北13km地点での濃度は、4.45・10-11Bq/cm3となる。この値は、事業許可申請書に書かれているこの数値5.2・10-11Bq/cm3より小さい。これは、本来定数ではない拡散係数を定数にしてしまったためと思われる。この後の批判的検討の中で定数でない場合の解を考慮する。 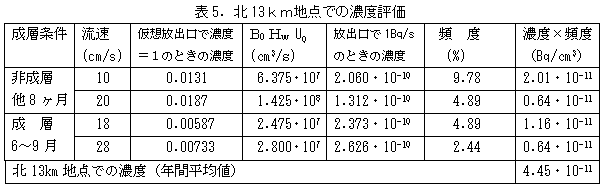 3.事業許可申請書の方法の批判 上記の事業許可申請書または文献1の方法について、2つの問題をとりあげて批判的に検討しよう。第1は、海流の向きに関する頻度の評価、第2は、拡散方程式の解に関する問題である。 (1)北向き流の頻度に関する評価 北13km地点での濃度評価にとって、北向き流が年間をつうじてどの程度の頻度で起こるかは決定的な影響をもつ。この点、文献1ではすでに見たように、はじめ7地点を選んだが、南向き流の頻度が高い水深100m地点を4点も含めていた。それを放出口での観測値で修正して表2の結果を導いた。さらに、北13km地点を評価する場合は、憩流分の頻度をエイヤッとばかりに南と北の比率で割り振った結果、北向き流の頻度は22%になって、表4の結果になったのである。 しかし、ここには大きな問題がある。北13km地点の評価を行う場合は、水深50mの等水深線に沿った動きが最も問題になる。そもそも海流は等水深線に沿って動くということを、事業許可申請書の解析では大前提においているのである。そうすると、北向き流の頻度については、放出口ばかりでなく、水深50mのすべての観測点でのデータを用いて評価すべきだということになる。放出口だけの評価では偶然に左右される恐れがあるからである。 そこで事業許可変更申請書の平成元年3月と平成3年版に出ている、水深50mの7地点における流向出現頻度のデータを用いて、北向きと南向きの出現頻度を調べてみる。北、北北東、北東、・・・、南、南南西、・・・、北北西の16方位の流向出現頻度がデータとして出ているので、これらを、北方向(北東~北西)と南方向(南西~南東)及びその他(西南西~西北西及び東南東~東北東)に分けて頻度を求める。これを各観測地点ごとに行ったのが表6である。観測点の名前、例えば20N50とは放出口北20km-水深50m地点、0050は放出口(水深50m)、15S50は放出口南15km-水深50m地点という意味である。 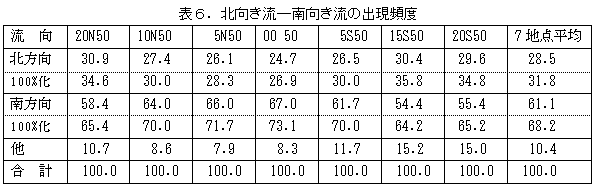 出所:平成元年3月事業許可変更申請書 第3.2-5表(1)~(4) 観測期別流向出現頻度 表6で各地点の頻度は、4つの季節(6月、8月、11月、2月)の頻度を平均化した値である。下段の数値は北方向と南方向だけで100%になるよう、再基準化した値である。南方面(15S50と20S50)では、等水深線が南北方向からずれているために、本当は南北方向を東南東~西北西方向に修正すべきなのだろうが、およその頻度を見るためなので修正はしていない(そこで「他」が少し高いのはそのためだと思われる)。 文献1では、憩流分の頻度をいきなり北向きと南向きの頻度に割り振ったのであるが、せっかく流向出現頻度のデータがあるのだから、これを用いて北向きと南向きに割り振る方が合理的である。しかもこの表で見ると、文献1が依拠した放出点(00 50)で北向き流の起こる頻度が一番低い。このような低さに依拠したのである。そうではなく、7地点平均か、あるいはさらに保守的にするなら、最も北向き流の頻度が高い場合(約35%)を選ぶべきである。 そこで以下では、北向き流の頻度を35%とする。文献1または事業許可申請書の場合はこの頻度を22%としていたから、この修正だけで、北13km地点での濃度は35/22=1.6倍となる。 (2)拡散の問題 放出口北13km地点での濃度評価は拡散の程度をどう評価するかによって相当に変わる。その拡散の度合いを決めるのが「拡散係数」であるが、その扱いについての問題点はすでに前節で述べた。文献2に依拠して拡散係数を決めると、拡散係数は時間の2乗に比例するのであるが、恐らく文献1ではそのような扱いをしていないと推測される。その理由は、前にも述べたように、文献1では定常状態を扱っているからである。 そこで我々は、付録に記述した時間の2乗に比例する拡散係数を用いた場合の解を用いて濃度を計算した結果を示そう。北13kmという遠方の値を求めるのが主眼なので、付録の拡散係数に登場する定数a00=0としている(そのため距離の短い点の値がかなり大きく出ている)。 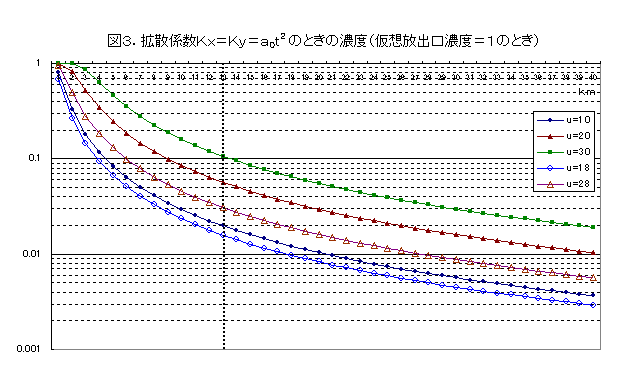 ここで、各uの値に対応するグラフは、(u=30を除いて)表5の各場合に相当している。この各グラフが図2のグラフと交わる付近で、拡散係数が定数の場合の図2グラフに置き換わると考えればよい。これによって、仮想放出口での濃度=1のときのx=13kmでの濃度が求まった。また、頻度は前記のように北向き流が35%になるようにする。この場合に表5を修正すると次の表7が得られる。 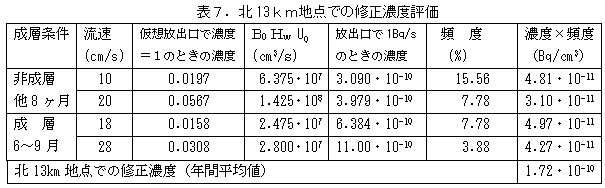 つまり、以上のような修正を加えた結果の、北13km地点における濃度は 17.15×10-11Bq/cm3となる。事業許可申請書での評価値が5.2×10-11Bq/cm3だから、約3.3倍高い値が得られたことになる。これが放出口北13km地点における濃度に関する新たな結論である。 4.ラ・アーグの放出実績を考慮に入れた被ばく線量-パンフレットの修正点 前のパンフレットの評価では、北13km地点の泊濃度として3.0×10-10としていたが、これを上記の値に修正しなければならない。前のパンフでは、まず11頁表6の海藻類欄にある[修正値]を修正する。それに伴って、パンフ14頁の表9の海藻類欄にある数値に1.72/3.0=0.573倍しなければならない。そのとき海藻類欄合計の数値が1.7881から1.0246に変わり、一番右の合計の数値が4.363から3.599に変わる。次に、パンフ26頁の表19の海藻類欄にある数値にやはり同じ0.573をかけることになる。そうすると、海藻類totalの数値が41.920から24.020に変わるので、一番右の合計の数値が60.318に変わる。 結局、新たに評価しなおした結果、泊漁港付近の放射能濃度の見直しだけで、液体放出による被ばく線量は約60μSvに達すると評価できる。 5.若干の議論 ここで行ったのは、放出口北13km地点の泊漁港で採れる海藻類による被ばく評価の見直しだけである。他の海産物の放射能濃度を決める海水濃度についても批判的検討が必要であるが、それはまだできていない。また、参考文献2では、9月期に、襟裳岬沖合いで南に向きを変えた津軽暖流が、さらに渦を巻くようにむつ小川原港方面に向かう流れのあることが指摘されている。このような周期的流れはないものと設置許可申請書では仮定されているので注目に値する。 他に、六ヶ所再処理工場で扱う使用済み燃料の燃焼度がラ・アーグの場合の1.5倍あるので、長寿命核種に関しては放射能の強さがおよそ1.5倍程度あるはずだが、それは考慮していない。 大気放出による分の被ばく線量も含め、これらの点を考慮すれば、六ヶ所再処理工場からの日常的放射能放出による最高の被ばく線量は年間で100μSvを十分超えるものと考えられる。この結果は、日本原燃が想定している安全性自体に明らかに反するものである。 [付録] 拡散係数と拡散方程式の解 ここでは、放出口北13km地点での濃度を求めることを念頭において、濃度Wに関する次の拡散方程式の解を2つの場合に求める。事業許可申請書にしたがって、座標は放出口真上を原点にとり、北方向をx軸の正に、東方向をy軸の正にとる(普通と逆だが、z軸を海底側にとっているためである)。そうすると放出口北13km地点は、y=0の線上にあり、それは水深50mの等水深線でもある。 文献1の元の方程式には海底からの摩擦の影響項も含まれているが、水深が深いので省略している。また、流速Uは時間的・空間的に一定の場合を扱えばよい。拡散係数Kx,Ky については、以下で2種類の場合を考える。 Case 1. 拡散係数一定のとき( Kx=1・10^5cm2/s, Ky=5・10^4cm2/s) 拡散係数が時間的・空間的に一定のときの解は、よく知られている。y軸方向に B0の広がりをもつ仮想放出口(x座標=X0)から、そこでの濃度=1で継続的に放出されるとき、y=0上の点(x, 0)での濃度は次式で与えられる。定常状態の場合は、時刻tを十分大きくとればよい。
Case 2. 拡散係数がリチャードソンの4/3乗則に従うとき 文献1または事業許可申請書では、拡散係数を
結局我々は、拡散係数が次の場合の解を求めればよいことになる。
文献1では領域をメッシュに分けて数値的に解いているようだが、無限領域の場合の正確な解を求めることができる(3km離れた海岸線での反射の影響でもほとんど問題にならないので、無限領域としても差し支えない)。それは次の変数変換を行えば可能である。
このτ-積分は実際には意外と厄介で病的あるが、積分領域を 拡散係数が定数に達するまでの領域では、この解を用いるのが妥当である。 |
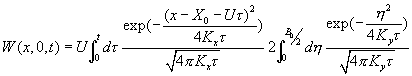 (2)
(2)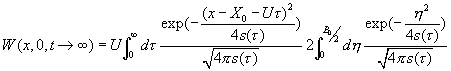 (8)
(8)