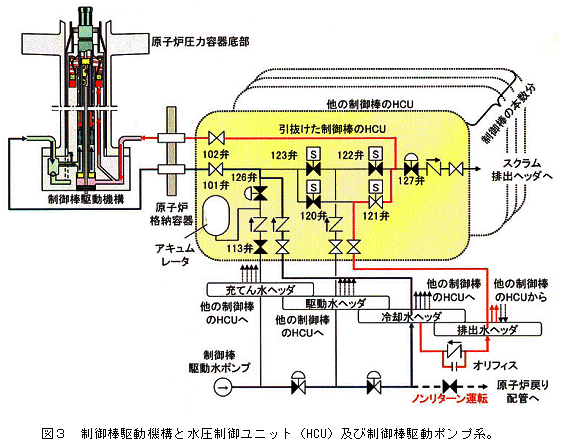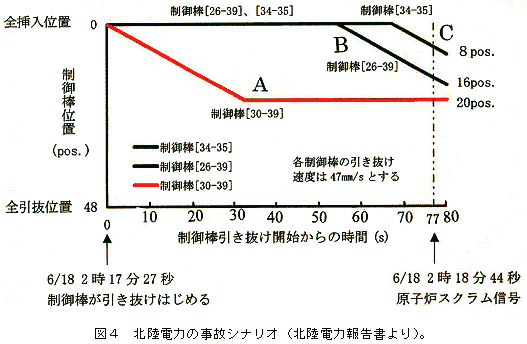| 事故の実態が未だ闇の中にある志賀1号臨界事故と BWR制御棒の構造的欠陥 |
組織ぐるみで隠蔽されていた志賀1号臨界事故の実態を明らかにしようとする際に、信頼できる情報だと考えられるのは、破棄されずに保存されていたアラームタイパー印字記録(A4一枚)と炉内中性子束モニターのチャートであろう。前者は原子炉の主要な動きについてのコンピュータ記録であり、原子炉スクラム信号発信や制御棒の位置等が時系列で記録されている。3種類ある中性子束モニターのチャートは、炉心における中性子数のペンレコーダによる記録である。最も低いレベルの中性子を計測する線源領域モニターSRMは2つとも瞬く間に振り切れている。次に、出力領域の十万分の一から百分の一程度の中性子を計測する中間領域モニターIRMも6つ全てが振り切れている。これらのチャートは臨界事故の確固とした証拠であるが、肝心な出力領域モニターの記録が公表されていない。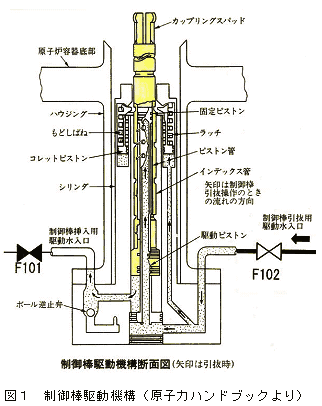 出力領域モニターの記録があれば発生した臨界事故の程度、すなわち、どのくらいの時間でどのようなレベルまで炉心出力が上昇したのかを知ることができる。そして作業員の被曝量についても誰もが納得し得るデータを提供する。ところが、北陸電力は「平均出力領域モニターについては点検中であった」と説明している。データを取らないこと、取れないようにすることが最大の事故隠しである。本当に点検中であったならば、炉心に燃料棒を装填し制御棒を操作していた時に同モニターを点検するという非常識が批判されるべきである。このような事情のために、臨界事故の実態を理解するには北陸電力がある意図を持って描いている事故シナリオにつき合わざるを得ない。ここでは同電力の事故シナリオを批判的に検討しつつ、BWR制御棒が持つ構造的欠陥を指摘する。
出力領域モニターの記録があれば発生した臨界事故の程度、すなわち、どのくらいの時間でどのようなレベルまで炉心出力が上昇したのかを知ることができる。そして作業員の被曝量についても誰もが納得し得るデータを提供する。ところが、北陸電力は「平均出力領域モニターについては点検中であった」と説明している。データを取らないこと、取れないようにすることが最大の事故隠しである。本当に点検中であったならば、炉心に燃料棒を装填し制御棒を操作していた時に同モニターを点検するという非常識が批判されるべきである。このような事情のために、臨界事故の実態を理解するには北陸電力がある意図を持って描いている事故シナリオにつき合わざるを得ない。ここでは同電力の事故シナリオを批判的に検討しつつ、BWR制御棒が持つ構造的欠陥を指摘する。誰も気づかない間に制御棒が抜けはじめた 1999年6月18日、アラームタイパー印字記録によると2時17分27秒に制御棒が抜け始めた。抜け始めたことに気づいた者が誰もいなかったことは北陸電力も認めている。運転員の意思に反して、また気づくこともできないままに制御棒が抜け出し、臨界事故が発生したのである。原子炉周辺の現場では、原子炉緊急停止の信頼性を向上させるために新たな信号回路を設置する「原子炉停止機能強化工事機能確認試験」が開始されていた。原子炉停止機能を強化するために行われた工事の試験中に、停止していた原子炉が勝手に動き始めたのである。BWRの制御棒は水圧によるピストン駆動であり、制御棒引抜用駆動水入口と挿入用駆動水入口という2つの入口にかける水圧で動かす構造になっている(図1参照:2つの入口にそれぞれ101弁と102弁とがついている)。進められていた「試験」では対象となる1本の制御棒をのぞく88本の制御棒駆動水系水圧制御ユニットを隔離する。具体的には88本の制御棒のそれぞれにある2つの入口に付いているバルブをひとつ一つ手動で閉める操作が行われていた(図2)。これが原因となって水圧の調整に異常をきたし、制御棒は抜けてしまった。制御棒の動きを封じるためにバルブを閉めたにも関わらず、制御棒は抜けてしまった。基本的な設計と構造がおかしいとしか言いようがない。 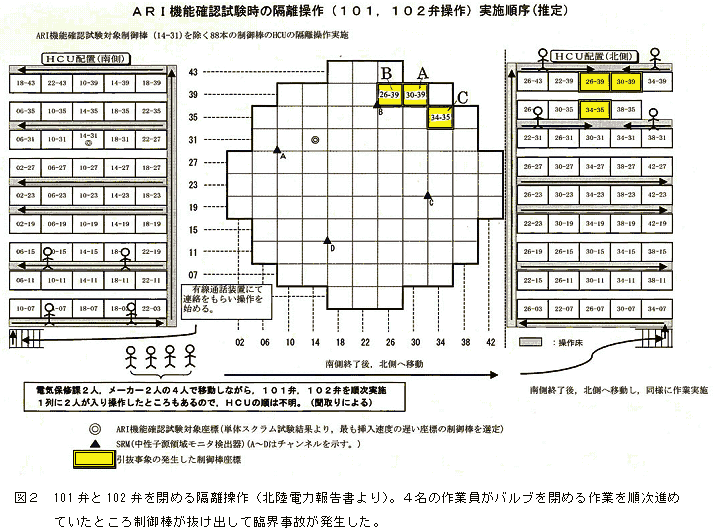 制御棒駆動機構の構造上欠陥のためにスクラムに失敗 抜けはじめてから74秒後、2時18分41秒に線源領域モニターSRMによる炉周期が11秒となり基準の20秒を割り込んだ。炉周期とは原子炉の出力が約2.7倍になる時間であるが、運転員に最初に異常を知らせたのがこの信号であった。しかし、わずか2秒後の18分43秒には「SRM高」のアラーム、18分44秒には「中間領域モニターIRM高」のアラームが発生し、原子炉スクラム信号もこの18分44秒に発生している。運転員にはものを考える暇がなかっただろう。事態の進行が余りにも速く、人為的な操作で食い止めることが不可能であるのが臨界事故の最大の特徴である。中間領域モニターIRMの値は振り切れたままになった。原子炉スクラム信号は発生したが、「試験」のために隔離用のバルブが閉じられており、また水圧をかけるためのアキュムレータもこの「試験」では充填されないことになっていたので制御棒は緊急挿入されなかった。スクラムに失敗したのである。臨界事故が発生したにもかかわらず、中央制御室からは原子炉を止めることができず、運転員にはそのような手段は何も無かった。図3に示すように、構造上101弁を閉めるとアキュムレータを充填していても制御棒の挿入は不可能である。燃料棒を装填した原子炉の緊急停止機能が101弁閉操作によって失われるのである。これは明らかな構造上欠陥である。
*通常運転時にはアキュムレータに高圧の窒素ガスで加圧された水が充填されており、スクラム時にはスクラム弁(126弁と127弁)が開く。普段は水が挿入用駆動水入口から駆動機構に入ることができるが101弁が閉まっているとそれは全く不可能になる。101弁は手動バルブであり運転制御室から開閉することはできない。原子炉の停止に15分も要した 運転員はスクラム信号から69秒後の2時18分53秒に制御棒の位置を確認している。制御棒30-39(以下制御棒A)が150センチ、制御棒26-39(以下制御棒B)が120センチ、制御棒34-35(以下制御棒C)が60センチそれぞれ抜けていた。21分50秒にも制御棒位置を確認しているが、3本とも約3分前と同じ位置にあった。この記録からある段階で制御棒の引き抜けが止まっていたと推論されている。制御棒の引き抜けが止まった要因としては原子炉スクラムによってスクラム弁(127弁:図3参照)が開き、102弁側の水圧が低下したことがあげられている。また幾つかの実験等に基づいて、北陸電力は制御棒抜け出し速度が毎秒47mmであるとしている。そして次のような事故シナリオを描いている(図4参照)。制御棒の隔離作業が進む中で水圧が高くなり2時17分27秒に制御棒Aが抜けはじめた。およそ32秒後に制御棒Aの動きが止まるが、これは現場で102弁が閉められたからであると北陸電力は説明している。このバルブ閉操作は「試験」を進めていただけであり、抜けている制御棒の動きを止めようと意図したものではなかった(そのような意味で偶然である)。水圧はさらに高くなったと考えられ、最初の抜け出しからおよそ55秒後に制御棒Bが、そして、約67秒後に制御棒Cが抜けはじめたと北陸電力は仮定している。74秒後くらいから原子炉に正の反応度が加わり原子炉出力が急上昇し、77秒後に原子炉スクラム信号が発信された。スクラム弁開による水圧の低下で80秒後くらいに制御棒の引き抜けが止まったとされている。このシナリオについては事実であるとも逆に事実と異なるとも証明することができない。すなわち、記録や何らかの証拠を根拠にしたものではない。
原子炉の暴走を食い止めたのは燃料棒の温度上昇であった。温度が上がるとドップラー効果とよばれる効果でU-238による中性子の吸収が強くなったからである。制御棒が挿入されなかったので出力は低下しながらも臨界は継続していた。最初の抜け出しからほぼ8分後、2時25分に現場に対して弁の復旧が指示され、3本の制御棒の101弁と102弁が開いたために制御棒の挿入が始まった。そして制御棒が抜けはじめてから15分後の2時33分に制御棒はようやく全挿入された。本来なら原子炉スクラム信号の直後に全挿入されなければならなかったことは指摘するまでもない。101弁と102弁とを閉めることが、原子炉のスクラムを不可能にするだけでなく、制御棒の操作機能を喪失させることと同じであることを、事故の収束過程自体が示している。 臨界事故の深刻さ 今回の事故によって燃料棒は破損していないのか。放射線モニター類の記録を見る限り著しい損傷の痕跡は見られないが、当時の炉水の分析結果は残されていないとされている。冒頭で述べた出力領域中性子束モニターの記録がないこととあわせて事故の実態は非常に分かりにくくなっている。しかも北陸電力の報告書には記述されていないことが多すぎる。 北陸電力のシナリオにしたがった解析によれば、即発臨界になっていた可能性が指摘されている(図5)。即発臨界とは制御棒によっては食い止めることのできないような出力上昇が起こる臨界であり、燃料棒の破損を含む暴走事故に至る可能性を持った臨界である。原子炉内で生まれた中性子が例えばU-235に吸収されるまでに要する時間は中性子寿命とよばれている。核分裂とともに発生する中性子(即発中性子と呼ばれる)が、衝突を繰り返して熱中性子になり拡散して燃料か減速材に吸収されるまでの時間はおよそ0.0001秒である。このような即発中性子だけで臨界が達成されるとわずかな反応度の添加で原子炉出力は急上昇し、核反応を安定に制御することは不可能である。実際の原子炉が制御可能であるのは、即発中性子以外に遅発中性子とよばれる、核分裂と同時にではなく、その後に核分裂生成物から飛び出す中性子があるからである。即発中性子が150個発生すると遅発中性子は1個発生する程度のわずかな比率であるが、この遅発中性子のおかげで中性子の平均的な寿命は0.1秒程度になり、小さな反応度の添加であれば遅発中性子の効果で原子炉出力はゆっくりと決定されることになる。 志賀1号の臨界事故でも即発臨界に十分なり得る反応度が添加されていたと考えられる。北陸電力の事故シナリオが正しいとして、制御棒Aは引き抜けはじめから32秒後に止まるが、それは現場でF102弁が偶然閉められたからであった。この制御棒Aがさらに抜けた状態で制御棒BとCとが抜けたとすれば、制御棒Bのみで臨界に達した後に制御棒Cが追い討ちをかけるように反応度を添加するような事態も十分にあり得たことになる。あるいは制御棒Aが最初に抜けはじめたとしても初期の水圧は低く、抜け出し速度はもっと遅かったかも知れない。しばらくある位置で停まっていた可能性もある。そうであるならば臨界に達したときには3本が抜け出していて(反応度がより高い)、原子炉出力が図5の計算例よりももっと高かった可能性もある。 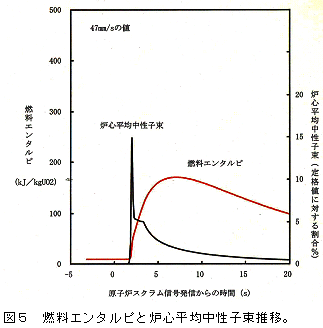 北陸電力や保安院の事故関連の報告書では、原子炉出力が低かったことを示して事故の深刻さを不問にしている。不問にできるようなシナリオのみを用意したとも言える。原子炉設置許可申請における安全解析のうち、燃料発熱量である燃料エンタルピーで比較すると「原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き」に匹敵する、あるいはそれを上回る規模の事故が、原子炉容器の蓋や格納容器の蓋を開放した状態で発生したという今回の事故の特徴をもっと深刻に受け取るべきである。また。1本ではなく3本の制御棒が同時に抜けてしまったという事実を直視し、安全解析での1本の引き抜きという想定を見直すべきである。 北陸電力や保安院の事故関連の報告書では、原子炉出力が低かったことを示して事故の深刻さを不問にしている。不問にできるようなシナリオのみを用意したとも言える。原子炉設置許可申請における安全解析のうち、燃料発熱量である燃料エンタルピーで比較すると「原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き」に匹敵する、あるいはそれを上回る規模の事故が、原子炉容器の蓋や格納容器の蓋を開放した状態で発生したという今回の事故の特徴をもっと深刻に受け取るべきである。また。1本ではなく3本の制御棒が同時に抜けてしまったという事実を直視し、安全解析での1本の引き抜きという想定を見直すべきである。
作業員の被曝問題に関しては計算ばかりが示されているが、当時の放射線管理にかかわるサーベイ記録を全て公表するべきである。燃料棒の健全性に関しても関係のありそうな12体の集合体のうち9体の調査結果しか記されていない。写真が示されているのはたった3体のみであり、それも外観だけでしかない。燃料体のシッピング検査も当然行われているはずであるが、その結果は全く公表されていない。 北陸電力は臨界事故を起こし、それを隠したのである。組織ぐるみで事故を隠蔽した犯罪会社であるにもかかわらず、国・保安院は徹底した事故関連の徹底した情報開示の指示・指導をしていない。その事故報告には(北陸電力のものも保安院のものも)、記録と証拠を伴う記述がほとんどない。記述されていない事柄があまりにも多すぎる。このままでは事故の責任を不問にし、免罪するための調査報告になってしまう。免罪するために事故シナリオを練り、事故解析するのでは北陸電力の体質は何ら改善されない。 |