| 12/3 第6回法廷 東海村臨界被曝事故裁判−中性子線被曝による健康被害が争点に 原告側はJCOの「しきい線量」論を全面批判 |
| 東海村臨界被曝事故裁判において原告側はこれまで、原賠法を根拠にJCOの親会社である住友金属鉱山の責任を問い、さらにPTSDを争点として被告JCOと争ってきた。それに引き続き、中性子線被曝による直接的な健康被害を次の争点とした。 これまで原告側は、本件臨界事故後に生じた種々の健康被害が、本件臨界事故による放射線被曝によって生じたものであると主張してきた。これに対して被告JCOは、「原告らの主張する各健康被害の身体的影響は、確定的影響に属するもの(準備書面(2))」とした上で、放射線の確定的影響にはしきい線量があるとし、「健康影響が生じうるしきい線量として確立されている知見は1グレイ(100mSv)[ママ]ないし250mSvである」と主張。そして、これを根拠に、原告の受けた被曝線量では、「原告らの身体的影響・確定的影響を認めえないことは明白である」と、原告の方々が訴える健康被害と中性子線被曝との間の因果関係を全面的に否定してきた。 これに対して原告側は、12月3日に開かれた第6回法廷で新たに準備書面(7)を提出し、JCOのしきい線量論を、法的側面と科学的側面の双方から全面的に批判した。準備書面(7)は、以下に紹介する4本の柱に沿って主張を展開し、原告の被った健康被害は被曝に起因するものだとしている。今後、被曝と健康被害の因果関係についての審理が本格的に開始されることになる。 しきい値論を前に押し立て、放射線の危険性と被曝被害を否定してきた国と原子力推進派への批判活動や、低線量被曝の危険性を明らかにする作業等々、これまで反原発運動の側が問題にしてきた課題が、まさに問われる局面に来ている。今後も、JCOの加害責任を問う裁判に対し、最大限の支援を行っていこう。ここでは、簡単ではあるが、今回原告側から提出された準備書面(7)に即して、その内容を簡単に紹介したい。 1.松谷訴訟最高裁判決に照らしてJCO側の主張の誤りは明らか JCOのしきい線量論に対し、原告側は長崎原爆松谷訴訟の最高裁判決(2000年)を対置し、これを第一の柱とした。原爆症認定申請却下の取り消しを求めた長崎原爆松谷訴訟では、原告である松谷英子さんが被った頭部外傷の治癒の著しい遅れ、その結果生じた右半身マヒ等の障害や、被爆直後の脱毛、下痢といった症状が、爆心から2.45km地点で受けた原子爆弾の放射線に起因するか否かが争点となった。国は、原爆症の認定に当たり基本的に爆心と被爆地点との距離から、松谷英子さんの被曝線量を20mGy〜30mGyとした。そしてその上で、確定的影響のしきい値理論を根拠に、20mGy〜30mGyという線量では健康被害は起こりえないものと主張した。しかし最高裁は、国側の主張を退け、原告勝訴の判決を下した。つまり最高裁は、国の線量評価で20mGy〜30mGyと推定された被爆者について、脱毛などの急性症状が、放射線に起因するものであると認定したのである。20mGy〜30mGyは、JCOの主張する「しきい線量」よりもはるかに低い線量である。 また、最高裁判決は、健康被害と放射線の因果関係の認定にあたり、距離に応じた線量評価としきい値理論の機械的適用によって因果関係を判断するような手法では、現実に生じている健康被害を十分に説明できないとして、このような手法そのものを否定している。ところがJCOは、松谷訴訟で敗訴した国側とまったく同じ手法を取っているのである。 原告側は、以上のような松谷訴訟の最高裁判決を武器に、しきい線量を根拠としたJCOの主張は誤っていると批判し、さらには計算線量としきい線量を機械的に適用して原告の健康被害を否定するJCOの手法そのものも根本的に誤っていると、重ねて指弾している。 2.JCOが主張するしきい線量以下と評価された被爆者・被曝者にも確定的影響が生じている 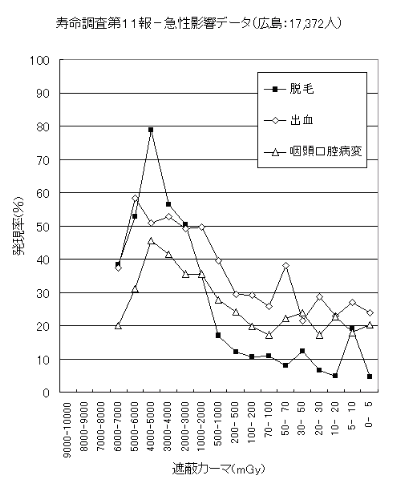 次に原告側は、第二の柱として、(1)広島・長崎の遠距離被爆者に発現した急性症状(確定的影響)に関する種々の調査、(2)阪南中央病院によって臨界事故後に行われた調査といった、科学的な見地から、原告らの被曝線量が、たとえ国の計算線量程度であったとしても現実に確定的影響が生じうることを論じている。 次に原告側は、第二の柱として、(1)広島・長崎の遠距離被爆者に発現した急性症状(確定的影響)に関する種々の調査、(2)阪南中央病院によって臨界事故後に行われた調査といった、科学的な見地から、原告らの被曝線量が、たとえ国の計算線量程度であったとしても現実に確定的影響が生じうることを論じている。広島・長崎の原爆での被爆による確定的影響については、これまで、放射線影響研究所(放影研)の寿命調査、日米合同調査団、東大医学部診療班、厚生省調査、マンハッタン調査団といった、被爆距離あるいは被爆線量と急性症状の発症に関する種々の調査が行われている。いずれの調査も共通して、爆心から2.5km以遠の遠距離被爆者の間でも、脱毛をはじめ、下痢や口内炎、出血(紫斑)等、急性症状が発現しているという結果を示している。2.5km以遠での被曝線量は、国の評価によれば広島で10mGy以下、長崎で20mGy以下となる。つまり、国の推定線量10mGy〜20mGy以下でも、現実に急性症状(確定的影響)が発現しているのである。 例えば、放影研が公表している寿命調査第11報の急性影響データセット(1998年−広島17,372人/長崎9,166人)によれば、線量の減少に伴って各急性症状の発現率は減少するが、広島・長崎共、0〜5mGyの範囲でも約5%の頻度で脱毛が起こったとされている。咽頭口腔内病変および出血(皮下出血・紫斑等)については脱毛より発現率が高く、国の評価で10mGy以下でも約20%の頻度で発生したことになる(グラフ)。原告側は、これらの科学的調査の結果から、原告の被曝線量がたとえ旧科技庁の評価による推定線量(約6.5mSv)であったとしても、早期影響を発現する可能性は否定できないとしている。 さらに原告側は、しきい線量という概念そのものを、ICRPのPublication41における定義にまで遡って明らかにし、JCOの主張を論破している。ICRPの考え方に基づけば、確定的影響におけるしきい線量とは、臨床症状の発現頻度が1〜5%を超えるあたりの線量を指すのである。ところが、被告JCOは「しきい線量とは影響があらわれる最低の線量」と「しきい線量」を絶対化し、現実に症状が発現しているにもかかわらず「影響を認めえないことは明白」としている。このようなJCOの主張は、しきい線量の概念を歪曲したものであり、科学的に見ても誤っているのである。 また原告側は、阪南中央病院・東海臨界事故被曝線量・健康実態調査委員会が実施した臨界被曝事故の「健康実態・被曝線量調査(2000年〜2001年実施)」を取り上げ、早期影響を疑わせるような症状が事故直後から1ヶ月の間に、数%〜10%程度の割合で発生しており、住民208名のうち、約3割が事故後1ヶ月以内に何らかの症状が発生したと訴えていること(下痢5.8%、吐き気・嘔吐4.3%、全身倦怠感11.1%等々)から、健康影響を訴えているのは原告のみで、それ以外に健康影響の発生は一切認められないとする被告JCOの主張がまったく現実を無視した不当なものであると、厳しく批判している。 3.旧科技庁の線量評価は大幅に過小評価されている 次に原告側は第三の柱として、具体的な根拠を示しながら旧科技庁の推定線量が大幅に過小評価されたものであることを明らかにし、原告らの被曝はさらに大きく約40mSvであったとし、旧科技庁の推定線量(約6.5mSv)を正しいものとするJCO主張を批判している。 まず原告側は、臨界事故当時、パリ声明(1985年)・ICRP1990年勧告を受け、すでに国際的には、中性子線の放射線荷重係数は最大20であると認知されていたにもかかわらず、旧科技庁が古い国内法を盾に、放射線荷重係数=10として線量計算を行い、これを正しい被曝線量としたことの不当性を指摘している。その上で、1990年勧告をベースとする2001年の法改正も踏まえ、JCOが原告の被曝線量だとする6.5mSvは少なくとも2倍にされなければならないと主張している。 次に原告側は、旧科技庁の推定線量が、すでに遮蔽効果を含んでいるような計算式を使って求められたものであり、二重の遮蔽効果を加算しているため約2.6分の1に過小評価されていることを、国の事故調査委員会の資料に基づいて詳細に論述している。 また、国のおこなった行動調査がずさんであると原告は主張し、阪南中央病院の行動調査の方が厳密性が高いと評価している(国の行動調査に対して阪南の行動調査は約1.3倍)。国の行動調査のずさんさを示す証拠として、原告側は、原告双方が事故当日明らかに異なった行動を取ったにもかかわらず、通知線量はまったく同じものであることを挙げている。 さらに、原告側は、国の推定線量には放射能雲による被曝線量が一切考慮されていないことや、国の公表している測定データには、隠蔽や改ざんの疑いがあることを詳細に論述し、国の推定線量には信頼性がないと強調している。 以上の種々の根拠から、原告側は、原告の被曝線量は約40mSvであると主張している。40mSvといえば、松谷英子さんの被曝線量を超えるような線量である。松谷訴訟の判例に照らしても、原告らの健康被害と被曝との因果関係は直ちに認められるべきであると、原告側は重ねて主張している。 4.中性子線の人体影響がさらに大きいことを示す新たな知見 第四の柱で原告側は、新たな知見によれば中性子線被曝による健康影響が従来考えられていたより遙かに危険であると考えられることを論じている。 臨界被曝事故は、照射線量に占める中性子の割合が非常に大きく、実効線量当量の9割以上を中性子線が占めるといった極めて特異な事故であった。中性子線被曝は非常に危険で、ベータ・ガンマ線と比較して人体への影響も大きい。今回の事故ほど大量の住民が主として中性子線による被曝を受けた事故例はこれまでになく、これが最大の特徴である。 ところが、中性子線の人体影響に関してはデータが乏しく、その危険性に関する現在の知見は、確立されたものとはいいがたい(事実、文部科学省は、放医研の中期目標(2001年)として、中性子線のリスクの定量化を目標に掲げている)。むしろ最新の知見によれば、中性子線の危険性は従来考えられてきたものよりももっと大きいと考えられるようになっているのである。健康管理検討委員会の主査代理を務めた佐々木正夫氏は放射線医学の権威であるが、同氏は、自らの研究で、JCO事故で被曝した作業員、周辺住民、消防士ら43名の血液中リンパ球の染色体異常を分析し、旧科技庁の推定線量よりも染色体異常から求めた線量の方が大きくなるという結論を出している。そして「最近になり、照射実験から低線量域での中性子の生物学的効果は従来考えられてきた値よりもかなり高く、RBE=50〜70という指摘がある。そうなると現在のICRPの中性子の実効放射線荷重係数も見直さなければならないだろう。はからずも今回の調査は中性子のRBEという問題を提起することになった」とまで述べている(RBE:生物学的効果比−放射線の種類による生体への影響度合いを表す)。 原告側は、佐々木氏の研究結果を中心に、中性線の人体影響について論述し、RBEを10とみなした旧科技庁の通知線量に従うことはできず、保守側に立って考えれば、中性子線の人体影響はさらに大きいものと考えなければならないとしている。また、中性子線被曝を特徴とする今回の事故の場合、まず実際に起こっている症状を重視し、そこから出発するという態度がより一層求められるのであり、過去の数少ない知見をもとに被曝線量は低いと断定し、「健康被害は出ない」と決めつけることは許されないとJCOを厳しく批判している。 |