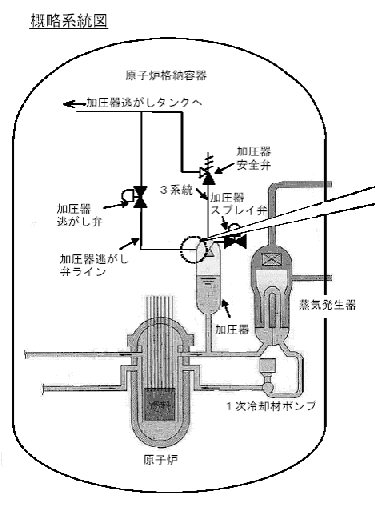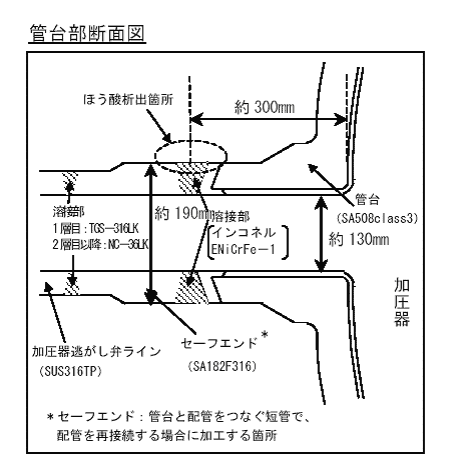| 敦賀2号機の加圧器配管系で、冷却材喪失事故につながる貫通割れ すべてのPWR原発を直ちに止め、加圧器系を点検せよ |
加圧器配管での損傷は、一次冷却材喪失事故に直結する 加圧器とは、1次冷却材が原子炉容器内で沸騰しないように、約150気圧の炉圧を一定に保つための装置である。ヒーターで加熱し、加圧器の上部に水蒸気の相を作り加圧している。この加圧器配管で亀裂が成長、破断という事態に至れば、一気に蒸気が噴き出す。続いて一次冷却水が噴出、冷却材喪失事故となる。そうなれば炉内の圧力は低下し、炉心部では沸騰が始まる。燃料の徐熱機能は失われ、燃料棒は破損・溶融する。 ギロチン破断に至らない貫通割れでも、深刻な冷却材喪失事故が引き起こされる。貫通割れの場合は破断口が小さいため、一次系圧力は降下しにくい。ECCSが働くのは高圧注入系だけであり、一次系を循環させながら蒸気発生器を通してゆっくり温度と圧力を下げる以外ない。そのため複雑な手順とコントロールが要求され、事故の収束は困難なものとなる。ECCSや弁・ポンプ等がうまく働かず、あるいは運転員のミスから徐熱に失敗すれば、たちまち炉心部では沸騰が始まり、燃料棒は破損・溶融する。1979年のスリーマイル島原発事故では、閉まりきらなかった加圧器逃し弁の指一本分程の小さな隙間から、一次冷却材が大量に流出し、炉心溶融という重大事故に至った。 さらに、炉内の水位が把握できなくなるという問題が事故の収束を一層困難なものにする。PWRには炉心の水位計が存在せず、加圧器が間接的に水位計の役割を果たしている。しかし、加圧器で破断が起これば、蒸気相の喪失により液面は上昇し、水位はまったく分からなくなる。
敦賀2号は1987年に運転開始し、稼働時間の累計は約11万時間である(設備利用率約82%)。貫通亀裂が生じた溶接部の厚さが約30mmであったことから、傷の進展速度は1年当たり約2.4mmとなる。なお、溶接部の材質はインコネルである。これに対して関西電力は、インコネル600製の上蓋管台について、亀裂進展速度は年当たり約0.26mmと評価している。従って、今回の亀裂は、上蓋管台の10倍もの速度で傷が成長したことになる。しかも、通常SCCが発生するのは液相と接触する部位なのだが、今回損傷が発生した部位は蒸気相との接触部分であり、従来の知見では説明がつかないような現象が起こっていた可能性がある。 すべてのPWR原発を直ちに止め、加圧器系を点検せよ 加圧器配管における損傷は、冷却材喪失事故に直結する危険性を持つものであり、全PWR共通の問題である。また、予想以上に短い時間で貫通割れに至ったのであり、事態は深刻である。事の重大性に照らせば、すべてのPWRを緊急に止めて保温材をはがし、加圧器の配管系を点検すべきである。維持基準の導入などもってのほかだ。当然、関西電力の全11基の原発も対象となる。我々は関電に対して質問書を出し、直ちに全ての原発を止め点検を実施するよう求めている。また、加圧器配管系の点検について、実施頻度、点検結果の詳細について明らかにするよう要求している。 |