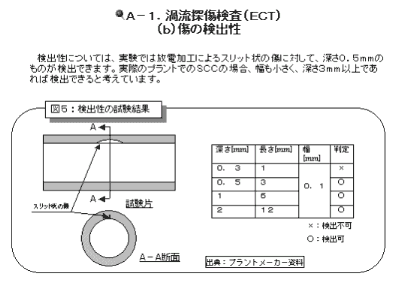| 美浜の会ニュース No.71 |
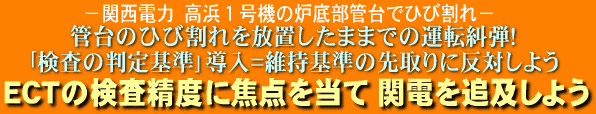 |
しかし、検査精度の問題が維持基準を大きく揺るがしている。東北電力女川1号機では、再循環系配管を切り出して調査したところ、実際の傷の深さに対して、超音波探傷検査(UT)で検出した傷深さが大幅に過小評価となることが明らかになった。UTでは深さ1mmだったものが、実測では最大8.5mm。あるいはUTで2.0mmだったものが、実測では最大12.2mm等々。これでは、ひび割れの正確な現状は把握できない。当然、進展予測や健全性評価などできるはずもない。維持基準そのものが成り立たない。 関西電力の原発でも同様に、渦流探傷検査(ECT)の検査精度が問題となっている。老朽化の進行によって、上蓋管台部での応力腐食割れの危険が表面化している。また別に、関電の高浜1号では、ECT検査の結果、炉底部の管台でひび割れの疑いのあることが新たに判明した。管台部でのひび割れが進展すれば、原子炉容器そのものに穴が明くことになる。一次冷却材の大量漏洩から重大事故へと発展する危険性がある。 関電の原発の場合、ECTの精度が保証されることが、安全性確保のための最低限の条件である。そこで、傷の探傷検査の精度に焦点を当て、2月19日、関電と交渉を行った。しかし関電は、精度について具体的な説明を拒んだ。「皆さんが納得できるような説明はできない」と居直り、検出性試験に使用した管の板厚といった基本的なデータすら明らかにしなかった。 ECTの検出精度について明確に説明できないにもかかわらず、関電は「検査の判定基準」なるものを導入し、管台にひび割れがある状態でも運転できるようにしようとしている。高浜1号機は、見つかった傷の詳細な調査も補修も行わず、これを放置したまま運転を再開した。明らかな維持基準の先取りである。国・電力は、検査精度の問題に頬被りしたまま、維持基準に向けて突き進もうとしている。関電の動きは、これと軌を一にしている。上蓋問題での関電との闘いは、同時に、全国で進められている維持基準導入に対する闘いの一環でもある。「検査の判定基準」=維持基準の先取りに反対しよう。ECTの検査精度の問題を前に押し立て、関電を粘り強く追及していこう。 関電はECTの検査精度=3mmの根拠を明らかにせよ。旧上蓋を切り出して調査せよ 昨年9月以降、ECTの検査精度に焦点をあて、上蓋管台部での応力腐食割れ(SCC)発生の危険性について関電を追及してきた。当初関電は、「十分な精度を有しております」の一点張りで、ECTの精度については具体的に明らかにしなかった。また、取り替えた旧上蓋を破壊検査にかけてECTの精度を確かめるべきだという要求も、明確な理由を示さず拒み続けてきた。しかし追及の結果、関電は「皆様や地元の方々の意見も踏まえた」として、昨年11月15日に「原子炉容器上蓋の保全対策」と題された報告書を公表した。この報告書は、ECTの検出精度を深さ3mm以上とし、人工的に作った傷に対する検出性試験の結果から導き出したものだとしている。 今回の交渉では、このECTの検出性試験に関する問題点を中心に追及した。まず第一に、報告書の説明図を見る限りでは、検出性試験は、サーマルスリーブや上蓋といった構造物が付属しない管だけの状態で実施されていることになっている。実機における測定の場合、サーマルスリーブや上蓋といった構造物や、管表面の付着物によるノイズが信号に載ってくるため、管だけの状態よりも検出精度が劣ることは明らかである。 第二に、試験で検出に成功したという人工的に作った傷は、放電加工であけた深さ0.5mm幅100ミクロンのスリットである。ところが、現実に発生するSCCの場合、亀裂の幅は10ミクロン以下ともっと小さく、従って信号も弱くなる。ところが報告書は傷の状況の相違について何も説明せず、いきなり「実際のプラントでのSCCの場合、幅も小さく、深さ3mm以上であれば検出できると」としている。深さ0.5mm幅100ミクロンの試験結果から、どのようにして深さ3mm幅10ミクロン以下という結論が導き出されるのか明らかでない。 以上の点を追及すると、スリーブや管台の付属しない、管だけの状態で試験したものであることを関電はようやく認めた。そこでさらに、試験に使われた管が実際の上蓋管台と同じ寸法を持つのかどうか確かめようと管の板厚を聞いたところ、「プラントメーカー(三菱重工)のデータであり、ノウハウに関することなので回答できない」と返してきた。板厚のような基礎的な実験条件に係わるような情報が、ノウハウなどであるはずがない。なぜ板厚すら答えられないのかと迫った。それでも関電は「ノウハウです」と繰り返すばかり。また、深さ0.5mm幅100ミクロンの試験結果から、どうやって実際のSCCの検査精度を導き出したかについて、それもノウハウであり一切答えられないという。具体的な実験条件も何も明らかにしないで、どうしてECTの信頼性について納得することができるのか。こう関電に詰め寄ると、「みなさんが納得できないというのはよく理解できますが、納得できるような説明はできません」と居直った。「ECTの精度は3mmだと私たちが言うのだから、それを黙って信じれば良い」という姿勢である。許し難い説明責任の放棄である。 そもそも、非破壊検査であるECTの検査精度は、実験だけでは確かめられない。検査対象を破壊検査にかけ、実測値と比較してはじめてその精度が確認できるのである。女川原発の例がそのことを示している。配管を切り出して内面研削にかけることで、超音波探傷(UT)の信頼性に問題があることがはじめて明らかになったのである。関電も取り替えた上蓋を切り出して徹底的に調査すべきである。関電は、検査精度に問題があることが明らかになることを恐れているに違いない。今後、老朽化によってひび割れが多く発生していく中で、検査の精度問題が関電にとって最大の弱点となるに違いない。ECTの検査精度の問題を軸に、厳しく関電を追及していこう。 高浜1号の炉底部管台でひび割れ。「検査の判定基準」導入は維持基準の先取り 関西電力は、高浜1号機の第21回定検(2002年11月~2003年2月)において、炉底に設置されている炉内計装筒管台部へのウォータージェット・ピーニングを実施した。ウォータージェット・ピーニングとは、高圧ジェット水を用いて、管内表面の応力を緩和させるものである。応力腐食割れの発生が否定できないため実施したと関電はしている。ピーニング施工に先立って関電は、全50本ある炉底計装筒管台に対してECTを実施した。その結果、外周部の1本で、深さ1mm以下とみられる発生初期の応力腐食割れ(SCC)が発生している疑いのあることが明らかになった。炉底管台部は、管径は異なっているが、構造、材質、温度条件の点で上蓋管台と極めて類似性が高く、同じ危険性を持つと考えられる部分である。今回見つかった損傷は、上蓋および炉底管台部で老朽化が進みつつあり、現実に損傷が発生していることを示す証拠である。 今回の事態を受け関電は「高浜1号機の原子炉容器炉内計装筒管台の保全について」という報告書をウェブサイト上で公開した。同報告書は、「検査の判定基準」として、深さ3mm以下を「良」とし、深さ3mmを超えた場合に「健全性評価を実施する」としている。同報告書によれば、この深さ3mmとは、ECTによって「明らかに傷と判断できるレベル」、つまりECTの検査精度によって基本的に規定されている。高性能のECTなら2㎜でもよいはずだ。 100%確実に傷だと判定できない場合は「良」、つまり補修も何も対策を取らない。3mmを超えた場合は傷と判定し、その上で傷の状態から強度評価等を行い、放置しておくか、何らかの対策を取るかを決めるというのである。これは、傷があっても補修しないことを明確に定めたものであり、「維持基準」の先取りに他ならない。これまでの「予防保全」の立場・原則からの大きな転換である。 この点を追及すると、答に窮し「テープSCC」の例等を持ち出して、これまでも維持基準的なやり方でやってきたというようなごまかしを持ち出してきたり、「告示501号に定めた技術基準は、そもそも運転中には適用されないのではないか」などと言い出した。現行法令を踏みにじり、「『新品同様』の原則などはじめからなかった」「従来からひび割れ等を放置しての運転が可能であった」などと言い出している保安院の苦し紛れの逃げ口上と同じである。これまで散々、「新品同様だから安全」と宣伝し続けてきたのではなかったか。老朽化が進み、現実に傷が見つかるようになって「新品同様というのは厳し過ぎるのでやめます」とはあまりに虫の良すぎる話である。 このような「検査の判定基準」なるものは今まで見たこともない。維持基準の先取りであることは明らかである。このことをはっきりさせるため、いつの時点から、このような「検査の判定基準」が導入されたのか。そして、3mm以上の傷が見つかった場合に実施するという健全性評価の中身について、次回交渉で具体的に説明することを約束させた。関電は、管台のひび割れを放置したままでの運転を容認する「判定基準」を撤回せよ。 例えば上蓋管台については板厚16mmのうち残り4~5mmまで傷が進んでも問題ない(関電) 関電は、維持基準導入に向けた検討と準備を内部的に進めているのは明らかである。関電の上蓋報告書は、「今後、検査で傷が確認された場合には、検査の判定基準として、次の様な考え方ができる」として、「① 次サイクル終了時でも、漏えいを発生させない傷の大きさ以下である。② 次サイクル終了時でも、破壊力学による強度評価上、問題を生じない傷の大きさ以下である。(米国で運用されている維持基準の考え方)③ 次サイクル終了時でも、解析により求めた応力が、許容応力より小さくなるような傷の大きさ以下である(国の技術基準(通産省告示第501号の考え方))」という3項目を示している。①~③について、各々の具体的な数値を示すように関電に求めると、関電は、①はフランスの例で、板厚約16mmの上蓋管台に対して許容される傷の深さは11mm。1サイクル当たりの進展速度は4mm。さらに②の場合は、深さ10mmまで許容でき、1サイクル当たりの進展速度は2mm。さらに③の場合は、深さ9mmまでは許容できるとした。 また別に、高浜1号の炉底部管台に関する報告書では別の数値が記載されている。同報告書は、「漏洩しないという観点からは、約2mmの板厚が残っていれば強度上問題ありません」とし、今後の対策としては「経年的な調査をする」としている。今後の炉底管台の傷の進展をどう評価しているのかと聞くと、「現在の状態を深さ1mmと考えると5年後には2.3mm、つまり5年間で1.3mm進むと評価している」と答えた。 傷の進展速度の評価は、かなり食い違っている。同じ上蓋管台でも、①の場合は1サイクルで4mm、②の場合は2mm。これに対して、関電の炉底管台の場合は、5年でたった1.3mmしか進まないという。上蓋管台、炉底管台はともに同じ材質であり、温度条件もほぼ同じであるにもかかわらず、傷の進展速度がなぜこれほど食い違うのか。女川原発1号機での切り出した配管の検査結果は、UTの検査精度に問題があることを明らかにしただけでなく、従来考えられていた傷の進展予測に対しても大きな疑義を投げかけている。東北電力は、再循環系配管での傷の進展速度を10年で1mmとしていたが、実際には10年で6mm以上の早さで進展していた可能性がある。関電の評価も現実を反映しない机上の想定に過ぎない。 以上の数値は、あくまでも例示であると関電はしている。しかし、例えば上蓋管台については板厚16mmのうち残り4~5mmまで傷が進んでも問題ないという程度の評価を関電が進めていることは明らかである。炉底管台の前記5年という想定は、国の「原子力発電設備の健全性評価等に関する小委員会」が進めている傷の成長を想定する期間と同じである。維持基準を念頭に、作業を進めていることは容易に想像できる。 さらに、高浜1号に関する報告書では、「仮に漏洩したとしても、その量は極めて少なく原子炉の安全には影響しません」としている。現実のSCCを受け、漏洩容認に一歩踏み込んだものである。「極めて少なく」とはどの程度と評価しているのかと聞くと「1時間当たり2.3㌧」だという。1秒間に600ccである。とても少量とはいえない。しかもこれは軸方向の最小限の貫通割れを想定したものに違いない。円周方向の割れであれば、さらに大規模な冷却材喪失事故となる。関電は、ひび割れの進展に加え、漏洩したままでの運転容認も視野に入れ、漏洩量の想定も水面下で進めていることを強く示唆している。 今後20万時間以上SCCは発生しないという予測は高浜1号での損傷発生によって覆された 関電は、高浜3・4、大飯3・4号機については上蓋を交換せず、炉頂部温度の低減化工事ですませている。上蓋報告書は、頂部温度を下げたため、材質はインコネル600のままでも、総寿命が40~60万時間に延長され、今後20万時間以上SCCは発生しないとしている。高浜3号機については、対策前の応力腐食割れ発生予測時間(運転開始からSCC発生まで)は27万時間であったが、対策後は発生時間が39万時間に伸びたとしている。高浜4号については27万時間から39万時間、大飯3号機については22間時間から53万時間、大飯4号機については22万時間から60万時間に延長されたとしている。 しかし、この運転開始から40~60万時間というSCC発生時間の予測は事実でもって覆されている。4基の温度低減化工事による温度低下は310℃→294℃(高浜3・4号機)、307℃→289℃(大飯3・4号機)である。一方、高浜1号機の炉底管台部の温度は289℃であり、現在までの運転時間は18万時間程度である。温度も同じ、材質も同じインコネル600という同等の条件下にある高浜3・4号機、大飯3・4号機の上蓋管台でもSCC発生の危険性があるというべきである。具体的には、運転開始から18万時間の高浜1号機の管台にSCC発生の可能性が否定できない以上、すでに14万時間近くが経過している高浜3・4号については、今後20万時間以上ではなく、後4万時間(約6年)でSCCが発生する可能性があるということである。しかも、高浜3・4、大飯3・4については温度低減化工事を実施するまで、高い炉頂部温度で運転を続けていた。そのことも考慮に入れれば、高浜1号よりももっと早期にSCCが発生する可能性があり、すでにSCCが発生している可能性も否定できないのである。交渉でこの点を追及すると、関電は「高浜1号のはSCCではなく、初めから存在した欠陥の可能性もある」などという苦しい言い逃れに終始した。関電は、高浜1号での検査結果を踏まえ、今後20万時間以上SCCは発生しないなどという評価を撤回すべきである。 また関電は、前回の交渉で高浜3号機については今年12月にECTを実施することを明らかにしたが、高浜4、大飯3・4号機については、「高浜3号機の検査結果を見てから決める」としている。関電は、SCC発生の危険性を認め、高浜4、大飯3・4号機の徹底した検査を即刻実施すべきである。 米デービス・ベッセ原発の上蓋損傷問題は、際めて大きな事件へと拡大・発展している。NRCは漏洩を知りながら、事業者と一緒になってこれを隠してきた。また、デービス・ベッセと同様のホウ酸腐食がセコヤ原発で見つかり、スイスのベズナウ原発1号機でも過去に同様の穴が発見されていたことが明らかとなっている。上蓋(炉底)管台はPWRのアキレス腱となりつつある。老朽化の進展に伴い、管台部での応力腐食割れ問題が急速に表面化している。 管台部でのSCC発生は、原子炉容器そのものの健全性に直結する極めて深刻な事態である。貫通割れ、特に円周方向の割れが発生すれば、大規模な一次冷却材漏洩となり、重大事故へと進展する可能性は否定できない。 管台だけではない。今後老朽化が進めば、あらゆる部分で機器の劣化は確実に進み、事故発生の可能性は高くなる。維持基準が導入され、本格的に運用されるようになれば、事故の危険性は飛躍的に大きくなる。関電は、管台部でのひび割れを維持基準導入のテストケースにしようとしている。維持基準を導入させてはならない。「検査の判定基準」=維持基準の先取りに反対しよう。ECTの検査精度の問題を軸に、関電を粘り強く追及していこう。 |