99.1/3000円+税
写真「休息するゲバラ」「若きゲバラとカストロ」

| 世界を見る-《ラテンアメリカ》 |
| ゲバラ コンゴ戦記1965 | |
| パコ・イグナシオ・タイボ?ほか著 神崎牧子・太田昌国訳/46判・376p/ 99.1/3000円+税 |
|
| 1965年2月アルジェの国際会議で激烈なソ連批判を行なって帰国したゲバラは、カストロと数日間の会談に入った。2週間後、彼はキューバから忽然と姿を消した。中ソ論争やカストロ路線との狭間で引き裂かれながら、自らの信念に基づいてコンゴに赴いた彼を待ち受けた運命は? 「これほどの孤独感をおぼえたことは初めてだ」と自ら記す、痛切な現代史ドキュメント。 写真「休息するゲバラ」「若きゲバラとカストロ」 |
 |
| エルネスト・チェ・ゲバラとその時代 | コルダ写真集 |
| ハイメ・サルスキー・太田昌国文/A4判・120p/98.10/2800円+ 税 |
|
|
「英雄的ゲリラ」と題されたあの写真はどんな状況で撮られたものだったか。ゲバラやカストロの思いがけぬ素顔を明かし、キューバ革命初期の躍動的な鼓動を伝える87枚の写真に加えて、写真とゲバラの関わりについての文章「写真解読のための註」など豊富な資料を備えた〈時代を読む〉写真集。 文=太田昌国「チェ・ゲバラと私たちの時代」 |
 |
| チェ・ゲバラ モーターサイクル南米旅行日記 | |
| エルネスト・チェ・ゲバラ=著 棚橋加奈江=訳/46判・202p/97.10/2000円+税 | |
| ゲバラは、若い時代にこんな旅行をしたんだ! 喘ぐ古バイクでアンデスを越え、船倉のトイレに隠れて「密航」し、野宿し、ヒッチハイクし、いかだでアマゾン川を下る。金はない、他人の好意にすがるのみ。無鉄砲だが、情熱的な旅のようすを、おもしろおかしく記録する青春真っ只中のチェ・ゲバラ。 |
 |
| 「ペルー人質事件」解読のための21章 | |
| 太田昌国著/新書版・256p/97.8/1500円+税 | |
| 大使公邸占拠・人質事件の本質はどこにあるのか。国家テロリズムの発動による人殺しを賛美する風潮は、社会をどこに向かわせるのか。ひたすら武力行使を是認する言論に抗する「人質事件」考。 |  |
|
[本書の目次] 関連日録 I 予告無き発端 南北格差残す自由主義に反発 *インタビュー II 過程 拡大する米州自由貿易体制に対する抵抗 III 終わりなき結末 強行突破をどう思うか *インタビュー |
| メヒコの芸術家たち シケイロスから大道芸人まで | |
| 伊高浩昭著/46判・244p/97.6/2500円+税 | |
| シケイロス、タマヨ、クエバス、トリオ・ロス・パンチョス、カンティンフラス、マリアッチ奏者たち、そして大道芸人たち--古き良きあの日々、青春真っ只中の著者に、人生とは何か、芸術とは何か、メヒコとは何かを教えてくれた芸術家たちを回想する。 |  |
|
【本書の目次】 I/壁画と画架のはざまで[シケイロス、タマヨ、クエバス]、II/アルィスタ群像[トリオ・ロス・パンチョス、カンティンフラスほか]、III/道ばたこそ劇場[惚れてはならぬ楽士たち、絶望的楽観性に生きる]、IV/ノケアルテ(殴打芸術)[われら醜い者たち:幾人ものボクサーの肖像] 【著者について】 伊高浩明(いだか・ひろあき):ジャーナリスト。67年以来、ラテンアメリカ、イベリア、南部アフリカ、沖縄などを取材。現在、共同通信編集委員。著書に、『青春のメキシコ』(77年、泰流社)『南アフリカの内側』(85年、サイマル出版会)『沖縄アイデンティティー』(86年、マルジュ社)『Cuba砂糖キビのカーテン』(92年、リブロポート)『イベリアへの道』(95年、マルジュ社)など多数。 【本書より】 「(ボクサーは)殴り殴ってランキングを駆け上がり、さらに殴って王座にうき、もっと殴って大金を稼ぎ続け、名士になる。絵画や音楽や映画や舞台をきわめて芸術家とたたえられるように「殴りの芸」で達人になる。私はこの「殴芸」を「ノケアルテ(殴打芸術)」と名づけた。ボクセアドール(拳闘士、ボクサー)は、芸術家と同じように孤独で、絶えず精進する。だが肉体は、重極、健康、闘志が基本だから、殴打芸術の活動年数はかぎられる。ノケアルテの神髄は、瞬間芸術であり、演じる者からみても短い瞬間芸術である。ときには、死に至る芸術となる。」 |
| カヌードス:百年の記憶 ブラジル農民、「土地と自由」を求めて |
|
| 小田輝穂著/46判・268p/97.8/2500円+税 | |
|
バルガス=リョサ、船戸与一、グラウベル・ローシャなど優れた作家と映画人の想像力を刺激してきた19世紀末のカヌードス戦争。1世紀後のいま、そのカヌードスの再生をめざしてたたかうブラジル農民の夢を追うノンフィクション。 【本書の目次】 |
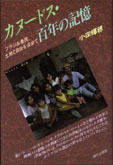 |
| バイクに乗ったコロンブス メキシコ・ホンダの日々 | |
| 黒薮哲哉著/46判・288p/95.6/2400円+税 | |
| 海外進出企業の日本人はどのように現地の人々と接しているか。朝日ジャーナル第7回ノンフィクション大賞「旅・異文化テーマ賞」受賞作品。 | 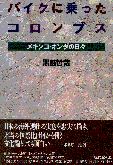 |
| GARIFUNA こころのうた | |
| 冨田 晃著/A4判・26p/95.6/1262円+税 | |
| ガリフナ、それはカリブの島に住んでいたモンゴロイドと奴隷船から流れ着いたアフリカの黒人との出会いが生んだ融合世界。人々の生きる姿を伝える写真集。 |  |
| もう、たくさんだ! メキシコ先住民蜂起の記録1 | |
| サパティスタ民族解放軍著 太田/小林編訳/A5判・468p/95.4/4500円+税 | |
| 94年初頭に起きたひとつの地域的な反乱は、実は現代世界の構造に通底するものを持っていた。サパティスタの魅力あふれるメッセージを紹介し、その意味を探る。 |  |
| 南のざわめき ラテンアメリカ文学のロードワーク | |
| 杉山晃著/46判・280p/94.9/2200円+税 | |
| マルケス、リョサら現代世界文学の最先端をゆくラテンアメリカ文学の魅力を、さまざまな角度から語り、読者を、この楽しいマジカル・ワールドへと誘う入門書。 | 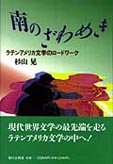 |
| 千の日と夜の記憶 | |
| 太田昌国著/46判・320p/94.4/2500円+税 | |
| 近代の宿痾が一斉に噴出したかのような1990年前後の世界。ラテンアメリカの先住民族、キューバ、ハイチの民衆など微少な声に耳を傾け現代世界の矛盾を抉る。 |  |
| 鏡の中の帝国 世紀末日本イデオロギー評註 | |
| 太田昌国著/46判・316p/91.2/2200円+税 | |
| キューバが混迷を深め、ニカラグアのサンディニスタが敗北した80年代後半。その情勢をどう捉えるか。ラテンアメリカ論にして、現代日本論集でもある第2論集。 |  |
| センデロ・ルミノソ ペルーの〈輝ける道〉 | |
| デグレゴリほか著 太田/三浦訳/46判・200p/93.5/2300円+税 | |
| ペルーには反体制闘争の社会的・政治的・経済的根拠がある。だがセンデロのあり方は、私たちの夢を作る材料そのものが、最悪の夢となりうるという現実を示す。 |  |
| 風みたいな、ぼくの生命 ブラジルのストリート・チルドレン | |
| ディメンスタイン著 神崎牧子訳/46判・228p/92.8/1800円+税 | |
| 700〜800万人といわれるブラジルのストリート・チルドレンに対する「戦争」が、「死の部隊」とか「正義派」を名乗る大人により遂行されている。 |  |
| 百年の孤独の国に眠るフミオに | |
| 伊藤百合子著/A5判変型・228p/92.5/1800円+税 | |
| 幼児期からスペイン、エクアドル、キューバ、メキシコ、コロンビアと異邦で暮らすことの多かった青年が、自然と身につけた、<世界性>の果てに抱いた絶望と夢。 | 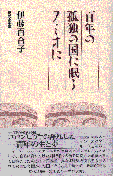 |
| アマゾンの戦争 熱帯雨林を守る森の民 | |
| シコ・メンデス著 神崎牧子訳/46判・216p/91.7/1800円+税 | |
| 88年12月、ブラジル・アマゾン河沿いの奥地で、シコ・メンデスが撃たれた。アマゾン河流域の森林とそこに暮らす人々に襲いかかる「開発」という名の暴力。 |  |
| はだしの医者、内戦エルサルバドルをゆく | |
| F・メッツイ著 太田/新川訳/46判・326p/90.7/2200円+税 | |
| ゲバラがゲリラ戦の不可能性を断言したエルサルバドルで続いた10年に及ぶ内戦。ゲリラ解放区で民衆医療に携わったベルギー青年が描くゲリラ地区の生と死。 |  |
| ゲリラのまなざし ニカラグア革命外史 | |
| ディーター・マズール画文 関西LA研 訳/46判・216p/89.8/1800円+税 | |
| 異国の革命に参加したドイツ人画家、時に切なく時にユーモラスに、草の根の人びとのたたかいの表情と心を描いた画文集。ニカラグア革命の詩と真実。 |  |
| 近代メキシコ日本関係史 | |
| エンリーケ・コルテス著 古屋・米田・三好訳/46判・216p/88.12/1800円+税 | |
| 北大西洋地域が世界の中心として振る舞っていた19世紀後半以降、太平洋を隔てて向き合うメキシコと日本がもうひとつの「世界」を形成する過程をたどる。 |  |
| ラテンアメリカ美術史 | |
| 加藤 薫著/A5判・384p/87.9/3800円+税 | |
| 古代から現代までのラテンアメリカ美術の全般を代表的作品420枚の写真を収めてわかりやすく解説したわが国初のラテンアメリカ美術史の入門書。 | 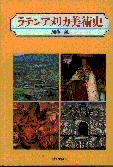 |
| インディアスを〈読む〉 世界史の舞台として | |
| 原広司・池田浩士ほか著/A5判・324p/84.10/2500円+税 | |
| ラテンアメリカを舞台に起こった歴史的事件をいかに読むか。歴史観の変革を迫る好著。石原保徳・菅孝行・花崎皋平・和田春樹・山崎カヲル・海老坂武・太田昌国ほか。 |  |